商業・法人登記のオンライン申請について
第1 はじめに
商業・法人登記は、オンラインによる申請をすることができます。
このページでは、一般的なオンライン申請をする場合の手続について説明しています。
初めてオンラインで登記の申請をする際には、パソコンの利用環境等の事前準備が必要です。詳しくは、以下のページから操作手引書及び説明動画を御覧ください(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。
登記・供託オンライン申請システムを利用して行うことができる商業・法人登記に関するオンライン申請は、登記申請(登記の嘱託を含む。),印鑑の提出又は廃止の届出、電子証明書の発行の請求です。審査請求は、オンライン申請の対象とはなりません。
オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出、電子証明書の発行の請求は、以下を御確認ください。なお、オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出は、オンラインによる登記の申請と同時に行う場合のみ可能です。
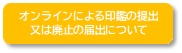
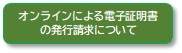
登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)の8時30分から21時までとなります。
なお、登記・供託オンライン申請システムの運転状況は、以下のページから御確認ください(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。
※ 登記所での登記の申請の受付時間は、8時30分から17時15分までです。申請書情報が17時15分以降に登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、申請書情報を送信した日の翌業務日に登記所で受付されます。
オンライン申請をする場合は、申請用総合ソフト(法務省が提供する登記・供託オンライン申請システムで取り扱う手続の全てを行うことができるソフトウェア)又は民間事業者による登記・供託オンライン申請システムを利用するためのソフトウェアによって作成した申請書情報とその登記の申請に必要な添付書面情報とを登記・供託オンライン申請システムに送信してする必要があります。
申請用総合ソフト及び申請用総合ソフトの操作手引書は、以下のページからダウンロードすることができます(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。
第2 オンラインによる登記の申請手続
なお、代表的な登記の目的ごとのオンライン申請手続の流れなどは、以下の登記・供託オンライン申請システムのホームページから操作手引書をダウンロードして御確認ください。
1 申請書情報の作成
「申請書様式一覧」画面で、申請用総合ソフトに用意されている登記申請書様式から、申請しようとする登記の目的などを確認し、適切な申請様式を選択します。登記申請書の記載内容については、以下の申請書様式・記載例を参考にしてください。また、「登記すべき事項」欄に登記すべき事項を入力する際は、以下の登記事項の作成例を参照してください。
作成した申請書情報には,申請人又はその代理人の電子署名を付与する必要があります。使用できる電子証明書や取得についての説明は、「第3 電子証明書の取得」を御確認ください。
2 添付書面情報の添付
登記申請に必要な添付書面情報を、申請書情報に添付します。必要な添付書面情報は、上記の商業・法人登記の申請書様式・記載例を参考にしてください。作成例は一例ですので、会社等の実情に合わせて作成してください。
商業・法人登記をオンラインで申請する場合に、添付書面情報として提出することができるファイルの種類は、以下のとおりです。
| 商業・法人登記関係手続 添付ファイルの種類 |
拡張子 |
|---|---|
| 署名付きPDFファイル ビットマップイメージファイル(注) XML電子公文書ファイル |
.pdf .bmp .xml |
添付書面情報には、作成者の電子署名を付与する必要があります。使用できる電子証明書や取得についての説明は、「第3 電子証明書の取得」を御確認ください。
申請用総合ソフトを使用して、添付書面情報(PDFファイル)に電子署名を付与することができます。
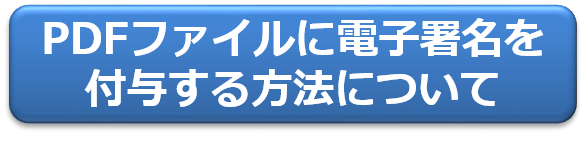
必要に応じて、PDF等により作成した登記に必要な添付書面情報を申請書情報に添付します。
電子定款を添付する際には、「添付ファイル一覧」画面で、「公文書フォルダ追加」をクリックし、添付する電子定款のフォルダを指定します。
なお、一つの申請で登記・供託オンライン申請システムに送信することができる添付書面情報のファイルの合計容量は、15MBまでとなります。
| ※ 添付書面が電磁的記録により作成されていない場合は、書面の提出又は送付も認められます。 添付書面を書面により提出又は送付する場合には、添付書面に申請番号を記載するか、又は、申請用総合ソフトの処理状況画面から「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷し、提出又は送付の際に添付してください。 |
【添付書面情報の特則(登記事項証明書の添付省略)】
次の登記の申請等で登記事項証明書を添付すべき場合には、当該法人の会社法人等番号を
申請書情報に記載して申請することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。
(1) 合併による変更の登記又は設立の登記の申請書に消滅会社の登記事項証明書を添付する
場合(同法第80条第5号等)
(2) 吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記の申請書に分割をする会社の
登記事項証明書を添付する場合(同法第85条第5号等)
(3) 株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の申請書に完全子会社の登記事項証明書を
添付する場合(同法第89条第5号等)
3 申請データの送信
他の登記所の管轄する区域への本店移転(管轄外移転)の登記申請等、2件の登記申請書を同時に送信する必要がある場合(同時申請)には、以下のページを御確認ください。
4 到達・受付のお知らせ
申請データが登記・供託オンライン申請システムに登録された時点で、到達のお知らせを取得し、申請番号、到達日時などを確認することができます。
登記・供託オンライン申請システムに登録された申請データが申請先登記所で受付された時点で、受付のお知らせを取得し、受付番号、受付日時などを確認することができます。
5 登録免許税・登記手数料の納付
オンラインで登記申請をする場合、登録免許税は、次のいずれかの方法により納付することとなります。
なお、納付する際の詳しい操作方法などについては、操作手引書(商業・法人登記 申請用総合ソフト編)を参照してください。
(1) 電子納付
インターネットバンキング、モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用して登録免許税を納付する方法です。
申請書情報及び添付書面情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると登録免許税の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。
「電子納付情報」が発行されると、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面にある「納付」ボタンが表示されますので、「納付」ボタンを押して納付内容の確認及び電子納付をします。
| ※ 電子納付する場合の納付期限は、申請書情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して3日間(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に掲げる休日は除きます。)です。例えば、申請書情報が金曜日の業務終了後登記・ 供託 オンライン申請システムに到達した場合は、月曜日から起算して3日目の水曜日が納付期限です。 |
なお,電子納付についての詳しい説明は、以下のページを参照してください(登記・供託オンライン申請システムのホームページが表示されます。)。
(2) 領収証書又は印紙納付
オンライン登記申請を行った場合でも、領収証書又は収入印紙を窓口に提出又は送付することによって、登録免許税を納付することができます。この場合には、受付番号等を記載した登録免許税・登記手数料納付用紙に領収証書又は収入印紙を貼り付けて、申請先の登記所が定める補正期限内に、当該登記所の窓口に提出又は送付願います(補正期限内に納付が行われなければ、申請は却下されます。)。
なお、登録免許税・登記手数料納付用紙は、申請用総合ソフトから印刷することができます(申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面にある「アクション」メニューの「登録免許税納付用紙の印刷(商業・法人)」をクリックしてください。)。
納付した登録免許税額又は登記手数料に不足がある場合(登録免許税額又は登記手数料の算定を誤っていた場合)には、登記所から補正のお知らせが送信されます(補正のお知らせについては,「6 補正・取下げ」を御確認ください)。
申請人は、補正のお知らせの内容に従って、不足している登録免許税又は登記手数料を納付することになります。追加納付の方法には、オンラインにより補正して納付を行う場合と、登録免許税・登記手数料納付用紙に領収証書又は印紙を貼り付けて納付する方法があります。
なお、追加納付する際の詳しい操作方法などについては、操作手引書(商業・法人登記 申請用総合ソフト編)を参照してください。
(1) 電子納付
登記所から送信された補正のお知らせに基づき、補正情報を作成し、その情報を登記・供託オンライン申請システムに送信した後に、歳入金電子納付システムから,登録免許税又は登記手数料を納付する方法です。補正情報を送信した後の手続の進行は、最初の納付の際と同じです。
なお、登記・供託オンライン申請システムに補正情報を送信し、登録免許税又は登記手数料の追加納付分について電子納付情報を得た後であっても,領収証書又は収入印紙(登記手数料については、登記印紙も使用可能)により登録免許税又は登記手数料の追加分を納付することができます。
(2) 領収証書又は印紙納付
追加納付分の領収証書又は収入印紙(登記手数料については、登記印紙も使用可能)を登録免許税・登記手数料納付用紙に貼り付けて登記所に持参又は送付する方法により納付することも可能です。この場合には、補正のお知らせに記録された納付期限までに登記所に提出する必要があります。
6 補正・取下げ
登記の申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合は、原則として、その登記の申請は却下されます。しかし、不備の内容が補正することができるものである場合において、登記官が定めた期間内にその不備を補正したときは、登記をすることができます。登記官の定めた期間内にその不備が補正されない場合は、その登記の申請は却下されます。なお、補正の方法には、オンラインによる方法と、書面による方法とがあります。
補正をする場合の手続の流れは、次のとおりです。なお、申請用総合ソフトの操作方法などに関しては、操作手引書(商業・法人登記 申請用総合ソフト編)を参照してください。
1 補正のお知らせ
登記の申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合には、登記所から、補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに送信され、「処理状況表示」画面の「補正」ボタンが表示されます。「補正」ボタンを押すと補正のお知らせが表示されますので、その内容を確認してください。
2 補正書の作成等
(1) オンラインによる補正
申請用総合ソフトに用意されている補正書の様式を用いて、補正情報を作成します。作成した補正情報は、電子署名を行った上、登記・供託オンライン申請システムに送信します。なお、登録免許税又は登記手数料を追加納付する場合の補正については、「5 登録免許税・登記手数料の納付」を御確認ください。
(2) 書面による補正
書面により補正をする場合は、以下の記載例を参照の上、補正書様式を御利用ください。
なお、書面による申請書情報の補正は、次のアからウまでの申請人等の別に応じ、それぞれに定める印鑑を押印した補正書と添付書面によって行うことになります。
| 申請人等 | 補正書に押印する印鑑 | 添付書面 |
| ア 管轄登記所に印鑑を提出している申請人等 | 提出している印鑑又は申請と同時に提出した印鑑 | ― |
| イ 印鑑を提出していない申請人等(委任による代理人を除く。)(注1) | 補正書と同時に提出する印鑑 | ― |
| ウ 委任による代理人であって、印鑑を提出していない者 | 代理人の印鑑 | 代理権限を証する書面(注2) |
(注)
1 管轄登記所に印鑑を提出していない場合には、補正書ともに印鑑届書を持参又は送付願います。
2 代理権限を証する書面(委任状)には、委任者の住所及び氏名を記載するとともに,委任者の別に応じて、下記のとおり措置を施してください。
・委任者がアの申請人等に該当する場合には、申請人等が提出している印鑑又は申請と同時に提出した印鑑を押印してください。
・委任者がイの申請人等に該当する場合には、申請人等が補正書と同時に提出する印鑑を押印してください。
登記の申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合は、原則として、その登記の申請は却下されます。しかし、申請人から、登記の申請の取下げをすることもできます(申請人から取下げがされない登記の申請については、登記官が却下することとなります。)。なお、申請の取下の方法には、オンラインによる方法と、書面による方法とがあります。 取下げをする場合の手続の流れは、次のとおりです。なお、申請用総合ソフトの操作方法などに関しては、申請者操作手引書(商業・法人登記 申請用総合ソフト編)を参照してください。
1 登記申請の不備
登記の申請書情報、添付書面情報などに不備がある場合には、登記所から、補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに送信され、「処理状況表示」画面の「補正」ボタンが表示されます。「補正」ボタンを押すと補正のお知らせが表示されますので、その内容を確認してください。なお、事案によっては、登記所の職員から電話により直接不備の内容をお伝えする場合もあります。
2 取下書の作成
(1) オンラインによる取下げ
補正の内容を確認した後、登記の申請を取り下げる場合(注)は、申請用総合ソフトに用意されている取下書の様式を用いて、取下書情報を作成します。作成した取下書情報は、電子署名を行った上、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
| (注) 登記の申請を取り下げる場合は、次の場合があります。 1 登記の申請の不備について、その不備を登記官が定める期間内に補正することができない場合 2 不備の内容が性質上補正することができないものである場合(例えば、登記所の管轄を誤って登記の申請をした場合などです。)。 |
(2) 書面による取下げ
取下書を窓口に持参又は送付する場合には、申請番号により申請を特定して行うこととなります。そのため、取下書には、申請番号を必ず記載願います。書面により取下げをする場合は、以下の記載例を参照の上、取下書様式を御利用ください。
なお、書面による取下げは、次のアからウまでの申請人等の別に応じ、それぞれに定める印鑑を押印した取下書と添付書面によって行うことになります。
| 申請人等 | 取下書に押印する印鑑 | 添付書面 |
| ア 管轄登記所に印鑑を提出している申請人等 | 提出している印鑑又は申請と同時に提出した印鑑 | ― |
| イ 印鑑を提出していない申請人等(委任による代理人を除く。) | 申請人等の実印 | 当該印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書で作成後3か月以内のもの |
| ウ 委任による代理人であって印鑑を提出していない者 | 代理人の印鑑 | 代理権限を証する書面(注) |
(注)添付する代理権限を証する書面(委任状)については、委任者の住所及び住所を記載するとともに、委任者の別に応じて、下記の措置を施してください。
・委任者がアの申請人等に該当する場合には、申請人等が提出している印鑑又は申請と同時に提出した印鑑を押印してください。
・委任者がイの申請人等に該当する場合には、申請人等の実印を押印し、当該印鑑につき市区町村が作成した印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を添付してください。
(3) 申請意思の撤回により取下げをする場合
登記の申請をした後、その登記が完了するまでは、登記の申請の意思を撤回して、当該登記の申請を取り下げることができます。ただし、代理人が登記の申請をした場合には、添付書面情報として提供した代理人の権限を証する情報とは別に、申請意思撤回の取下げに関する代理人の権限を証する情報が必要となります。
第3 電子証明書の取得
| 【電子証明書の有効性に関する注意事項】 1 申請書情報及び取下書情報にされた電子署名及び電子証明書については、申請人等が登記・供託オンライン申請システムに、これらの情報を送信した後に署名検証及び有効性確認を行うこととなります。そのため、登記・供託オ ンライン申請システムに、これらの情報を送信する時点(送信ボタンを押す時点)において電子証明書が有効でない場合には、エラーとなり、登記の申請をすることができません。 2 補正情報にされた電子署名の電子証明書については、その電子証明書が既に失効している場合であっても、申請書情報と併せて提供された電子証明書と同一のものであるときは、有効な電子証明書の提供があったものとして取り扱います(ただし、補正の内容が電子証明書の失効に関するものでない場合に限ります。)。 3 委任状情報にされた電子署名の電子証明書については、既に無効となった電子証明書を登記・供託オンライン申請システムに送信した場合であっても、エラーとはなりません。しかし、委任状情報にされた電子署名の電子証明書は、その性質上、申請書情報にされた電子署名の電子証明書と同じ取扱いをする必要があります。そのため、登記・供託オンライン申請システムが、これらの情報を受信する時点において有効な電子証明書が提供されていない場合には、商業登記法第24条第7号に基づく却下の対象となります。 4 添付書面情報(委任状情報を除きます。)にされた電子署名の電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点において、有効なものであれば、有効な電子証明書の提供があったものとして取り扱います。 |
【商業登記電子証明書取得について】
商業登記電子証明書は、管轄の法務局で取得することができ、また、オンラインで請求することも可能です。管轄の法務局や、商業登記電子証明書の詳細は、以下を御確認ください。
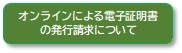
なお、会社・法人等の商号、本店・主たる事務所、代表者の資格・氏名等の変更に関する登記のオンラインを申請を行う場合には、その申請を行うことによって、申請書情報と共に送信された電子証明書が失効する場合があります(ただし、一定の条件を満たす場合には、再発行の申請(手数料不要)をすることができます。
申請書情報、補正情報、取下書情報及び添付書面情報それぞれについて、必ず電子証明書が必要となります。
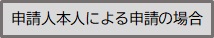
◇ 申請書情報、補正情報及び取下書情報の場合
| 電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
| 申請人 | (1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 (注3) 「セコムパスポート for G-ID」 (セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名、住所、出生年月日を確認することができるものに限る。) (4)官職証明書 (注4) ア 「政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書」 イ 「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)発行の職責証明書」 |
| 電子署名を付与する者 | 添付書面情報 | 送信すべき電子証明書の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付書面情報作成者全員 (注6) | ・添付書面に市町村 の印鑑証明書が必要 とされているもの ・添付書面に認証者の 認証が必要とされている場合の、認証者に関するもの |
(1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 (注3) ア 「セコムパスポート for G-ID」 (セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) イ 「e-Probatio PS2」 (NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) ウ 「TDB電子認証サービスTypeA」 (株式会社帝国データバンク) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) エ 「AOSignサービスG2」 (日本電子認証株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) オ 「DIACERTサービス」 (三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) カ 「DIACERT-PLUSサービス」 (三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) キ 「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証センター)(注8) ク 「司法書士認証サービス」 (注8) ケ 「ビジネス認証サービスタイプ1-E(一般行政手続用電子証明書)」(日本商工会議所)(注8) コ 「ビジネス認証サービスタイプ1-G(行政書士用電子証明書)」 (日本商工会議所)(注8) (4)官職証明書 (注4) ア 「政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書」 イ 「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)発行の職責証明書」 (5) 指定公証人電子証明書(注5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
上記(1)から(5)までのほかに、
|
◇ 申請書情報、補正情報及び取下書情報の場合
| 電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
| 委任による代理人 | (1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 (注3) ア 「セコムパスポート for G-ID」 (セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) イ 「e-Probatio PS2」 (NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) ウ 「TDB電子認証サービスTypeA」 (株式会社帝国データバンク) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) エ 「AOSignサービスG2」 (日本電子認証株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) オ 「DIACERTサービス」 (三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) カ 「DIACERT-PLUSサービス」 (三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (4)官職証明書 (注4) ア 「政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書」 イ 「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)発行の職責証明書」 |
◇ 委任状情報の場合
| 電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
| 委任者 | (1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 (注3) 「セコムパスポート for G-ID」 (セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名、住所、出生年月日を確認することができるものに限る。) (4)官職証明書 (注4) ア 「政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書」 イ 「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)発行の職責証明書」 |
| 電子署名を付与する者 | 添付書面情報 | 送信すべき電子証明書の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付書面情報作成者全員 (注6) | ・添付書面に市町村 の印鑑証明書が必要 とされているもの ・添付書面に認証者の 認証が必要とされている場合の、認証者に関するもの |
(1)商業登記電子証明書 (注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書 (注2) (3)特定認証業務電子証明書 (注3) ア 「セコムパスポート for G-ID」 (セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) イ 「e-Probatio PS2」 (NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) ウ 「TDB電子認証サービスTypeA」 (株式会社帝国データバンク) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) エ 「AOSignサービスG2」 (日本電子認証株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) オ 「DIACERTサービス」 (三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) カ 「DIACERT-PLUSサービス」 (三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) キ 「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」(株式会社中電シーティーアイ中部認証センター)(注8) ク 「司法書士認証サービス」 (注8) ケ 「ビジネス認証サービスタイプ1-E(一般行政手続用電子証明書)」(日本商工会議所)(注8) コ 「ビジネス認証サービスタイプ1-G(行政書士用電子証明書)」 (日本商工会議所)(注8) (4)官職証明書 (注4) ア 「政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書」 イ 「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)発行の職責証明書」 (5) 指定公証人電子証明書(注5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
上記(1)から(5)までのほかに、
|
(注)
1 商業登記電子証明書
商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。商業登記電子証明書は、管轄の登記所で取得することができます。また、オンラインで請求することも可能です。詳しくは、「商業登記に基づく電子認証制度」を御確認ください。
ICカードでの利用を希望される場合には、商業登記電子証明書をICカードに格納するサービスを御利用ください。なお、このサービスは民間事業者が提供しています。サービスの詳細は、「リンク集 ICカード形式の電子証明書について(参考)」に掲載する各事業者にお問い合わせください。
2 公的個人認証サービス電子証明書
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。
3 特定認証業務電子証明書
電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。
4 官職証明書
政府認証基盤(GPKI)又は地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)が発行する電子証明書です。申請人が官庁の場合や官庁から取得した電子文書を登記申請に用いる際に必要となります。
5 指定公証人電子証明書
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書をいいます。
6 作成者とは、作成する権限のあるものでなければなりません。例えば、取締役会議事録であれば、これに署名すべき出席取締役などが作成者に該当します。
7 商業登記規則第102条第5項第2号に定める「法務大臣の定める電子証明書」の指定に係る基準及び手続については、「商業登記規則第102条第5項第2号に定める「法務大臣の定める電子証明書」の指定に係る基準及び手続【PDF】」を御確認ください。
8 キの「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」の電子証明書については平成25年7月31日に、クの「司法書士認証サービス」の電子証明書については平成24年8月4日に、ケの「ビジネス認証サービスタイプ1-E(一般行政手続用電子証明書)」及びコの「ビジネス認証サービスタイプ1-G(行政書士用電子証明書)」の電子証明書については平成25年1月26日に全て失効していますが、添付書面情報を作成し、電子署名を行った時点で有効な電子証明書であれば、当該添付書面情報と併せて送信することができます。
9 例えば、添付書面情報が代表取締役の選任(重任を含む。)を証する情報(取締役会議事録等)である場合、変更前の代表取締役が(1)商業登記電子証明書、(2)公的個人認証サービス電子証明書又は(3)特定認証業務電子証明書(ア~コ)を記録すれば、他の取締役は(6)その他の電子証明書を記録すれば足ります。
なお、(6)その他の電子証明書を利用して作成された添付書面情報に、(1)商業登記電子証明書、(2)公的個人認証サービス電子証明書又は(3)特定認証業務電子証明書(ア~コ)による電子署名も付与する場合には、「申請用総合ソフトを使用した商業登記申請添付情報電子署名付与ガイド【PDF】」を御確認ください。
10 該当の記事が掲載されている1ページごとの官報PDFのみを送信してください。
お問い合わせ先
【登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク】
電話番号:050-3786-5797
障害等により上記番号を利用できない場合は、次の連絡先になります。
電話番号:050-3822-2811又は2812
なお、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は、事前に次のホームページも御確認ください。
Word 形式のファイルをご覧いただく場合には、Microsoft Office Word Viewerが必要です。
Microsoft Office Word Viewer をお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
リンク先のサイトはMicrosoft社が運営しています。
Microsoft Office Word Viewer のダウンロード![]()
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。
一太郎 形式のファイルをご覧いただく場合には、一太郎ビューアが必要です。
一太郎ビューア をお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
リンク先のサイトはジャストシステム社が運営しています。
一太郎ビューア のダウンロード![]()
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

