第1節 就労の確保等
(1)障害者・生活困窮者等に対する就労支援の活用【施策番号15】
法務省及び厚生労働省は、保護観察官、ハローワーク職員から構成される就労支援チームを設置して、障害者、生活困窮者も含めて、保護観察対象者等に対する就労支援を実施している(【施策番号7ア】参照)。
法務省は、矯正施設在所者のうち障害等により就労が困難な者に対し、社会内で利用できる就労支援制度を紹介するためのリーフレットを配布している。
厚生労働省は、障害を有している犯罪をした者等が、就労意欲や障害の程度等に応じて就労できるよう、引き続き、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、就労定着支援事業(以下「就労系障害福祉サービス」という。資2-15-1参照。)に取り組んでいる。
そうした中で、障害福祉サービス事業所が矯正施設出所者や心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に基づく通院医療の利用者等である障害者(以下「矯正施設出所者等である障害者」という。)を受け入れるに当たっては、①きめ細やかな病状管理、②他者との交流場面における配慮、③医療機関等との連携等の手厚い専門的な対応が必要であるため、「社会生活支援特別加算」において、訓練系、就労系障害福祉サービス(就労定着支援事業を除く。)事業所が、精神保健福祉士等の配置により矯正施設出所者等である障害者を支援していること又は病院等との連携により精神保健福祉士等が事業所を訪問して矯正施設出所者等である障害者を支援していることを報酬上評価することで、受入れの促進を図ることとしている。
また、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく、就労準備支援事業(資2-15-2参照)や就労訓練事業(資2-15-3参照)により、犯罪をした者等を含む一般の企業等での就労が困難な生活困窮者に対する就労支援を行っており、個々の状態像に合わせた個別の支援を展開している。
さらに、福祉事務所設置地方公共団体の任意事業である就労準備支援事業について、2018年度(平成30年度)から、その実施を努力義務としたほか、対象者の年齢要件を撤廃し65歳以上も利用可能とすること等により、多様化する就労支援ニーズをとらえた事業の実施を図っている。
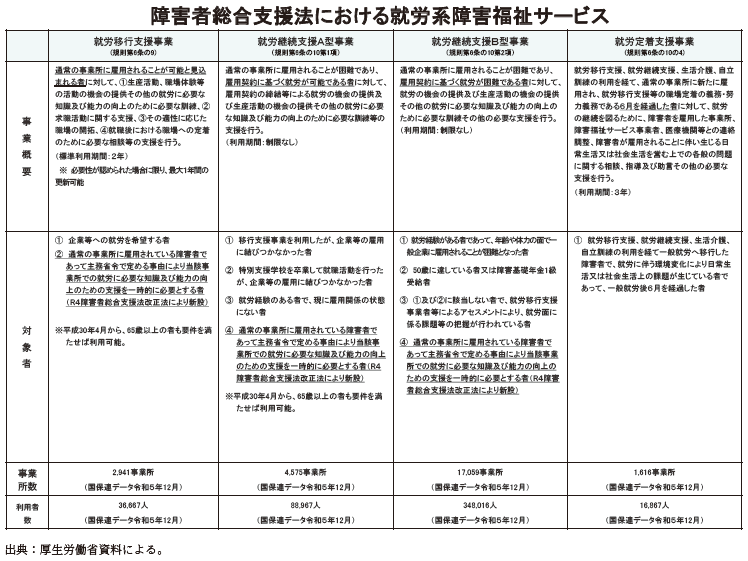
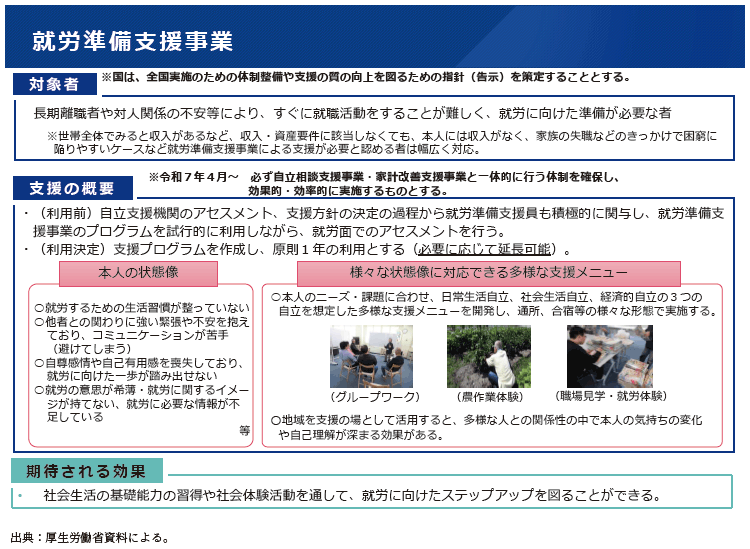
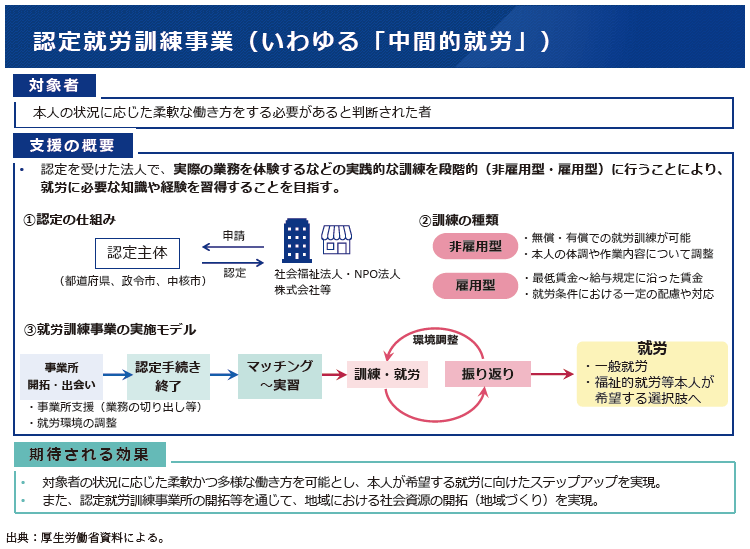
(2)農福連携に取り組む企業・団体等やソーシャルビジネスとの連携【施策番号16】
法務省は、全国の保護観察所において、労働市場で不利な立場にある人々のための雇用機会の創出・提供に主眼を置いてビジネス展開を図る、いわゆる「ソーシャル・ファーム」との連携を進め、2024年(令和6年)5月末現在、全国195団体(前年:181団体)との間で、雇用や受入れ等の連携を実施している。また、いわゆる「ソーシャル・ファーム」と保護観察所との間で「ソーシャル・ファーム雇用推進連絡協議会」を開催し、相互理解を深めるとともに、一般就労と福祉的支援との狭間にある者への就労支援について協議を行い、協力雇用主への登録に理解を示すソーシャル・ファームについて、協力雇用主としての登録も促している。
また、2021年度(令和3年度)から、一部の刑事施設において、農福連携※21に関する団体(以下「農福連携関係団体」という。)との意見交換会を開催し、2022年度(令和4年度)からは刑事施設66庁において実施している。農福連携関係団体からの意見を実際に聞くことで、矯正施設及び農福連携関係団体それぞれが抱える課題等について理解を深め、農福連携の取組を活用した社会復帰支援に向けた連携体制の構築につなげている。2022年度からは、刑事施設15庁において、農福連携関係団体の職員等を招へいの上、就農意欲を有する受刑者への面接や指導を実施し、刑務所出所者の就農に向けた取組の推進を図っている。2023年度(令和5年度)からは、農林水産省等の協力を得て、一部の少年院の職員が「農福連携技術支援者育成研修」を受講し、農業や福祉に関することを学び、農園芸指導等に農福連携の視点を取り入れている。
2019年(令和元年)6月に決定された「農福連携等推進ビジョン※22」において、犯罪をした者等の立ち直りに向けた取組への広がりが示されたことから、法務省及び農林水産省が連携し、一般就労と福祉的支援との狭間にある犯罪をした者等の就農に向けた取組を推進している。
また、経済団体、農林水産業団体、福祉団体その他の関係団体、地方公共団体、関係省庁等の様々な関係者が参加し、国民的運動として農福連携等を展開していくため、2020年(令和2年)3月に農福連携等応援コンソーシアムを設置するとともに、2020年度(令和2年度)からは、農福連携に取り組んでいる優れた事例を表彰し、全国への発信を通じて横展開を図る「ノウフク・アワード」を実施している。
【環境大臣賞受賞】
矯正局における再犯防止分野のEBPMの推進に向けた挑戦について
~刑務所における受刑者の就労支援希望の申出促進策に関する調査・分析~
法務省矯正局
2024年(令和6年)1月、刑事施設における就労支援に関する課題解決のため、行動経済学(ナッジ)の知見を活用した介入方策を考案し、その介入方策として、ランダム化比較試験(RCT:Randomized Controlled Trial)の手法(介入を実施する対象をランダムに選択して実験し、その結果得られたデータを分析する手法)による効果検証を実施した取組が、環境省が主催するベストナッジ賞(環境大臣賞)1を受賞しましたので、御紹介します。
刑事施設においては、受刑者に対する就労支援に取り組んでいますが、就労支援は、希望者に対して実施される取組であるため、その対象者は、出所者全体の約2割程度に留まっており、受刑者に対して、就労支援の利用をより一層促進することが課題となっています。
そこで、その課題解決の手段として、「選択を禁じることも、経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、人々の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチャー2のあらゆる要素」を特徴とする行動経済学(ナッジ)の知見の活用に向けた検討を進めました。
まずは、ナッジの知見を活用した介入方策案を検討するため、受刑者が就労支援を受けるまでのジャーニーマップ3を作成し、どこにどのような課題(就労支援を受けない理由)があるのかを整理しました。そして、その結果を踏まえ、介入方策として、受刑者に対し、就労支援に関するチラシを配布することとしました。
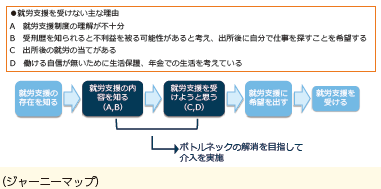
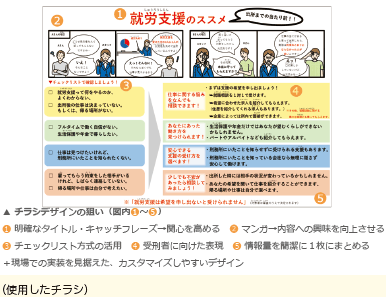
介入(チラシ配布)の効果を検証するため、就労支援の希望の有無等を確認する内容のアンケートを作成するとともに、五つの刑務所を試行庁とし、各刑務所における工場をランダムに介入工場(チラシとアンケートを配布する工場)と非介入工場(アンケートだけを配布する工場)に割り付けする層別ランダム割り付けを行いました。
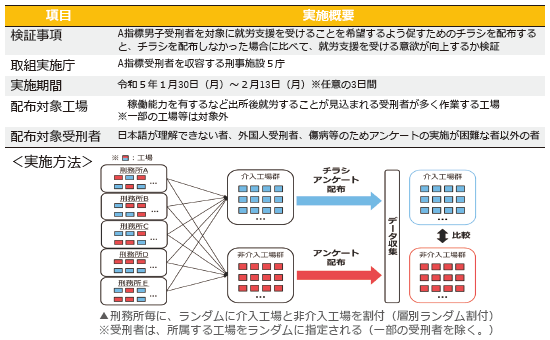
チラシ配布の結果を分析したところ、「就労支援を受けることを希望する」ことについて、介入工場の受刑者と非介入工場の受刑者間に統計的に有意な差は確認できず、今回の効果検証においては、チラシ配布が「就労支援を受けることを希望するようになる」という成果に対する効果があったとは言えませんでした(ただし、ないとも言えません。)。しかし、それは、それとして一つのエビデンスを蓄積できたと捉えています。
また、今回の試行のような介入(チラシ配布)について、高いエビデンスレベルを求める効果検証デザインにより介入と成果の因果関係の検証を行うことは、今後、様々な施策を検討する上で重要なことだと考えており、この結果を材料としてより良い改善策を検討することとしています。
さらに、今回の試行を通じ、刑事施設における効果検証デザインについてのアドバンテージとして、
① 受刑者の属性情報等のデータが既に取得されている
② 介入の対象者/非対象者を明確に定義しやすい
③ 介入群と非介入群が接触することで介入効果が非介入群に及んでしまうリスク(いわゆるコンタミネーションリスク)を最小化できる
④ 刑事施設の性質上、外部要因の影響を受けにくい
という点を整理することができました。
今回の調査・分析を通じて、就労支援の改善に向けた様々な示唆が得られました。EBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)4の実践に当たっては、効果検証等の結果だけにとらわれるのではなく、施策の見直しや改善に向けたヒントが得られる貴重な機会として、果敢に効果検証に取り組んでいくことが重要です。本取組で得られた知見も活用しつつ、刑事施設ならではの利点があることを十分に理解した、現場の実情を踏まえた効果検証を行うことで、今後も質の高いエビデンスを蓄積することができると考えています。エビデンスは、公共財であるものの、共有されづらい側面があることから、引き続き、国として、エビデンスの蓄積とその共有を進めてまいります。
なお、詳細は、法務省ホームページ5に掲載されておりますので、御覧ください。
- 1 ベストナッジ賞(環境大臣賞)
環境省等が行動経済学会との連携により、平成30年度から、ナッジを始めとする行動科学の知見を適切に活用し、また、普及させることを目的に行っているコンテスト。 - 2 選択アーキテクチャー
行動科学の知見を活用し、人々の行動を望ましい方へ導くための環境設計のこと。設備構造や情報の見せ方を「設計」することで自発的な意思決定を促すところに特徴がある。 - 3 ジャーニーマップ
サービスの受け手が目的を達成するに当たってたどる流れを旅(ジャーニー)のプロセスに見立てて可視化するもの。 - 4 EBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)
政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化した上で合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすること。(出典:内閣府ウェブサイト) - 5 「刑務所における受刑者の就労支援希望の申し出促進策に関する調査・分析」について
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei13_00006.html
- ※21 農福連携
農業と福祉が連携し、障害者等の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者等の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組。 - ※22 農福連携等推進ビジョン
2019年(令和元年)6月に決定されてから5年が経過し、農福連携を取り巻く現状や課題が変化していることを踏まえて見直しが行われ、2024年(令和6年)6月、農福連携等推進会議において、「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」を決定し、新たに2030年度(令和12年度)までの取組目標等が取りまとめられた。