第2節 薬物依存の問題を抱える者への支援等
法務省及び検察庁は、薬物事犯者の再犯を防止するため、刑事施設内における処遇に引き続き、社会内における処遇を実施する刑の一部の執行猶予制度(資3-42-1参照)の適切な運用を図っている。
法務省は、同制度の施行を契機として、刑事施設及び保護観察所における薬物事犯者に対するプログラムについて効果検証※16を実施した。その結果、同プログラムには、再犯防止に一定の処遇効果が認められた。この結果を踏まえ、より効果的かつ一貫性のある指導を実施するため、プログラムの一層の充実に向けた検討を行っている。
刑事施設では、薬物事犯者の再犯防止のための取組として、2019年度(令和元年度)から、薬物依存からの「回復」に焦点を当て、出所後の生活により近い環境下で、社会内においても継続が可能となるプログラムを受講させるとともに、出所後に依存症回復支援施設に帰住等するための支援を行う女子依存症回復支援モデル事業を実施している(資3-42-2参照)。
更生保護官署では、官民一体となった“息の長い”支援を実現するため、薬物依存のある受刑者について、一定の期間、更生保護施設等に居住させた上で、薬物依存症者が地域における支援を自発的に受け続けるための習慣を身に付けられるよう地域の社会資源と連携した濃密な保護観察処遇を実施する取組を行っており、2024年(令和6年)4月現在で、9施設において実施している。
また、法務総合研究所では、2016年度(平成28年度)から、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターと共同で薬物事犯者に関する研究を実施し、覚醒剤事犯で刑事施設に入所した者に対する質問紙調査等から得られた薬物事犯者の特性等に関する基礎的データの分析等を行っている。
厚生労働省は、2019年度から、麻薬取締部に公認心理師等の専門支援員を配置し、麻薬取締部において薬物事犯により検挙された者のうち、保護観察の付かない全部執行猶予判決を受けた薬物初犯者を主な対象として、希望者に対し、「直接的支援(断薬プログラムの提供)」、「間接的支援(地域資源へのパイプ役)」、「家族支援(家族等へのアドバイス)」の三つの支援を柱とする再乱用防止対策事業を実施している。2021年度(令和3年度)からは、法務省と連携し、本事業の対象者を麻薬取締部以外の捜査機関において薬物事犯により検挙され同様の判決を受けた者等にも拡大している。さらに、同連携については、2021年(令和3年)から4地区に限定した上で試行的に行ってきたが、2023年(令和5年)に、試行対象地区を麻薬取締部の拠点である全ての地区(9地区)に拡大した。
また、厚生労働省では、医薬品医療機器制度部会の下に医学・薬学・法学等の専門家、医療関係団体、地方公共団体関係者を構成員とする「大麻規制検討小委員会」を設置し、2022年(令和4年)5月から計4回開催した。同年10月に公表したとりまとめ※17において、薬物乱用者に対する回復支援の対応を推進し、薬物依存症の治療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も充実させるべきとの基本的な方向性が示された。
法務省及び厚生労働省は、2018年度(平成30年度)から「薬物事犯者の再犯防止対策の在り方に関する検討会」を開催しており、2023年度(令和5年度)は同検討会実務担当者会議において、薬物事犯者の再乱用防止に向けた効果的な方策の具体化に向けた検討に着手した。
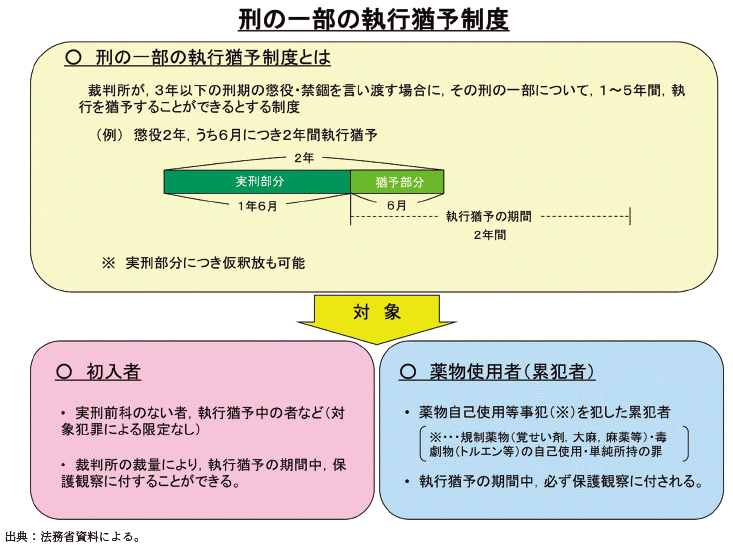
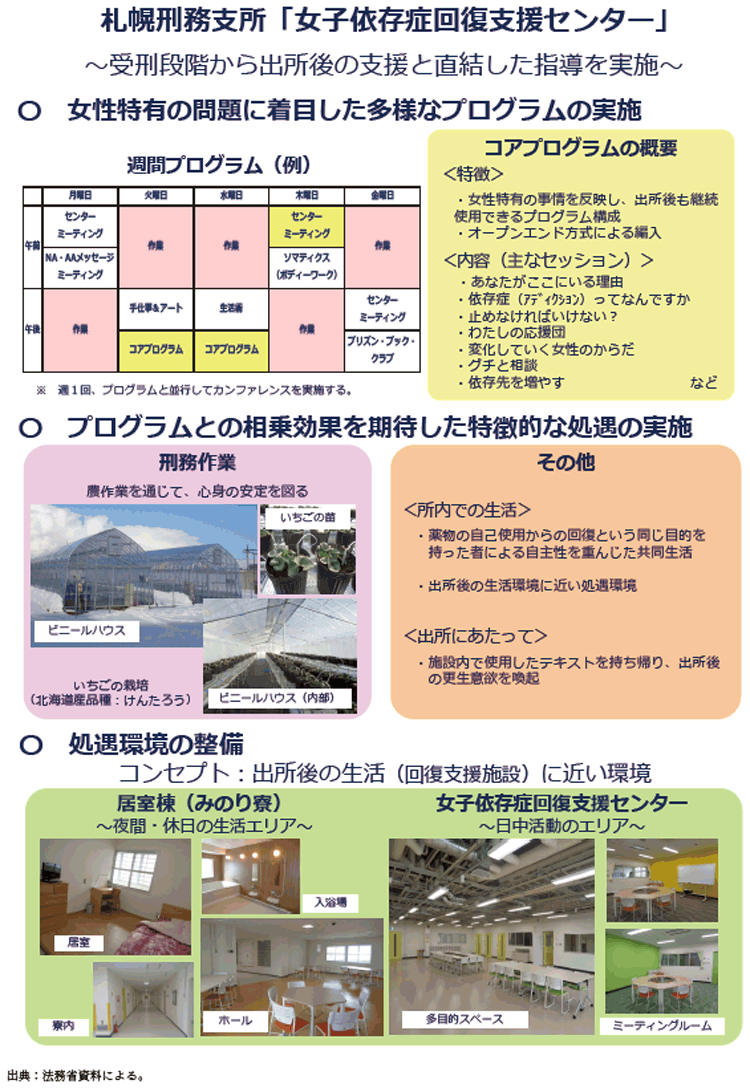
- ※16 刑事施設及び保護観察所における薬物事犯者に対するプログラムの効果検証結果について
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo10_00030.html
- ※17 大麻規制検討小委員会 とりまとめ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25666.html