第2節 薬物依存の問題を抱える者への支援等
(1)薬物依存の問題を抱える者等に対応する専門医療機関等の拡充及びその円滑な利用の促進【施策番号38】
厚生労働省は、薬物依存症を含む依存症対策について、各地域において、医療体制や相談体制の整備を推進するとともに、地域支援ネットワーク構築、依存症全国拠点機関による人材育成・情報発信、依存症の正しい理解の普及啓発等を総合的に推進している(資3-38-1参照)。
また、厚生労働省は、2017年度(平成29年度)から、依存症対策全国拠点機関として独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターを指定している。同センターでは、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターと連携して薬物依存症を含む依存症治療の指導者養成研修を実施するとともに、都道府県及び指定都市の医療従事者を対象とした依存症治療の研修を実施している。
このほか、厚生労働省は、都道府県及び指定都市が薬物依存症の専門医療機関及び治療拠点機関の選定や薬物依存症者への相談・治療等の支援に関わる者(障害福祉サービス事業所や福祉事務所の職員等)を対象とした研修を進めていくに当たり、財政的、技術的支援を行っている。厚生労働省は、毎年全国6ブロック(北海道・東北地区、関東信越地区、東海北陸地区、近畿地区、中国・四国地区、九州・沖縄地区)において、「再乱用防止対策講習会」(【施策番号33】参照)と併せて、「薬物中毒対策連絡会議」を主催しており、2023年度(令和5年度)は山形県、神奈川県、愛知県、福井県、徳島県及び福岡県で開催した。同会議では、薬物依存症治療の専門医のほか、各地方公共団体の薬務担当課・障害福祉担当課・精神保健福祉センター・保健所、保護観察所、矯正施設等の薬物依存症者を支援する地域の関係機関職員が、地域における各機関の薬物依存症対策に関する取組や課題等を共有するとともに、それらの課題に対する方策の検討を行い、関係機関の連携強化を図っている。さらに、厚生労働省は、都道府県及び指定都市において、行政や医療、福祉、司法等の関係機関による連携会議を開催するに当たり、財政的、技術的支援を行っている。同会議では、薬物依存症者やその家族に対する包括的な支援を行うために、地域における薬物依存症に関する情報や課題の共有を行っている。
警察は、「第六次薬物乱用防止五か年戦略」(2023年(令和5年)8月薬物乱用対策推進会議決定。資3-38-2参照)※13等に基づき、各地域において薬物依存症対策を含めた総合的な薬物乱用対策を目的として開催される「薬物乱用対策推進地方本部全国会議」等に参加し、地方公共団体や刑事司法関係機関等と情報交換を行っている。また、相談の機会が必要と認められる薬物乱用者やその家族に向けた再乱用防止のためのパンフレット「相談してみませんか」※14を作成して、全国の精神保健福祉センターや家族会等の相談・支援窓口に関する情報提供を行っている。
法務省及び厚生労働省は、2015年(平成27年)に策定された「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」(資3-38-3参照)に基づき、保護観察所と地方公共団体、保健所、精神保健福祉センター、医療機関その他関係機関とが定期的に連絡会議を開催するなどして、地域における支援体制の構築を図っている(資3-38-4参照)。
法務省は、刑事施設と保護観察所との効果的な連携の在り方について共通の認識を得ることを目的として、「薬物事犯者に対する処遇プログラム等に関する矯正・保護実務者連絡協議会」を開催し、刑事施設及び保護観察所の指導担当職員等が、双方の処遇プログラムの実施状況等の情報を交換している。同協議会では、大学教授や自助グループを含む民間団体等のスタッフを外部機関アドバイザーとして招へいするなどしており、今後も、依存症専門医療機関の医師等を招へいして、薬物依存症者の支援及び関係機関との連携の在り方を検討していくこととしている。
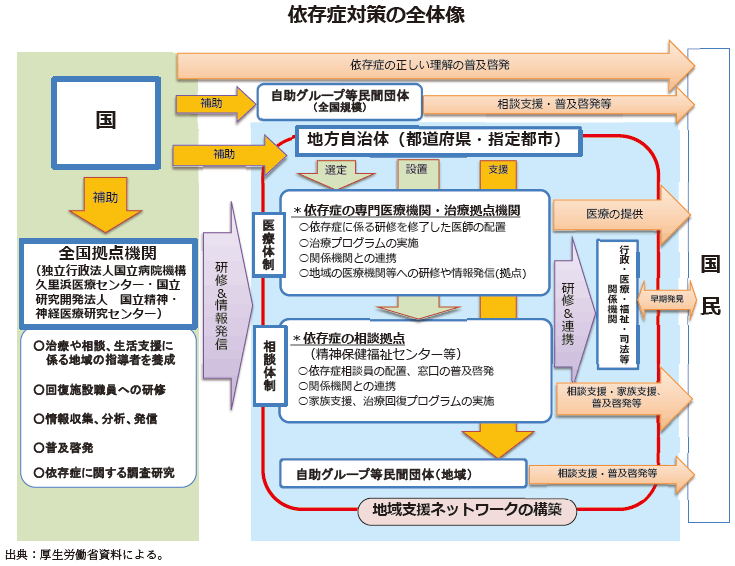
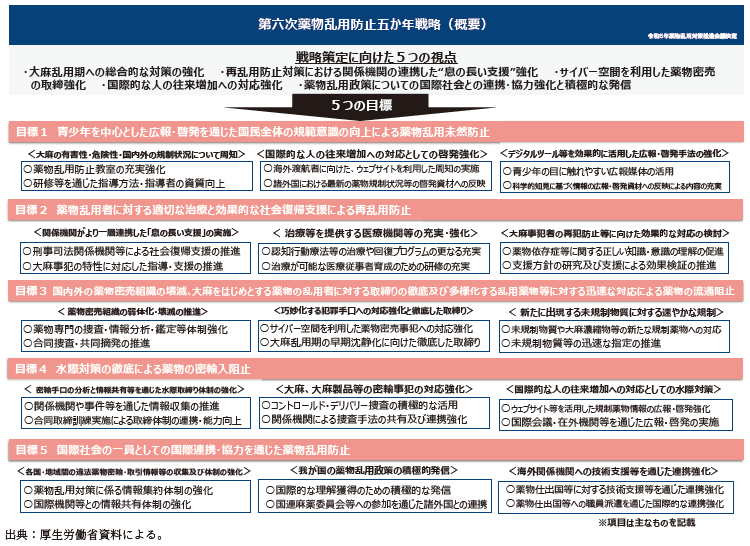
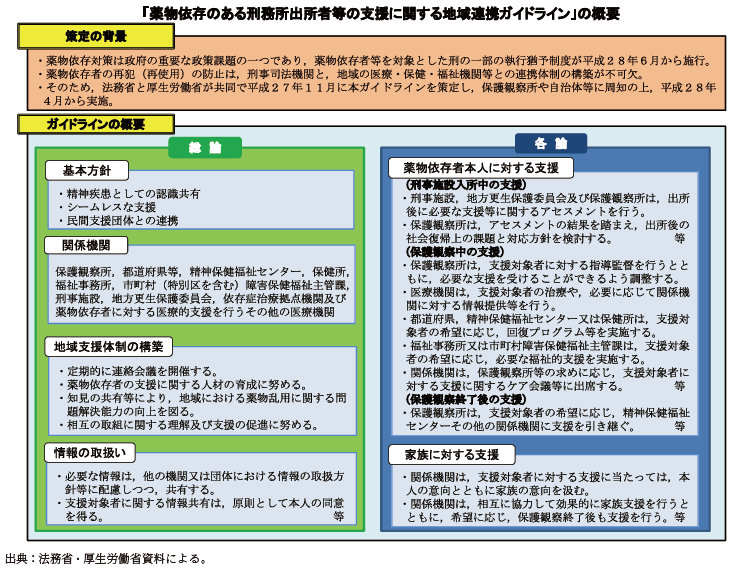
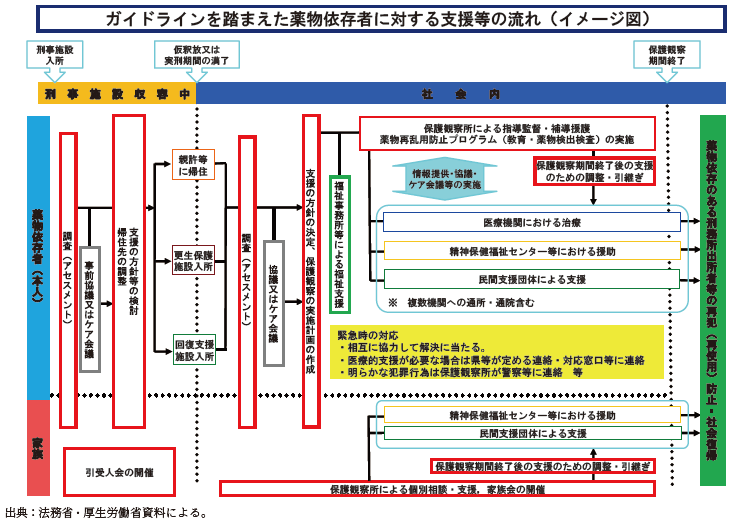
(2)自助グループ等の民間団体と共同した支援の強化【施策番号39】
法務省は、刑事施設において、受刑者に対する薬物依存離脱指導の実施に当たり、自助グループや専門機関関係者等との連携を図ることとしている。少年院においては、在院者に対する薬物非行防止指導の実施に当たり、自助グループや医療関係者等の協力を受けることとしている。
また、保護観察所においては、依存性薬物に対する依存がある保護観察対象者等について、自助グループ等の民間団体等に薬物依存回復訓練を委託して実施している。薬物依存回復訓練では、民間団体等が行う依存性薬物の使用経験のある者のグループミーティングにおいて、依存に至った自己の問題性について理解を深めるとともに、依存の影響を受けた生活習慣等を改善する方法を習得することを内容としている。
さらに、民間団体等が行う専門的な援助であって、法務大臣が定める基準に適合するものを受けることを特別遵守事項として保護観察対象者に義務付ける制度を2023年度(令和5年度)から導入した。これは、保護観察対象者が地域での援助や支援を受けるきっかけを作り、それによって保護観察終了後も継続して民間団体等とつながり、援助や支援を受け続けることができるようにすることを目的としたものである。
厚生労働省は、2017年度(平成29年度)から、地域で薬物依存症に関する問題に取り組む自助グループ等民間団体の活動を地方公共団体が支援する「薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業(地域生活支援促進事業)」を実施しており、2018年度(平成30年度)からは、全国規模で活動する民間団体の活動を支援する「依存症民間団体支援事業」を実施している。
(3)薬物依存症に関する知見を有する医療関係者の育成【施策番号40】
厚生労働省は、2020年度(令和2年度)からの医師臨床研修制度において、精神科研修を必修化するとともに、経験すべき疾病・病態の一つとして「依存症(ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博)」を位置付けたところであり、引き続き臨床研修を推進する。
(4)薬物依存症に関する知見を有する福祉専門職や心理専門職等の育成【施策番号41】
精神保健福祉士及び社会福祉士は、薬物依存症に関する知識を身に付けることで、薬物依存症者が地域で生活するために必要な支援ニーズを把握し、関係機関へつなげるなどの相談援助を実施している。
厚生労働省は、薬物依存を始めとする各依存症について教育内容を充実させるため、精神保健福祉士及び社会福祉士の養成カリキュラムの見直しを行い、2021年(令和3年)4月入学者から、複数の科目において、心理面や社会問題、地域生活課題といった視点で依存症を学ぶこととしている。
公認心理師※15は、薬物依存症の回復支援において、アセスメントや依存症集団療法等の専門的支援等、心理的側面から助言、指導その他の援助等を行っている。
公認心理師試験の出題基準には、「依存症(薬物、アルコール、ギャンブル)」の項目等が組み込まれている。また、厚生労働省は公認心理師の養成カリキュラムにおいて、公認心理師となるために必要な科目として、「健康・医療心理学」、「精神疾患とその治療」、「保健医療分野に関する理論と支援の展開」等の科目を規定している。大学等によっては、それらの科目の中で薬物依存症を取り上げている。
- ※13 第六次薬物乱用防止五か年戦略
2023年(令和5年)8月8日、薬物乱用対策推進会議において、令和10年8月までの取組事項等を取りまとめた「第六次薬物乱用防止五か年戦略」が決定された。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubutsuranyou_taisaku/index.html
- ※14 再乱用防止のためのパンフレット「相談してみませんか」
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubutujyuki/yakubutu/soudanshitemimasenka.pdf
- ※15 公認心理師
心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する相談、援助等の業務に従事する者。平成27年に成立した公認心理師法(平成27年法律第68号)に基づく国家資格であり、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働等の様々な分野で活躍している。