第1節 持続可能な保護司制度の確立とそのための保護司に対する支援
第6章 民間協力者の活動の促進等のための取組
第1節 持続可能な保護司制度の確立とそのための保護司に対する支援
1 持続可能な保護司制度の確立に向けた検討・試行【施策番号64】
1950年(昭和25年)の保護司法(昭和25年法律第204号)制定により、現在の保護司制度の骨格が作られてから、保護司※1は、罪を犯した人や非行のある少年たちの立ち直りを支援する処遇活動を行うとともに、広報啓発や犯罪予防などの地域活動にも積極的に取り組んできた。しかし、近年、保護司の担い手確保が次第に困難となり、高齢化が進んでいることが課題となっている。
こうした状況を踏まえ、第二次計画においては、「持続可能な保護司制度の確立に向けた検討・試行」を行うこととされ、2023年(令和5年)5月、法務省に「持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会」(以下「検討会」という。)を設置し、所要の検討を進め、2024年(令和6年)3月に中間取りまとめを行った(資6-64-1参照)。
資6-64-1 持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会(中間取りまとめ概要)
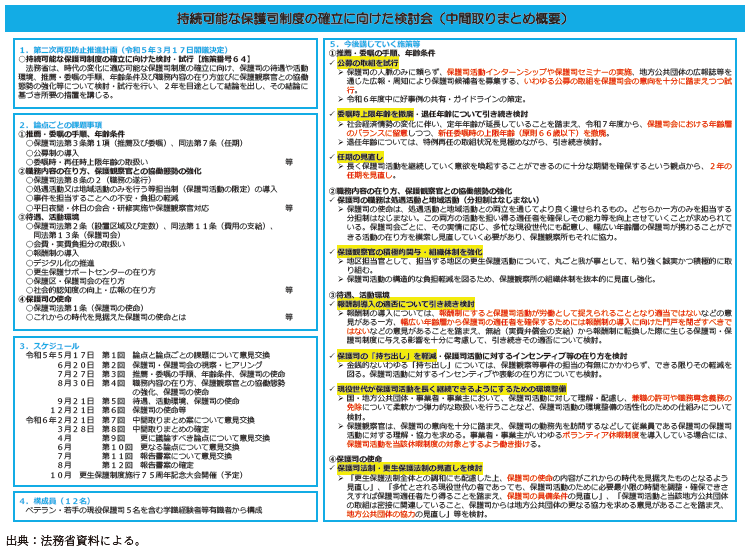
また、2024年5月、滋賀県大津市の保護司が自宅において殺害され、同保護司が担当していた保護観察対象者が殺人容疑で逮捕される事案が生じたことを受けて、法務省においては、保護司の不安等の聴取や活動環境等の調査を実施するとともに、保護司の不安解消・安全確保に関する対策として、担当保護司の複数指名※2の積極的運用、保護観察官による直接指導等の直接関与の強化、自宅以外の面接場所の確保等の取組を実施しており、検討会においても保護司の安全確保について議論が行われた。
- ※1 保護司
犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアである。その身分は法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員であり、保護観察の実施、犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行っている。保護司の定数は、保護司法(昭和25年法律第204号)により5万2,500人を超えないものと定められている。 - ※2 担当保護司の複数指名
保護観察所においては、保護観察及び生活環境の調整を行うに当たり、保護観察官及び保護司の協働態勢を基本としているところ、保護観察又は生活環境の調整の実施上必要な場合には、複数の保護司で事件を担当する複数担当制を導入している。2023年度(令和5年度)は、保護観察で1,211件(前年度:1,319件)、生活環境の調整で926件(前年度:993件)の複数担当を実施した。