第1節 特性に応じた効果的な指導の実施等
法務省は、刑事施設において、罪の大きさや犯罪被害者等の心情等を認識させるとともに、犯罪被害者等に誠意を持って対応するための方法を考えさせるため、特別改善指導(【施策番号62】参照)として被害者の視点を取り入れた教育(資5-63-1参照)を実施している(2023年度(令和5年度)の受講開始人員は481人(前年度:530人)であった)。
少年院では、全在院者に対し、被害者心情理解指導を実施している。また、特に被害者を死亡させ、又は被害者の心身に重大な影響を与えた事件を起こし、犯罪被害者や遺族に対する謝罪等について考える必要がある者に対しては、特定生活指導として、被害者の視点を取り入れた教育(資5-63-2参照)を実施しており、2023年度は、45人(前年度:41人)が修了した。これらの指導の結果は、継続的な指導の実施に向け、保護観察所に引き継いでいる。
また、刑事施設及び少年院では、受刑者・在院者の矯正処遇等に被害者や御遺族の心情等をより直接的に反映し、被害者等の立場や心情への配慮等を一層充実させるとともに、受刑者等に反省や悔悟の情を深めさせ、その改善更生を効果的に図ることを目的として、2023年(令和5年)12月1日から、刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度の運用を開始した。
保護観察所では、犯罪被害者等の申出に応じて犯罪被害者等から被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況等を聴取し、保護観察対象者に伝達する制度(心情等聴取・伝達制度)において、当該対象者に被害の実情を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるための指導監督を徹底している(2023年中に、心情等を伝達した件数は154件(前年:170件))。
なお、本制度は刑法等の一部を改正する法律による改正後の更生保護法が2023年12月から施行されたことに伴い、犯罪被害者等からの申出に応じて、保護観察対象者に伝達する場合に限らず犯罪被害者等の心情等を聴取することができることとされ、聴取した心情等を保護観察における指導監督を行うに当たって考慮するなど、その適正な運用を図っている。
また、上記の改正更生保護法において、犯罪被害者等の被害の回復又は軽減に誠実に努めるよう、必要な指示等の措置をとることが保護観察対象者に対する指導監督の方法として加えられ、また、犯罪被害者等の被害を回復し、又は軽減するためにとった行動の状況を示す事実について、保護観察官又は保護司に申告し又は当該事実に関する資料を提示することが、保護観察における遵守事項の類型に加えられたことから、これらに基づく指導監督の充実を図るなど、犯罪被害者等の思いに応える保護観察処遇の一層の充実を図っている。なお、特に被害者を死亡させ若しくはその身体に重大な傷害を負わせた事件又は被害者に重大な財産的損失を与えた事件による保護観察対象者に対しては、しょく罪指導プログラム(資5-63-3参照)による処遇を行い、犯罪被害者等の意向にも配慮して、誠実に慰謝等の措置に努めるよう指導している(2023年に、しょく罪指導プログラムの実施が終了した人員は1,502人(前年:373人))。
なお、矯正施設及び保護観察所では、家庭裁判所や検察庁等から送付される処遇上の参考事項調査票等に記載されている犯罪被害者等の心情等の情報を指導に活用している。
加えて、一定の条件に該当する保護観察対象者を日本司法支援センター(法テラス)※19に紹介し、被害弁償等を行うための法律相談を受けさせ、又は弁護士、司法書士等を利用して犯罪被害者等との示談交渉を行うなどの法的支援を受けさせており、保護観察対象者が、犯罪被害者等の意向に配慮しながら、被害弁償等を実行するよう指導・助言を行っている。
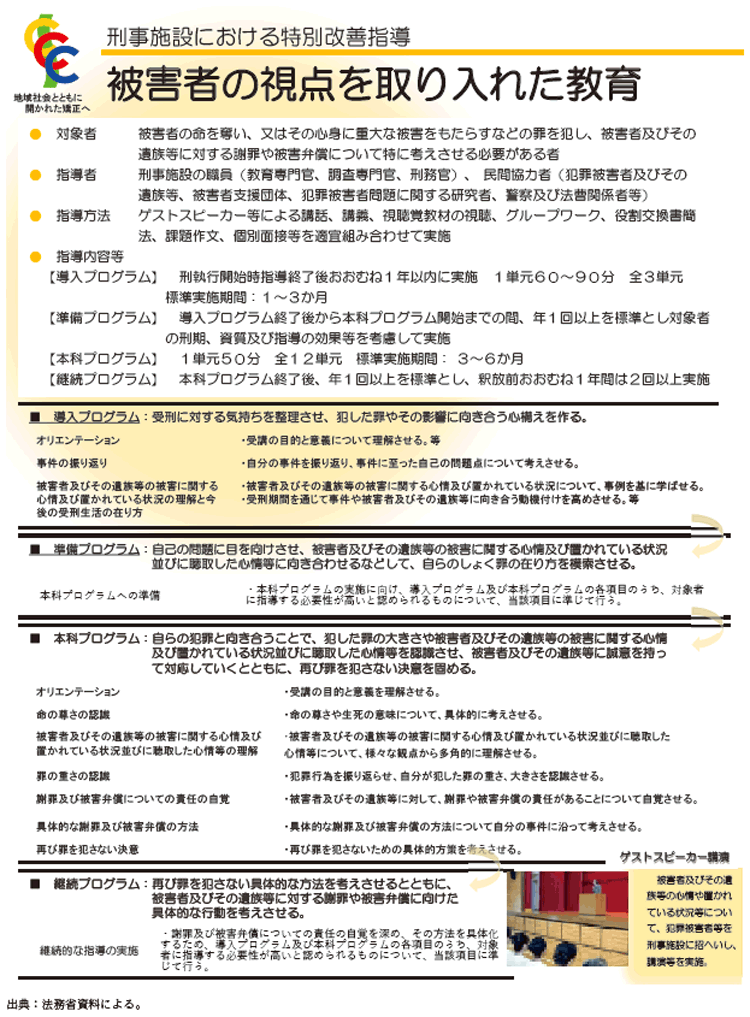
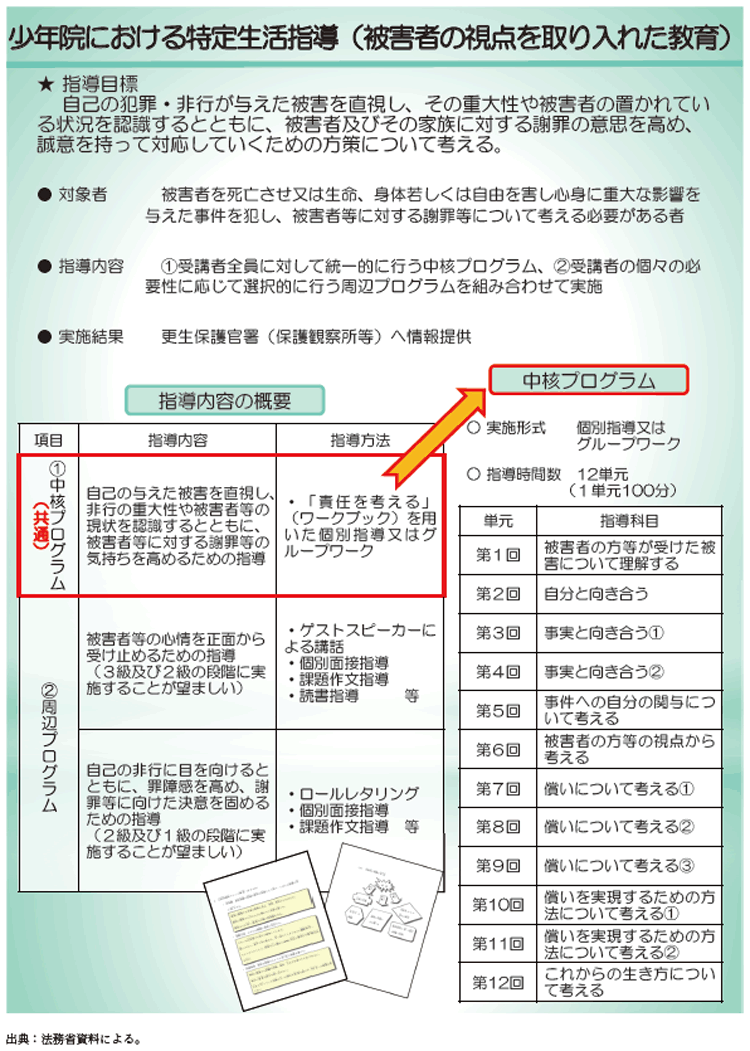
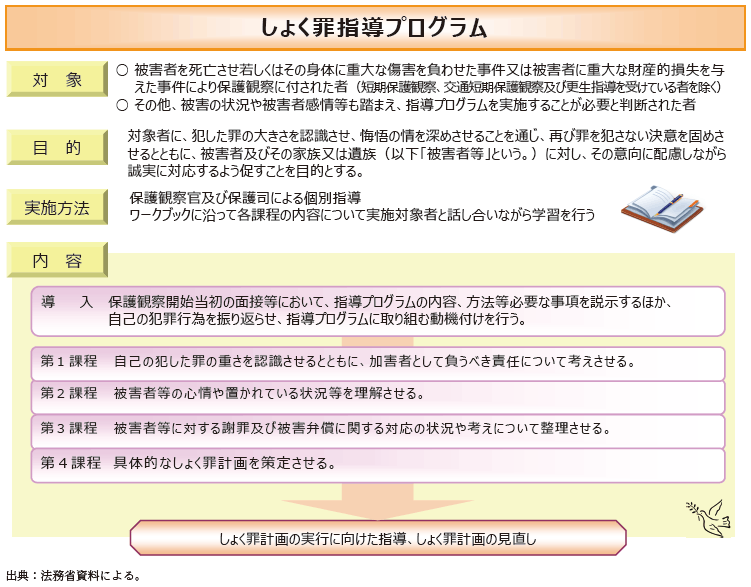
札幌刑務所における精神障害受刑者処遇・社会復帰支援モデル事業について
札幌刑務所
札幌刑務所は、主に犯罪傾向の進んだ男子受刑者を収容する刑事施設であり、札幌矯正管区管内の「医療重点施設」として、精神又は身体に疾病や障害を有する受刑者の治療を行っているほか、「調査センター」として、高度な専門的知識及び技術を活用して受刑者の資質及び環境に関する科学的調査を行うなど、管内刑事施設の基幹となる施設です。
2021年(令和3年)4月に当所敷地内に北海道大学病院附属司法精神医療センター(医療観察法指定入院医療機関)が開設され、当所では、同センターで実施するプログラムなど、精神医療に関する知見を得ることが可能になったこともあり、2023年度(令和5年度)から、「精神障害受刑者処遇・社会復帰支援モデル事業」を実施することとなりました。
2022年(令和4年)の新受刑者のうち、精神障害(知的障害を含む。)を有すると診断された受刑者は、2,435名(新受刑者総数の約17%)であり、うち、入所回数が2回以上の者は、66.9%に上っており、診断のない受刑者のその割合(54.5%)と比較すると、再入所者の占める割合が高い状況となっています。これまでも刑事施設においては、精神障害を有する受刑者に対し、出所後に保健医療・福祉サービス等の必要な支援につなげ、地域生活への定着を図るための取組を進めてきたものの、受刑者本人が、自らの精神障害や各種支援について正しく理解していないなどの理由により、支援を拒むケースも少なくありません。2016年(平成28年)に取りまとめられた法務総合研究所研究部報告56※によると、出所後に各種支援を利用しなかった者は、利用した者に比べて短期間での再犯の割合が高くなる状況にあることも指摘されており、障害受容や福祉的支援等への理解促進を含め、精神障害を有する受刑者への再犯防止に向けた処遇・支援の充実は大きな課題となっています。
本モデル事業においては、適切な精神科治療と障害特性に応じた処遇を実施しつつ、対象者の障害受容を促し、各種支援の必要性を十分に理解できるよう働き掛けを行った上で、
① 保健医療サービスの利用に係る調整
② 福祉サービス等の受給に必要な精神障害者保健福祉手帳の取得に向けた調整
③ 個々の稼働能力や就業意欲、障害の程度に応じた就労支援の実施
④ 保健医療・福祉関係機関、地方公共団体等が連携した在所中から出所後までの息の長い支援を実現するための社会復帰に係る調整
を包括的に実施しています。具体的には、刑務官のほか、刑事施設に勤務する医師、看護師、作業療法士、調査専門官、教育専門官、福祉専門官等の多職種が連携して、個々の受刑者の特性に応じて、指導・支援方法をケース会議等で検討しながら処遇することで、精神障害を有する受刑者が、出所後に必要な医療・福祉支援を活用しながら自立した地域生活を送ることを目指しています。
本モデル事業の実施に当たり、2024年(令和6年)4月22日、地方公共団体や外部協力機関の多数の関係者の御臨席の下、北海道大学病院附属司法精神医療センター、法務省矯正局、矯正研修所及び札幌刑務所の間で、連携協力して、相互に有する資源、研究等の効果的な活用を図りながら、精神障害を有する受刑者の再犯防止及び円滑な社会復帰に寄与することを目的とした協定を締結しました。こうした関係機関との連携を強みとして、多職種・多機関連携によるチーム処遇を実施しつつ、精神障害を有する受刑者の再犯防止に向けた取組を一歩ずつ着実に進めてまいります。
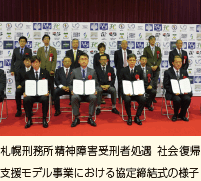
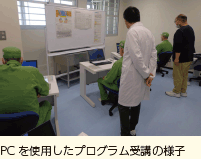
- ※ 法務総合研究所研究部報告56「高齢者及び精神障害のある者の犯罪と処遇に関する研究」
https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00091.html
- ※19 日本司法支援センター(法テラス)
国により設立された、法による紛争解決に必要な情報やサービスを提供する公的な法人