第1節 特性に応じた効果的な指導の実施等
(1)性犯罪者・性非行少年に対する指導等
ア 性犯罪者等に対する効果的な指導等の実施【施策番号51】
法務省は、刑事施設において、特別改善指導(【施策番号62】参照)として、認知行動療法に基づくグループワークによる性犯罪再犯防止指導(資5-51-1参照)を実施し、性犯罪につながる自己の問題性を認識させるとともに、再犯に至らないための具体的な対処方法を考えさせたり、習得させたりするなどしている(2023年度(令和5年度)の受講開始人員は526人(前年度:553人))。
同指導では、知的能力に制約がある者を対象とした「調整プログラム※7」や、刑期が短いこと等により受講期間を十分確保できない者を対象とした「集中プログラム※8」を開発し、指導の充実を図っている。また、同指導については、2019年度(令和元年度)に効果検証の結果を公表しており、プログラム受講群の方が、非受講群よりも再犯率が10.7ポイント低いことが示され、一定の再犯抑止効果が認められた。2022年度(令和4年度)からは、対象者の達成したい目標や強みをより一層活用するとともに、特定の問題性や特性を有する者にも対応した内容にプログラムを改訂するなど、刑事施設収容中から出所後までの一貫性のある効果的な指導の充実を図っている。さらに、グループワーク指導担当者が効果的な指導を行うことができるよう、集合研修の充実、指導担当者による事例検討会の定期的な開催、外部の専門家による指導担当者への助言等による指導者育成を行っている。
少年院では、不同意性交等、不同意わいせつや痴漢といった性犯罪や、例えば、下着の窃盗等、性的な動機により非行をした在院者に対し、特定生活指導として性非行防止指導(資5-51-2参照)を実施しており、2023年度は、132人(前年度:122人)が修了した。また、男子少年院2庁(北海少年院及び福岡少年院)が重点指導施設として指定されており、他の少年院から在院者を一定期間受け入れ、認知行動療法等の技法に通じた外部の専門家等の協力を得て、グループワークを中心とした指導を行うなど、実施施設の中でも特に重点的かつ集中的な指導を実施している。2023年度は、20人(前年度:21人)が同指導を修了した。これらの指導の結果は、少年院仮退院後の継続的な指導の実施に向け、保護観察所に引き継いでいる。
保護観察所では、自己の性的欲求を満たすことを目的とした犯罪行為を繰り返すなどの問題傾向を有する保護観察対象者に対して、その問題性を改善するため、認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラムを実施してきた。2019年度に実施した効果検証の結果においては、プログラム受講群の方が非受講群よりも性犯罪の再犯率が11.1ポイント低く、一定の再犯抑止効果が示唆された。2022年度からは、対象者の達成したい目標や強みをより一層活用することや性的な興味関心・問題への対処状況の継続的な点検等を目的として、従前のプログラムの改訂を行い、性犯罪再犯防止プログラム(資5-51-3)を実施している。2023年度のプログラム受講者数は846人(昨年度:792人)であった。
なお、2022年度以降の刑事施設及び保護観察所における性犯罪者等に対する専門的処遇の具体的な運用等については「刑事施設及び保護観察所の連携を強化した性犯罪者に対する処遇プログラムの改訂について(令和4年度~)」※9を参照。
また、法務省では、2023年(令和5年)に、地方公共団体が利用可能な支援ツールとして、「性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライン~再犯防止プログラムの活用~※10」を策定し、各都道府県等に提供した。法務省としては、各都道府県等に対し、引き続き、その活用を働き掛けるとともに、保護観察所において、同ガイドラインの活用に当たっての相談や問合せ等に対応することによって、同ガイドラインが活用されるよう、支援を行っていくこととしている。
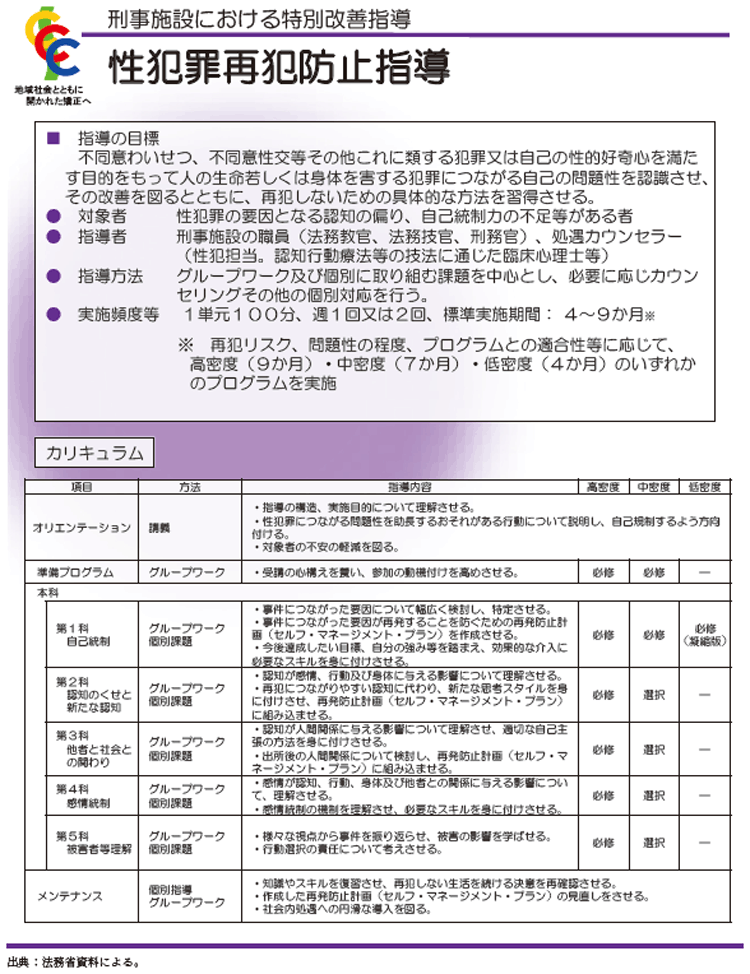
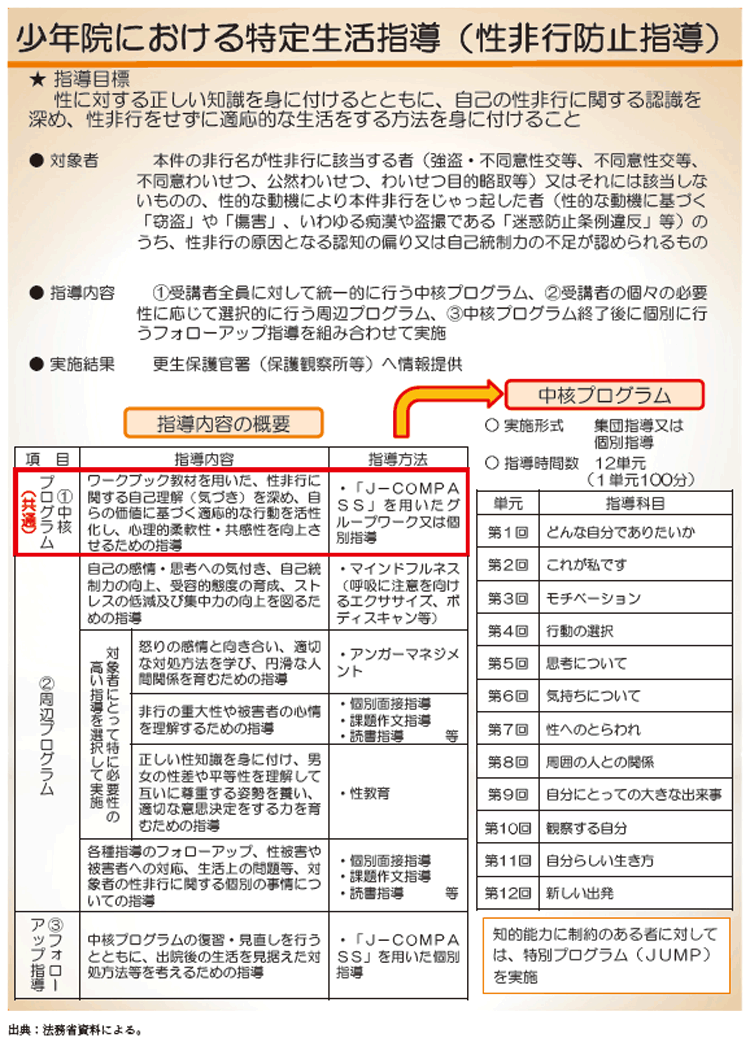
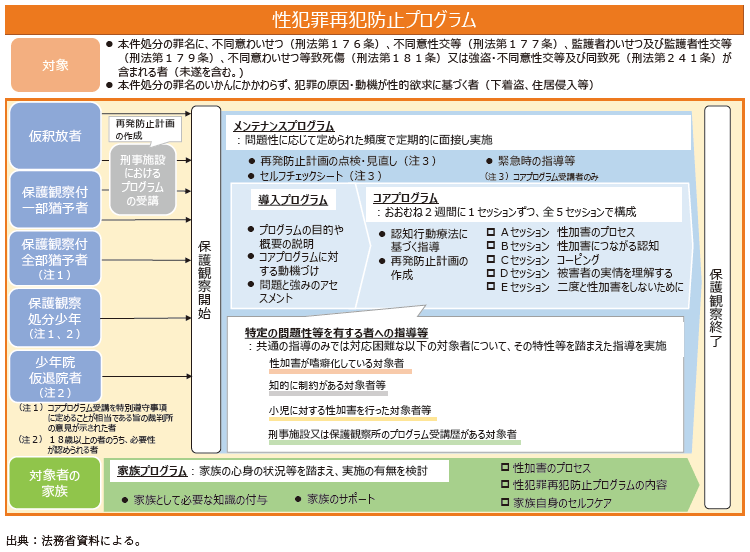
イ 子供を対象とする暴力的性犯罪をした者の再犯防止【施策番号52】
警察は、16歳未満のこどもに対して不同意わいせつ等の暴力的性犯罪をした刑事施設出所者について、法務省から情報提供を受け、各都道府県警察において、当該出所者と連絡を取り、同意を得て面談を行うなど、再犯防止に向けた措置を講じている※11。
(2)ストーカー・DV加害者に対する指導等
ア 被害者への接触防止のための措置【施策番号53】
警察及び法務省は、2013年度(平成25年度)から、ストーカーやDV事案等の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について、被害者等に接触しようとしているなどの問題行動等の情報を共有するなど、緊密かつ継続的な連携によって、こうした者の特異動向等を双方で迅速に把握することができるようにしている。
また、保護観察所では、警察から得た情報等を基にして、必要に応じ再加害を防止するための指導を徹底するなどしており、遵守事項※12違反の事実が確認されたときは、仮釈放の取消しの申出又は刑の執行猶予の言渡しの取消しの申出を行うなど、ストーカー・DV加害者に対する適切な措置を実施している。
イ ストーカー加害者等に対するカウンセリング等【施策番号54】
警察は、加害者への対応方法や治療・カウンセリングの必要性について精神科医等の助言を受け、加害者に治療・カウンセリングの受診を勧めるなど、地域の精神科医療機関等との連携を推進している。また、ストーカー加害者への対応を担当する警察職員に、精神医学的・心理学的アプローチに関する技能や知識の向上に係る研修を受講させている。
さらに、2024年(令和6年)3月から、ストーカー行為の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく禁止命令等を受けた加害者全員を対象として、電話連絡や面談による近況等の把握を通じ、その都度、加害者の再犯性や報復のおそれの有無等についてのリスク評価を行うとともに、被害者に講ずべき保護措置の見直しを行うなど、被害者の安全の確保をより確実なものとするための取組を推進している。
また、法務省では、DV加害者である保護観察対象者について、保護観察所における類型別処遇(【施策番号62】参照)に基づき、その処遇指針である「類型別処遇ガイドライン」を踏まえた処遇を行っている。具体的には、DV加害者である保護観察対象者を「配偶者暴力」類型に認定した上、DVのきっかけ、被害者との関係、DVに結び付きやすい考え方等に焦点を当てるなどし、その特性を踏まえた処遇を実施している。
(3)暴力団からの離脱、社会復帰に向けた指導等【施策番号55】
法務省は、刑事施設において、警察、弁護士等と協力しながら、暴力団の反社会性を認識させる指導を行い、離脱意志の醸成を図るため、特別改善指導(【施策番号62】参照)として暴力団離脱指導(資5-55-1参照)を実施している(2023年度(令和5年度)の受講開始人員は408人(前年度:374人)であった。)。
また、保護観察所では、暴力団関係者の暴力団からの離脱に向けた働き掛けを充実させるため、警察、暴力追放運動推進センター※13及び矯正施設との連携を強化しており、暴力団関係者の離脱の意志等の情報を把握・共有して必要な指導等を行っている。
さらに、警察及び暴力追放運動推進センターでは、矯正施設及び保護観察所と連携し、離脱に係る情報を適切に共有するとともに、矯正施設に職員が出向いて、暴力団員の離脱意志を喚起するための講演を実施するなど暴力団離脱に向けた働き掛けを行っている(同働き掛けによる暴力団離脱人員については、資5-55-2参照)。
警察は、暴力団からの離脱及び暴力団離脱者の社会復帰・定着を促進するため、都道府県単位で、警察のほか、暴力追放運動推進センター、職業安定機関、矯正施設、保護観察所、協賛企業等で構成される社会復帰対策協議会の枠組みを活用するなどして、就労や預貯金口座の開設を支援するなど暴力団離脱者のための安定した雇用の場を確保し、社会復帰の促進に取り組んでいる。
金融庁は、業界団体に対し、口座開設に係る反社会的勢力の排除に向けた取組は、口座の利用が個人の日常生活に必要な範囲内であるなど、反社会的勢力を不当に利するものではないと合理的に判断される場合にまで、一律に排除を求める趣旨のものではないことの周知を依頼するとともに、警察が行う預貯金口座の開設支援の内容及びその趣旨の周知も依頼している。
(なお、2024年(令和6年)4月からは、法務省と金融庁が連携して、現に協力雇用主の下で就労し、社会復帰を目指し努力している保護観察対象者等について、金融機関に対して、過去の前歴等だけでなく現在の状況も踏まえた口座開設の判断がなされるよう、保護観察所から金融機関への保護観察等に係る事項や就労状況等の情報提供を行うことを推進している。)
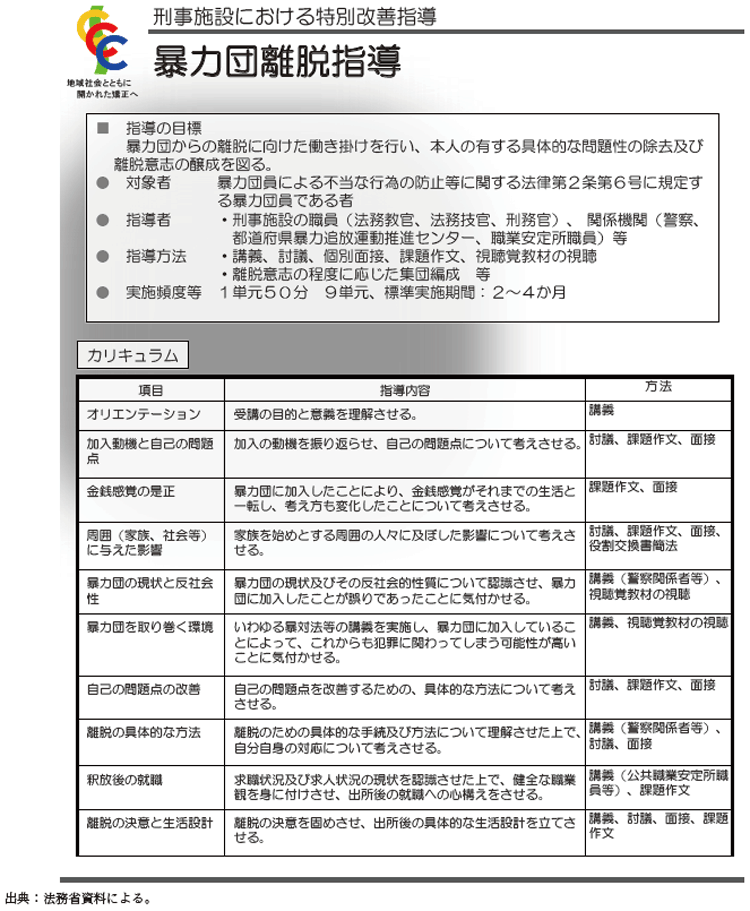
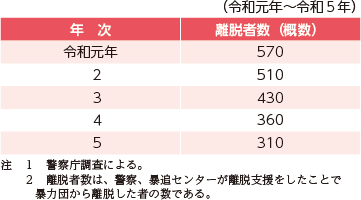
(4)少年・若年者に対する可塑性に着目した指導等
ア 刑事司法関係機関における指導体制の充実【施策番号56】
法務省は、少年院において、適正な処遇(資5-56-1参照)を展開するため、生活の場である集団寮における指導を複数職員で行う体制の充実を図っている(2023年度(令和5年度)は、22庁(前年度:21庁)で複数指導体制を実施)。
少年鑑別所においては、在所者の自主性を尊重しつつ、職員が相談に応じたり助言を行ったりしている。また、在所者の情操を豊かにし、健全な社会生活を営むために必要な知識及び能力を向上させることができるよう、地域の関係機関や民間ボランティア等の協力を得ながら、在所者に対して、学習、文化活動その他の活動の機会を与えている。
また、2020年(令和2年)10月の法制審議会諮問第103号に対する答申において、若年受刑者を対象とする処遇内容の充実が求められた。具体的には、刑事施設において、少年院の知見・施設を活用して、若年受刑者(おおむね26歳未満の受刑者)の特性に応じた処遇の充実を図ることとされ、①少年院における矯正教育の手法やノウハウ等を活用した処遇を行うこと、②特に手厚い処遇が必要な者について、少年院と同様の建物・設備を備えた施設に収容し、社会生活に必要な生活習慣、生活技術、対人関係等を習得させるための指導を中心とした処遇を行うことが求められた。
これを踏まえ、①については、川越少年刑務所及び美祢社会復帰促進センターにおいて、若年受刑者のうち、犯罪傾向が進んでいない者を収容し、小集団のユニットで共同生活を送らせることにより、基本的な生活能力、対人関係スキル等の向上を図り、受刑者と職員間の対話を通じた信頼関係に基づく処遇を行う「若年受刑者ユニット型処遇」を2022年度(令和4年度)から実施している。
また、②については、少年院であった「市原学園」を刑事施設に転用した「市原青年矯正センター」(資5-56-2参照)において、知的障害等を有し、特に手厚い処遇が必要な若年受刑者を収容の上、社会生活に必要な生活習慣、生活技術、対人関係等を習得させるための指導を中心として行う「少年院転用型処遇」を2023年度から実施している。
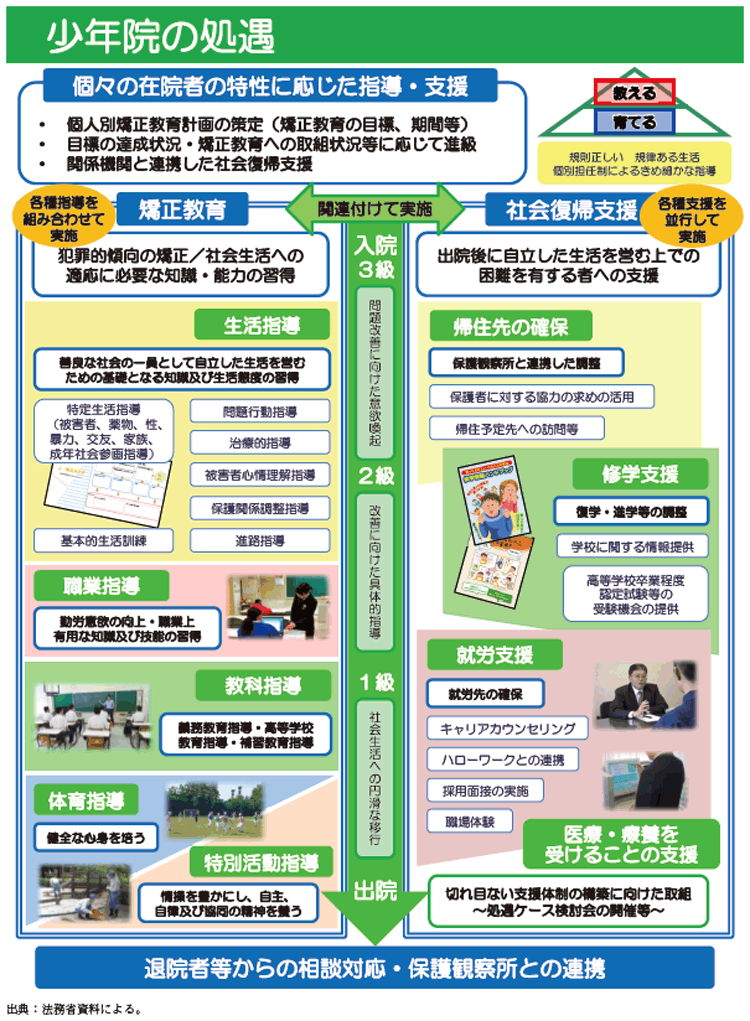
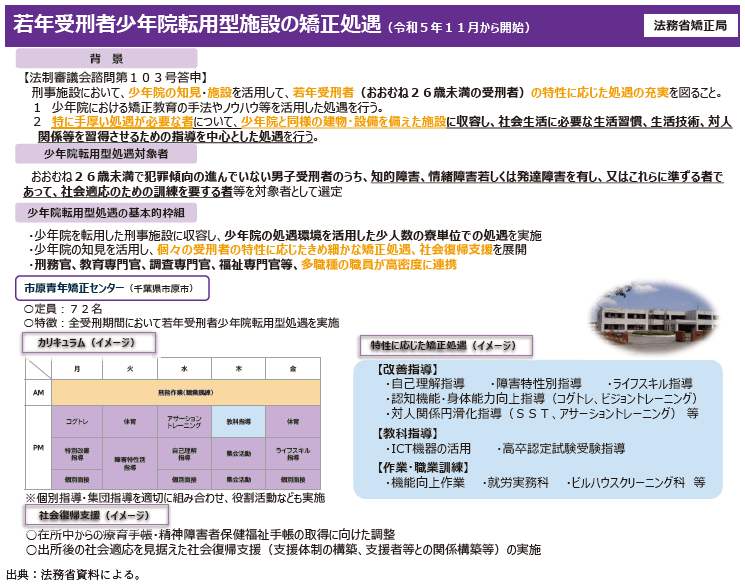
イ 関係機関と連携したきめ細かな支援等【施策番号57】
法務省は、少年院において、家庭裁判所や保護観察所、少年鑑別所、児童相談所等の関係機関の担当者が一堂に会して、少年院在院者を対象とした処遇ケース検討会を実施し、処遇の一層の充実を図るとともに、関係機関との実質的な連携・協力体制を強化している(2023年度(令和5年度)は、全少年院において、合計253回(前年度:224回)の処遇ケース検討会を実施)。
少年鑑別所(法務少年支援センター)では、地域援助を通じて、地域における関係機関との連携に係るネットワークの構築に努めている。児童相談所や児童福祉施設、福祉事務所等を含む福祉・保健機関からの心理相談等の依頼が多く寄せられており、依頼内容も、問題行動への対応や、その背景に知的な問題や発達障害等が疑われる者への支援等、幅広いものとなっている。2023年(令和5年)におけるこれら福祉・保健機関等からの心理相談等の依頼件数は、2,704件(前年:2,479件)であった。また、少年鑑別所(法務少年支援センター)が、所在する地域の警察と少年の立ち直り支援活動に関する協定書を結ぶなど、都道府県警察少年サポートセンター等との連携を強化している。そのほか、2020年度(令和2年度)から、法務省児童虐待対策強化プランに基づき、全国の少年鑑別所(法務少年支援センター)が、法務省の児童虐待担当窓口の一つとして位置付けられたことを踏まえ、児童相談所等関係機関とより一層緊密に連携し、児童虐待の早期発見・早期対応に協力できる体制の維持・構築を推進している。
保護観察所では、被虐待経験や、心身の障害を有するなどして何らかの支援を必要とする保護観察対象者について、児童相談所等の関係機関の担当者との情報共有や協議を行うなど、必要に応じて関係機関との連携を行い、きめ細かな支援等を実施している。
ウ 非行少年に対する立ち直り支援活動の充実【施策番号58】
警察は、非行少年を生まない社会づくり(【資5-58-1】参照)の一環として、少年サポートセンターが主体となって、少年警察ボランティア(【施策番号44】参照)や、少年と年齢が近く少年の心情や行動を理解しやすい大学生ボランティア、関係機関と連携して、非行少年の立ち直りを支援する活動に取り組んでいる。この活動では、個々の少年の状況に応じて指導・助言を実施しているほか、周囲の人々とのつながりの中で少年に自己肯定感や達成感を感じさせ、また、他人から感謝される体験を通じてきずなを実感させることを目的として、社会奉仕体験活動、農業体験等の生産体験活動、スポーツ活動等への参加の促進を図っている。
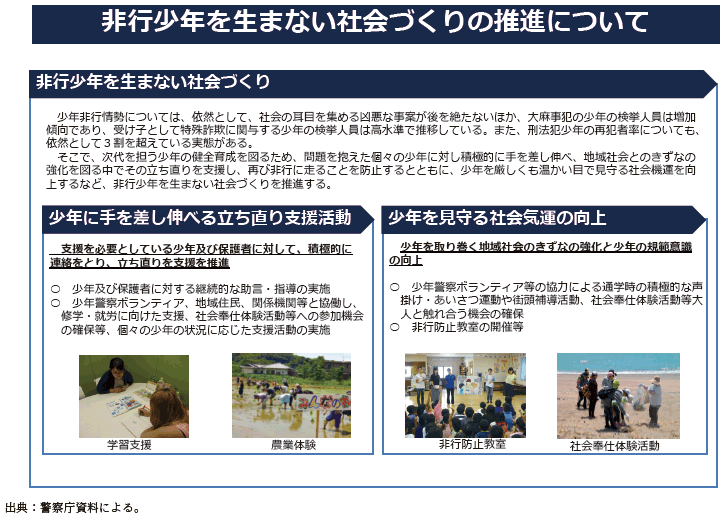
エ 保護者との関係を踏まえた指導等の充実【施策番号59】
法務省は、少年院において、在院者とその保護者との関係改善や在院者の処遇に対する保護者の理解・協力の促進、保護者の監護能力の向上等を図るため、保護者に対して、「保護者ハンドブック」の提供や面接等を実施するとともに、在院者が受ける矯正教育を共に体験してもらう保護者参加型プログラムを実施している(【施策番号18】参照)。
保護観察所では、保護観察対象少年に対し、保護者との関係改善に向けた指導・支援を行うとともに、保護者に対する措置として、対象者の処遇に対する理解・協力の促進や保護者の監護能力の向上を図るための指導・助言を行っている。具体的には、「保護者のためのハンドブック」※14の提供や、講習会、保護者会を実施しており、2023年度(令和5年度)の保護者会等の実施回数は34回(前年度:36回)であった。また、保護者による適切な監護が得られない場合には、児童相談所等の関係機関や民間団体等と連携し、本人の状況に応じて、社会での自立した生活に向けた指導・支援を行っている。
(5)女性の抱える困難に応じた指導等【施策番号60】
法務省は、全国の女性刑事施設12庁のうち、PFI手法を活用した刑事施設※15である美祢社会復帰促進センター及び公共サービス改革法を活用した刑事施設※15である喜連川社会復帰促進センター以外の10庁の女性刑事施設において、女性受刑者特有の問題に対処するため、看護師、助産師、介護福祉士等、医療・福祉等の地域の専門家の協力・支援を得て、女性受刑者に対する助言・指導や職員に対する研修等を行う、「女子施設地域連携事業」を実施している。さらに、医療専門施設である東日本成人矯正医療センター、西日本成人矯正医療センター(2024年(令和6年)3月までは大阪医療刑務所)及び北九州医療刑務所に臨床心理士を配置し、全国の摂食障害女性受刑者を収容することで、より効果的な治療が受けられる体制の整備を行っており、全国の女性刑事施設に収容中の摂食障害女性受刑者を当該医療専門施設に移送し、治療を実施している。
少年院では、女子の少年院入院者の多くが虐待等の被害体験や性被害による心的外傷等の精神的な問題を抱えていることを踏まえ、2016年度(平成28年度)から、女子少年院在院者の特性に配慮した処遇プログラム(資5-60-1参照)を試行しつつ、同プログラムの効果検証を進め、2022年度(令和4年度)から本格的な運用を開始した。
さらに、地域社会の中でも女性の特性に配慮した指導・支援を推進するため、2017年度(平成29年度)から、女性や女子少年を受け入れる各更生保護施設の職員を1人増配置している。
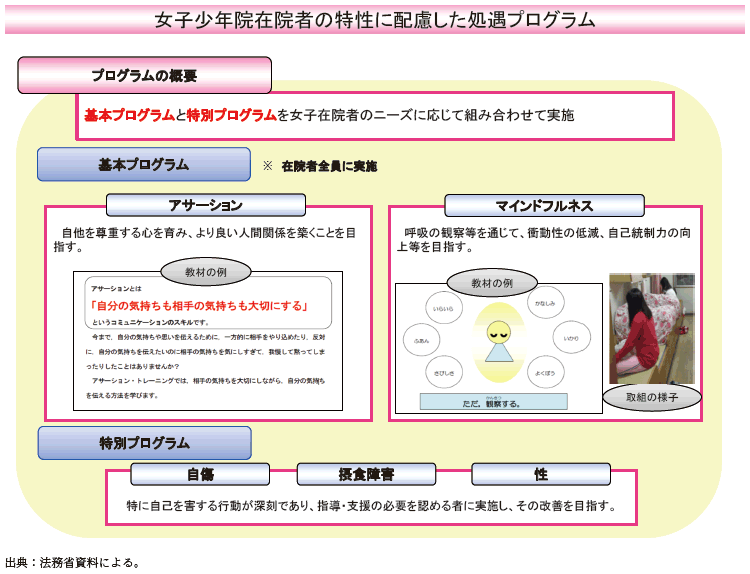
(6)発達上の課題を有する犯罪をした者等に対する指導等【施策番号61】
法務省は、長崎刑務所において、2022年度(令和4年度)から、九州各県所在の刑事施設から知的障害を有する又はその疑いのある受刑者50名程度を集約し、障害者福祉の専門的知見やノウハウを有する社会福祉法人と業務委託契約を締結して、これらの受刑者に対し「①特性に応じたアセスメントと処遇計画の立案」、「②処遇計画に基づく訓練・指導」、「③療育手帳等の取得に向けた調整」、「④息の長い寄り添い型支援を可能とする調整」の四つの取組を実施することを柱とする事業を展開している(資5-61-1参照)。
また、少年院において、在院者の年齢や犯罪的傾向の程度等に着目し、一定の共通する類型ごとに矯正教育課程※16を定め、発達上の課題を有する者については、その特性に応じて、支援教育課程※17Ⅰ~Ⅴのいずれかを履修するよう指定している。2023年(令和5年)に支援教育課程Ⅰ~Ⅴのいずれかを指定された在院者は578人(前年:439人)であった。発達上の課題を有する在院者の処遇に当たっては、「発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラム実施ガイドライン」(資5-61-2参照)を活用しているほか、2018年度(平成30年度)からは、身体機能の向上に着目した指導を導入し、その充実に努めている。
保護観察所では、類型別処遇(【施策番号62】参照)における「発達障害」類型に該当する、又はその他発達上の課題を有する保護観察対象者について、必要に応じて、児童相談所や発達障害者支援センター等と連携するなどして、個別の課題や特性に応じた指導等を実施している。また、更生保護官署職員及び保護司に対し、発達障害に関する理解を深め、障害特性を理解した上で的確な支援を行うための研修や教材の整備を実施している。
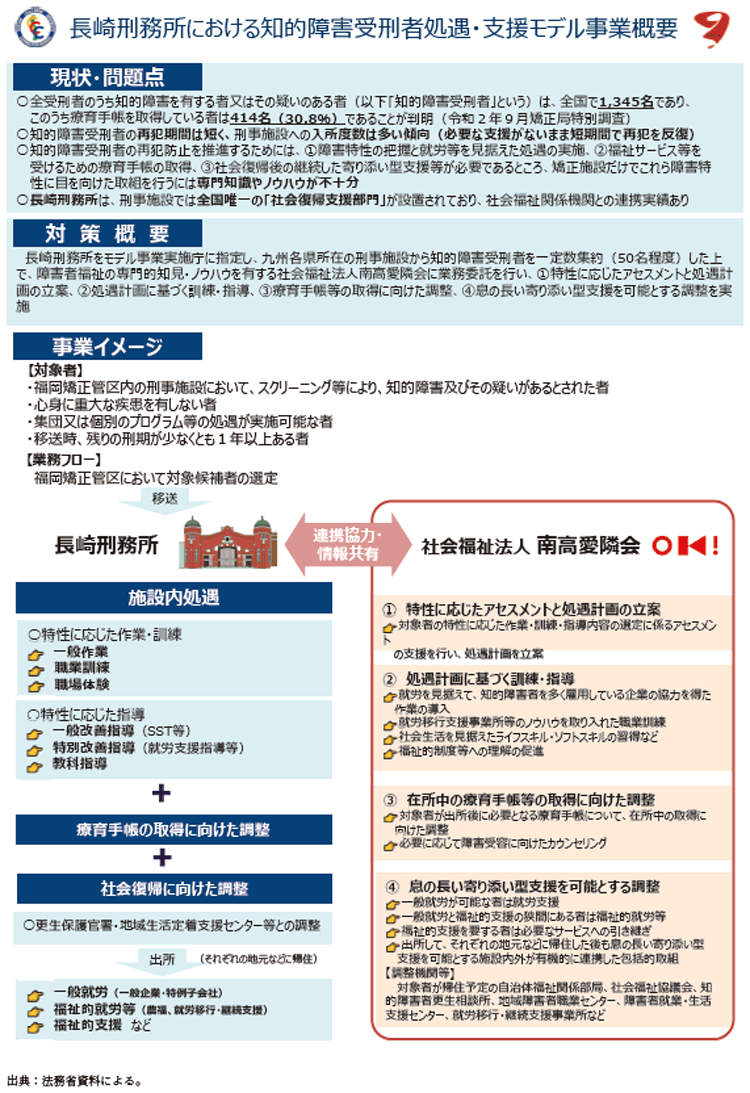
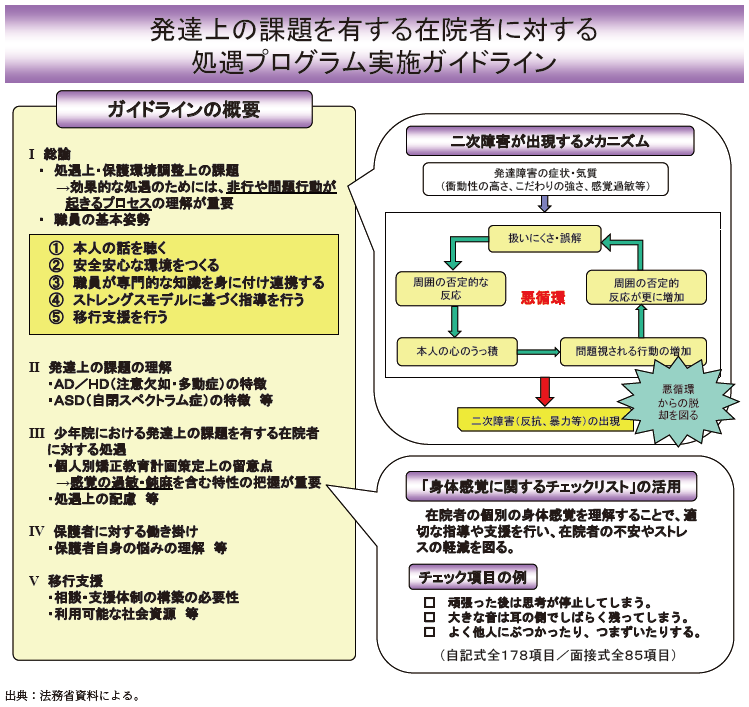
(7)各種指導プログラムの充実【施策番号62】
法務省は、刑事施設において、性犯罪再犯防止指導(【施策番号51】参照)や薬物依存離脱指導(【施策番号34】参照)等の特別改善指導(資5-62-1参照、同指導の受講開始人員は資5-62-2参照)のほか、一般改善指導(資5-62-1参照)としてアルコール依存回復プログラム(資5-62-3参照)や暴力防止プログラム(資5-62-4参照)等を実施している。
特に、児童等に対する虐待行為をした受刑者に対しては、暴力防止プログラムの中で、再加害防止に向けて、本人の責任を自覚させ、暴力を振るうことなく生活するための具体的なスキルを身に付け、実践できるようにするため、家族を始めとした親密な相手に対する暴力に関するカリキュラムを実施しているほか、必要に応じて、犯した罪の大きさや被害者の心情等を認識させ、再び罪を犯さない決意を固めさせるための被害者の視点を取り入れた教育(【施策番号63】参照)も実施している。
少年院では、2018年(平成30年)から、特殊詐欺の問題性を理解させ、再犯・再非行を防止するための指導を一層充実・強化するための教材整備を行っており、ワークブックに加え、被害に関する理解等を深めるため、被害者の方々に協力いただいて視聴覚教材を作成し、2021年度(令和3年度)から、特殊詐欺に関与した少年院在院者を対象に、これらを用いて特殊詐欺非行防止指導を体系的に実施している。
保護観察所では、保護観察対象者に対し、認知行動療法に基づく専門的処遇プログラムを実施している(同プログラムの開始人員は資5-62-5参照)。専門的処遇プログラムは、性犯罪再犯防止プログラム(【施策番号51】参照)、薬物再乱用防止プログラム(【施策番号34】参照)、暴力防止プログラム(資5-62-6参照)及び飲酒運転防止プログラム(資5-62-7参照)の4種類がある。保護観察対象者の問題性に応じて、各プログラムを受けることを特別遵守事項として義務付けるほか、必要に応じて生活行動指針※18として設定するなどして実施している。なお、2022年度(令和4年度)からは、少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)の施行に伴い、18歳以上の保護観察処分少年及び少年院仮退院者に対する処遇の充実を図ることを目的として、各プログラムを特別遵守事項として義務付けて実施することを可能とする対象者の範囲を、従来の仮釈放者及び保護観察付執行猶予者のみならず、18歳以上の保護観察処分少年及び少年院仮退院者にまで拡大し、特定の犯罪的傾向の改善のため、各プログラムを実施している。
2019年(令和元年)から、児童に対する虐待行為をした保護観察対象者に対しては、暴力防止プログラム(児童虐待防止版)(資5-62-8参照)を試行的に実施し、身体的虐待につながりやすい考え方の変容、養育態度の振り返り、児童との適切な関わり方の習得、身体的虐待を防止するために必要な知識の習得を図っている。
また、2020年(令和2年)3月から、保護観察対象者のうち嗜癖的な窃盗事犯者に対しては、「窃盗事犯者指導ワークブック」や、自立更生促進センターが作成した処遇プログラムを活用し、窃盗の背景要因や問題を分析し、窃盗を止める意欲を高め、具体的な行動計画を考えさせることなどを通じて、その問題性に応じた保護観察処遇も実施している。
さらに、保護観察対象者の問題性その他の特性を、その犯罪・非行の態様等によって類型化して把握し、類型ごとに共通する問題性等に焦点を当てた処遇として「類型別処遇」(資5-62-9参照)を実施している。類型別処遇では、保護観察対象者に対する類型ごとの処遇指針として、「類型別処遇ガイドライン」を定め、同ガイドラインをアセスメント、保護観察の実施計画の作成及び処遇の実施等に活用した処遇を実施している。例えば、「特殊詐欺」類型の保護観察対象者については、特殊詐欺グループ以外の居場所を持てるよう、就労や就学を中心とした健全な生活を送るための指導等を行うとともに、特殊詐欺が被害者に与えた影響について理解させ、罪しょう感を深めさせることにより、謝罪や被害弁済等の今後行うべきことを考えさせている。
以上に加え、保護観察対象者について、自己有用感の涵養、規範意識や社会性の向上を図るため、公園や河川敷等公共の場所での清掃活動や、福祉施設での介護補助活動といった地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を継続的に行う社会貢献活動(資5-62-10参照)を、特別遵守事項として義務付けたり、必要に応じて生活行動指針として設定したりして実施している。
2023年度(令和5年度)末現在、社会貢献活動場所として2,101か所(前年度:2,085か所)が登録されており、その内訳は、福祉施設が1,033か所(前年度:1,029か所)、公共の場所が820か所(前年度:813か所)、その他が248か所(前年度:243か所)となっており、社会貢献活動を364回(前年度:362回)実施し、延べ642人(前年度:570人)が参加した。
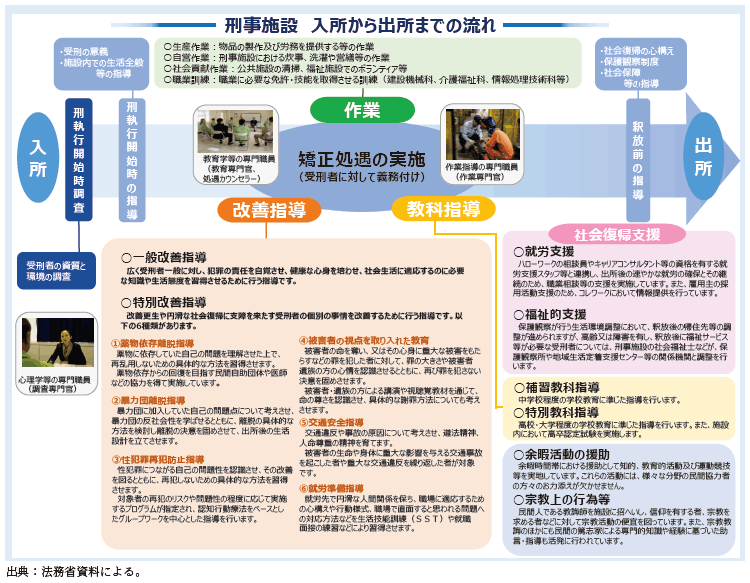
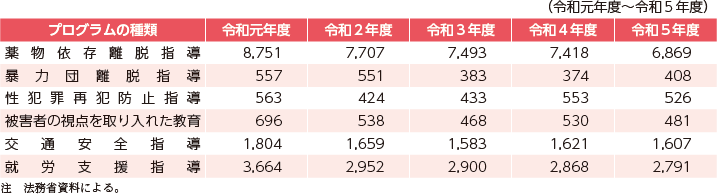
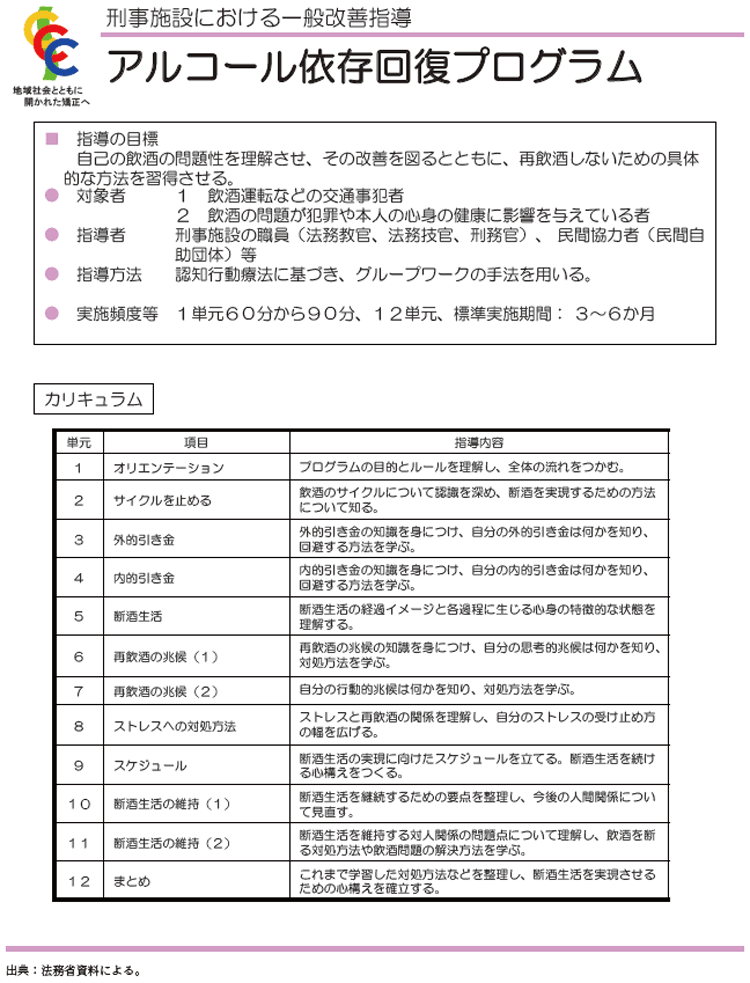
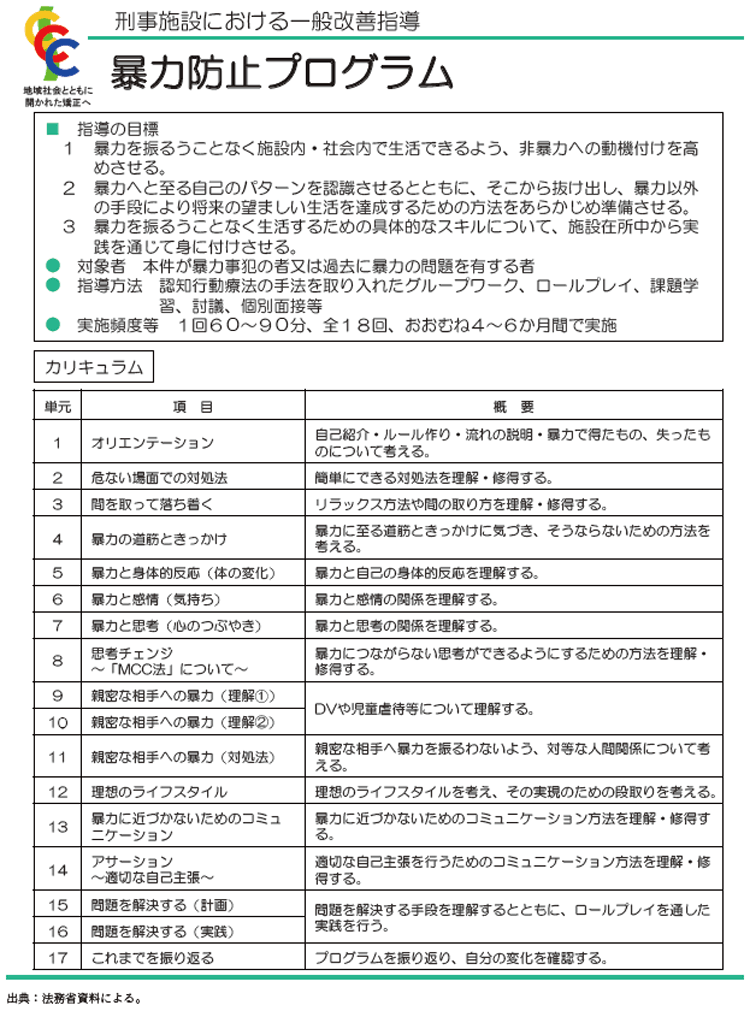
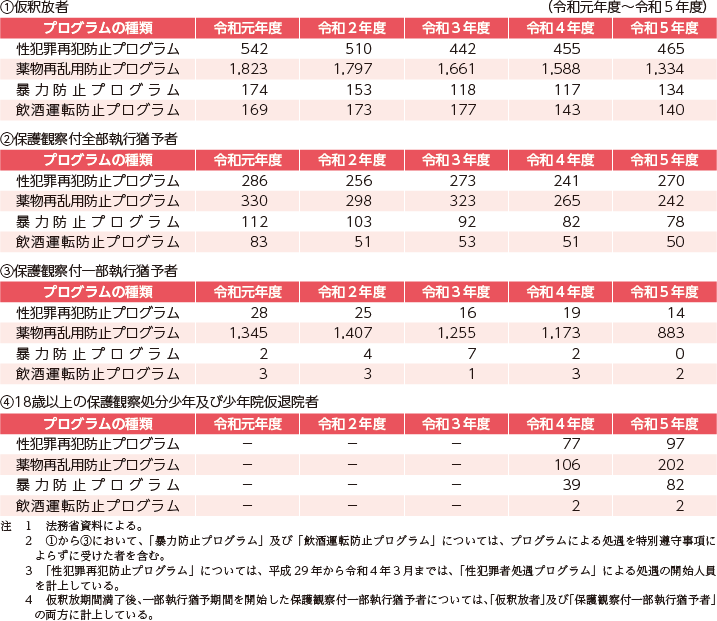
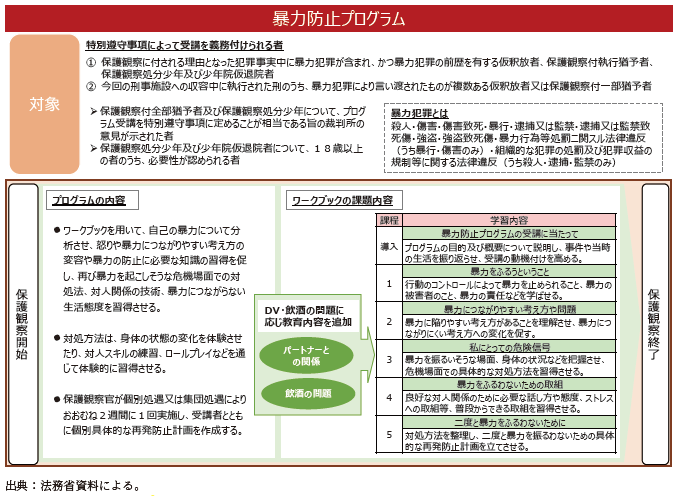
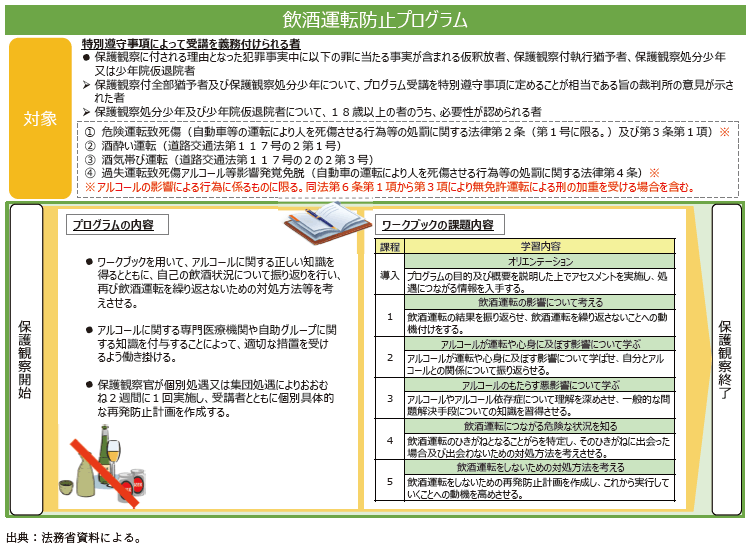
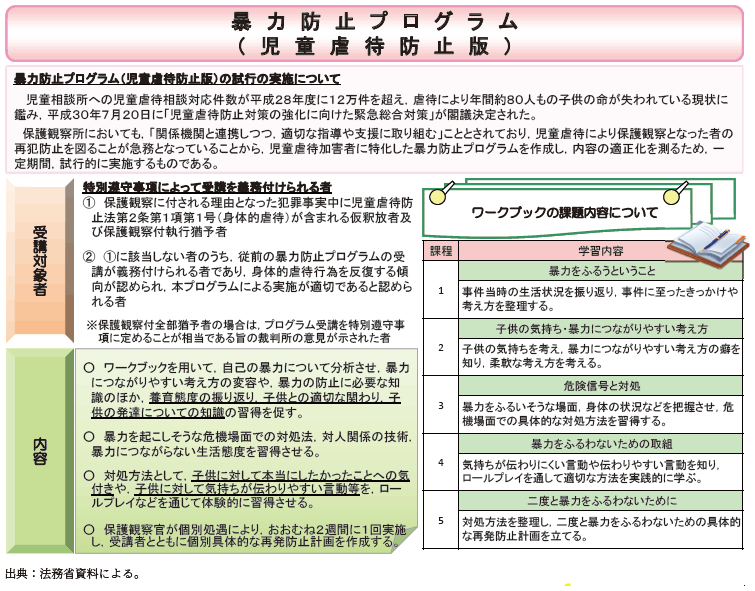
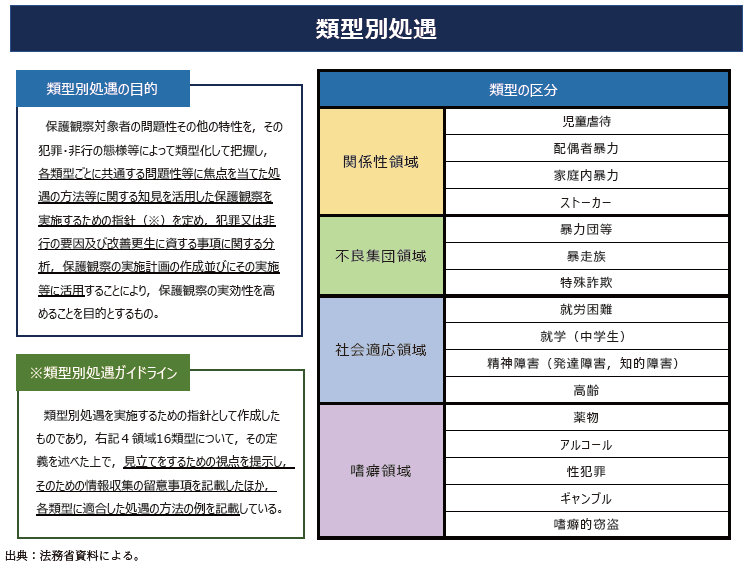
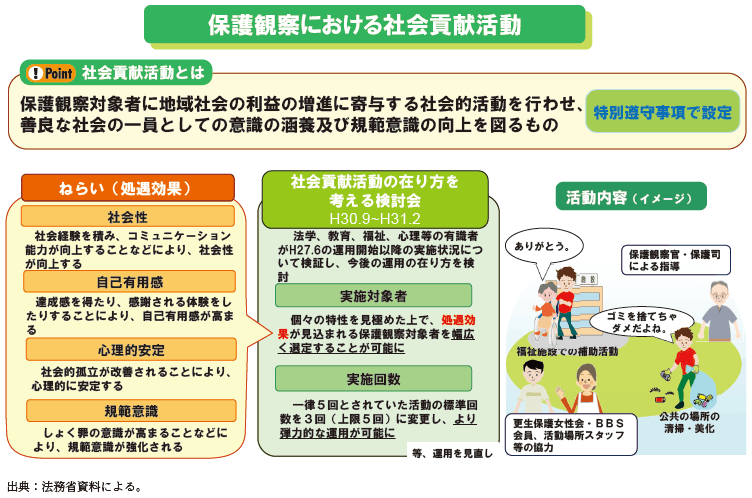
- ※7 調整プログラム
知的能力に制約がある者を対象としたプログラムであり、イラスト等の視覚情報やSST等の補助科目を効果的に取り入れるなどして実施する。 - ※8 集中プログラム
刑期が短いこと等の理由で通常の実施期間を確保できない者を対象としたプログラムであり、通常のプログラムの内容を凝縮し、短期間で実施する。 - ※9 「刑事施設及び保護観察所の連携を強化した性犯罪者に対する処遇プログラムの改訂について(令和4年度~)」
https://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo06_00002.html
- ※10 性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライン~再犯防止プログラムの活用~
https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi/hisho04_00091.html
- ※11 2023年(令和5年)7月13日に刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)が施行され、刑法(明治40年法律第45号)の性犯罪に関する規定が改正されたことを受け、警察は、16歳未満の子供に対して不同意わいせつ等の暴力的性犯罪をした刑事施設出所者について、法務省から情報提供を受け、再犯防止に向けた措置を講じるよう制度を見直した。
- ※12 遵守事項
保護観察対象者が保護観察期間中に守らなければならない事項。全ての保護観察対象者に共通して定められる一般遵守事項と、個々の保護観察対象者ごとに定められる特別遵守事項がある。遵守事項に違反した場合には、仮釈放の取消しや刑の執行猶予の言渡しの取消し等のいわゆる不良措置がとられることがある。 - ※13 暴力追放運動推進センター
暴力団員による不当な行為の防止と被害の救済を目的として、市民の暴力団排除活動を支援する組織であり、各都道府県公安委員会又は国家公安委員会に指定される。 - ※14 保護観察所における「保護者のためのハンドブック」
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00049.html
- ※15 PFI手法や公共サービス改革法を活用した刑事施設
刑事施設の整備・運営にPFI(Private Finance Initiative)手法(公共施設等の建築、維持管理、運営等を民間の資金・ノウハウを活用して行う手法)や公共サービス改革法の活用が図られている施設。美祢社会復帰促進センター及び喜連川社会復帰促進センターにおいても、民間のノウハウとアイデアを活用し、女性受刑者特有の問題に着目した指導・支援を行っている。 - ※16 矯正教育課程
在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、社会生活への適応に必要な能力等、一定の共通する特性を有する在院者を類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めたもの。 - ※17 支援教育課程
障害又はその疑い等のため処遇上の配慮が必要な者に対して指定する矯正教育課程をいう。支援教育課程のうち、Ⅰは知的障害、Ⅱは情緒障害若しくは発達障害、Ⅲは義務教育終了者で知的能力の制約や非社会的行動傾向のある者等に対して指定する。また、Ⅳは知的障害、Ⅴは情緒障害若しくは発達障害のある者等で、犯罪的傾向が進んだ者に対して指定する。 - ※18 生活行動指針
保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めるときに保護観察所の長が定める保護観察対象者の改善更生に資する生活又は行動の指針である。保護観察対象者は、生活行動指針に即して生活し、行動するよう努めることを求められるが、これに違反した場合に、直ちに不良措置をとられるものではない点で、特別遵守事項とは異なる。