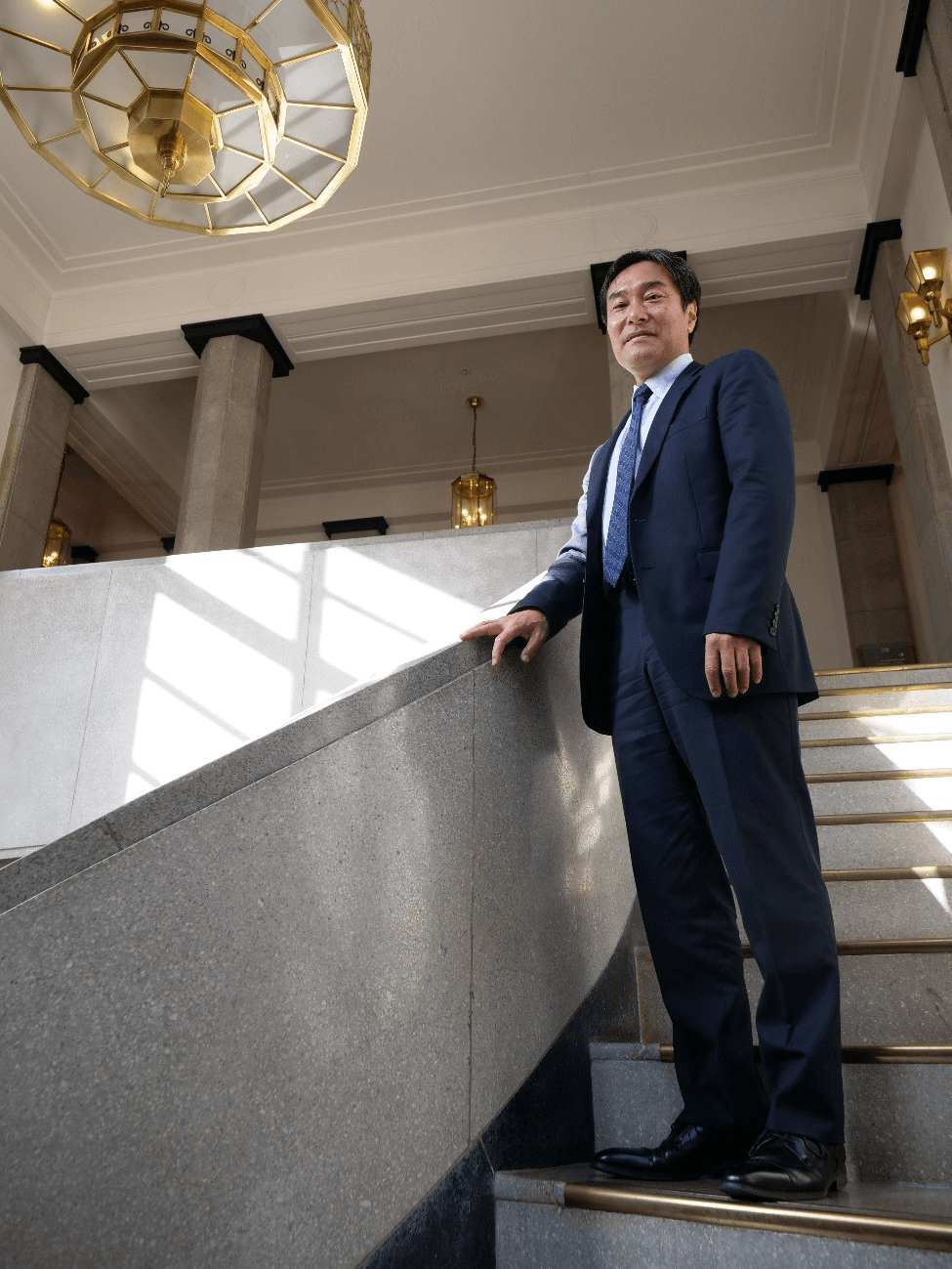施策紹介
MEASURE本企画は、法務省各局(部・庁)のトップに立つ局長(部長・長官)に、法務省及び各局(部・庁)の組織及び施策に対する思いなどを語っていただき、その模様を「ほうむSHOW」編集局が撮影・取材し、国民の皆様に発信するものです。
本企画を通じ、法務省に興味・関心を持っていただけますと幸いです!
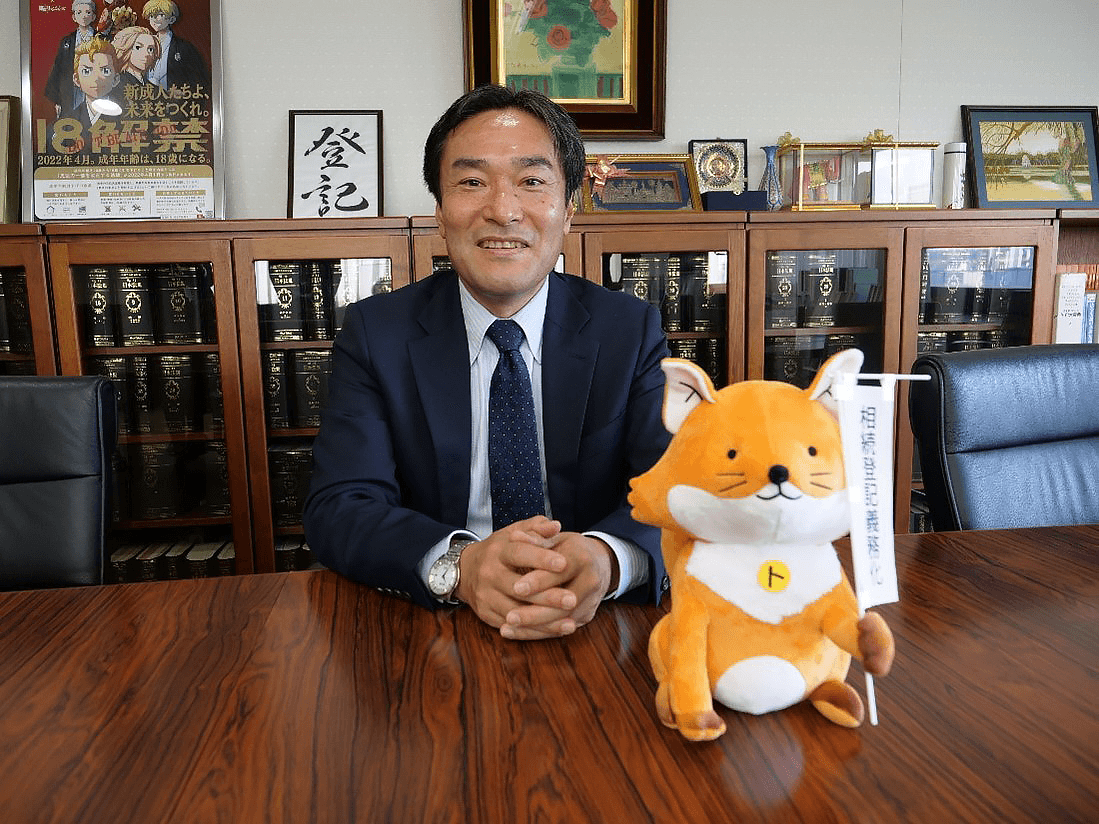
民事局の竹内局長にインタビューを行いました。
民事局の業務について丁寧に御説明いただき、当編集局員も、同じ法務省とはいえ、他部局の業務について分からないことも多いため、大変勉強になりました。
民事局の所管は非常に広いです。全国に法務局、地方法務局、支局、出張所があり、それらは全部で413あります。その中で、社会基盤の整備を担っています。「社会基盤」というと様々なものがありますが、その中でも民事の分野での社会基盤の整備を行っているのが、民事局の特徴です。
民事局の具体的な業務内容を順に説明していきますと、まず、登記(不動産登記 、商業・法人登記、成年後見登記など)があります。いろいろなところに登記は使われています。
また、戸籍に関する事務があります。日本国民は誰でも戸籍を持っています。
さらに、国籍に関する事務があります。具体的にいえば、外国人の方はもちろん、日本人の方でも日本の国籍を離れる場合など、いろいろな面で国籍は関係してきます。
そして、供託があります。債権者が誰だか分からない場合、供託をすると債務の弁済と同じ効果があります。
加えて、日本は高齢化社会になっていますので、遺言がこれから重要になっていくということで、法務局で作成した遺言書を保管する「遺言書保管 」という制度も所管しています。遺言書を作成したら、その人自身で保管していてもよいのですが、遺言というのは亡くなるまで秘密にしておかなければならないもので、遺言書を作成した者が「これ書いたよ」と宣言するものではありません。そのため、被相続人が遺言書を作成したのか作成していないのか、作成したとしてもどこに保管しているのか分からなくなってしまうことがあるため、作成した遺言書をあらかじめ法務局に保管するという制度なのです。それにより、遺言に関する相続人の争いが防止されます。
このように、民事局では、登記、戸籍、国籍、供託、遺言書保管に関する事務を所管しています。
また、不動産登記とも関連しますが、日本全国の地図を作成しています。これは地道でとても大変な作業です。大げさにいえば国土がどのようになっているのか、小さくいえば自分の土地はどうなっているのか、どこからどこまで自分の土地なのかということをきちんと測り、きちんと地図にすることで、地価も分かり、取引や公共事業が行いやすくなります。
さらに、こういったことを支える民事基本法制 、例えば、民法や、会社の関係だと会社法、家族の関係だと家族法を整備するというようなことをやっています。
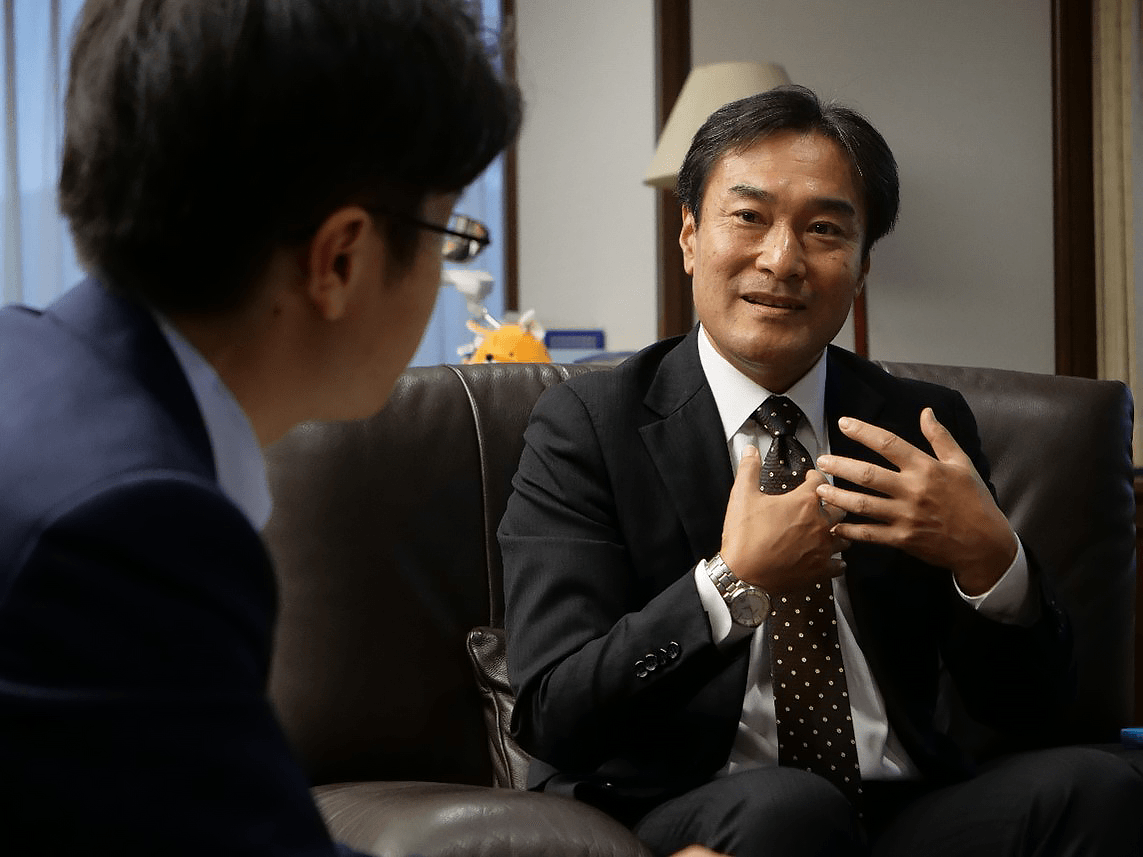
いろいろな特徴があると思いますが、所管が広いため、国の政策のいろいろな部分で関与していると思っています。そういう意味では、民事局で働く職員としては、いろいろな分野に興味を持ってアンテナを張っておくというのが大事ではないかと思います。
例えば、どこかの官庁が、「景気を良くするための経済政策」、「起業促進のための経済政策」を実施したいと言った際には、民事局の所管として、民事基本法制が関与してきます。関係省庁から、「民法上はどうなっているのか」、「不動産登記、商業・法人登記との関係はどうか」という照会が来たり、あるいは、様々な連絡会議の構成員になったりすることがあります。国会から説明を求められたり、議員の先生方から説明を求められたりという機会もかなり多いです。
このようなところが民事局の大きな特徴かなと思っています。何かしら、新しい施策をやろうということになると、まずは、民事局に聞いてみようということになるのです。頼りにしてもらっていて、それはありがたいなと思っています。
また、民事局は、参事官室という部署を抱えており、そこでは民事基本法制の整備を担当していますが、そこには多くの法律家たちが勤務しており、深い議論をしていただいていると感じています。
社会基盤は、朝令暮改的に変わるべきではないと思っていますが、時代に応じて新しくしていくべきものがあります。そこを適切に見極めて、変えないものは変えない、変えるべきものは変えるという形で、様々な課題に取り組んでいくこと自体に、非常にやりがいを感じています。
デジタル化の時代なので、登記一つをとっても大きく変化しています。昔は登記所に行って紙で申請し、お金を払うという形でしたが、今はオンラインで申請ができるようになっており、スマホで簡単に申請できるようにやり方も変えてやっています 。登記という大きく確固たる制度としてありつつ、時代に合わせて変えていくということなのかなと思います。
高齢化をとってもそうです。先ほども遺言を例に出しましたとおり、遺言の制度はあるわけですが、その制度を全く変えないでいるというわけにはいかないですし、高齢化社会になってきますと、高齢の方も増えてきて遺言の機会も増えてくるので、法務局で作成した遺言書を保管して、相続をめぐる紛争を防止しようというように、遺言の制度も時代に合わせた制度になってきています。
あるいは、所有者不明土地についても、高齢化社会になると、土地を相続しても登記をしないことがあり、その土地の登記を見ても、いったい誰の土地か分からないということになります。こういった所有者不明土地の発生を防止するため、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりますが、これも時代に応じて新しい制度を作っていく取組の一つではないかと思います。
まとめますと、基盤整備として変えるべきではない部分はきちんと維持していく、一方で、変えるべき部分は柔軟に変えていく、このようにして、どのように国民の生活を守っていくのかということを考えられることが、民事局の業務で非常にやりがいを感じるところではないかと思っています。
改めて考えてみますと、やはり、社会基盤として残すべきものと変えていくべきものを見極めていくこと、これが求められていると感じています。
民法や商法、会社法などは、頻繁に変えることが望ましくない法律です。民法というのは、まさに人と人との取引の基本的な部分を規律する法律であり、国民の生活に直結しますので、これが頻繁に変更されれば、社会はかなり混乱するおそれがあります。そういうものは、原則としては、ちゃんと残していかなければいけないと思っています。
他方で、時代の変化は速いので、時代に合わせて変えていくべきものも多くあるだろうと思っています。つい最近も、民法の一部である債権法を改正し、所有者不明土地問題で民法の一部である物権法も改正し、時代の要請に合わせて変えていくべきところは変えていこうということで我々は仕事をしています。また、社会的にもそれを求められているのではないかなと思っています。
先ほど、経済政策の例を出しましたけれど、民事基本法制がベースになって、その上で、経済政策が初めて成り立っていくと思います。何かやろうというときに根っこの部分がどうなっているのか分からないと、新しいものも作れません。なので、その根っこの部分をしっかりと整備していくことも大切かと思います。
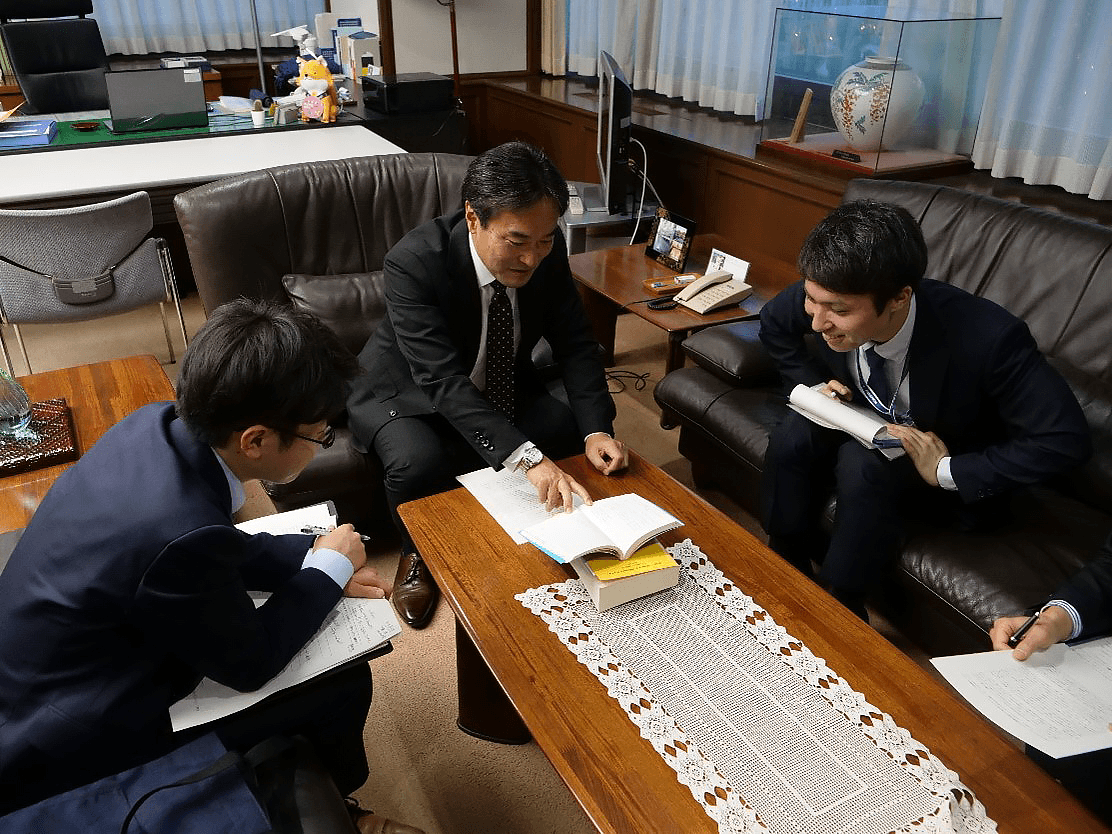
以前、私は、法整備支援をやっていたことがあって、ベトナム政府と法制度の在り方について議論していましたが、そのときにベースとなるのはやはり基本法制なのです。まず基本的なルールがあって、その上に、例えばそれぞれの業界の取引が成り立っているので、まずは基本法制の整備に取り組もうという話になるわけです。
民事局の仕事は、とても地味ですが、社会基盤の整備をしなければ、社会が成り立たないと思うのです。
「法務省って動かないよね」とか、「法務省って固いよね」と言われることがありますが、むしろ「それでよいのだ」と思っています。変えていくべきことと変えてはいけないことを見極めていくということが大事です。これが難しいのですけどね。
広報とは、本当に大事なもので、どんなに良い運用をしていても、それを知ってもらわないと、知って使ってもらわないと、絵に描いた餅というか、やった意味がない。したがって、どうやって広報をしていくかというのはかなり大事な話だと思います。
制度の広報というと固くなりますが、例えば、法務省がどんな仕事をやっているのかという全体的な広報なのか、就職用の広報なのか、目的によって広報の仕方を変えていかなければいけない。対象とする人がどんな人たちで、どんなメディアを使っているのかということを分析した上で、それではそこに向けてどんな形で知らせたら伝わりやすいかということを考えることが重要かなと思っています。
そこは、アイディアの世界なので、自由にやってよいと思うのです。見出しの付け方やレイアウトの仕方、フォントをどうするか、色使いをどうするかというのは、若い職員の皆さんは本当に上手いので、自信をもってやっていただいたらよいと思います。
広報は、本当に楽しい仕事なので、前向きだし、楽しいじゃないですか。静止画でも動画でも良いのですけど、いろんなアイディアがあってもいいし、失敗してもよい。
法務省の広報は、大ヒットしなくても、バズらなくてもよいじゃないですか、あんまりハードルを上げないでやっていくことが大事だと思います。とにかく楽しくやればよいと思います。自分たちが取り敢えずやりたいようにやってみるというところから始めてみて、どうしてもいろいろなことを言う人がいて、固く収まっちゃうところもあるかもしれないですが、もっとはっちゃけてもよいと思います。
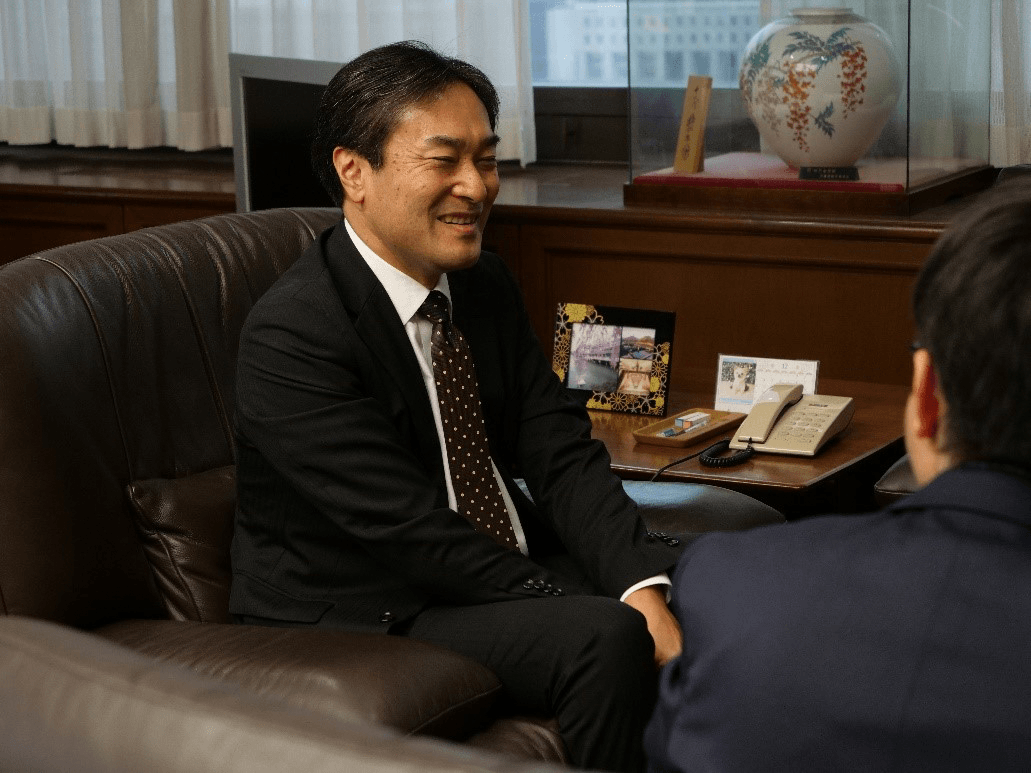
民事局の広報といわれるとなかなか難しいところもありますが、登記制度の改正の周知に係る漫画を作って配布してみるということはやってみました。また、桃太郎を題材に民法の広報用の漫画を作って配布しました。ロースクール生とコラボして、学生のアイディアを使ってやったりしていました。割と漫画は評判がよかったです。
広報とは関係ないかもしれませんけど、いろんなアイディアって大事だなぁと思っていますし、僕は広報が大好きなので、「ほうむSHOW」編集局のことも応援しています。ぜひ頑張っていただきたい。
民事局の仕事、本省の仕事もそうなのですが、最初にお伝えしましたとおり、全国には法務局や地方法務局があります。この広い職場の中で、社会の法的基盤を企画して整備するという仕事をやっています。変えないところはきちんと残しつつ、時代に合わせて柔軟に変えていこうという姿勢でみなさん仕事をしています。
令和6年3月には戸籍の事務が変わることになっていて、これまで本籍地でしか取得できなかった戸籍の証明書が全国で取れるようになります。時代の要請に合わせたものですよね。これもみんなで企画をし、考えて、こういう制度にしようということにしてやっているものですし、また、高齢化社会を迎えて、所有者不明土地がどんどん増えていく中で、その原因を探り、その対策として「相続登記の義務化」という回答を出して、令和6年4月から実施しようとしています。こうやって、新しい制度、しかも国民の生活に直結した新しい制度を企画して構築していける職場だと思っています。そういう意味で、法的なことに少しでも興味があるとか、法的な仕事をやってみたいという人にとっては、平凡な言い方かもしれませんが、すごくやりがいがあり、自分の能力を十分に発揮してもらえる職場だと思っています。
そういう意味で、これから就職を考えている学生の皆さんには、ぜひ民事局や法務局で一緒に仕事をしていただきたいと思っています。