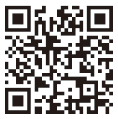第2節 民間協力者(保護司を除く)の活動の促進
(1)民間協力者の活動に関する広報の充実【施策番号75】
警察は、2024年(令和6年)4月現在、少年警察ボランティアとして、少年補導員約4万6,000人、少年警察協助員約220人及び少年指導委員約5,600人を委嘱しているほか、2024年3月現在、大学生ボランティア約7,700人が全国で活動している。これらのボランティアの活動への理解や協力を促進するため、啓発資材の作成・配布、警察のウェブサイト※16等を通じて、ボランティア活動に関する広報を行っている。
法務省は、“社会を明るくする運動”(【施策番号95】参照)の広報・啓発行事や、エックス(旧ツイッター)等のSNS※17を通じて更生保護ボランティアの活動を紹介したり、啓発資材を作成・配布したりすることによって、更生保護ボランティアの活動に関する広報の充実を図っている。
また、法務省は、保護司の適任者確保や保護司活動への協力の促進を図るため、保護司が地域の関係機関・団体、民間企業等に対し、保護司活動等について紹介する保護司セミナーに取り組んでいる。
(2)民間協力者に対する表彰【施策番号76】
内閣官房及び法務省は、2018年度(平成30年度)から、内閣総理大臣が顕彰する「安全安心なまちづくり関係功労者表彰」において、再犯の防止等に関する活動の推進において特に顕著な功績又は功労のあった個人又は団体を表彰している。2023年度(令和5年度)は、法務省を含む関係省庁や地方公共団体から推薦を得て、再犯を防止する社会づくりについて功績・功労があった合計8の個人及び団体を表彰した※18(資6-76-1参照)。
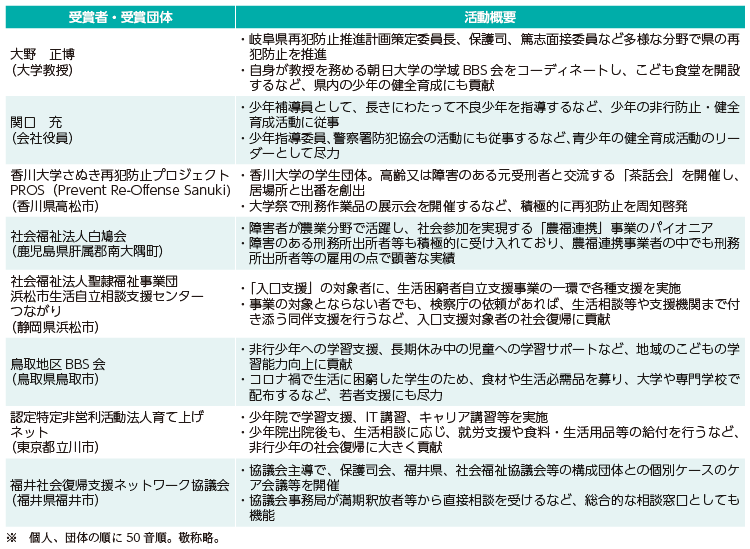
再犯防止を支える民間協力者の方々 篤志面接委員
麓刑務所 郡嶋かおる
1 篤志面接委員として活動するまでの経緯について教えてください。
知的障害者更生施設勤務から社会人人生をスタートさせた後、20年以上にわたり知的障害児通園施設(現・福祉型児童発達支援センター)で児童指導員として、勤務しました。その後は専門学校教員を経て、福祉系の大学の教員となりました。このように、矯正とは全く無縁の環境の中で過ごしていました。
そのような中、ある専門学校で出会いをいただいた先生から、「とくめんにならないか?」と声を掛けられ、「とくめん?何ですか?スペシャルな面接員ですか?」と返したのがきっかけとなり、「篤志面接委員」のことを初めて知り、信頼する先生からのお誘いということもあって、お引き受けし、今日に至っています。
2 篤志面接委員の活動内容について教えてください。
満期釈放前指導と希望による個人面接を行っています。被収容者の年齢層は、30歳代から高齢者までと幅広く、それぞれに家庭があります。そのような彼女たちに、できるだけ出所後の未来の青写真を描けるように、趣味を始めとして、挑戦してみたいことなどについて話すことで、これからの人生に希望を持って過ごしてもらえるように心掛けています。
3 篤志面接委員の活動のやりがいを教えてください。
被収容者と話していると、自己肯定感が非常に低い人が多いことを強く感じます。褒めてもらう経験や成功体験が希薄だったことが容易に想像できます。中には自分の生い立ちや、どうして刑務所に入ることになったのか、ポツリポツリと話してくれる人もいます。
彼女たちから教えられたことは、罪を犯しているけれども、それと同時に、被害者の側面を持っている人が多いことです。面接の時間だけでも、彼女たちがほっと心穏やかに過ごせること、自分の心を少しでも開放できることを願っています。
彼女たちの笑顔や涙を見るとき、そして、他者には話すことをちゅうちょするような内容を話してくれるとき、受け入れてもらったと喜びを感じるとともに、篤志面接委員になって良かったと痛感しています。
4 印象に残っている体験談を教えてください。
篤志面接委員になった当初の釈放前指導での面接で、親が突然いなくなったこと、成人してから結婚した男性が覚醒剤の密売人だったことで、自らも犯罪行為に関係し、人生のほとんどの時間を刑務所で過ごしていると語った被収容者がいました。
しかし、面接をしていると、女性であることの生きづらさや困難さを抱えていることには、共感できる部分がありました。人は「変わることができる存在」であるということを信念として、「諦めない、投げ出さない、折れない心」を基本姿勢として活動をしていきたいと考えています。

再犯防止を支える民間協力者の方々 教誨師
帯広刑務所 小澤眞了
1 教誨師として活動するまでの経緯について教えてください。
1981年(昭和56年)10月から保護司を拝命していたところ、保護司の仲間の中に教誨師の先生がおられ、帯広少年院(2022年(令和4年)4月1日閉庁)で教誨をしてもらえないかとのお話があり、不安を持ちながらも1992年(平成4年)にお引き受けいたしました。
教誨師としての最初の教誨活動が同院であり、教誨師としての活動の第一歩は「お盆法要」での在院者に対する宗教行事でした。研修を受けることなく「ぶっつけ本番」で当日を迎えました。緊張しながら、ただ僧侶が執り行う読経と法話の延長のような時間が流れ、訳が分からないまま終えてしまい、全く教誨にならなかったと自信をなくしてしまったことを覚えております。しかし、その後諸先輩からいろいろと御指導いただき、前向きに研鑽しつつ被収容者と共に歩みたいと思うようになりました。
2 教誨師の活動内容について教えてください。
被収容者に対する教誨では、どうしてこの人が罪人に、と思うことがよくあるのですが、被害者に対する反省の念を素直な心で語っていると感じられるときなどは、私は聞き役に徹しています。そうすることで、その方の気持ちが手に取るように伝わってきます。何より、人間としての尊厳を大切にするようにしています。また、個人教誨のときは、心を許して話をされる方が多く、私自身も身の引き締まる思いで臨んでいます。
十勝帯広は、明治期に当時の被収容者によって開拓された経緯があるのですが、開拓に従事しつつ亡くなられた方々がおられ、この方々の追弔法要を企画したこともあります。その際には、引受人がなく、亡くなっても誰からも手を合わせてもらえないという方々もいるということを、帯広市民に呼び掛けるような活動を行いました。
3 教誨師の活動のやりがいを教えてください。
ある時、街中で偶然に、かつて私の教誨を受けていた方がお孫さんと思われる方の手を引いて歩いている時に擦れ違ったことがありました。お互い軽い会釈をしてそのまま通り過ぎましたが、私のことを覚えていただけたのだとうれしさを感じました。その方は、教誨を始めた頃は私をにらむようにしておられましたが、1年程経つと、優しい目でよくうなずきながら話を聞いてくれるようになっていました。そんな日々があった後の偶然のすれ違い、更には笑顔で歩いている姿をお見掛けすることができ、感激しました。
教誨をしている時は、聞いてもらえているかどうか分からないと思うこともありますが、心に響いて届いている方もいるのだなと思う時、活動を続けて良かったと自分に納得します。また、心のケアになったかなと感じられる時や、被収容者の社会復帰した姿を見ると、やりがいを感じ、心が一杯になります。
4 印象に残っている体験談を教えてください。
刑務所の運動会に出席して感じたことがあります。運動会では、それぞれの班に分かれて種目に取り組むのですが、全ての方が全力疾走で、また、応援も全力で、老いも若きも一生懸命に運動・応援する姿を見ることができました。班を分けても隔てなく楽しんでいる姿、真剣な姿、刑務官やその他の職員の方々と一体となっている場面など、素晴らしい風景が印象深く記憶に残っています。家庭や学校で見られるような、家族や同級生と同じような輝いた彼らの姿に、感謝・感激・感動がありました。
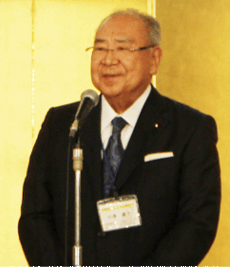
再犯防止を支える民間協力者の方々 外部講師(少年院特別指導)
特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち 久保田菜々子
1 少年院において活動するまでの経緯について教えてください。
私たち「芸術家と子どもたち」は、「すべての子どもたちに、アートとの幸福な出会いを」という理念の下、主に東京都内の公立小中学校や児童福祉施設等に、プロの現代アーティストを連れて行き、子ども参加型のワークショップを実施しています。私は、コーディネーターとして、どんな活動にしたいか施設職員の希望を確認するとともに、ダンスや音楽、美術、演劇等、多彩なジャンルのアーティストと子どもたちとの幸福な出会いが実現できるよう、事前準備から当日までの橋渡し役を務めています。活動を続ける中、私たちの活動は、社会に生きづらさを感じている子どもたちにとって、その後の人生を生きていく力になるのではという思いを持ち、少年院での活動を始めました。
2 活動内容について教えてください。
少年院での活動は、2022年度(令和4年度)、東日本少年矯正医療・教育センター(東京都)での、医療措置課程の女子少年と共に身体表現のワークショップからスタートしました。自分の身体をマッサージするところから始め、少しずつオリジナルの創作活動にも挑戦しながら、最終日には少年院の職員の方に向けたミニ発表会も実施しました。翌年度から活動をスタートした宮川医療少年院(三重県)では、支援教育課程の中学生の男子少年と一緒に、真っ白なシーツテントを様々な素材や画材で彩り、自分の空間を作る美術ワークショップを行いました。それぞれの活動の様子はWeb記事でも紹介しているので、是非ご覧ください。
★東日本少年矯正医療・教育センター
https://www.children-art.net/post_column/post_column-9492/
★宮川医療少年院
https://www.children-art.net/staffblog/archives/3897
3 活動のやりがいを教えてください。
初めての出会いの時には、子どもたちも(大人たちも)緊張していて、表情や空気が硬いのですが、ワークショップが進むにつれて、少しずつ身体も心もほぐれていき、動きや作品にその子ならではの遊び心が見えてきたりします。そんな瞬間をアーティストが逃さず、声を掛けていくことで、その場全体が柔らかい空気に包まれ、子どもも大人も自然と優しい表情になっていく…そんな場面に立ち合えた時に、この活動をしていて良かったと心から感じます。施設の特性上、少年院には様々なルールや制約がありますが、その中でも、外部から私たちが来ることによって、子どもたち一人ひとりの心に残る、特別な瞬間を作ることができていたらうれしいです。
4 印象に残っている体験談を教えてください。
「(決まったエリア内を自由に歩くワークショップ中)すれ違う他の人たちや先生たちも笑っていて、すごい胸がぽかぽかしました。なんか、「独りじゃないんだ」って思えて、本当に、一生の宝物です。」これは、参加した少年から受け取った感想です。アーティストとの出会いは、少年院にいる子どもたちにとって、どんな意味があるのか。それは、できないことができるようになったり、すぐ目に見えるような成果や効果があったりするものではないかもしれません。しかし、「アーティスト」という、子どもたちの表現を引き出し、応答し、人と人とのふれあいの場を紡ぐプロの方々と過ごす時間によって、子どもたちの心に灯る光があると信じて、これからも活動を続けていきたいです。
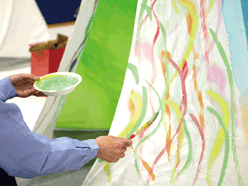

再犯防止を支える民間協力者の方々 更生保護女性会
伊豆中央地区更生保護女性会 井邑玲子
1 更生保護女性会員として活動するまでの経緯について教えてください。
私は家事と農作業の傍ら視聴覚障害者のための点字翻訳や音訳のボランティアをしていました。2014年(平成26年)に菩提寺の先輩役員から更生保護女性会の活動に誘われて入会いたしました。
「更生保護」という言葉はそのときに初めて聞き、最初に参加したリハビリ施設での夏祭りのお手伝いで、更生保護女性会員の皆さんの取組や関わり方を見て、自分にもできることで更生保護の活動に協力したいと思いました。
楽しみながら活動を続けている会員の皆さんの姿を見て、これからも、その輪の中に加わっていきたいと思っています。
2 更生保護女性会の活動内容について教えてください。
地区全体での活動としては、更生保護施設「少年の家」での食事作り・清掃活動があり、また、七つある支部独自の活動としては、子育て支援センター「すみれ広場」で未就園児の母子と交流したり、地域内の福祉施設・介護施設を訪問し、タオルや雑巾を寄贈したりしています。また、保護司と連携を図りながら、“社会を明るくする運動”だけではなく刑務所・警察署見学を行ったり、小中学校での交流会・講演会・あいさつ運動・登下校見守り・ミニ集会・懇談会・福祉イベントを警察署・民生委員・教育委員会・学校関係者・日赤奉仕団と協働して行ったりしています。
3 更生保護女性会のやりがいを教えてください。
保護司会と協働して毎年交流会等を開催しているところ、中学校で弁護士の講演会を開催したことがありました。その時に、事件の容疑者として逮捕され新聞に載ってしまい、無実であったのに訂正の報道がされなかったため、その後社会で生きづらくなってしまった人の話を聴きました。長い講演時間でしたが、中学生たちが真剣に内容を受け止めている様子が印象に残っており、講演会を開催して良かったと思いました。
更生保護女性会の活動の中で初めて知ることや、思いもかけない出会いをいくたびか経験させてもらっています。七つの支部間の情報交換も密で、協力しながらできることを探し話し合うのも楽しい時間です。
4 力を入れて取り組んでいる活動について教えてください。
年2回25名程で市の公用マイクロバスや民間バスを借りて2時間かけて更生保護施設「少年の家」を訪問し、食事作りや屋内外の掃除等を行っています。明るい雰囲気の館内では在所者と挨拶したり、備品の場所を教えてもらったり、草取りなど一緒に作業をし、時間が経つにつれ少しずつ会話も増え、笑顔をお土産に温かい気持ちで帰路につきます。十数年続けている「すみれ広場」での子育て支援や近隣の施設との交流は地域に根ざした活動として続けていきます。ここ数年、保護司会との協力活動も増え、うれしく思っています。

再犯防止を支える民間協力者の方々 BBS会
左京区BBS会 出口花
1 BBS会員として活動するまでの経緯について教えてください。
私は大学1年生の終わり頃にBBS会に入会しましたが、それまではごく普通の学生生活を送っており、特に更生保護に関わる知識も経験もありませんでした。大学では教育学部に所属していたため、子どもに関わる活動に興味は持っていましたが、BBS会の存在すらも知らない状態でした。もともと子どもが大好きで、何か子どもと触れ合えるサークルを探していましたが、大学入学と同時に新型コロナウイルス感染症が猛威をふるい、まともに活動できているサークルはほとんどありませんでした。そのような状況の中、大学サークル一覧でBBS会は活動を継続していることを知り、学部の先輩も所属していたこともあって入会してみることにしたのがきっかけです。
2 BBSの活動内容について教えてください。
左京区BBS会では、家庭裁判所や少年院、児童自立支援施設などの関連機関と連携させていただき、子どもたちの支援に関わっています。具体的には勉強を教えたり、一緒にスポーツをしたり、楽しく会話したりといった内容です。また、地域の小中学校に伺ったり、行事に参加したりすることもあります。会員の多くが大学生であることを生かし、子どもたちと同じ目線で共に成長しながら活動しているのが特徴です。そのため会員同士の交流会や研修会など、会員が勉強できる場も定期的に設けています。
3 BBSの活動のやりがいを教えてください。
子どもたちと継続的に関わることで、心を開いてくれたり楽しそうに話しかけてくれたりしたときには非常にやりがいを感じます。今まで硬い表情だった子が笑顔で話してくれたり、帰り際に「また来てください!」と言ってくれたり、日常の些細なことがとても印象に残り、うれしく感じます。また、学習支援をした子から受験合格の報告を受けるのも本当にうれしい瞬間の一つです。私たちBBS会員は専門家でもなければ経験も少なく、子どもたちに与えられる影響はほんのわずかなものです。それでも私たちと会っている間、彼ら・彼女らが子どもらしく無邪気に笑い、楽しく過ごしてくれていたら、私たちにとってこんなにうれしいことはありません。
4 “ 社会を明るくする運動” について、具体的な活動内容や工夫していることなどについて教えてください。
左京区BBS会では、左京区保護司会の方々と連携し、“社会を明るくする運動”に取り組んでいます。年に一度開催される公開講演会では、会場の設営や受付などを担当し、実際に講演も聞かせていただいています。また、 小中学生を対象に実施される作文コンテストにおいて、作文の審査や冊子作りの補助、表彰式の受付などを行なっています。基本的には左京区保護司会の皆さんのお手伝いをさせていただく形ですが、他の関連団体の方々も含めて協力を深め、様々な活動に参加しています。
再犯防止を支える民間協力者の方々 協力雇用主
開星運輸株式会社 代表取締役 中原英多郎
1 協力雇用主になったきっかけについて教えてください。
2018年(平成30年)から、協力雇用主として刑務所出所者を延べ50人以上雇い入れています。協力雇用主となったきっかけは、知り合いの同業者で既に協力雇用主として刑務所出所者を雇っていた方から、刑務所内で求職者の面接をして採用をしているとの話を聞き、興味を持ったことです。
私は運送会社の二代目で、子供の頃からいろいろな個性ある従業員を見てきました。その中には、過去に罪を犯し、刑務所を出た後は限られた業種でしか働くことができず、自動車運転免許の資格を生かしてトラックの運転手をしていた人もいましたので、刑務所出所者を雇い入れることに何の抵抗もありませんでした。
協力雇用主の活動を知る前、一般の求人募集で、たまたま近くの更生保護施設に入所中の人を採用したことがあり、刑務所出所者を雇い入れる不安もありませんでした。そのことで、微力ながら、仕事をしたいと思う方々に対し、私のできる範囲でお手伝いをすることが協力雇用主となることでした。
2 協力雇用主の活動内容について教えてください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前は、刑務所や少年院に出向き、採用面接を行っていました。現在はオンライン面接が多くなりましたが、できる限り対面で面接するように心掛けています。満期出所者や更生保護施設を出た後に居住地が決まらない人たちには、私が用意したアパートへ入居することができるようにし、社会復帰後の自立支援の力添えになればと考えています。
3 協力雇用主の活動のやりがいを教えてください。
犯罪や非行をした人には身勝手な者や未熟な者が多く、それが原因で犯罪に及んでしまったと自ら気付くまで、何度も面談を繰り返し、指導しています。すると、少しずつ変わってくる様子が感じられます。中には、今まで定職に就いた経験のなかった者が、次第に、社会生活を送る中で「働くこと」は必要不可欠なことであるとの意識を持ち始め、仕事以外の時間についても気にすることができるようになり、「夜更かしや深酒をやめました。」と言ってきたことがありました。また、今まで身勝手なことばかりしてきたと後悔の言葉を聞いたときは、協力雇用主として活動して良かったとやりがいを感じました。そんな彼らも雇用開始から5年目となり責任感を持って働いてくれています。
4 非行や犯罪をした人を雇用する上で工夫していることを教えてください。
人は周囲にうまく理解してもらうことができず、失敗することもありますが、私が今まで経験してきた中で、犯罪や非行をした人は自分自身から発信することが苦手な人達が多いように見受けられます。ですので、できる限り私から彼らに声掛けをし、気軽に話をできる環境を作っていくことが重要だと考えています。
当然ながら、実際にはそんなにうまくいくことばかりではありませんが、歩み寄る意識が伝わると、彼らから話しかけてくることも多くなってきます。
彼らには、仕事を任されているという責任感を持ってもらい、ルールは自分自身を守るためのツールだと認識してもらいます。そもそも、社員の中で孤立させず、特別扱いせずに一般社員と同様に接しますので、そこは理解してもらえていると思っています。
本人が希望すれば、日払いやアパートへの入居、自動車運転免許証の資格取得支援制度等も一般社員と同様にサポートしています。
再犯防止を支える民間協力者の方々 更生保護協会
更生保護法人秋田県更生保護援護協会 理事長 加賀谷文秋
1 秋田県更生保護援護協会の成り立ちや現在の組織の概要について教えてください。
当協会は、1956年(昭和31年)に発足し、財団法人を経て、1996年(平成8年)から更生保護法人として活動しています。役員等は地元の経済界や更生保護団体等による理事19名、監事2名、評議員24名から構成され、会員約750名によって支えられています。
2 活動内容について教えてください。
更生保護事業法に基づき、事業を実施しています。具体的には、地域連携・助成事業として、保護司会や更生保護女性会、更生保護施設等の更生保護関係団体が、それぞれの特性を生かしながら、充実した更生保護活動を実施できるよう必要な助成をしているほか、“社会を明るくする運動”秋田県推進委員会への参画や、広報啓発資材の配布等を通じて、更生保護の普及啓発を行っています。また、通所・訪問型保護事業として、更生緊急保護対象者や生活に困窮した保護観察対象者に対し、金品給与を行っています。
3 最近力を入れている取組について教えてください。
広報啓発活動の一環として、2022年(令和4年)にウェブサイト「秋田県の更生保護」を開設しました。ウェブサイトでは、当協会のほか、秋田県保護司会連合会、更生保護施設秋田至仁会、秋田県更生保護女性連盟、秋田県BBS連盟、秋田県就労支援事業者機構のそれぞれについて沿革や活動内容、機関誌を紹介しており、更生保護に携わる方々だけでなく、更生保護に初めて触れる方々にも関心を持ってもらえるよう、分かりやすい内容とするよう工夫しています。実際、ウェブサイトをご覧になって保護司になることを希望する方もおられ、地域の皆様に更生保護を知っていただく身近なチャンネルとして、これからもサイトの充実を図っていきたいと考えています。行事等があった場合は随時更新していますので、是非御覧ください。
4 今後の展望について教えてください。
秋田県は高齢者率が最も高い都道府県であり、2045年(令和27年)には人口の半数が高齢者になるとの推計もあります。高齢者による再犯を防止することはもちろんのこと、更生保護の諸活動を息長く続けるためには、それぞれの更生保護関係団体が強みを生かし、相互に連携し合いながら、生き生きと活動していくことが大切だと思っています。当協会はこれからも秋田県での更生保護が充実・発展するよう、普及啓発やネットワーク化に力を尽くしてまいりたいと考えております。
- 秋田県の更生保護ウェブサイト https://akita-kouseihogo.com


- ※16 警察庁ウェブサイト「少年非行防止対策」
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/syonen/index.html
- ※17 更生保護ボランティアの活動を紹介するSNS
法務省エックス(旧ツイッター) https://x.com/MOJ_HOUMU
法務省保護局エックス(旧ツイッター) https://x.com/MOJ_HOGO
法務省保護局インスタグラム https://www.instagram.com/moj_kouseihogo/
- ※18 令和5年安全安心なまちづくり関係功労者表彰の受賞者及び功績概要
https://www.moj.go.jp/content/001403526.pdf