第1節 再犯防止に向けた基盤の整備等
(1)啓発事業等の実施【施策番号95】
法務省は、国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間(写真8-95-1参照)である7月を中心に、広報・啓発活動を積極的に展開しており、2023年度(令和5年度)は、再犯防止啓発ポスター等の作成やSNSを活用した広報啓発を実施した。また、2023年(令和5年)12月には「陣内智則がレポート「再犯防止の現場」~農園での立ち直り支援~」をYouTube法務省チャンネルで配信した。同動画は、タレントの陣内智則氏とタケト氏が、犯罪や非行をした人を雇用し、その立ち直りを支援している農園「埼玉福興株式会社」を訪問し、少年院に入院していた経験のある当事者やその支援者へのインタビューを通じて、再犯防止においては、民間協力者の存在が不可欠であることなどについて学んでいく内容となっている。
その他、法務省は全国8ブロックにおいて再犯防止シンポジウムを開催している。本シンポジウムは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、2020年度(令和2年度)以降、開催を中止していたが、2023年度は、「検察庁が関わる社会復帰支援・多機関連携」をテーマとして開催し、合計で2,724人の参加を得た。
以上に加え、法務省では、「“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~」を主唱している。この運動は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動である。2014年(平成26年)12月に犯罪対策閣僚会議において決定した「宣言:犯罪に戻らない・戻さない」において、全ての省庁を本運動の中央推進委員会の構成員にするとともに、2015年(平成27年)からは、毎年、国民の理解を求める内閣総理大臣メッセージを発出するなど、本運動は政府全体の取組としてその重要性が高まっている。再犯防止啓発月間である7月は、本運動の強調月間でもあり、全国各地において、運動の推進に当たっての内閣総理大臣メッセージや、ポスター等の広報啓発資材を活用し、地方公共団体や関係機関・団体と連携して、国民に対して広く広報啓発を行っている。
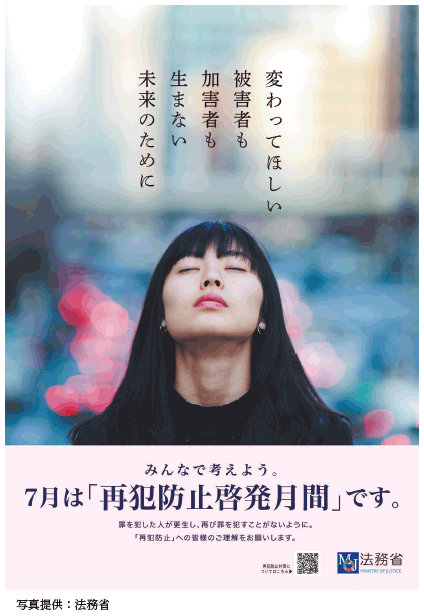
2023年に実施した第73回“社会を明るくする運動”では、「#生きづらさを生きていく。」をテーマ(写真8-95-2参照)に、全国で4万5,926回(前年:4万2,660回)の行事が実施され、延べ139万8,782人(前年:128万4,167人)が参加した(【指標番号21】参照)。同運動では、デジタルサイネージや、SNS等の多様な媒体を用いた広報等が行われた(写真8-95-3参照)。また、若年層を始めとする幅広い年齢層の方々にとって身近で親しみの持てるような広報を展開するため、更生保護マスコットキャラクターである「ホゴちゃん」の活用、吉本興業株式会社と連携した広報・啓発活動が行われた。
法務省の人権擁護機関では、刑を終えて出所した人の社会復帰に資するよう、「刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう」を人権啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を実施するとともに、全国の法務局や特設の人権相談所において人権相談に応じている。人権相談等を通じて、刑を終えた人に対する差別等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じている。2023年における刑を終えた人に対する差別待遇に関する人権侵犯事件の件数は2件であった(前年:4件)。
検察庁においては、学生や一般の方々を対象に実施する広報活動等において、検察庁における再犯防止・社会復帰支援に関する取組を説明するなど、再犯防止に関する広報・啓発活動を推進している。
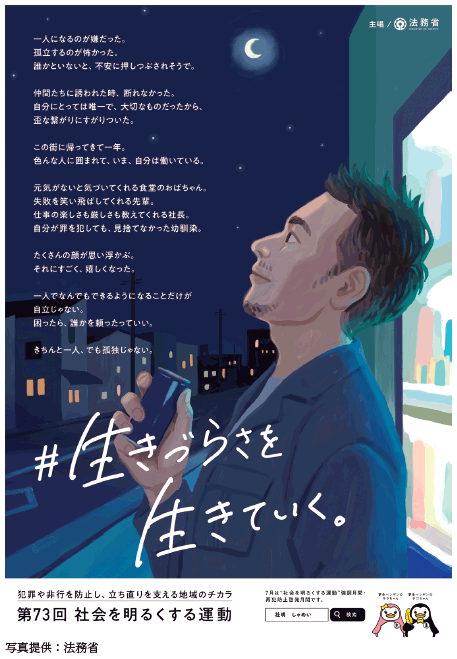
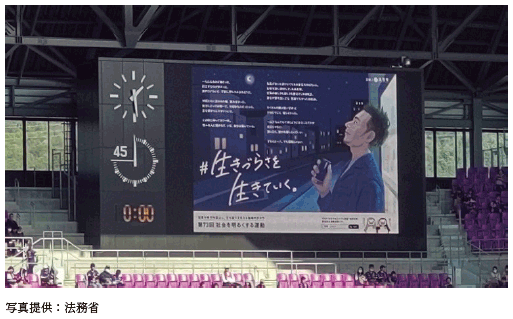
(2)法教育の充実【施策番号96】
法務省は、学習指導要領を踏まえた学校教育における法教育※4の実践の在り方及び教育関係者と法曹関係者による連携・協働の在り方等、法教育に関する取組について多角的な視点から検討するため、法教育推進協議会及び部会を開催(2023年度(令和5年度):10回、前年度:6回)している。
2023年度は、2022年(令和4年)4月に成年年齢が18歳に引き下げられたことを踏まえ、高校2年生を主な対象として、契約や私法の基本的な考え方を学ぶことができる高校生向けのリーフレットを全国の高等学校等に配布したほか、リーフレットの内容に関する専門家の解説動画等を法務省ウェブサイトで公開するなどした※5。
また、発達段階に応じた法教育教材を作成し、全国の小中学校、高等学校、教育委員会等に配布しており、2022年度(令和4年度)には、刑事裁判手続を模擬的に体験できる視聴覚教材である「もぎさい」法教育教材を作成し、教員用の説明資料、授業用ワークシート等の補助資料とともに法務省ウェブサイトで公開した※6。
これらの教材の利用促進を図るため、同教材等を活用したモデル授業例を法務省ウェブサイトで公開しているほか、法教育の具体的な実践方法を習得してもらうため、教員向け法教育セミナーを実施している。
さらに、学校現場等に法教育情報を提供することによって、法教育の積極的な実践を後押しするため、法教育に関するリーフレット※7を作成し、全国の小中学校、高等学校、教育委員会等に配布しているほか、学校や各種団体からの要請に応じて、法務省の職員を講師として派遣し、教員、児童・生徒や、一般の人々に対して法的なものの考え方等について説明する法教育授業を実施している。
矯正施設においても地域の学校等で法教育を行っているところ、特に、少年鑑別所(法務少年支援センター)では、地域援助として、教員研修において少年院・少年鑑別所に関する内容を始めとする少年保護手続等について講義を行うほか、参観の機会等を利用して少年鑑別所の業務等について説明を行うなどの法教育を行っている。主な内容としては、「少年保護手続の仕組み」、「特定の非行・犯罪の防止(薬物・窃盗・暴力等)」、「生活態度・友達づきあい」、「児童・生徒の行動理解及び指導方法」等である。2023年度には、矯正施設全体として約2,300回、延べ約11万3,000人に対して法教育を実施した(前年度:約1,500回、延べ約7万4,000人)。
また、保護観察所においては、学校との連携を進める中で又は広報の一環として、保護観察官や保護司が学校等に赴いて、更生保護制度等に関する説明を行うなどの法教育を実施しており、2023年度には、約350回、延べ約2万3,700人に対して法教育を実施した(前年度:約270回、延べ約1万7,500人)。
検察庁においては、学生や一般の方々に対し、刑事司法制度等に関する講義や説明等を実施するなどし、法教育を推進している。
ノウフクフェアの実施について
法務省保護局
「農福連携」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。「農業」と「福祉」が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現することで、「農業」と「福祉」の両分野がWin・Winの関係を構築することを目指す取組です。
この「農福連携」が本白書のテーマである「再犯防止」とどのように関係するのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。政府が2019年(令和元年)6月に農福連携等推進会議において決定した「農福連携等推進ビジョン」には、「「福」の広がりへの支援」として「犯罪や非行をした者の立ち直りに向けた取組」の項目が設けられています。「農福連携」の取組は障害者に限らず、犯罪や非行をした者にも広がりを見せるなど、更なる展開が期待されているのです。実際に、ソーシャル・ファームとして、社会福祉法人等が刑務所を出所した障害のある方を始めとする多様な人々を受け入れ、野菜の生産や畜産などの仕事で活躍する場を提供している例があります。法務省においても、茨城県ひたちなか市と北海道雨竜郡沼田町に「就業支援センター」を設置して、刑務所を仮釈放となった者や少年院を仮退院となった者等を受け入れ、自治体や地域の方々の協力を得ながら一定期間、農業実習を行うなど、就農等による円滑な社会復帰や立ち直りを支援しています。
しかし、特に、犯罪や非行をした者の農業分野における立ち直り支援の取組の広がりはまだまだ途上といったところです。農福連携等推進ビジョンにも広報活動の必要性が取り上げられているように、取組を広げていくためには、まずは知ってもらうことが何よりも重要です。
そこで、2023年(令和5年)10月には、農福連携の普及・啓発を目的とした「ノウフクウィーク2023」が開催されました。これは、農林水産省の呼び掛けにより、特定の一週間に農福連携関連のイベントが集中的に行われたものですが、この期間内に、法務省においても、農福連携等を推進する他の3省庁(農林水産省、厚生労働省、文部科学省)との共同プロジェクトとして「ノウフクフェア」を実施し、各省内の食堂の協力を得て、農福連携等により生産された農産物を用いたコラボメニューの提供を行いました。法務省内の食堂においては、刑務所出所者等を受け入れてくださっている事業所において生産された食材に加え、上述した就業支援センターの入所者が農業実習において生産した野菜や刑務所内において刑務作業として生産された食材を用いて、期間限定のパスタなどが提供されました。
2023年の取組は、基本的には法務省職員が利用する法務省内の食堂での実施となりましたが、今後は一般の方々の目にもとまりやすいような形での取組を検討しています。
読者の皆様も、今後、もしこのようなイベントに接する機会がありましたら、是非とも御参加いただき、食を通じて、農福連携等と再犯防止の取組への関心を高めていただければと思います。


- ※4 法教育
法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎となっている価値を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育であり、法教育の実践は自他の権利・自由の相互尊重のルールである法の意義やこれを守る重要性を理解させ、規範意識を涵養することを通じて再犯防止に寄与するものである。 - ※5 成年年齢引下げに向けた高校生向けリーフレット
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/houkyouiku_koukouseimukeleaflet.html
- ※6 「もぎさい」法教育教材
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/houkyouiku_mogisaiban.html
- ※7 法教育リーフレット
https://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/index2.html