第1節 就労の確保等
(1)多様な業種の協力雇用主の確保【施策番号9】
法務省は、コレワーク(【施策番号7イ】参照)において、刑務所出所者等の雇用に興味がある企業等に対して、刑務所出所者等の雇用に関する制度等について説明する雇用支援セミナーや、同セミナーと矯正施設の見学をセットにしたスタディツアー(写真2-9-1参照)等を開催するなど、刑務所出所者等の雇用に関する働き掛けを積極的に実施しており、2023年度(令和5年度)には、1,934件(前年度:1,609件)の広報活動を実施した。

また、2015年度(平成27年度)から、法務省が発注する矯正施設の小規模な工事の調達について、協力雇用主としての刑務所出所者等の雇用実績を評価する総合評価落札方式による競争入札を実施している。さらに、更生保護官署が少額の随意契約による調達を行う場合には、見積りを求める事業者の選定に当たって、当該契約案件に適した協力雇用主を含めるよう考慮している。その結果、更生保護官署が発注した公共調達について、協力雇用主が受注した件数は2023年度は25件(前年度:22件)であった。
以上のほか、2023年(令和5年)12月末現在、全国の都道府県及び市区町村のうち、協力雇用主としての刑務所出所者等の雇用実績等について、入札参加資格の審査で評価している地方公共団体は198団体、総合評価落札方式において評価している地方公共団体は79団体であった(資2-9-1参照)。
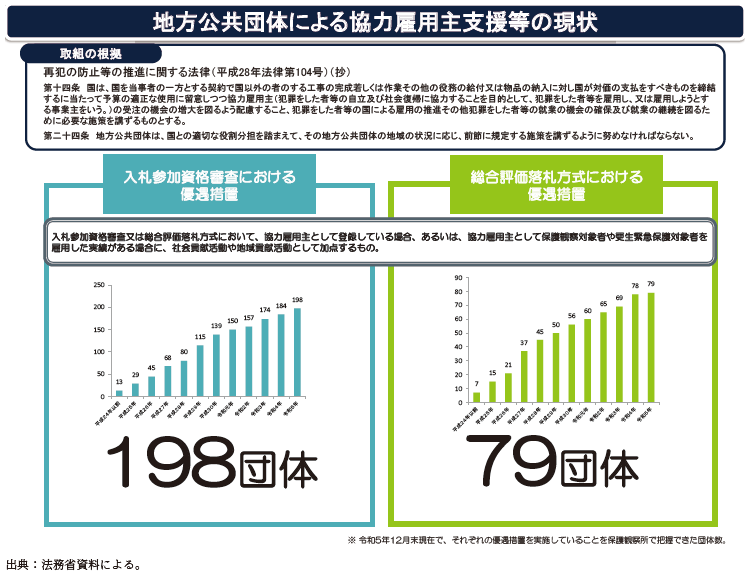
保護観察所では、各都道府県の就労支援事業者機構※16や更生保護関係者、矯正施設、労働局、ハローワーク、地方公共団体、商工会議所等経済・産業団体その他関係機関・団体等と連携して、協力雇用主募集パンフレット※17の配布、協力雇用主募集ポスター※18の掲示、事業所への個別訪問、説明会の開催等を通じて協力雇用主に係る広報活動を積極的に行い、協力雇用主の少ない業種を含め多様な業種の協力雇用主の開拓・確保に努めるとともに、保護観察対象者等の雇用についての理解と協力を求めている。
これらの取組により、協力雇用主の数は、2023年10月現在、24,969社となっている(【指標番号9】参照)。
なお、保護観察所において協力雇用主を登録する手続は、警察庁及び厚生労働省と協議した上で2018年(平成30年)8月に作成した「協力雇用主登録等要領」に基づいて適切に運用している。
農林水産省は、2016年度(平成28年度)から、農林漁業の関係団体のほか、個別の事業者に対しても、新規雇用に関する補助事業の説明会等において、協力雇用主制度の周知・登録要請等を行っている。なお、農林漁業関係の協力雇用主の数は、2023年10月1日現在、457社(前年:474社)であった。
(2)協力雇用主等に対する情報提供【施策番号10】
法務省は、厚生労働省と連携し、刑務所出所者等の就労支援に係る各種制度を紹介するパンフレットを作成し、協力雇用主等に配布して更なる理解促進に努めている。保護観察所では、協力雇用主を対象とした研修等を実施し、協力雇用主として承知しておくべき基本的事項や雇用管理上の留意すべき事項について情報提供を行っているほか、協力雇用主の間では、実際に刑務所出所者等を雇用する上でのノウハウや活用できる支援制度、危機場面での対処法等について、相互に情報交換が行われている。
また、協力雇用主が刑務所出所者等を雇用する上で必要な個人情報については、保護観察所において、当該刑務所出所者等から同意を得た上で提供している。
(3)協力雇用主の不安・負担の軽減【施策番号11】
法務省は、刑務所出所者等が雇用主に業務上の損害を与えた場合等に見舞金が支払われる身元保証制度(資2-11-1参照)の活用、刑務所出所者等と雇用主の双方への寄り添い型の支援を行う更生保護就労支援事業(【施策番号7ウ】参照)の実施、刑務所出所者等を雇用して指導に当たる協力雇用主に対し年間最大72万円を支給する刑務所出所者等就労奨励金支給制度(資2-11-2参照)の活用、受刑者の採用面接等を行う協力雇用主等に対する面接時の矯正施設までの旅費の支給等により、協力雇用主の不安や負担の軽減を図っている。刑務所出所者等就労奨励金支給制度においては、2022年度(令和4年度)に、他の年齢層と比べて、職場定着に困難を抱えやすい18・19歳の者を雇用し、かつ、その者に対して手厚く指導に当たる協力雇用主に対して、加算金を支給する制度を導入していたところ、2023年度(令和5年度)からは、被雇用者が18歳未満の場合も加算対象とし、協力雇用主への支援の更なる充実を図った。2023年度は、身元保証を1,403件(前年度:1,372件)、刑務所出所者等就労奨励金の支給を2,661件(前年度:2,919件)実施した。
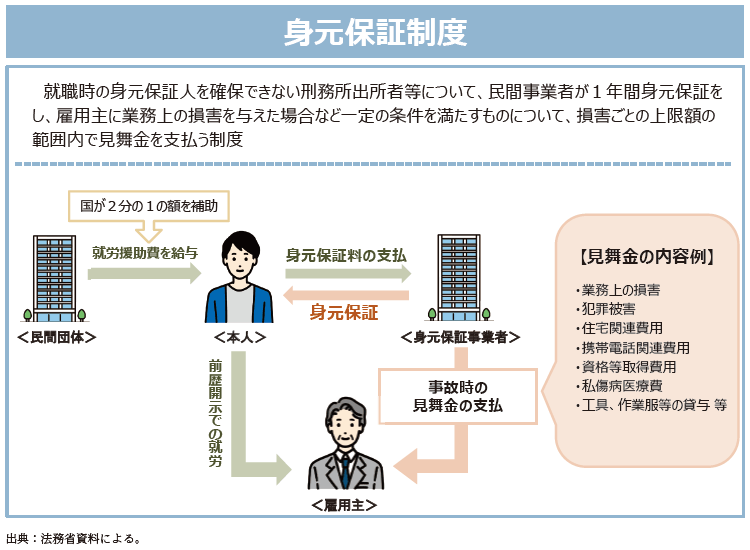
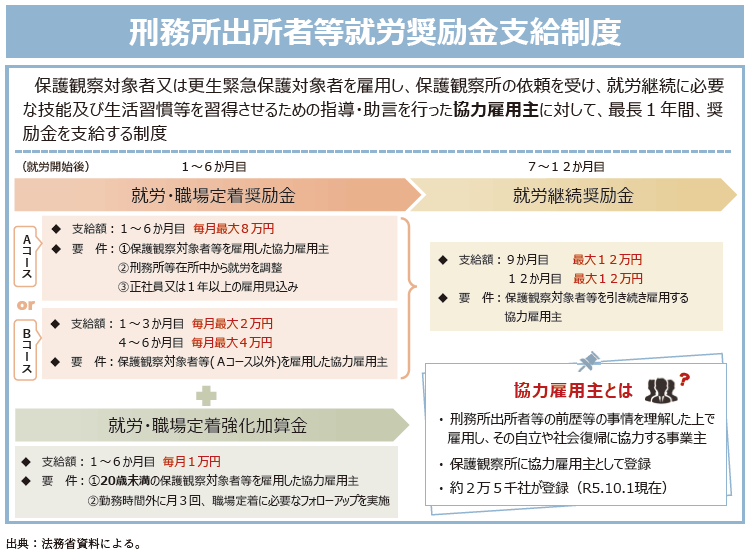
加えて、2018年度(平成30年度)からは、企業がコレワーク(【施策番号7イ】参照)に無料で電話相談ができる無料通話回線を開設しているほか、コレワークに刑務所出所者等の雇用について豊富な知見を持つ雇用支援アドバイザーを招へいして就労支援に係る相談会を実施するなど、刑務所出所者等を雇用する企業の不安や負担の軽減等に努めている。
(4)協力雇用主に関する情報の適切な共有【施策番号12】
法務省及び厚生労働省は、関係省庁における協力雇用主に対する支援の円滑かつ適切な実施に資するよう、協力雇用主募集のパンフレット及びポスター(【施策番号9】参照)を作成し、関係省庁に配布した上で、これを活用した積極的な広報を依頼している。
また、協力雇用主に関する情報を法務省ウェブサイトに掲載し、随時更新や見直しを行っている。
(5)国による雇用等の推進【施策番号13】
法務省及び厚生労働省は、2013年度(平成25年度)から、保護処分を受けた保護観察対象者※19を非常勤職員として雇用する取組を行っており、2023年度(令和5年度)末までに、法務省89人(うち少年鑑別所79人)、厚生労働省1人の合計90人の少年を雇用した。雇用期間中は、少年の特性に配慮しつつ、就労を体験的に学ぶ機会を提供するとともに、必要に応じて少年からの相談に応じるなどのサポートを行っている。
法務省は、これらの取組実績を踏まえ、保護処分を受けた保護観察対象者を雇用する上での留意事項を整理した上で、2019年度(令和元年度)に、他の関係省庁に参考指針を示し、2023年度には、これを改定して、改めて関係省庁に対し、保護観察対象者の雇用受入れについて協力を求めている。
なお、地方公共団体のうち、保護観察対象者を雇用する取組を実施している団体は、2023年(令和5年)12月末時点で71団体であり、2010年(平成22年)から2023年までで、延べ82人の保護観察対象者が雇用された。
- ※16 就労支援事業者機構
犯罪をした人等の就労の確保は、一部の善意の篤志家だけでなく、経済界全体の協力と支援により成し遂げられるべきとの趣旨に基づいて設立され、事業者の立場から安全安心な社会づくりに貢献する活動を行う法人。認定特定非営利活動法人全国就労支援事業者機構(全国機構)と50の都道府県就労支援事業者機構(都道府県機構)がある。
全国機構は、中央の経済諸団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)や大手企業関係者が発起人となり設立され、都道府県機構等に対する助成や協議会の開催等全国的なネットワークでの事業推進を図っており、都道府県機構は、協力雇用主等を会員に持ち、保護観察所等の関係機関や保護司等の民間ボランティアと連携し、具体的な就労支援の取組を行っている。 - ※17及び18 協力雇用主募集のパンフレット及びポスター
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00030.html
- ※19 保護処分を受けた保護観察対象者
非行により家庭裁判所から保護観察の処分を受けた少年や、非行により家庭裁判所から少年院送致の処分を受け、その少年院から仮退院した者。