第1節 高齢者又は障害のある者等への支援等
(1)保健医療・福祉サービスの利用に向けた手続の円滑化【施策番号29】
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳※4(以下これらを合わせて「障害者手帳」という。)については、矯正施設在所中の交付手続がより一層促進されるよう、2021年度(令和3年度)から、一部の刑事施設において、障害者手帳の交付を受けるために必要な医師による診察等を実施している。また、障害福祉サービス等については、出所後に円滑に利用されるように、市町村の認定調査員が矯正施設を訪問するなどして矯正施設在所中の者に対する障害支援区分の認定を行い、障害福祉サービス等の支給決定を行っている。さらに、生活保護については、生活保護制度における保護の実施責任が要保護者の居住地(要保護者の居住事実がある場所)又は現在地により定められるとされていることから、要保護者が矯正施設の出所者の場合、帰住先が出身世帯であるときはその帰住先を居住地とし、そうでないときはその帰住先を現在地とみなすこととし、国から地方公共団体へその旨周知している。
法務省は、受刑者等の住民票が消除されるなどした場合にも、矯正施設出所後速やかに保健医療・福祉サービスを利用できるよう、矯正施設職員向けの執務参考資料を作成し、協議会や研修において、職員に対して住民票の取扱いを含めた保健医療・福祉サービスを利用するための手続等の周知を図っている。
(2)社会福祉施設等の協力の促進【施策番号30】
障害福祉サービス事業所が矯正施設出所者や医療観察法に基づく通院医療の利用者等である障害者(以下「矯正施設出所者等である障害者」という。)を受け入れるに当たっては、①きめ細かな病状管理、②他者との交流場面における配慮、③医療機関等との連携等の手厚い専門的な対応が必要であるため、業務負担に応じた報酬を設定することが求められている。
厚生労働省は、このような状況を踏まえ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において、障害のある人が共同生活する場であるグループホーム等で、矯正施設出所者等である障害者に対し、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合を報酬上評価している。
また、「社会生活支援特別加算」において、訓練系、就労系障害福祉サービス(就労定着支援事業を除く。)事業所が精神保健福祉士等を配置している場合等に、矯正施設出所者等である障害者に対し、①本人や関係者からの聞き取りや経過記録・行動観察等によるアセスメントに基づき、他害行為等に至った要因を理解し、再び同様の行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた個別支援計画等の作成、②指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催、③日中活動の場における緊急時の対応等の支援を行うことを報酬上評価している(【施策番号15】参照)。
(3)被疑者等への支援を含む効果的な入口支援の実施【施策番号31】
法務省及び厚生労働省は、2021年度(令和3年度)から、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対する支援を開始した。具体的には、地域生活定着支援センターが実施している地域生活定着促進事業の業務として、新たに被疑者等支援業務を加え、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対して、地域生活定着支援センターと検察庁、弁護士会、保護観察所等が連携し、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行うとともに、釈放後も地域生活への定着等のために支援等を行う取組を実施している(資3-31-1参照)。
また、2022年度(令和4年度)からは、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者を被疑者等支援業務による支援に更につなげられるようにするため、弁護士との連携強化を促進している。
保護観察所では、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対する上記の取組を含め、検察庁等と連携した起訴猶予者等に対する更生緊急保護の措置として、一定の期間重点的な生活指導等を行うとともに、福祉サービス等に係る調整のほか、就労支援等の社会復帰支援を行う「更生緊急保護の重点実施等」を行ってきた。また、2023年(令和5年)12月1日に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正後の更生保護法(平成19年法律第88号)が施行されたことに伴い、「更生緊急保護の重点実施等」の運用を踏まえ、勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めた者について、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行う「勾留中の被疑者に対する生活環境の調整」を開始するとともに、勾留中の被告人についても同様の調整を実施している。2023年4月から11月までに、検察庁から事前協議を受け、更生緊急保護の重点実施等を行った人員は、345人(前年度:473人)であり、2023年12月に勾留中の被疑者又は被告人に対する調整を開始した人員は、58人であった。
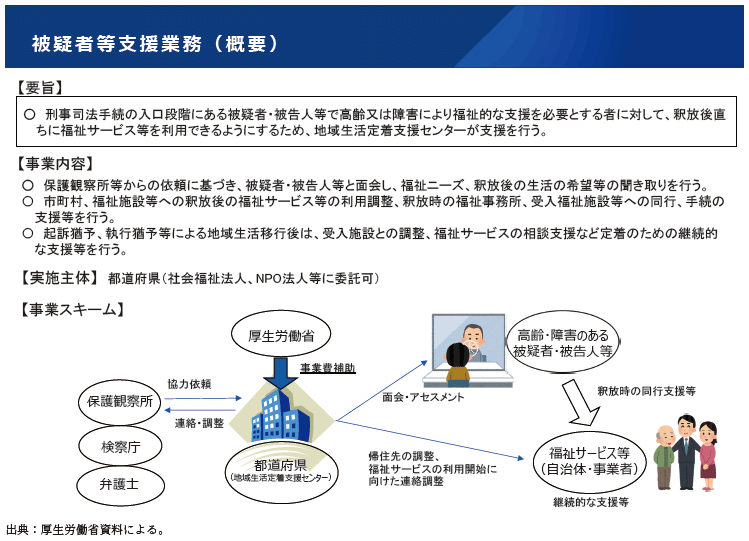
(4)保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための研修・体制の整備【施策番号32】
ア 刑事司法関係機関
法務省は、検察官に対する研修等において、犯罪をした者等の福祉的支援の必要性を的確に把握することができるよう、再犯防止の取組等について講義を実施している。
矯正施設職員に対しては、各種集合研修において、高齢者又は障害のある者等の特性についての理解を深めるため、社会福祉施設における実務研修(勤務体験実習)や社会福祉施設職員による講義・指導等の実施、高齢受刑者に対する改善指導とその課題等についての講義を実施している。また、2023年度(令和5年度)現在、刑務官を対象とした研修として、認知症サポーター養成研修を合計76庁、福祉機関における実務研修を合計32庁でそれぞれ実施している。また、発達上の課題を有する在院者の処遇に当たる少年院職員に対し、適切に指導するための知識、技能を付与することを目的とした研修を実施している。
更生保護官署職員に対しては、高齢者又は障害のある者等の特性や適切な支援の在り方についての理解を深めるため、新任の保護観察官、指導的立場にある保護観察官及び福祉的支援を行う保護観察官に対する研修において、地域生活定着支援センター職員等による講義を実施している。
また、検察庁は、社会復帰支援業務を担当する検察事務官の配置や社会福祉士から助言を得られる体制の整備により、社会復帰支援の実施体制の充実を図っている。
さらに、保護観察所においては、社会復帰対策班を設置し、入口支援(【施策番号31】参照)にとどまらず、更生緊急保護の対象者に継続的に関与し、その特性に応じた支援が受けられるよう関係機関等と調整を行うなどの社会復帰支援の充実を図っている。
イ 更生保護施設
法務省は、一部の更生保護施設を指定更生保護施設に指定し、社会福祉士等の資格等を持った職員を配置し、高齢者又は障害のある者の特性に配慮しつつ社会生活に適応するための指導を行うなどの特別処遇(資3-32-1参照)を実施している。指定更生保護施設の数は、2024年(令和6年)4月現在で、77施設であり、2023年度に特別処遇の対象となった者は、1,860人(前年度:1,861人)であった。
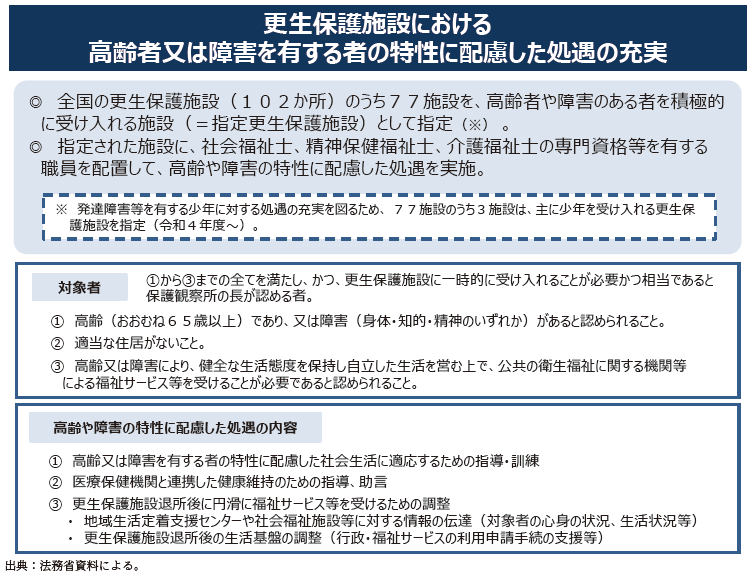
ウ 地域生活定着支援センター、保健医療・福祉関係機関
厚生労働省は、地域生活定着支援センターについて、その実施主体である都道府県と協働し、地域の支援ネットワークの構築を通じて活動基盤の充実を図るとともに、2020年度(令和2年度)から、同センター職員の専門性や支援の質の向上を目的とした研修を実施している。
また、法務省は、地域の保健医療・福祉関係機関の職員等に対し、刑事司法手続等に関する必要な研修を実施している。
「孤独」に加えて「制度の狭間」で苦しんでいる生活者の支援
浜松市生活自立相談支援センターつながり
浜松市生活自立相談支援センターつながり(以下「当事業所」という。)は、生活困窮者自立支援制度が施行された2015年度(平成27年度)から、浜松市から(社福)聖隷福祉事業団が受託運営しており、様々な理由で経済的に困窮している世帯に対して相談に応じ、「断らずに聴き伴走する」を大切にしながら支援を実施しています。具体的には就職を目指した支援、家計のやりくりや債務・滞納の対応、住居を提供しながら自立を目指す支援、子供たちの学習支援や将来を描くためのキャリア支援、ホームレスの方の巡回支援等を実施しています。
当事業所に相談に来られる方のほとんどが、頼れる親族がいない、医療や福祉等の制度につながりにくい「孤独」に加えて「制度の狭間」で苦しんでいる方で、それら相談者の中には、万引きや無銭飲食等の犯罪をし、裁判所における審理後に釈放される方もいます。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動の抑制の影響で、経済的困窮に陥ったことも犯罪につながる要因であることを支援を通して痛感しています。
静岡地方検察庁刑事政策推進室から釈放後の支援依頼をいただくようになり、「孤独」と「制度の狭間」に苦しんでいる方々とつながる機会が増加しました。
当事業所は、支援を開始するに当たり、対象者との面談を実施し、その方の生活背景や心身の状況、社会経験等を限られた時間の中で丁寧に聞きながら、関係性を作り、「再び生きていく」、「この人になら話をしよう」と思っていただけることを心掛けて関わっていますが、毎回難しさを感じています。
釈放後の支援に関わった中で、冒頭に述べた「断らずに聴き伴走する」ことを改めて考えさせられた対象者の支援を紹介します。
対象者は外国籍の方であり、就労目的で来日されました。しかし、その方はもともと精神的な不調を抱えていたため離職して経済的に困窮することとなり、携帯電話の充電を自宅ではできないためコンビニのコンセントを使用していたところ、注意をした店員へ手を挙げてしまい逮捕されました。言語の問題や精神的に不安定な状況、何より手持ち金がない状態であった本人が単独で生活を再建することは困難でした。また、生活保護を考えましたが、在留カードの住所が他県であったため手続には現地まで行く必要もありました。
静岡地方検察庁から依頼を受けたとき「この方を支援できる制度はない」と思ったものの、それと同時に「当事業所がやらねば誰がやる」と思い、支援を開始しました。他県への生活保護の申請同行、住まい探し、医療・福祉へのつなぎ等を短期間で実施しました。その中で、行政機関や不動産事業者、福祉事業所等も本来の枠を超えて連携していただき、「熱量を持った支援は周りに伝わる」ことを実感しました。
現在の日本は各種制度が整えられ、病気や障害等の心身上の危機、離職等の経済的危機等の様々な危機的場面を回避できる制度が整っています。一方で、これまで述べてきたように「孤独」と「制度の狭間」にいる方は存在し続けています。それらの社会的課題に対しては「熱量を持ち枠から半歩足を出した支援」を展開していくことが重要であり、これこそが社会福祉の源流であると考えます。これからも静岡地方検察庁の皆様、行政機関や地域の関係機関、民間の方々と顔の見える関係を作りながら「熱量を持ち枠から半歩足を出した支援」とは何かということを語って共有し、「孤独」と「制度の狭間」にいる方々を支えられる地域づくりに尽力していきます。


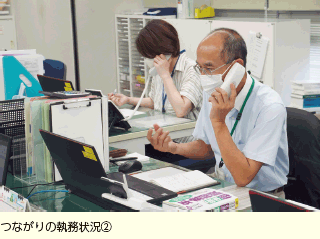






- ※4 療育手帳
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して、都道府県知事又は指定都市市長(一部の児童相談所を設置する中核市市長)が交付する手帳である。