第1節 学校等と連携した修学支援の実施等
(1)学校等と保護観察所が連携した支援等【施策番号45】
法務省は、保護観察所において、学校に在籍している保護観察対象者等について、類型別処遇(【施策番号62】参照)における「就学」類型として把握した上で、必要に応じて、学校と連携の上、修学に関する助言等を行っている。
文部科学省は、児童生徒が非行問題を身近に考えることができるよう、外部講師として保護観察官や保護司、BBS会員を招へいして講話を実施するなど、非行防止教室を積極的に実施するよう学校関係者に依頼している。
また、保護司会においては、犯罪予防活動の一環として行っている非行防止教室や薬物乱用防止教室、生徒指導担当教員との座談会等の開催を促進するなどして、保護司と学校との連携強化に努めている。
法務省及び文部科学省は、2019年(令和元年)6月に、矯正施設における復学手続等の円滑化や高等学校等の入学者選抜及び編入学における配慮を促進するため、相互の連携事例を取りまとめ、矯正施設、保護観察所及び学校関係者に対して周知し(資4-45-1参照)、さらに2023年(令和5年)12月には、改訂版の周知を行った。
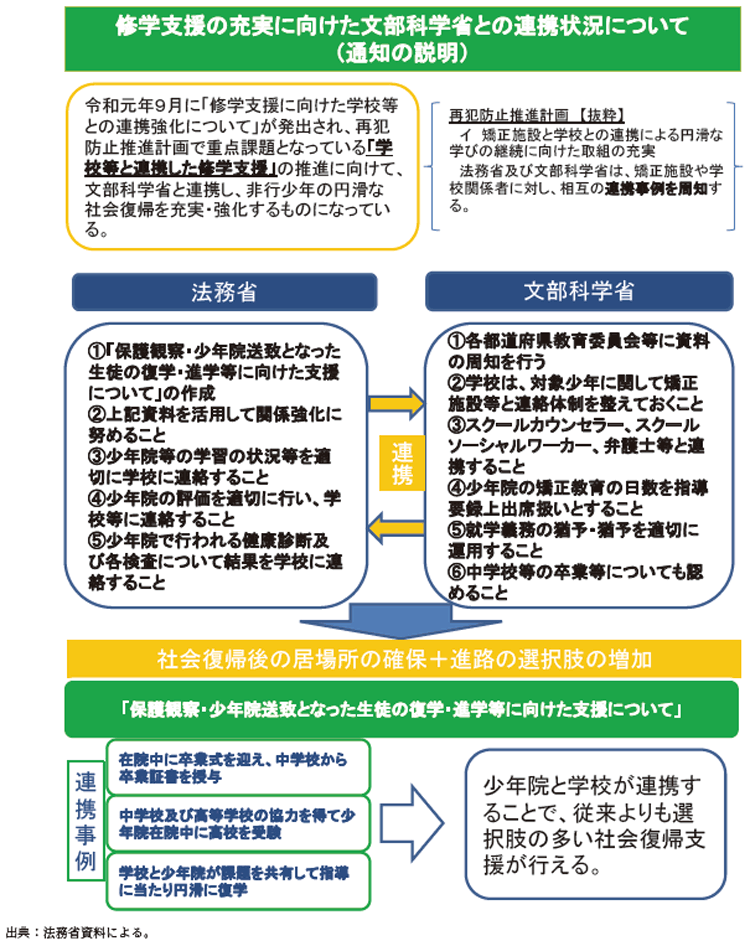
(2)矯正施設と学校との連携による円滑な学びの継続に向けた取組の充実【施策番号46】
法務省は、刑事施設において、社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し、教科指導を実施しており、2023年度(令和5年度)の受講開始人員は補習教科指導※12が666人(前年度:701人)、特別教科指導※13が362人(前年度:382人)であった。松本少年刑務所には、我が国において唯一、公立中学校の分校が刑事施設内に設置されており、全国の刑事施設に収容されている義務教育未修了者等のうち希望者を中学3年生に編入させ、地元中学校教諭、職員等が、文部科学省が定める学習指導要領を踏まえた指導を行っている。また、松本少年刑務所及び盛岡少年刑務所では近隣の高等学校の協力の下、当該高等学校の通信制課程で受刑者に指導を行う取組を実施しており、そのうち松本少年刑務所では全国の刑事施設から希望者を募集して、高等学校教育を実施しており、所定の課程を修了したと認められた者には、高等学校の卒業証書が授与されている。
少年院では、義務教育未修了者に対する学校教育の内容に準ずる内容の指導のほか、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる在院者に対して教科指導を実施している。また、在院者が出院後に円滑に復学・進学等ができるよう、矯正施設や学校関係者の研修等の際には講師を相互に派遣するなどして、相互理解に努め、通学していた学校との連携や、進学予定である学校の受験機会の付与等を行っている。加えて、2021年度(令和3年度)から、在院者が高等学校教育についての学びを継続するための方策として、少年院在院中から通信制課程を設置する高等学校(以下「通信制高校」という。)に入学し、インターネット等を活用した学習を可能にするとともに、少年院の矯正教育で高等学校学習指導要領に準じて行うものを通信制高校での単位として認定するなどの措置を講じることを一部の少年院において試行していたところ、2024年度(令和6年度)からは、全ての少年院において、希望する在院者に対して高等学校教育の機会を提供することとしている。なお、2023年(令和5年)には、85人(前年:83人)が復学又は進学が決定した上で出院した。
少年鑑別所では、在所者に対する健全な育成のための支援として、学習用教材を整備しており、在所者への貸与を積極的に行うとともに、学習図書の差入れ等についても配慮している。また、小・中学校等に在学中の在所者が、在籍校の教員等と面会する際には、希望に応じて、教員等による在所者の学習進度の確認、学習上の個別指導の実施が可能となるよう、面会の時間等に配慮している。
2018年度(平成30年度)から、少年鑑別所在所者が希望した場合には「修学情報ハンドブック」を配付し、自分の将来について考え、学ぶ意欲を持つことができるよう配意している。また、少年院では、出院後に中学校等への復学が見込まれる者や高等学校等への復学・進学を希望している者等を修学支援対象者として選定し、重点的に修学に向けた支援を行っている。特に、修学支援対象者等については、修学情報ハンドブック等を活用して、出院後の学びについて動機付けを図っているほか、少年院内で実施した修学に向けた支援に関する情報を保護観察所等と共有することで、出院後も本人の状況等に応じた学びが継続できるよう配意している。さらに、民間の事業者に委託して、修学支援対象者が希望する修学に関する情報の収集と提供を行っており(修学支援デスク)、2023年度には、延べ286人(前年:265人)が利用した。
法務省及び文部科学省は、2023年12月に、矯正施設における復学手続等の円滑化を図るため相互の連携事例を取りまとめた資料を改訂し、矯正施設・保護観察所及び学校関係者に対して周知している(【施策番号45】参照)。あわせて、文部科学省は、出院後の復学を円滑に行う観点から、学齢児童生徒が少年院及び少年鑑別所に入・出院(所)した際の保護者の就学義務や当該児童生徒の学籍、指導要録の取扱い等に関し、少年院における矯正教育や少年鑑別所における学習等の支援に係る日数について、学校は一定の要件下で指導要録上出席扱いにできることとするなど、適切な対応を行うよう各都道府県教育委員会等に周知している。
(3)矯正施設における高等学校卒業程度認定試験の指導体制の充実【施策番号47】
法務省及び文部科学省は、受刑者及び少年院在院者の改善更生と円滑な社会復帰を促す手段の一つとして、刑事施設及び少年院内で高等学校卒業程度認定試験を実施している。
法務省は、4庁(川越少年刑務所、笠松刑務所、加古川刑務所及び姫路少年刑務所)の刑事施設を特別指導施設に指定し、同試験の受験に向けた指導を積極的かつ計画的に実施している。全国の刑事施設における2023年度(令和5年度)の同試験受験者数は303人(前年度:366人)であり、同試験合格者(同試験の合格に必要な全ての科目に合格し、大学入学資格を取得した者をいう。以下同じ。)が129人(前年度:170人)、一部科目合格者(同試験の合格に必要な科目のうち一部の科目に合格した者をいう。以下同じ。)が151人(前年度:167人)であった。
少年院では、在院者の出院後の修学又は就労に資するため、同試験の重点的な受験指導を行うコースを13庁に設置し、外部講師を招へいするなどの体制を整備している。全国の少年院における2023年度の同試験受験者数は424人(前年度:377人)であり、同試験合格者が162人(前年度:151人)、一部科目合格者が239人(前年度:213人)であった(【指標番号19】参照)。
- ※12 補習教科指導
学校教育法(昭和22年法律第26号)による小学校又は中学校の教科の内容に準ずる内容の指導 - ※13 特別教科指導
学校教育法による高等学校又は大学の教科の内容に準ずる内容の指導