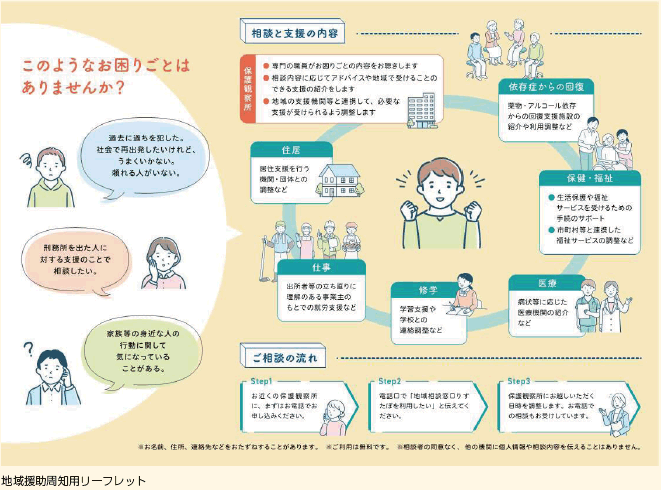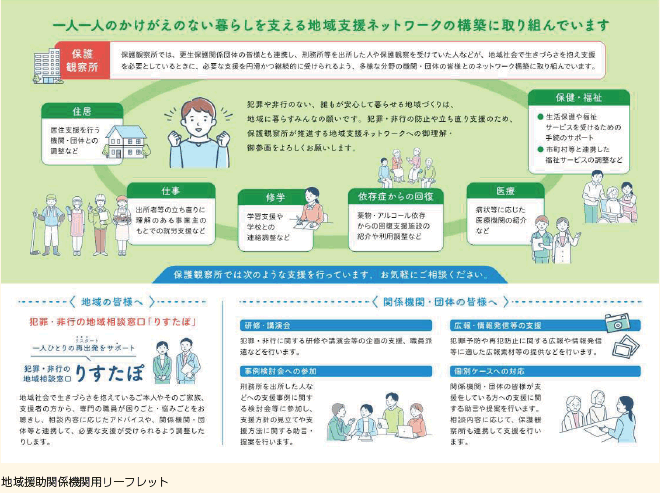第1節 地方公共団体との連携強化等
(1)刑執行終了者等に対する援助の充実【施策番号86】
法務省は、保護観察所において、2023年(令和5年)12月1日から施行された改正更生保護法により新設された、刑執行終了者等に対する援助を実施している。保護観察所においては、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、その特性や支援ニーズに応じた情報の提供、助言等を行うほか、地域の関係機関・団体等による必要な支援につながるよう必要な調整を行うなどの援助を実施している。刑執行終了者等に対する援助は、本人からの自発的な申出を待つことなく、保護観察所が能動的に働き掛けて実施することが可能なもので、かつ法定期間の定めもないという点で、更生緊急保護(【施策番号25】参照)を補完する援助の措置として位置付けられる。
(2)更生保護施設による訪問支援事業の拡充【施策番号87】
法務省は、更生保護施設退所者等が地域生活に定着するまでの間の継続的な支援として、2017年度(平成29年度)から更生保護施設に通所して支援を受けるフォローアップ事業(【施策番号20】参照)を委託する取組を実施してきたところ、自発的に更生保護施設に通所できないなど、フォローアップ事業では支援の手が届かない者に対して必要な支援を行うため、2021年(令和3年)10月からは、自宅等を訪問するなどして生活相談支援等をアウトリーチで行う訪問支援事業の委託を開始した。フォローアップ事業については、2023年度(令和5年度)の委託実人員は1,159人(前年度:905人)、延べ人員は8,505人(前年度:5,866人)であり、訪問支援事業については、2024年(令和6年)4月現在で全国19施設において実施し、2023年度の委託実人員は445人(前年度:345人)、延べ人員は2,858人(前年度:2,087人)である(資7-87-1参照)。
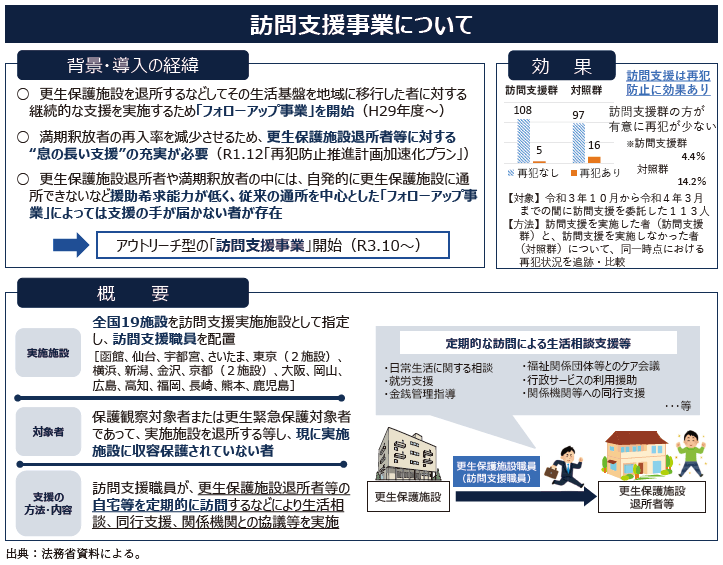
地域再犯防止推進事業
法務省大臣官房秘書課
再犯防止施策の効果を上げていくためには、国が主体的にその取組を進めていく必要があることは言うまでもありませんが、刑事司法手続を終了した後、すなわち、国の関与が及ばなくなった後も、犯罪をした者等が切れ目なく必要な支援を受けられるようにすることが重要です。その支援の主な実施主体としては、住民に対して様々な行政サービスを提供する地方公共団体が想定されています。
この点に関し、国・地方が具体的に担う役割が不明確であるとの地方公共団体の声を受け、資料上段に記載のとおり、2023年(令和5年)3月17日に閣議決定された「第二次再犯防止推進計画」において、国・都道府県・市区町村の役割が明示されました。
具体的には、それぞれの役割について、
・国は、刑事司法手続段階における指導・支援を実施することに加え、地方公共団体や民間協力者等に対する財政面を含めた必要な支援を行うこと
・都道府県は、広域自治体として、各市区町村で再犯防止の取組が円滑に行われるよう、市区町村に対する必要な支援や域内のネットワークの構築に努めるとともに、市区町村が単独で実施することが困難と考えられる専門的な支援を実施すること
・市区町村は、地域住民に最も身近な基礎自治体として、保健医療・福祉等の各種行政サービスを必要とする犯罪をした者等が、地域住民の一員として地域で安定して生活できるよう、適切にサービスを提供すること
などが明記されています。
こうした役割分担に基づき、地方における再犯防止の取組を一層促進するため、国及び都道府県の取組として、2023年度(令和5年度)から「地域再犯防止推進事業」を開始しています。
本事業は、都道府県が
・市区町村に対する施策の企画立案支援(域内の市区町村における再犯防止の取組が円滑に実施できるよう支援を行うもの)
・市区町村に対する理解促進・人材育成(域内の市区町村の職員等が再犯防止に関する理解を深めることができるよう支援を行うもの)
・犯罪をした者等に対する直接支援(犯罪をした者等に対し、市区町村が単独では実施することが困難と考えられる支援や罪種・特性に応じた専門的な支援を行うもの)
を実施するに当たり、国(法務省)がその経費の1/2、最大150万円を補助する事業です。
本事業の実施により、域内の市区町村の再犯防止の体制・基盤が整備され、市区町村における再犯防止の取組が促進されることや、市区町村レベルでは対応が難しい就労・住居支援、性犯罪者・薬物事犯者等に対する専門的支援等の効果的な実施などが期待されます。
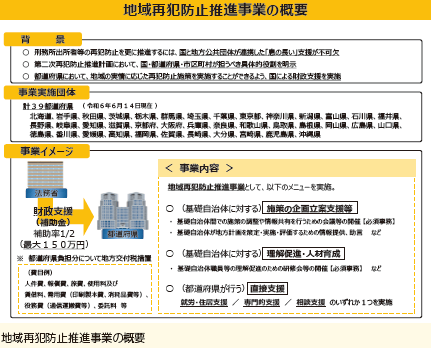
罪を犯した依存症者の支援拠点づくり
ジャパンマック福岡
2013年(平成25年)、福岡市に依存症からの回復と成長を目指す人たちを支援する施設「ジャパンマック福岡」が誕生しました。多くの依存症者と関わっていく中で、依存症が背景にあり罪を犯してしまう人々の支援にも携わるようになりました。薬物依存症や窃盗症(クレプトマニア:万引き・物盗りがやめられない)、性依存症(性嗜好障害:盗撮や痴漢行為がやめられないなど)の場合は依存行為そのものが法に触れてしまいますし、ギャンブル依存症でギャンブルするために会社のお金を横領する、アルコール依存症で酔っ払ってお酒を万引きする…という人もいます(私たちはこれらの依存症を「触法依存症」と呼んでいます。)。そうした人の中には、動機付けがなかなかうまくいかず、依存症の治療につながらない人が一定数います。また、再犯を繰り返す人は、一度矯正施設に入所すると支援が途切れてしまい、出所後も同じことを繰り返してしまう傾向にあることから、入所中も支援を継続することが再犯の防止に寄与すると考えました。そのような支援はこれまでの障害福祉サービスの枠組みの中だけでは難しいものでしたが、休眠預金活用事業(2019年度(令和元年度)通常枠:事業実施期間は2020年(令和2年)3月から2023年(令和5年)3月まで)により、触法依存症者への支援を行う「犯罪を犯した依存症者の支援拠点づくり」事業を開始しました。事業を行う機関として、ジャパンマック福岡内に「依存症者回復支援センター」を設置し、名称を「エール」(応援団:https://yell-fukuoka.jp/jmac/)として活動を行うことになりました。
エールには大きく分けて四つの役割があります。
①顕在化支援…当センターだけでなく、矯正施設や留置場、病院等へ面会に出向き、依存症について知ってもらい、回復への動機付けを行う支援。啓発のための漫画冊子の作成・配布、社会資源の紹介、裁判支援(情状証人、支援計画等の作成など)などを行います。矯正施設入所者に対しては、手紙や面会等で支援を継続します。
②回復支援…顕在化の活動を経た、継続的な回復のための支援(期限のない支援)。個別の回復支援計画を立て、回復の場への同行支援、継続的な面談、回復プログラムへの参加促進(窃盗症の人及び性依存症の人向けの回復プログラムの作成・実施)等を行います。
③家族支援…疲弊し不安を抱えた家族に対し依存症という病気について知ってもらうため、定期的な面談を行うほか、家族会などの社会資源の紹介・つなぎを行います。
④関係機関との連携…触法依存症者の方々は依存症の問題だけではなく、多様かつ複雑な問題を抱えている場合が少なくありません。一か所だけでの支援で解決することは困難ですし、一か所にしかつながっていないと、そこから離れてしまったときにつながることのできる場がなくなってしまいます。そこで、地域の関係機関とネットワークを作り、複数の機関で協力し合って息の長い支援をしていきます。これまで、主に、検討委員会(連携会議・年2回開催)の中で事業報告や事例検討を行い、関係機関職員向け研修会(年1回)を開催する中で、少しずつエールの存在が認知され、関わりのある機関が増えてきました。2023年度(令和5年度)からは、同じく休眠預金活用事業(2023年度通常枠:事業実施期間は2023年4月から2026年(令和8年)3月まで)により「人生の再出発を支援し、支援者も支えるネットワークづくり」事業を開始しているところで、現在、保護観察所や更生保護団体等にも少しずつネットワークが広がっており、医療や福祉、司法や更生保護等様々な分野の機関と協力しながら触法依存症者やその家族のサポートを行っています。
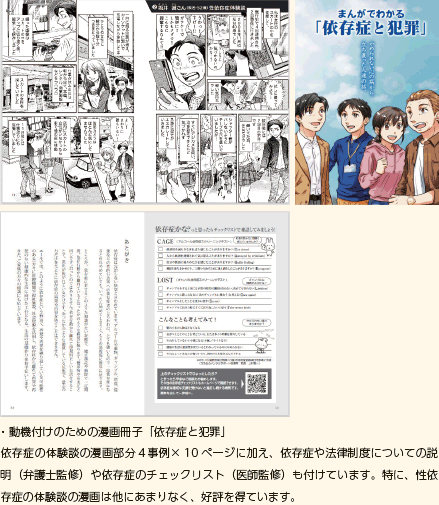

- ※ 休眠預金活用事業
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(平成28年法律第101号)に基づく資金分配団体の一つとして、更生保護法人日本更生保護協会が、民間公益活動を行う団体に対して助成を行う事業。
https://www.kouseihogo-net.jp/hogokyoukai/exercise.html
- ※ 依存症者回復支援センターエール(YELL)https://yell-fukuoka.jp/jmac/

地域食堂「みんなで来んさいな」はじめました。
更生保護施設鳥取県更生保護給産会
鳥取県更生保護給産会は、鳥取県内唯一の更生保護施設として、行き場のない刑務所出所者等を積極的に受け入れ、自立更生のため、個々の状況に応じて、福祉及び就労等の支援、専門的プログラム、退所後の生活環境の調整などを実施してきました。また、施設入所者の円滑な社会復帰には、地域社会の理解と協力が不可欠であると考え、施設入所者と職員は、施設近隣の道路や公共施設駐車場の清掃、地元小学校の生垣せん定など年間約70回の清掃活動に加え、地域イベントへの参加(手伝い)、冬には近隣道路の雪かきをするなどの地域貢献活動を30年以上続けており、これらの活動は、施設入所者の社会参加の意欲を高めることにもつながっています。
近年は、高齢化が進むなど、医療や福祉制度の利用を必要とする施設入所者が増えていることに加え、以前にも増して一人ひとりに寄り添った支援が必要となっています。当会では就労や住居の支援に加え、福祉や医療機関との調整などを、日々、丁寧に行い、当会から巣立った彼らが地域社会に定着し、犯罪とは縁のない生活を送り続けてほしいと願ってきました。
そのため、2017年度(平成29年度)からは施設退所者に対しフォローアップ支援を行ってきました。支援内容は、電話や来所・訪問による生活相談、当会が行う地域交流活動への参加を呼び掛けるなどして孤立を防いだり、福祉等関係機関と連携して見守りを行うなど様々です。2018年度(平成30年度)からはフードバンクを活用した退所者への食糧支援も開始しました。職員が施設退所者と定期的に会って「一人じゃない。困ったらいつでも相談してね。」というメッセージを送り続けることで、孤独と孤立の解消に努めてきました。これにより施設退所者の再犯は減少したものの、それでも孤立して再び罪を犯してしまう者が一定数いるという現実にジレンマを抱えてきました。「施設退所後の彼らの孤立を原因とした再犯をなくしたい。」、「地域に開かれ、地域に貢献する更生保護施設でありたい。」これは、全職員の思いです。
2023年度(令和5年度)、様々な出会いや御縁があり、「ふれあい食堂」(鳥取県にある地域食堂)を運営している大門代表から助言もいただき、検討した結果、当会の食堂を利用して地域食堂を立ち上げることにしました。併せて、地域食堂の参加者のために隣室で保健師による健康相談も実施することにしました。地域の方に来ていただき、実際に施設の雰囲気を見ていただくことが、施設に対する偏見の解消につながると考え、参加者は施設退所者に限定せず、公民館を通して、高齢者を始め、地域の住民全員に声掛けしました。もちろん、施設退所者に対しては、当会がホーム(拠り所)となり、気軽に相談に訪れることができるようになってほしいという願いがありました。
地域食堂応援隊として登録いただいた方々にもお手伝いいただき、2024年(令和6年)1月28日に第1回地域食堂「みんなで来んさいな」を開催したところ、施設退所者9名を含む86名が来所し、施設退所者にとっても地域の方々にとっても素晴らしい時間を過ごせたのではと思います。また、同年3月の第2回は施設退所者7名を含む115名が、同年5月に開催した第3回は施設退所者4名を含む126名の来所があり、参加者は回数を重ねるごとに増えています。
最後に、「出会いは財産。それはみんなに共通して言えることであり、鳥取県更生保護給産会に縁のあった元寮生たちにも気付いてほしい。地域食堂に継続的に来所し、何気ない会話や食べることを通して、地域と緩やかにつながり続けてほしい。」そのような願いを込めて、2024年度(令和6年度)からは本格的(奇数月の最終日曜日)に地域食堂を定例開催します。


地域における「居場所と出番」の創出
香川大学さぬき再犯防止プロジェクト PROS
PROS(香川大学さぬき再犯防止プロジェクト(Prevent Re-Offense Sanuki)、プロス)は、犯罪や非行の前歴がある方(以下「対象者」という。)の「居場所と出番」を作り、再犯を防止し、地域の方たちが安全・安心に暮らせる社会の実現に資するための活動として、2020年度(令和2年度)に始動した学生プロジェクトである。学部を限定しているわけではないが、発足以来、主に法学部の学生約20名と顧問教員や学外の福祉関係者で活動している。
再犯防止が刑事政策上の喫緊の課題であることもあって、本プロジェクトは再犯防止という名称を用いて活動を開始した。しかし、pros and cons(長所と短所)を由来として、PROSという名称が「互いの長所を見よう」という意味を有していることが示すように、出所者を含めて失敗した人も社会の一員として受容して、再出発を応援できるような包摂的な社会にすることを目標としている。
活動は、①対象者との交流会、②研修、③啓発活動の三つを主軸としている。メインとなる①対象者との交流会は、1か月に一回程度、定期的に学外で集まるものである。対象者は、複数回の刑務所入所経験があり、高齢又は障害を有する香川県内在住者で、香川県地域生活定着支援センター等を通して個別に参加依頼をし、同意を得られた方である。そして、交流会は、支援という形ではなく、双方にとって、社会で暮らす一員としての学びとなるような「居場所」にすることを目指している。また、対象者と学生は、氏名を含めて個人情報の交換をせず、お互いをPROSネーム(PROSの活動時のニックネーム)で呼び合う。さらに、学生には、活動中に知った対象者の個人情報は一切口外しないとの誓約書の提出を義務付けているほか、毎年一度以上の「街で対象者に出会ったときのシミュレーション実習」への参加も義務とするなど、個人情報の保護に関しては、細心の注意を払っている。
交流会開始当初、会話はほとんど成立せず、一問一答に終始した。事前にお互いの情報を知らず、対象者は、自分のことを説明することや主体的に動くことに慣れていない一方で、社会経験がない学生にとっては、これまで交流してこなかった人と話をすることに慣れていないからである。そのため、対象者が語りやすい雰囲気を作ることを心掛け、折り紙などの手作業的なことや料理を取り入れるようになり、現在では、対象者が語る依存の経験や被虐待経験、人生の先輩としての学生への応援メッセージに耳を傾ける時間となっている。また、対象者の中には、交流会を「宝物」と表現し、交流会参加以降「再犯しない最長期間記録」を更新中である者もいる。学生自身も、これまで想像しなかった価値観に歩み寄ろうとしながら、生きづらさを抱えた人の人権を守ることの重要さを実感しているようである。
②研修では、交流会をより充実したものにするため、刑事司法制度や再犯者率等刑事政策上の課題、対象者と交流する際の接し方等を、多方面の専門家から学び、必要な知識を得る機会を設けている。そして、③啓発活動では、刑務所・少年院等についての映画上映会や受刑経験者等の講師をお招きしたシンポジウム、大学祭でのCAPIC製品(刑務所作業製品)の展示会を開催して、受刑者や出所者という立場の人について、地域の方や大学生を含めた大学関係者に理解していただこうとしている。そのような機会のほか、関係機関等からも様々な機会を得て、PROSの活動内容を説明し意見交換等も行っている。
これらの活動に対し、PROSは、2023年(令和5年)「安全安心なまちづくり関係功労者表彰(内閣総理大臣表彰)」をいただく栄誉にあずかった。今後も、第二次再犯防止推進計画のいう「地域による包摂の推進」を念頭に、包摂的な社会を目標にした、互いが学ぶ場としての「居場所と出番」作りの活動を継続させていくつもりである。


保護観察所による犯罪・非行の地域相談窓口「りすたぽ」の取組
法務省保護局
出所受刑者の2年以内再入率は、近年低下傾向にありますが(【指標番号3】参照)、満期釈放者等の2年以内再入率は仮釈放者よりも高く、5年以内再入率も低下傾向にあるもののなお高い水準にあることなどを踏まえ、今後の再犯防止対策においては、刑事手続の入口段階から出口段階、そして保護観察や更生緊急保護を終えた後を含め、地域社会に至るまでの処遇をシームレスに捉え、切れ目のない支援を確保するなど「息の長い」社会復帰支援の推進が重要課題とされています。
このような背景も踏まえて、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により更生保護法(平成19年法律第88号)が改正され、新たに更生保護に関する地域援助に係る規定が設けられ、2023年(令和5年)12月から施行されています。
今般の法改正を機に、更生保護では「地域とともに歩み、地域に貢献する更生保護」を旗印としました。この実現に向けた中心的業務の一つとして位置付けられているのが更生保護に関する地域援助です。更生保護に関する地域援助は、保護観察官が、生きづらさを抱えているご本人やそのご家族、支援者の方などの地域住民の皆様や関係機関・団体の皆様からの犯罪や非行などに関する相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用した援助を行うものです。また、更生保護に関する地域援助を効果的に実施するため、保護観察所と地域における関係機関・団体との連携体制の構築や関係機関・団体が実施する研修、事例検討会への参加協力なども行います。
保護観察所では、広く地域からの相談を受け付けるため、2023年12月から犯罪・非行の地域相談窓口「りすたぽ」を設置し、法務省のウェブサイトやリーフレットにより周知を行っています。「りすたぽ」は「リスタート・サポート」の略であり、「リスタート」には、過去の過ちの有無にかかわらず、未来に向かって挑戦できる社会、つまり、「つまずいても立ち上がれる」社会を目指す願いを込めています。「りすたぽ」の名称には、過去に犯罪や非行をした人、犯罪や非行に結び付くおそれのある問題を抱えた人、その家族や関係者等、地域援助の対象は様々ですが、その一人一人が、自分にとっての再出発(リスタート)ができるよう、保護観察所がこれを支えて(サポート)地域に貢献していきたいという思いを込めています。
地域社会における犯罪予防・再犯防止に関する相談窓口として、必要なときに必要な人が保護観察所に相談できるよう、今後とも周知・広報を積極的に行うとともに、保護観察官が地域に出向くなどして相談しやすいものとし、関係機関・団体との連携の下、必要な支援を行うことができるよう、更生保護に関する地域援助の取組をより一層充実させていきます。