第1節 民間協力者の活動の促進等
(1)少年警察ボランティア等の活動に対する支援の充実【施策番号91】
警察は、少年を見守る社会気運を一層高めるため、自治会、企業、各種地域の保護者の会等に対して幅広く情報発信するとともに、少年警察ボランティア等の協力を得て、通学時の積極的な声掛け・あいさつ運動や街頭補導の実施、社会奉仕体験活動等を通じて大人と触れ合う機会の確保に努めている(【施策番号60、78、88】参照)。こうした少年警察ボランティア等の活動を促進するため、当該活動に関する広報の充実を図るとともに、謝金や交通費等を必要に応じて支給するほか、研修の実施や民間団体等が実施する研修への協力を推進するなど、支援の充実を図っている。
(2)更生保護ボランティアの活動に対する支援の充実【施策番号92】
法務省は、保護司、更生保護女性会員、BBS会員等の更生保護ボランティアが、それぞれの特性をいかして活動することを促進するため、各種研修の実施を始めとする支援を行っている。また、保護観察所は、各都道府県等に置かれた更生保護協会等の連絡助成事業者(2021年(令和3年)4月現在、全国で67事業者)と連携し、同事業者が行う保護司等の更生保護ボランティアの円滑な活動を支えるための助成、研修等のほか、犯罪予防や更生保護に関する広報活動等を推進している(【コラム9】参照)。
2014年度(平成26年度)から、民間協力者による更生保護の諸活動を一層充実したものとするため、保護司会、更生保護女性会及びBBS会の相互の連携を強化することに焦点を当て、各団体の取組を共有するとともに、新たな連携方策を検討するための講義及びグループワークを行うことなどを主な内容とする三団体合同の研修も各地において行っており、同研修がきっかけとなって“社会を明るくする運動”(【施策番号101】参照)における広報啓発活動等で具体的な連携が進むなど、効果を上げている。
また、保護司の複数担当制(保護観察事件や生活環境調整事件について、1件の事件につき複数の保護司が事件担当として指名されるもの)(【施策番号98】参照)や地域処遇会議(複数の保護司が集まり、処遇や地域活動に関して情報の交換や共有を行うための会議や打合せ会)等、保護司相互の相談・研修機能を促進する取組を行っているほか、保護司会が関係機関との連携を更に促進し広報啓発活動をより充実して行うことができるよう、引き続き、保護司及び保護司会活動への支援の充実を図っている。
なお、2018年度(平成30年度)及び2019年度(令和元年度)においては、法務省保護局、北海道沼田町及び特定非営利活動法人日本BBS連盟の共催により、沼田町就業支援センター※2(資6-92-1参照)において、BBS会員が同センターの入所少年と農業実習等を体験するプロジェクトを実施するなど、BBS活動の更なる充実を図るための支援を行った。また、2020年度(令和2年度)においては、BBS会において、法務省保護局が作成した研修教材(施策番号96参照)を参考に、クラウドファンディングにより、このプロジェクトを継続するための資金を独自に確保した。
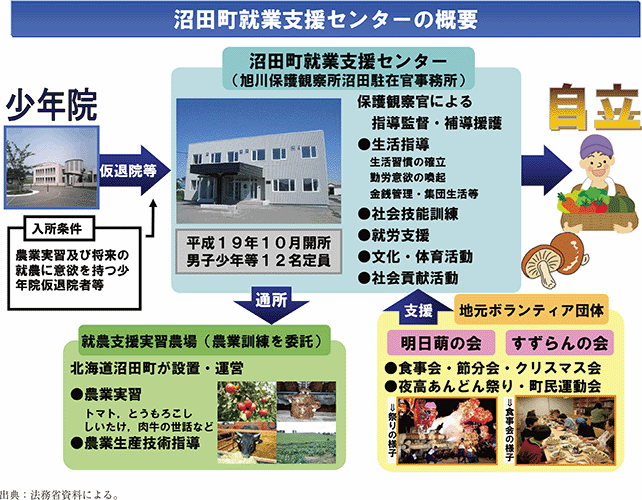
(3)更生保護サポートセンターの設置の推進【施策番号93】
更生保護サポートセンター(資6-93-1参照)は、保護司会を始めとする更生保護関係団体と、地域の関係機関・団体及び地域住民との連携を強化し、更生保護活動の一層の充実強化を図ることを目的とした更生保護ボランティアの活動拠点である。多くの更生保護サポートセンターでは、保護司が保護観察対象者等との面接場所の確保が困難な場合に利用できるよう面接室も備えているほか、更生保護サポートセンターは、保護司会活動の活発化や地域のネットワークの構築の拠点としても機能している。
法務省は、2008年度(平成20年度)から、地方公共団体等と連携して更生保護サポートセンターの整備を行い、2019年度(令和元年度)末までに全ての保護司会に整備した。更生保護サポートセンターは、市役所、福祉センター、公民館等に設置されている。
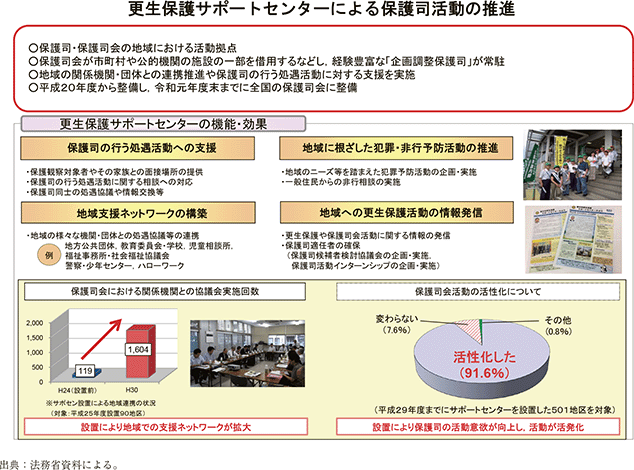
COLUMN8 再犯防止を支える民間協力者の方々
矯正施設や更生保護の分野で活動している民間協力者の方々に、その取組について伺いました。
多摩少年院 大塚 啓志
Q:篤志面接委員になったきっかけを教えてください。
A:定年後は社会貢献活動をしたいと考えていたところ、退職時に元矯正職員の知人から篤志面接委員の存在を教えていただきました。その後、篤志面接委員制度のパンフレット等を拝読して、是非参加したいとお伝えしたことがきっかけです。
Q:篤志面接委員のやりがいを教えてください。
A:自分の言葉が少年の生き方に新たな希望とヒントを与え、社会内で更生する手助けになると実感したときにやりがいを覚えます。
いわゆる「オレオレ詐欺」事件の受け子の少年には、「被害者のその後を知っているかい。」と問い掛けたり、少年が被害者に与えた物的・金銭的・精神的損害を金銭に換算するとどのくらいになるのかを説明したりしています。また、「役割分担の程度」や「手にした分け前の金額」で責任の範囲が決まるわけでないことを理解させ、犯罪がいかに割に合わない行為であるかについて認識させるとともに、被害者の人生を狂わせたことに向き合わせます。自らの責任を漠然としか理解できていなかった少年が、自らの責任と正面から向き合い、二度とこのような愚かなことをしないと決意表明した後、面接を重ねていくにつれて、表情が明るくなっていくのを見ると、やりがいを感じます。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響とそれに対する対処を教えてください
A:新型コロナウイルス感染症が社会経済全般に多大な影響を及ぼす中、篤志面接活動も大きな影響を受けています。具体的には、個人面接の際に、少年との間に飛沫防止用のパーティションが設けられ、ソーシャルディスタンスを保って面接することとなっているほか、定期的に換気をすることとなっています。また、地域の感染拡大状況によっては、篤志面接活動が中止となることもあります。
小規模の室内で少年と対面し、時間をかけて会話するこれまでの面接のスタイルを今後も維持できるか固唾をのんで見守りつつ、新しいニーズや生活様式の変化に対応できる新たな篤志面接活動の在り方について、思いを巡らせているところです。
Q:印象に残っている対象者の体験談を教えてください
A:飲酒・無免許運転による交通事故で被害者に多額の損害を与えた少年が印象に残っています。
その少年から、「民事責任は自分でなく親が負うのか。」、「祖父母が損害賠償金を支払うと聞いたが、祖父母に支払義務はあるのか。」といった相談を受けました。私は、未成年者でも中学生程度になれば責任能力はあり、不法行為による損害賠償責任は自らが負うこと、当然、祖父母には責任はないことなどを説明しました。また、少年は気持ちの浮き沈みが激しく、規律違反を繰り返すなど感情のコントロール方法に課題があったため、少年院における生活についても相談に乗っていました。
出院後は自分の力で被害弁償をして、将来は飲食店を経営したいと笑顔で話していた少年でしたが、新型コロナウイルス感染症に関する報道を見るたびに、少年の面影を重ねて息災を願う昨今です。

府中刑務所 髙岡 精司
Q:教誨師になったきっかけを教えてください。
A:教誨師を務めていた先輩の紹介で、教誨を始めました。教誨師になる際、学生時代に法学の講義で、「法律とは涙を去って律すること」と解説を受けたことを思い出しました。そうであるならば、私は教誨師として、罪を犯し、刑の執行を受ける人々に涙を持って接し、更生の道を共に考える存在になろうと心得たのでした。
Q:教誨師のやりがいを教えてください。
A:被収容者と接していて、彼らが早い時期に宗教に触れる機会があれば、犯罪を回避することができたのではないかと思われることが多くありました。知識として宗教による考え方を参考にできれば、罪を犯すことを回避し、被害者と加害者が生じることもなかったかもしれません。
教誨師とは、信仰を強制することなく、宗教を礎にした考え方を話し、正しい生き方を被収容者と共に考える存在だと思います。活動を重ねる中で、常に中立の立場を崩さず、罪を責めることなく、被収容者の立場に立って一緒に人生を考えていくことが大切だと思うようになりました。最初は厳しい視線で私を見ていた被収容者と幾度も話を重ね、やがて彼らの顔に笑顔が浮かぶようになったとき、教誨師の活動の大切さが理解できたように感じられたのです。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響とそれに対する対処を教えてください
A:矯正施設では、厳正な規律の下、健康な心と身体で社会復帰を目指す努力が日々なされているものと承知しています。そのため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時期には、教誨活動が中断されてしまうなど、満足に教誨活動を実施できない状況が続いています。
一般社会ではリモートによる会議や教育が行われていますが、矯正施設においては施設内の規律秩序の維持と被収容者の権利擁護、そして、外部協力者の安全確保を踏まえると、現状ではリモートによる教誨を行うことは困難でしょう。したがって、教誨師一人ひとりが正しい情報による感染症拡大防止に努めるとともに、一般社会における感染が収束へ向かう状況が来て、ようやく教誨活動が正常化されるのではないでしょうか。それまで教誨師は、自己の研鑽(けんさん)に励むことが大切であると考えています。
Q:印象に残っている体験談を教えてください
A:知り合いの住職が自分の寺で法話会を行っていたとき、聴衆の一人がその住職に次のように話しかけたそうです。「自分は刑務所で高岡教誨師の教誨を受けたが、お勤めの読経をする意義の説明を受けなかった。」
この話を聞いたとき、思い返すと心当たりがありました。出所した被収容者が再犯をして再び刑務所に戻り、私の教誨を求めて来たことが度々あったため、「教誨を行ってもまた戻ってくる。自分の教誨は役立っていないのか。」という思いに満ち、初心を忘れ、一方的に話をする教誨になってしまっていたのです。しかし、被収容者が社会復帰し、偶然にも知人の住職の法話会に参加して、話をしてくれた。このことが私の慢心を諫(いさ)めてくれました。それからというもの、私は元被収容者の言葉に感謝して、初心を忘れることなく、被収容者に接していくように心掛けています。
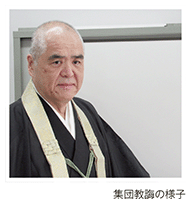
FC東京クラブコミュニケーター 石川 直宏
Q:少年院での活動を始めることになったきっかけを教えてください。
A:FC東京普及部のコーチが多摩少年院を訪問してサッカー教室をする機会があり、その際に一緒に参加したのがきっかけです。
現役を引退して、FC東京クラブコミュニケーターとなり、FC東京を地域に愛されるクラブにしていくために、地域社会と一体となって行うホームタウン活動にも積極的に関与していく中で依頼があったものです。サッカー教室だけでなく、当クラブの施設で少年たちの職業体験を受け入れた際も、少年と話をしたりしています。
Q:活動のやりがいを教えてください。
A:職業体験の一環として、少年たちにクラブの施設へ来てもらった際は、歓声を浴びてスタジアムで躍動する選手たちが繰り広げる試合の裏側でピッチや芝の手入れ、ジャージ、スパイクの準備などに多くの人が関わっていることや、その一員として「自分も役に立っているんだ。」という充実感・達成感を感じてもらえたらと思っています。少年たちにとって「誰かを応援し、その応援で誰かのチカラになれた。」という体験になってくれたのであれば、こんなに嬉しいことはありません。少年たちと関わるとき、正直最初は構えてしまうところもありましたが、サッカーを通じて段々と彼らと距離を縮めることができ、最初は見られなかった少年たちの笑顔や明るい表情を見ることができました。また、少年たちからは、私たちの姿を通じて、「社会でも頑張れそうだ。」、「チャレンジする勇気をもらえた。」といった、前向きな言葉を聞くこともできました。サッカーが持つ力、またクラブとして取り組んでいる地域社会と一体となった活動の価値を再認識することにつながりました。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響とそれに対する対処を教えてください。
A:緊急事態宣言の発令に伴い、これまでのように少年たちを招いて、クラブの施設での職業体験の機会を作ることができなくなってしまいましたが、多摩少年院との関係が途切れないよう、ビデオレターを通じて少年院にメッセージを届けるアクションを提案させてもらいました。少年たちには、自己肯定感を高めてもらうこと、社会から取り残されていると思ってもらいたくないこと、社会で応援している人もいることをきちんと感じてもらいたくて、ビデオメッセージに想いを込めて届けました。多摩少年院からは、ルヴァン杯の決勝(注)前に激励メッセージを書いたボールを贈ってもらい、選手からもお礼や決勝戦への決意を、改めてメッセージとして届ける形で交流を続けてきました。また、多摩少年院を長くサポートされてきた地域の皆さんに対しても、私たちのクラブがこうした交流を重ねていることを報告し、応援してくれている人々の横のつながりが広がっていくように心掛けています。
2021年(令和3年)1月4日に開催されたJリーグYBCルヴァンカップ決勝(柏レイソル対FC東京)
Q:活動を行う上で心掛けていることを教えてください。
A:年齢や立場に関わらず、フラットな関係性やコミュニケーションを意識しています。これは、相手が誰であっても意識していることで、まず相手に対して興味を持って、相手のことを知りたいと思うこと、話を聞くことを大事にしています。
サッカーを通じて大切に思っているのは相手をリスペクトすることです。ファン・サポーターや味方チームはもちろん、相手チームに対しても、リスペクトを持たないとサッカーは成り立ちません。選手時代に、けがをしたり、試合に出られないときは、苦しい反面、周りの人からの応援などを実感できる時間でもありました。うまく行っていないときこそ、色々な人の声が心に響いて、それが困難を乗り越える力になりました。少年院の少年たちもまた、つまずいた経験があるという点では自分に重なる部分もあって、周囲の人からの頑張れという声を立ち直りに生かしてほしいと思います。しんどいときこそ、自分自身に目を向けて努力や信頼を積み上げながら課題を乗り越えるきっかけにできるか、うまく行かないことを人や環境のせいにしてしまうかの分かれ道です。少年たちの心の中で、うまく行かない時期こそ、自分の課題を乗り越えるチャンスだという気付きや発見につながってくれればいいなと思います。

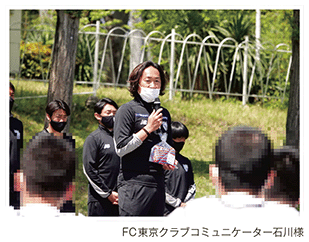
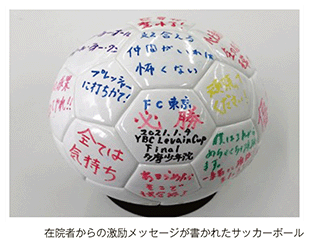
佐世保地区保護司会 岡﨑 公一
Q:保護司になったきっかけを教えてください。
A:祖父が保護司をしていた頃、祖父の活動の大変さを強く感じていました。私自身、年を重ね、更生保護について関心を持つようになり、祖父が行っていた保護司活動の重要性や必要性を感じました。加えて、父が就労支援事業を行っていたことや保護司会からの推薦もあって、保護司になることを決めました。
Q:保護司のやりがいを教えてください。
A:保護観察対象者が保護観察中に更生に向けて頑張っている様子を近くで見られるとやりがいを感じます。担当していた保護観察対象者から、保護観察終了後に結婚したと連絡があり、嬉しく思ったこともありました。
また、保護司会の活動では、保護司全体で盛り上がって一緒に活動ができれば良いですが、地区内の保護司数が多いので、一部の保護司だけで進めていかざるを得ない実情があります。会長としては、保護司会全体が一緒に盛り上がるための活動を考え、それを実現させていくことに面白さを感じています。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響とそれに対する対処を教えてください
A:2020年(令和2年)は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、なかなか思うように活動できない状況が続きました。保護司会でコロナ禍でもできる活動について検討し、これまで行っていた活動に感染防止対策を講じ、工夫しながら実施しました。
これまで実施していた薬物乱用防止教室については、中学校に出向き、別室から生徒に対しオンラインで講話を行いました。毎年実施している弁論大会も中止を考えましたが、無観客での開催、発表者のマイクは毎回消毒する等の対策を講じながら実施することができました。
また、“社会を明るくする運動”の広報活動については、非接触型の活動として、広報車を利用し、保護区内を約1週間にわたって巡回して実施しました。広報車による巡回は、地域住民に直接訴える良い機会となりました。
Q:力を入れている取組について教えてください
A:“社会を明るくする運動”の活動の一環として「心に花を咲かせようプロジェクト」を発足させました。
更生保護サポートセンターで試行的に、社明運動のシンボルであるひまわりを種から育てました。今後、苗を保育園、コミュニティセンター、更生保護施設佐世保白雲や駅の構内等に配るほか、休耕地も利用してひまわりの花を咲かせる予定です。
更生保護に対し深い関心を持ってもらい、意識の高揚が図られることを願って活動を行っています。

鹿児島県更生保護女性連盟 長野 瑳や子
Q:更生保護女性会に入ったきっかけを教えてください。
A:私自身が、人のために尽くす教えである「島津いろは歌」(注)の7首「科ありて 人を斬るとも 軽くすな いかす刀も ただ一つなり(解釈:悪いことをしたからといって、その人を軽々しく罰してはいけません。もう一度チャンスを与えて生かすこともできるのです。)」を知り、戦国時代から博愛の精神が詠まれていることに深く感銘を受けたこと、また先達の教えもあって自然に人のために尽くす活動をしようと考えたこと、そして島津久子日本更生保護女性連盟名誉会長の長年の思いを綴られた著作「星に花に愛」に感銘を受けたことから、更生保護女性会に入会しました。
Q:更生保護女性会のやりがいを教えてください。
A:鹿児島県においても地方再犯防止推進計画が策定され、その取組の一つとして、保護司会やBBS会と連携して、刑務所出所者や保護観察を終えた人などを対象に「ひまわり教室」を実施しています。
料理教室やグランドゴルフ、農業体験等を通じて楽しく居場所づくりや仲間づくりをすることで、再犯防止につながればと思って活動をしています。
料理教室で鹿児島のふるさとの味「がね」(芋、ニラなどのかき揚げ)をみんなで作ったときには、料理をしたことのない人も多く、不格好な「がね」がたくさん出来上がりました。それでも自分たちで作った料理は格別に美味しく感じられるようで、「はじめてこんな料理作った!」「はじめてこんな料理食べた!」と興奮気味にたくさん平らげる彼らの様子を見て、とても嬉しく感じました。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響とそれに対する対処を教えてください
A:昨年度は、「ひまわり教室」で計画していた様々な行事が、新型コロナウイルスの影響で中止を余儀なくされました。でも、「コロナだからこそできることをやろう!」と心機一転、考え方を変えて、感染症対策を取りやすい屋外での「農業体験」と「そば打ち体験」を新たに計画しました。
感染拡大が落ち着いてきた2020年(令和2年)9月、感染症対策をしっかりと行った上で、農業経験者の指導のもと、みんなでそばの種まきを行いました。そして年越しそばに合わせて2020年12月上旬に収穫をしたのですが、感染拡大の影響で延期となり、拡大状況が落ち着いた2021年(令和3年)3月上旬、収穫したそばを使って自分たちでそば打ちをし、みんなでかけそばを食べることができました。食べ終わった後は「心の相談員」として、参加者に対して「何か困ったことはない?」などと雑談の中で声をかけます。みんな心を開いて涙を流しながら話してくれました。
Q:今後、更生保護女性会としてどのような取組みをしていきたいか教えてください。
A:地域に受け皿となる居場所があれば、出所者にとってどれほど心強いことでしょう。「ひまわり教室」では、今後も保護司会やBBS会のみならず、更生保護法人、協力雇用主会、県や市町村とどんどん連携の輪を広げ、例えば空き家を活用する等、多角的な支援を可能として、より良い居場所づくりに取り組んでいけたらと思っています。
また、将来的には、「心の相談員」の育成に力を入れていきたいと考えています。更生保護ボランティアには保護司・更生保護法人・BBS会等様々な関わり方がありますが、更生保護女性会としての特性を生かし、支援が必要な方に対し、優しさや奉仕の精神、慈しみを持った関わりのできる「心の相談員」を育成することで、一人でも多くの方の心に寄り添い、より良い居場所づくりに貢献していきたいと考えています。

SGU江別BBS会 工藤 大輝
Q:BBS会員になったきっかけを教えてください。
A:元々高校生の頃から、ボランティアのような、人のために何かをすることが好きでした。その後、大学に入学した際、同期から「BBS会というボランティアサークルがある」と教えてもらったのをきっかけに、活動に興味を持ち入会しました。
Q:BBS会における活動のやりがいを教えてください。
A:活動で関わる少年や子どもたちは、私たちには想像がつかないような環境に置かれていることが多いです。彼らと“ともだち”という対等な立場に立つことで、新たな価値観に出会うことも多く、活動では、BBS会員が少年や子どもたちを一方的に支援するだけでなく、逆に少年や子どもたちから何かを与えられることもあり、充実感があります。
そんな彼らとの関わりの中で、どのような関わり方が最善なのかを考えながら新しいことにチャレンジし、その結果、少年や子どもたちとより良い関係を築くことができたり、活動に関係する大人の方々に認めてもらえたりすると、「学生である自分にも誰かのためにできることがあるのだな」とやりがいを感じます。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響とそれに対する対処を教えてください。
A:私たちの活動の根幹は人と人との関わりなので、コロナ禍の中ではどうしても出来ることが限られてしまいます。そんな中でも、なんとか少年や子どもたちと関わることができないか、模索しているところです。
また、大学での対面講義が無くなったことで、新しく入会してくれた会員と一度も顔を合わせることができないという問題も発生しています。新会員とは定期的に連絡をとって、できる限り繋がりを保つようにしています。
Q:SGU江別BBS会が行ったクラウドファンディングによる資金調達について、取組を始めた経緯や苦労したこと、工夫したことなど教えてください。
A:2018年(平成30年)から、少年院を仮退院し沼田町就業支援センターに入所している少年たちと交流する活動を開始しました。しかし、この活動の予算は2年間の期限付きだったので、予算がない3年目以降に沼田町就業支援センターでの活動を続けることは困難でした。沼田町就業支援センターでの活動に強い思い入れがある会員もおり、その活動が終了を余儀なくされることは残念でなりませんでした。そこで、沼田町における活動の資金を調達するため、クラウドファンディングに挑戦することにしました。
クラウドファンディングを行う上で一番難しかったのは、取組を様々な方に知ってもらうことでした。開始直後は、沼田町やBBS会の関係者の方からの支援が多かったので、関係者だけではなく、更生保護の活動自体をあまり知らない人にもこの活動を知ってもらいたいと考えるようになりました。そこで、地域の新聞に、当会のクラウドファンディングについての記事を掲載していただくことにしました。こうしたより広い層の方に活動を知ってもらうための工夫が功を奏したのか、結果的には目標の倍額以上の寄附を集めることができました。この寄附を活用して、沼田町就業支援センターにおける活動を2020年(令和2年)も実施することができました。

山梨県の協力雇用主 TAC武田消毒株式会社代表取締役 中村 猛志
Q:協力雇用主になったきっかけを教えてください。
A:知り合いの協力雇用主の方から話を聞き、協力雇用主の存在を知りました。最初は刑務所を出られた方を雇用することに対して迷いもありましたが、立ち直り支援に興味があり、彼らが将来的に再犯しないことに繋がるならば協力したいという思いから、協力雇用主になりました。
Q:協力雇用主のやりがいを教えてください。
A:これまで3名の保護観察対象者を雇用したことがあり、そのうち2名は勤続期間が3年近くになりました。
当社では、社員全員に日報を手書きで書いてもらい、私が本人の上司や同僚から業務の報告を受けます。仕事に関するものなので、うそを書けばわかりますし、心が入っていないことも文脈一つから伝わります。字を見ても、今日は調子がいいなということが読み取れます。彼らの日報を読むと、一日一日、少しずつ変わっていく姿が感じられ、彼らが会社の雰囲気に溶け込んでいこうと努力していることが伝わってきます。日報だけでなく、入社してから彼らの目つきや言葉遣いも徐々に変わり、今では他の社員の模範となるような社員になってくれました。彼らが日々研鑽を重ねていく姿がとても頼もしく、少しずつ変わっていく彼らの姿を見ることは、自分のやりがいにも繋がっています。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響とそれに対する対処について教えてください。
A:長期に及ぶコロナ禍により、当社も会社運営の厳しさが増していますが、消毒業務だからこそ、県内の行政機関や企業等から新型コロナウイルス関連での業務依頼があり、社員一丸となって頑張っている状況です。
深夜に消毒業務を行うこともあり、これまでの雇用形態とは異なる部分や、重要度の増した緊張感のある仕事に対し、彼らは嫌な顔一つせず、一層の責任感を持って取り組んでくれています。新型コロナウイルス感染症対策の現場の第一線で働く方々の苦労についても、思いをはせて口にすることがあります。
刑務所の中では、指示を受けたことをこなしていけばよかったかもしれませんが、当社では、必ず「なぜなのか」と自分の頭で考えてもらいます。普段から考えることを実践し、自分の役割への意識や、他人を思いやる想像力が培われた彼らだからこそ、コロナ禍の激務でも活躍してくれたのだと思います。
Q:協力雇用主として、保護観察対象者と関わる上で、大切にしていることを教えてください。
A:犯罪や非行をした人だからといって特別扱いをするのではなく、人間対人間であることを常に意識して接しています。「いつ辞めてもらってもいい。」と思いながら接していると本人たちにも伝わるので、こちらも彼らと真摯に向き合っています。
お客様が喜ぶことを第一に考えることが当社の経営理念であり、保護観察対象者にも会社のことを理解してもらうために、この経営理念を繰り返し伝え続けてきました。そうすることで、彼らも当社の信念を理解し、仕事にも一生懸命取り組んでくれています。
仕事を通して自分自身で考える力を身につけ、働きがいややりがいを見付けることが、彼らが社会の中で立ち直っていくことに繋がるのではないかと思っています。今後も、彼らが自ら気付きを得られるまで何度も会話を重ねることを大切にしていきたいと思っています。

更生保護法人滋賀県更生保護事業協会 事務局長 新庄 博志
Q:滋賀県更生保護事業協会の組織概要を教えてください。
A:当団体は1939年(昭和14年)、滋賀司法保護委員事業助成会を起源とし、社団法人、財団法人を経て1996年(平成8年)に更生保護法人となりました。会員数770名、役員は地元経済界や市町村長会、更生保護団体による理事16名、監事2名、評議員は22名です。事務局は滋賀県更生保護ネットワークセンターにあります。
Q:活動内容を教えてください。
A:更生保護事業法に係る事業・活動を基本としています。保護観察所と連携して、更生緊急保護対象者や生活に困窮した保護観察対象者に対し、金品給与を行っています。また、刑務所出所者等を雇用した協力雇用主への身元保証を年間50件程度扱っています。さらに、県内の更生保護関連団体と更生保護施設に対する助成や、犯罪予防、更生保護の啓発活動といった活動も行っています。具体的には、20近くの組織・団体に助成するとともに、滋賀県保護司会連合会と共同で年2回、機関紙「更生保護びわこ」を発刊し、関係機関に配布しています。毎年7月に行われる「社会を明るくする運動」では、諸団体に対し啓発資料・資材を提供しています。近年では、滋賀県からの「再犯防止地域支援員設置事業」の受託や、休眠預金活動事業から資金提供を受けた「更生保護団体による息の長い支援基盤整備事業」を実施するなど活動の輪を広げています。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響とそれに対する対処を教えてください
A:新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、早急に事務局のICT化を進めました。会計管理はクラウド会計に移行し、オンライン会議を実施できるシステムを導入しました。県内更生保護団体事務局や各保護区の更生保護サポートセンターに対しても、オンライン会議が実施できるよう支援をしています。一方で未だ大規模な集会や各種行事は中止や縮小を余儀なくされ、情報共有や意思疎通に苦慮しているところです。また、手渡しによる啓発資材の配布が困難なため、地元テレビ放送局と協力し、報道情報の提供や、啓発番組の制作も行いました。その結果、滋賀県知事と滋賀県内の更生保護団体の長との懇談会の様子の報道や、協力雇用主会の研修の模様や実際の協力雇用主へのインタビュー番組が放映されるなどし、各方面から好評を得ました。このように、コロナ禍の終息後にも繋がる取組が実施できました。
Q:滋賀県更生保護事業協会として実施している、保護司会等の民間団体の活動をサポートする取り組みについて、教えてください
A:滋賀県においては、保護観察を終えた後も支援の必要な方を対象とした、更生保護団体による息の長い寄り添い支援の取組を始めています。当協会は更生保護関係者が地域の再犯防止活動に関わることが一番の近道だと考え、推進法の理念の伝播と同期させながら更生保護関係団体の活動を支援しています。守山保護司会は協力雇用主会と連携した就労支援サポート事業を、彦根保護司会と高島保護司会は、子供食堂やスポーツ研修を企画し、寄り添いや見守り事業を実施しています。今後はこうした各地域の独自事業を進め、更生保護サポートセンターを軸とした地元の福祉や雇用、教育、医療等の関係者とのネットワークを築き、相談や支援体制の充実を図ることを計画しています。「支援者である更生保護関係団体への支援」と「網の目のネットワーク」を構築することは、地域の再犯防止に必ず寄与するものと思います。

- ※2 沼田町就業支援センター
2007年(平成19年)に北海道雨竜郡沼田町に開所した、旭川保護観察所沼田駐在官事務所に付設する宿泊施設に少年院を仮退院となった少年等を宿泊させて保護観察を実施するとともに、沼田町が設置運営する農業実習施設において、専門指導員の下で農業に関する訓練を実施することにより、農業を中心とした就業、自立を促進し、改善更生を図ることを目的とする施設。 - ※3 篤志面接委員
【施策番号98】参照。 - ※4 教誨師
【施策番号98】参照。 - ※5 保護司
【指標番号15】参照。 - ※6 更生保護女性会
【施策番号59】参照。 - ※7 BBS会
【施策番号59】参照。 - ※8 協力雇用主
【施策番号1、2】参照。 - ※9 更生保護協会
保護司、協力雇用主、更生保護女性会、BBS、更生保護法人等更生保護に協力する民間人・団体に対して助成、研修会の実施、顕彰等を行い、その活動を支援する団体。全国組織である日本更生保護協会と、各保護観察所に対応する形で都道府県単位の更生保護協会がある。