第1節 民間協力者の活動の促進等
(1)少年警察ボランティア等の活動に対する支援の充実【施策番号91】
警察は、少年を見守る社会気運を一層高めるため、自治会、企業、各種地域の保護者の会等に対して幅広く情報発信するとともに、少年警察ボランティア等の協力を得て、通学時の積極的な声掛け・あいさつ運動や街頭補導の実施、社会奉仕体験活動等を通じて大人と触れ合う機会の確保に努めている(【施策番号60、78、88】参照)。こうした少年警察ボランティア等の活動を促進するため、当該活動に関する広報の充実を図るとともに、謝金や交通費等を必要に応じて支給するほか、研修の実施や民間団体等が実施する研修への協力を推進するなど、支援の充実を図っている。
(2)更生保護ボランティアの活動に対する支援の充実【施策番号92】
法務省は、保護司、更生保護女性会員、BBS会員等の更生保護ボランティアが、それぞれの特性をいかして活動することを促進するため、各種研修の実施を始めとする支援を行っている。また、保護観察所は、各都道府県等に置かれた更生保護協会等の連絡助成事業者(2022年(令和4年)4月現在、全国で67事業者)と連携し、同事業者が行う保護司等の更生保護ボランティアの円滑な活動を支えるための助成、研修等のほか、犯罪予防や更生保護に関する広報活動等を推進している。さらに、民間協力者による更生保護の諸活動を一層充実したものとするため、保護司会、更生保護女性会及びBBS会の相互の連携を強化することに焦点を当て、各地で三団体合同の研修を実施し、各団体の取組を共有するとともに、新たな連携方策を検討するための講義やグループワークなどを行っている。
また、保護司については、その減少傾向と高齢化に歯止めを掛けるため、保護司の活動支援及び担い手の確保の取組を進めてきたところ、2021年(令和3年)1月には、総務大臣から法務大臣に対して、これらの取組をより一層推進するための必要な措置を講ずるよう勧告もなされた。こうした経過を踏まえ、情報技術が利用できる環境を整備するため、保護司活動の一部をウェブサイト上で行うための保護司専用ホームページ“H@(はあと)”を開発し、運用を開始し、一部の保護司会にタブレット端末等を配備するとともに、面接場所の確保や保護司適任者の情報提供等について、法務大臣から、都道府県知事及び市区町村長宛てに協力を求める書簡を送付したほか、法務省と総務省の連名による地方公共団体宛て協力要請文書を発出するなどし、保護司の活動支援及び担い手の確保についての取組を進めた。これらに加え、複数担当制(【施策番号98】参照)や地域処遇会議(複数の保護司が集まり、処遇や地域活動に関して情報の交換や共有を行うための会議や打合せ会)等、保護司相互の相談・研修機能を促進する取組を行っている。
BBS会については、令和4年2月、新たに福島大学の学生有志による「福島大学BBS会」が発足した(写真6-92-1)。今後、更生保護施設や児童養護施設などを訪問し、行き場のない人の心の居場所づくりや悩みを抱える子どもたちの非行防止に取り組むこととしている。

(3)更生保護サポートセンターの設置の推進【施策番号93】
更生保護サポートセンター(資6-93-1参照)※5は、保護司会活動の活発化や地域のネットワークの構築の拠点として、2019年度(令和元年度)末までに全国全ての保護司会に設置された。同センターは、地方公共団体との連携の下、市役所、福祉センター、公民館等に設置されており、保護司が保護観察対象者等との面接場所の確保が困難な場合に利用できるよう面接室も備えている場合も多い。
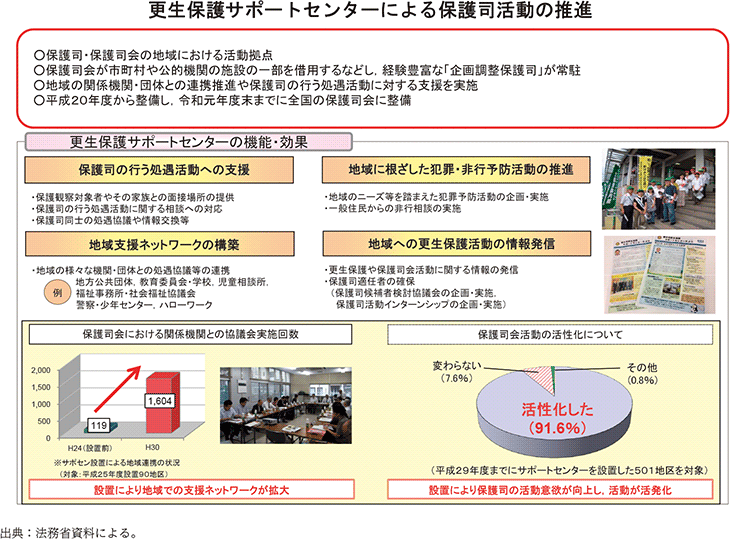
Column07 再犯防止を支える民間協力者の方々
1 篤志面接委員※6
岐阜刑務所篤志面接委員 田川 裕子
① 篤志面接委員として活動するまでの経緯について教えてください。
イベントや式典、TV・ラジオ等の司会業と、ピアノ講師、音楽療法士、メンタル心理カウンセラーを仕事としています。何足ものわらじですが、どれも関連性のあることとして勉強しながら活動しています。
音楽療法の受講時代、大変感銘を受けた先生が岐阜刑務所の篤志面接委員をされていて、お声をかけてくださったのがきっかけです。「刑務所内ラジオ放送を立ち上げるにあたり、パーソナリティをやってみませんか。」とのお話でした。このような施設においても誰かのお役に立てるのならと、ありがたく篤志面接委員の仲間に入れていただきました。歌謡ショーの司会として、いくつかの刑務所慰問にお邪魔した時以来のご縁です。
② 篤志面接委員の活動内容について、教えてください。
刑務所内ラジオリクエスト放送のパーソナリティと、高齢者指導分野の音楽療法を実施させていただいています。ラジオは収録で、ひと月に一度、リスナーである受刑者からのリクエスト曲をかけながら、メッセージを読んだり四季折々の話題を提供したりしています。高齢者指導の音楽療法は月に一回、10人前後の人数設定で、歌うことを主として、時代背景をひもときながらの回想や身体を動かすストレッチ、ゲーム感覚でできる脳のトレーニングなどを行っています。
③ 篤志面接委員の活動のやりがいを教えてください。
どちらの活動にも共通して願うのは、受刑者の心の安定です。二度と同じ過ちを犯さないために、受刑者の中にある良心や感情を思い起こしてもらうことができたときはとても嬉しいです。メッセージで家族のことを思い出して涙する人も、懐かしい歌を歌って子どもの頃の純粋な自分を思い返している人も、音楽に合わせたトレーニングゲームで苦戦している人もみんな素敵な笑顔になります。笑うことは心の安定につながり、満たされていくので、言葉も顔つきも変わっていきます。そして、この人いい人なんだなと感じたとき、ありのままの心の声を話してもらえたときに、この人も更生できると信じる気持ちが湧いてきて、私自身も喜びと感動を頂いています。
④ 音楽療法セッションで発見したことを教えてください。
音楽療法では参加者に自由に話をしてもらうようにしていますが、最初は慣れないせいか、自発的に発言をすることがありませんでした。そんなスタートでしたが今は入退室の時に、身体の不自由な人に手を貸しながら動く人の姿があります。セッション中は物知りな人を頼りにしたり、故郷を思い出す歌でポロポロ涙を流す人がいたり、優しい感情を素直に出し、協調しあって参加してくださいます。障害により震えの止まらなかった参加者の身体が、楽器活動中に止まっていたときは本当に驚きました。毎回発見がいっぱいです。

2 教誨師※7
東京拘置所教誨師 川上 宗勇
① 教誨師として活動するまでの経緯について教えてください。
私は寺で生まれて、僧侶として生きていくと、幼少の頃より決めていました。その中で中学3年の時に読んだ「やさしい刑法入門」という本の中に、極刑の場面で、僧侶が被収容者の隣に立っている、そんな挿絵があり、受刑者に寄り添う宗教者の存在を知り、そのような活動をしてみたいと考え始めました。
前任者が高齢で施設教誨師をお辞めになることになった際、若い人にも教誨師になってほしいとの要望もあり、35歳で教誨師を拝命しました。
② 教誨師の活動内容について、教えてください。
教誨には、被収容者が教誨受講の希望を施設に願い出て、グループで教誨を受講する「集合教誨」や、個人と対話をする「個人教誨」があります。この二つの教誨では「いのち」を見つめながら、被収容者が自己の生き方を調える道を共に模索します。
また、私自身が被害者支援都民センターで被害者支援ボランティアのプログラムを受講した経験から、一般改善指導※8のグループワークにおいて、外部講師として指導に参加したこともありました。
さらに、花まつりや盆法要等の仏教行事や、施設内での運動会をはじめとした各種行事、全国矯正展等のお手伝いをさせていただいております。
③ 教誨師の活動のやりがいを教えてください。
被収容者に寄り添っていると、どうしても「情」が移ってしまいます。しかし、彼らの後ろには必ず、悲惨な状況に追い込まれている被害者が存在します。被害者に想いをめぐらせ続けながら活動することは、民間のボランティアとしては、非常に責任の重い活動であると思います。そんな教誨師を根底から常に支えて下さっている、矯正施設の職員の皆さんの存在があります。職員の皆さんの活躍が、社会の表に出ることは稀でありますが、社会の「縁の下の力持ち」といえる職員の皆さんと一緒に、被収容者の教育指導、社会復帰のお手伝いをさせていただける、そのような部分にやりがいを感じています。
④ 教誨師として活動する中で、特に印象に残ったエピソードを教えてください。
出所者から一度だけ手紙を頂いたことがあります。内容は、社会復帰を果たしたことと、それまでの粒粒辛苦の日々がつづられていました。「履歴書を200通から書いて仕事を探しました。もうだめだと諦めかけた時に、先生の、生きているという事は可能性がある。絶対に諦めるな!という言葉が響き、最後の一通と思って書いた履歴書が今の会社です。ありがとうございました。」ゼロと1パーセントは違う。可能性を信じて、相手を信じる。これが教誨師であると思います。このお礼の手紙は、私への、激励の手紙となりました。
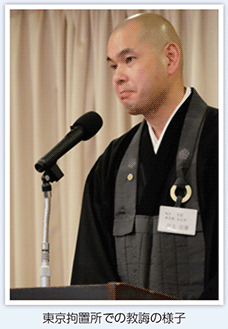
3 矯正施設で活動するその他の民間協力者
ショートショート作家 田丸 雅智
① 少年院において活動するまでの経緯について教えてください。
短くて不思議な「ショートショート」を専門に書く「ショートショート作家」として活動を行っているのですが、自身の執筆活動と並行して全国各地でショートショートの書き方講座を開催しています。オリジナルのメソッドに従いながら90分ほどの時間内でアイデア出しから作品完成、発表までを行うというもので、対象は小学1年生くらいからシニアの方までと幅広く、企業等でも開催していたりします。
その講座を少年院で開催させていただくようになったのは、出院者らの就労支援等を行う一般社団法人チーム太陽の故・北村啓一さんとの出会いがきっかけでした。2017年(平成29年)2月に群馬の赤城少年院で初開催をして以来、これまでおよそ2か月に1度のペースで活動を行ってきています。
② 少年院での活動内容について、教えてください。
ワークシートに従いながら、1人1作品、「ショートショート」の創作を自由に行っていただいています。最初は「無理」「できない」と言っていた少年たちも、最後には「雑草を食べて身体の色が緑になった犬の話」や「海水浴が好きなパソコンの話」等の作品を執筆、発表してくれます。
創作を通じて、文章力はさることながら、アイデアを考える発想力や、それをまとめる論理的思考等を磨くきっかけにしていただければと願っています。また、「最初は無理だと思ったことが意外とできた」というプチ成功体験を通して、挑戦することの大切さ等もお伝えしています。
③ 少年院での活動のやりがいを教えてください。
少年たちの反応や変化を目の当たりにできたときに、特にやりがいを感じます。少年院での講座の場合は、特にワークの初期段階で、取り組む前から「分かりません」「できません」という少年がとても多いのですが、「大丈夫」「いいですね」と声をかけるにつれて、少年たちは不安そうな顔をしながらも「こんなのでいいんですか……?」と筆を動かし始めてくれ、いつしか自分の力で進み始めます。そして、作品ができあがると、達成感に包まれた素敵な表情を見せてくれます。
この瞬間に立ち会うたびに、言いようのない喜びを覚えます。それと同時に、少年犯罪の難しさにも改めて思いをはせます。
④ 活動を行う上で心掛けていることを教えてください。
何よりも、創作を自由に楽しんでいただくことを心掛けています。想像力はネガティブな反応に対して委縮しやすく、一度そうなると再び膨らませるのがとても困難になるため、少年たちが書いてくれたことを絶対に否定しないことも大切です。また、少年たちがたとえワークの途中で詰まっていても、こちら側から「答え」を押し付けたりせず、いかに少年たちの中から引き出すことができるかを大事にしています。少年たちには自分の頭で考えて、講師がいなくとも自走していける力を身につけていただきたいと願っています。
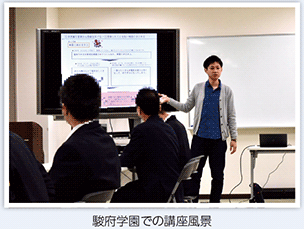
4 保護司※9
和歌山保護司会 会 長 小川 史乘
和歌山保護司会 副会長 得津 壽美代
① 貴会において、どのような経緯で保護司になる方が多いか、保護司となるまでにどのような背景をお持ちの方が多いか、保護司のやりがいを教えてください。
当保護司会では、退任予定の保護司から誘われて保護司になっている人が多いと思います。
「私は、夫の父親が保護司だったこともあり、保護司になりました。一番最初に薬物事件を担当した時は、最初の面接まで不安があったのですが、実際に会ってみると、どこにでもいるような普通の方で、安心しました。ケースごとに感心させられることも多く、いろいろな人の人生から学ぶこともあります。」(得津保護司)
「保護司になって、はや35年が過ぎました。いろいろな出来事、いろいろな人との出会いがあり、その度に私の人生は豊かなものになっていきました。保護司になって本当によかったと思います。」(小川保護司)
② SNSやホームページ等のICTを活用した広報活動内容について、教えてください。
当保護司会では、ホームページやSNSを活用して広報活動を行っています。
ホームページには、当保護司会の成り立ちや各支部の概要、更生保護サポートセンター和歌山の案内を掲載しているほか、広報誌のデータファイルもダウンロードできます。SNSでは、“社会を明るくする運動”などの地域活動の様子について発信していますので、是非ご覧ください。
また、コロナ禍で集まって会議をすることができなくなったため、パソコンを操作することができる保護司に教わりながら、オンライン会議を行うようになりました。最初は分からないことだらけでしたが、最近は少しずつ慣れてきました。やればできるものです。画面越しの相手にわかりやすいよう、保護司会・更生保護女性会・BBS会の名前が入った“幸福の黄色いバックパネル”を作成したり、みんなで知恵を出し合いながら頑張っています。
③ 貴会で取り組んでいることについて、教えてください。
当保護司会では、新任保護司を計画的に育成する取組として、「新任さんいらっしゃ~い」と題して、経験の浅い保護司とベテラン保護司による座談会を開催しています。
更生保護サポートセンター※10に集まり、ベテラン保護司がこれまでの様々な体験を紐解きながら保護司としての心構えを伝え、悩んだり迷ったりしがちな新任保護司のサポートを行っています。
こうした活動を通じて、更生保護サポートセンターを「処遇活動を支えてくれる心強い場所」、「いつでも気軽に立ち寄れる身近な場所」として知ってもらうことで、保護司同士のつながりづくりに取り組んでいます。
2021年度(令和3年度)はコロナ禍の影響を受け中止になりましたが、今年度こそはと意気込んでいます。
④ 今後の活動について教えてください。
コロナ禍以前は、保護司・更生保護女性会・協力雇用主会が合同の研修を行っていたのですが、今後は、BBS会を含めて四者連携を進めていく予定です。行動制限の状況を見ながら、「新任さんいらっしゃ~い」などの取組を少しずつ再開して、保護司同士のつながりを深めていきたいと考えています。
また、「更生保護サポートセンター和歌山」が2012年(平成24年)6月の開所から10周年になります。これまでの歩みを地域の皆様と共に振り返り、今後の和歌山保護司会の発展に向けて気持ちをひとつにできるような記念行事についても検討しています。
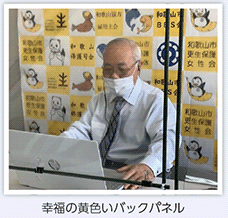
5 更生保護女性会※11
釧路更生保護女性会会長 穗積 貴美子
① 更生保護女性会員として活動するまでのことについて教えてください。
釧路更生保護女性会は、1999年(平成11年)に子育て支援地域活動のモデル地区に指定され、地域の小学校や児童館等で、保護者や住民を対象としたミニ集会を積極的に開催していました。ミニ集会では、子供のしつけなど「子育て」をテーマに話し合っていて、当時、小学校の教員として働いていた私は、「活発な活動をしている婦人会があるな」と思っていました。ある日、釧路更生保護女性会で熱心に活動していた同僚から、「一緒に活動しましょう」と誘われたのがきっかけで、入会しました。教員の仕事と同じで、子供たちの幸せを願う活動を行っている団体であることを知り、力になりたいと考えたのです。
② 釧路更生保護女性会の活動内容について教えてください。
釧路市内にある更生保護法人釧路慈徳会、釧路刑務支所、釧路少年鑑別支所、児童養護施設等で生活する方々への支援を行っています。特に、釧路慈徳会へは、寄付金や生活必需品の提供を長年続けています。また、他の更生保護団体との連携にも力を入れています。1977年(昭和52年)、釧路地区保護司会、釧路BBS会、釧路更生保護女性会の三者で「木もれ陽協議会」を立ち上げ、お互いの活動で不足しているところを補い合うことを目的とし、定期的に集まって情報交換を行う場を設けています。
③ 更生保護女性会の活動のやりがいを教えてください。
現在、不織布マスクの着用が呼び掛けられていますが、それ以前に釧路慈徳会に届いた新品の布マスクが、使われないまま倉庫にしまわれていました。使い道がなく、施設側も困っていたところ、会員の提案で、布マスクの糸を全部ほどいてから手洗いし、アイロンをかけ、縫い直し、ガーゼハンカチを作ることになりました。出来上がったハンカチには、手書きのメッセージカードを一枚ずつ付けて、退所する人たちにプレゼントしています。一人一人ができることは小さいですが、みんなで力を合わせて社会に貢献する活動に参加し、役割をいただくことで、誰かの役に立っているという「成就感」が生きがいにつながっています。
④ 力を入れて取り組んでいる活動について教えてください。
毎年、“社会を明るくする運動”の一環として、当会主催で「名士職域かくし芸芸能大会」を実施しています。コロナの影響を受け、ここ数年開催できなかったものの、2022年(令和4年)1月に2年ぶり66回目の開催にこぎつけました。当日は、検温や消毒はもちろん、出来る限りのコロナ対策を行う中、子供たちのミュージカルや日本太鼓演奏等の出し物で大いに賑わいました。保護観察所、保護司会、BBS会を始め、市内の多くの団体の御協力の下、開催することができ、人と人とが繋がることの大切さを再認識することができました。
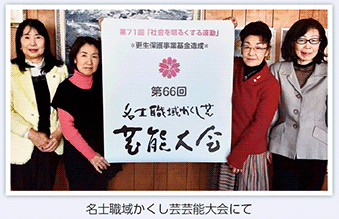
6 BBS会※12
横浜市西区BBS会 会長 橋本 夏希
① BBS会員になったきっかけについて教えてください。
大学3年生の時に、他大学の「犯罪心理学」の授業を受講した際、講師の先生からBBS会というボランティア団体があることを聞き、興味を持ったのがきっかけです。思い返せば、中学生の時に非行には至っていないものの、生きづらさを抱えている同級生に対して何もできなかったことが心残りで、いつか悩んでいる子供たちの力になりたいという思いが根底にあったのだと思います。BBS会では、ともだち活動やグループワークを通して少年と直接関わることができ、また、自分と同じくらいの若い世代の会員が中心となって活動をしているところに魅力を感じ、入会しました。
② BBSの活動内容について、教えてください。
1つ目はともだち活動です。保護観察中の少年とBBS会員が主に1対1で関わる活動です。少年と一緒に遊びに出掛けたり、勉強をしたりする中で、少年の自立を支援することを目的としています。2つ目はグループワークです。少年とBBS会員が複数名で各種レクリエーションを通して交流します。3つ目は自己研鑽活動です。更生保護の基礎的な知識の習得、ともだち活動の事例研究などを通してスキル向上を図っています。
③ BBSの活動のやりがいを教えてください。
やりがいを感じる点として、様々な人と関わることができるところがあります。少年はもちろん、保護司会、更生保護女性会など関係団体の方々や、BBS会の仲間たちとのつながりを通して、多くの学びがあると日々感じています。入会当初は、少年に対して力になりたい、でもどのような声掛けをしたら良いのか分からなく、自分に何ができるのかという漠然とした不安がありました。でも実際にともだち活動等の経験をしてみると、少年から教わることがたくさんあり、自分自身の成長にもつながっていることに気付かされました。これがBBS活動のやりがいなのだと思います。BBS会員の皆さんには、あまり気負わず少年と楽しくコミュニケーションを取ってこの楽しさを実感してほしいです。
④ 所属地区会で実施している主な活動(学習支援等)について教えてください。
ともだち活動はもちろんですが、グループワークと自己研鑽に注力しています。ここ数年のグループワークでは、バーベキュー、横浜の街散策、ビーチボールバレー、お好み焼き作りを実施しました。グループワークに少年が参加してくれたことがきっかけで、ともだち活動が始まったケースもあり、継続的に少年と関わる機会を作り続けることが重要だと考えています。ともだち活動は、年間数名の少年を途切れることなく担当しており、毎月開催している定例会の中で進捗を報告し、会員や保護司の方から様々な角度でアドバイスをもらい、定例会が研鑽活動の場にもなっています。また、新たな活動として、横浜市西区内にある児童家庭支援センター「らいく」への訪問活動を開始し、地域に根ざした活動も行っています。

7 協力雇用主※13
有限会社芦名商会 芦名 鉄雄
① 協力雇用主として活動するまでについて教えてください。
幼い頃、父と一緒にリヤカーを引いて廃品回収をしていましたが、会社組織にしてだんだん規模を拡大し、現在、一般・医療系廃棄物処理業を営んでいます。
1993年(平成5年)頃、刑務所を出所した人の雇用を保護観察官から依頼されたことが協力雇用主として活動するきっかけでした。初めは刑務所や少年院を出所した人を“雇用してあげる”という気持ちでしたが、彼らの雇用を続けていくにつれ、すぐに辞めていく人、とても手がかかる人、立ち直るために真剣に頑張っている人など様々な人に出会い、そのうちに情が湧いてきて、気がつけば長年協力雇用主として活動していました。
② 協力雇用主の活動内容について、教えてください。
協力雇用主として刑務所や少年院を出所した人を雇用するとともに、1995年(平成7年)に岩手県で立ち上がった協力雇用主の組織である、岩手県更生保護協力事業主連絡協議会の事務局長を長年務め、昨年度からは会長を務めています。
岩手県更生保護協力事業主連絡協議会は、岩手県下14地区の更生保護事業主会の連合会ですが、NPO法人岩手県就労支援事業者機構とも手を携え、各地区更生保護事業主会の総会に合わせて研修会や親睦会を開催するなど、岩手県における刑務所や少年院を出所した人に対する就労支援の充実のために活動しています。私も、岩手県更生保護協力事業主連絡協議会の会長として、各地区の総会・研修会に出席させてもらっています。
③ 協力雇用主の活動のやりがいを教えてください。
親元に帰れず、私がアパートの保証人となって預かった人のことが心に強く残っています。
彼の将来のために必要だと思い、運転免許を取得させることにしましたが、本人も頑張ったものの学科試験に合格することができずにいました。朝出社してこないのでアパートまで訪ねていったら、本人は恥ずかしくて合わす顔がないなどと言うので、説得して納得させて出社させ、また、学科試験に受かるために一緒に勉強しました。
ついに本人が運転免許を取得した時の喜びはひとしおで、このことを通じて、彼らと一緒に喜んだり、悲しんだり、悩んだりして、一緒に取り組むことの大切さを学びました。
④ 非行や犯罪をした人を雇用する上で工夫していることを教えてください。
これまでに刑務所や少年院を出所した人を20名程雇用し、失敗もありましたが、今心掛けていることは、「自分はこの会社に必要な存在である」と思ってもらえるように接すること、話をしてくれた際には丁寧に聞くこと、どのような仕事がしたいかを確認し、できるだけ希望に添う仕事を与えること、一般社員と区別をしないで平等に接することです。そして、彼らには、我が社で働くことで再犯をしないことはもちろんですが、社会の一員としてやりがいを持って仕事に取り組み、幸せな人生を送ってもらいたいと思います。

8 更生保護協会※14
更生保護法人岐阜県更生保護事業協会事務局長 廣瀬 等
① 岐阜県更生保護事業協会の組織概要を教えてください。
当協会は、1951年(昭和26年)9月8日に設立され、1984年(昭和59年)3月に財団法人の認可を受け、1996年(平成8年)に更生保護法人となりました。現在、正会員760名、賛助会員470名、理事20名、監事2名、評議員は22名で、事務局は、岐阜県更生保護会館内にあります。同会館は、県下の保護司等の有志により1958年(昭和33年)に「保護司会館」として建設されたのが起源で、その後、1994年(平成6年)に岐阜市役所西別館1階部分に移転、2021年(令和3年)には同別館2階・3階部分と土地を岐阜市から購入し、全館が「岐阜県更生保護会館」となり、これまで入居していた当協会、岐阜県保護司会連合会、岐阜山県保護区保護司会、岐阜山県更生保護サポートセンターのほか、岐阜県更生保護女性連盟、岐阜県BBS連盟、岐阜県就労支援事業者機構が入居しています。
② 活動内容について、教えてください。
更生保護事業法に定められた届出事業者(更生保護法人)で、地方公共団体からの補助金、篤志者からの寄附、賛助会員からの会費等を原資として、一時保護事業と連絡助成事業を行っています。一時保護事業として、犯罪をした人や非行のある少年に対して金品の給与、就職の援助等を行っています。また、連絡助成事業として、保護司(会)、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主及び更生保護施設等更生保護関係団体への助成や、犯罪予防活動等を行っています。
③ 活動のやりがいや困難であったことを教えてください。
基本財産の一部として国債を所有し、利子を果実収入として活動の原資の一部としていましたが、ゼロ金利政策等により果実収入は見込めず、また、不景気やコロナ禍における経済活動の低下が続いている現況において、更生保護を支援いただいている賛助会員が減少傾向にあります。それに伴って収入が減少し、関係団体への助成を一部制限せざるを得ない状況が続いています。当協会の活動を支えてくださっているのは社会の方々であり、より一層、更生保護活動に理解と支援が得られるよう、更生保護会館に入居する各団体とこれまで以上に連携しながら、広報等にも力を入れていかなければと考えています。
④ 岐阜県更生保護事業協会として今後の展望、新たに取り組みたいこと等について、教えてください。
前記のとおり、更生保護会館に各団体が集まったことにより、「更生保護センター」として、各団体の相互連携や活動拠点としての機能を効果的に発揮できる環境が整えられました。今後、県下の再犯防止の支援機関・団体のハブとしての機能の充実を図っていくことになります。
また、県下各保護司会に設置された更生保護サポートセンター(【施策番号93】参照)をサテライトとして、「更生保護センター」とインターネットでつなぐことにより、保護を必要とする人にとって身近な地域の更生保護サポートセンターを通所・訪問場所とし、必要な保護を、必要な場所で受けられる環境を構築したいと考えています。

- ※5 更生保護サポートセンター
更生保護サポートセンターは、保護司会を始めとする更生保護関係団体と、地域の関係機関・団体及び地域住民との連携を強化し、更生保護活動の一層の充実強化を図ることを目的とした更生保護ボランティアの活動拠点である。 - ※6 篤志面接委員
【施策番号98】参照。 - ※7 教誨師
【施策番号98】参照。 - ※8 一般改善指導
【施策番号83】参照。 - ※9 保護司
【指標番号15】参照。 - ※10 更生保護サポートセンター
【施策番号93】参照。 - ※11 更生保護女性会
【施策番号59】参照。 - ※12 BBS会
【施策番号59】参照。 - ※13 協力雇用主
【施策番号1、2】参照。 - ※14 更生保護協会
保護司、協力雇用主、更生保護女性会、BBS会、更生保護法人等更生保護に協力する民間人・団体に対して助成、研修会の実施、顕彰等を行い、その活動を支援する団体。全国組織である日本更生保護協会と、各地方更生保護委員会や保護観察所に対応する形で更生保護協会がある。