高校生向けリーフレットに関する確認テスト
第5問
契約の相手方が契約した内容を守らず、自ら契約上の義務を果たさない場合は、裁判所に訴えることが唯一の解決手段である。
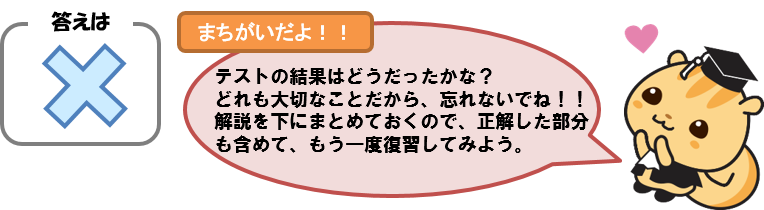
≪解説≫
契約の相手方が自ら契約上の義務を果たさない場合は、第三者の助けを借りて、紛争を解決することができます。裁判による紛争解決のほかに、裁判以外の中立・公正な第三者による紛争解決(ADR)もあります(リーフレット7p参照)。
自分でトラブルを解決できないときは、一人で悩まず、家族や専門家など、ほかの人に相談するようにしましょう。
■ 法テラス・サポートダイヤル
■ 全国の弁護士会・弁護士会連合会
■ 司法書士総合相談センター
■ 消費者ホットライン
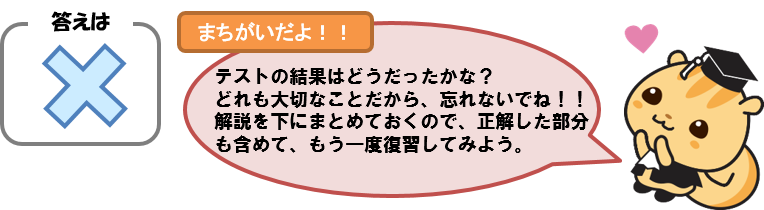
≪解説≫
契約の相手方が自ら契約上の義務を果たさない場合は、第三者の助けを借りて、紛争を解決することができます。裁判による紛争解決のほかに、裁判以外の中立・公正な第三者による紛争解決(ADR)もあります(リーフレット7p参照)。
自分でトラブルを解決できないときは、一人で悩まず、家族や専門家など、ほかの人に相談するようにしましょう。
■ 法テラス・サポートダイヤル
■ 全国の弁護士会・弁護士会連合会
■ 司法書士総合相談センター
■ 消費者ホットライン
確認テスト一覧
| 第1問 | 18歳・19歳の者が親の同意を得ずにした契約については、取り消すことができる。 |
| × | 2022年(令和4年)4月1日以降、18歳をもって成年と扱われ、18歳・19歳は未成年者ではありません。 未成年者が契約するときは、親などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます(未成年者取消し)。 成年になってした契約については、未成年者取消しはできず、契約から生じる責任を果たさなくてはなりません(リーフレット2p参照)。 |
| 第2問 | 契約書を作成しなければ、契約は成立しない。 |
| × | 契約は、当事者双方の意思表示(考えを表すこと)が合致することによって成立します(リーフレット3p参照)。 原則として、口頭の約束でもよいとされています(リーフレット5p参照)。 |
| 第3問 | 「契約自由の原則」とは、いつでも自由に契約を解消できるという意味である。そのため、契約を結んだとしても、内容が気に入らなければ、いつでも一方的に契約を取り消すことができる。 |
| × | 「契約自由の原則」とは、「契約を結ぶかどうか」、結ぶとしても「誰と結ぶか」「どのような契約内容にするか」を当事者が自由に決めることができるという原則です(リーフレット3p参照)。 もっとも、一度契約が成立すると、合意した内容をお互いに守る義務が発生します(契約の拘束力)。契約した内容と違うことをしたり、一方的な都合で契約を解消することはできません(リーフレット6p参照)。 ※ ただし、消費者トラブルが発生しやすい取引については、一定の期間内であれば理由を問わず、契約をやめることができます(クーリング・オフ制度)。 困ったときは、消費者ホットラインにお電話ください。 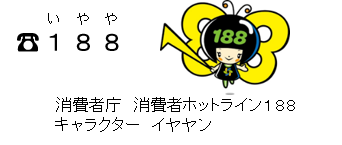 |
| 第4問 | 売買契約の目的物として渡された物が壊れていた場合(例えば、お店でゲーム機を買い、家に帰って確認したときに、壊れていることに気付いた場合など)、買主は、売主に対し、ゲーム機の修理や交換を求めることができる。 |
| ○ | 一度契約が成立すると、合意した内容をお互いに守る義務が生じます(契約の拘束力)。もし相手が契約どおりのことをしない場合、相手に契約した内容を実現するよう求めることができます。 売買契約で引き渡された物が契約で決めた内容と違うときは、買主は、売主に、その物の修理や、新しい物との交換を求めることができます(リーフレット6p参照)。 |
| 第5問 | 契約の相手方が契約した内容を守らず、自ら契約上の義務を果たさない場合は、裁判所に訴えることが唯一の解決手段である。 |
| × | 契約の相手方が自ら契約上の義務を果たさない場合は、第三者の助けを借りて、紛争を解決することができます。裁判による紛争解決のほかに、裁判以外の中立・公正な第三者による紛争解決(ADR)もあります(リーフレット7p参照)。 自分でトラブルを解決できないときは、一人で悩まず、家族や専門家など、ほかの人に相談するようにしましょう。 ■ 法テラス・サポートダイヤル ■ 全国の弁護士会・弁護士会連合会 ■ 司法書士総合相談センター ■ 消費者ホットライン |

