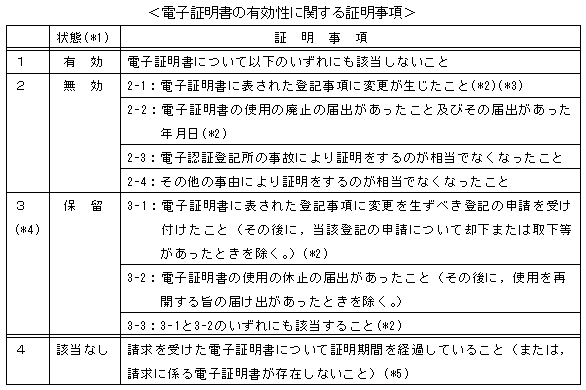| 3 |
|
電子証明書の請求手続(書面申請の場合)
※電子証明書の請求方法として、「書面申請」と「オンライン申請」の二つの方法があります。以下、「書面申請」の手続について、説明します。
なお、「オンライン申請」については、「オンラインによる商業登記電子証明書の請求等について」を御確認ください。 |
|
(1 |
) 申請人 |
| |
登記所に印鑑を提出した会社代表者又はその代理人に限られます(前記1「電子証明書の発行を請求することができない者」に御注意ください。)。 |
| |
| (2 |
) 申請書・公開鍵等の提出 |
| |
会社代表者が電子証明書の発行請求をする場合には、会社の登記がされている管轄登記所に、会社代表者の印鑑(管轄登記所に届け出ている印鑑)を押印し、手数料分の印紙を貼付した「電子証明書発行申請書」[PDF]を提出します。
この申請に当たっては、自己の公開鍵等の必要事項を記録した証明書発行申請ファイル(CD、DVD又はUSBメモリに格納してください。これらの媒体は返却します。)を添付する必要があります。(注)
発行申請を受けた管轄登記所においては、これらの提出書類等を基に、申請人の本人確認等を行います。
なお、申請人は、一人で複数の公開鍵を届け出て、複数の電子証明書の発行を受けることができますが、申請は、公開鍵ごとに行う必要があります。また、有効な電子証明書が発行されている公開鍵を再度届け出て、別の電子証明書の発行申請をすることはできませんので、新たな公開鍵を生成して申請するか、既に発行を受けている電子証明書について使用廃止の届出を行った上で、電子証明書の発行申請をしてください。
| (注) |
電子証明書の取得時(後記3(5)参照)には、この自己の公開鍵に対応する(同時に生成された)秘密鍵が必要となりますので、データの削除等により秘密鍵を紛失することのないよう御注意ください(秘密鍵を紛失されますと電子証明書を取得することができなくなります。)。 |
|
<申請書記載事項> |
| ・ |
商号、本店、資格、氏名、生年月日 |
| ・ |
代理人によって請求するときは、その氏名及び住所(注1) |
| ・ |
電子証明書の証明期間(注2) |
| ・ |
手数料の額、申請年月日、登記所の表示 |
|
|
| |
|
| (注1 |
) 代理人による申請の場合 |
| |
会社代表者の代理人が申請する場合には、代理権限を証する書面(会社代表者が登記所に提出した印鑑を押印したものに限ります。)が必要になります(法務省ホームページで提供している申請書様式では、申請書と委任状が一体となっています。)。 |
| |
|
| (注2 |
) 「電子証明書の証明期間」の設定に当たっての注意事項 |
| ・ |
「電子証明書の証明期間」とは、電子認証登記所に対して、発行後の「電子証明書」の有効性(会社の商号、本店、代表者の資格・氏名等の電子証明書に表された事項に変更が生じていないか等。後記5参照)について、インターネットを通じて証明を請求することができる期間をいい、電子証明書の内容が有効とされる期間ではありません。
この「証明期間」内であっても、自己の秘密鍵(署名鍵)が使用することができなくなる場合があります。「証明期間」内に電子証明書に記録された事項(会社の商号、本店、代表者の資格・氏名等)に関する変更の登記がされた場合には、電子証明書の証明内容に変更が生じることとなり、電子認証登記所は、これ以降(証明期間が満了するまで)に電子証明書の有効性の確認請求を受けたときは、「無効」(電子証明書に記録された事項に変更が生じた旨)を証明することになるため、この場合も、その者の署名鍵は使用することができなくなります(この場合、手数料の払戻しはいたしません。ただし、一定の条件を満たす場合は、再発行の申請(手数料不要)をすることができます。詳しくは、管轄登記所にお問い合わせ願います。)。
したがって、「証明期間」を定めるに当たっては、会社代表者の任期や本店移転、商号変更等の予定を考慮する必要があります。これらの予定が見込まれる場合には、「証明期間」を過度に長期に設定しないよう、注意する必要があります。 |
| ・ |
「証明期間」は、1か月、又は3か月単位で最長27か月まで選択することができます。手数料の額は、この「証明期間」に応じて定められています。 |
| ・ |
「証明期間」の経過後は、電子認証登記所はその電子証明書の有効性確認請求に応ずることができません。そのため、電子証明書が証明する公開鍵に対応する秘密鍵(署名鍵)で行われた電子署名について、取引の相手方等は署名者を確認することができないこととなり、秘密鍵(署名鍵)を使用することはできないこととなります。 |
| ・ |
電子証明書の発行後に電子証明書の「証明期間」を変更することはできません。 |
| |
|
| |
|
|
| (3 |
) 証明書発行申請ファイルの記録事項 |
| |
「電子証明書発行申請書」とともに管轄登記所に提出する証明書発行申請ファイルは、専用ソフトウェアを使用して作成する必要があり、電磁的記録媒体(CD、DVD又はUSBメモリ)に格納して提出します。
この証明書発行申請ファイルに記録する事項は次のとおりです。 |
| |
| <証明書発行申請ファイル記録事項> |
| |
| ・ |
商号、本店、資格、氏名 |
| ・ |
電子証明書の証明期間 |
| ・ |
自己の公開鍵の値(自動的に記録されます。) |
| ・ |
電子署名の方式を特定する識別符号(自動的に記録されます。) |
| ・ |
電子証明書の使用休止の届出用暗証コード |
|
|
| |
| ※商号・代表者氏名の英字情報 |
| |
証明書発行申請ファイルには、上記のほか、申請人による任意の記録事項として、次の情報を記録することができます。この記録事項は、電子証明書に表示されます。 |
| |
・ |
商号(またはその略称)の表音・訳語をローマ字・英数字で表したもの |
| |
・ |
会社代表者の氏名の表音をローマ字で表したもの |
| |
ただし、ローマ字等による商号の表記の情報を証明書発行申請ファイルに記録して申請する場合には、それを証明する「定款」等を提出する必要があります。 |
| |
|
|
| ◆重要◆ 証明書発行申請ファイルの作成に当たっての留意点 (←クリック) |
| |
| (4 |
) 電子証明書の番号の告知 |
| |
電子認証登記所は、発行申請の手続を行った管轄登記所からの通知を受けて、電子証明書の発行処理を行います。
電子証明書の発行処理が終了すると、電子証明書の発行申請の手続を行った管轄登記所の窓口において、その電子証明書の番号(シリアル番号)が告知されます。 |
| |
|
| |
| |
(注 |
) 電子証明書の記録事項の確認 |
| |
|
電子証明書の番号の告知は、原則として、「電子証明書発行確認票」という書面を交付して行います。この「電子証明書発行確認票」には、電子証明書の番号(シリアル番号)のほかに、申請情報に基づき電子証明書に記録された事項として、商号/名称、商号/名称(英字)、本店/主たる事務所、資格、氏名、氏名(英字)、電子証明書の証明期間、管轄登記所名が表示されるため、速やかにその内容を確認する必要があります。 |
|
| |
|
| (5 |
) 電子証明書の取得 |
| |
管轄登記所の窓口において電子証明書番号の告知を受けた(電子証明書発行確認票を受領した)申請人は、告知された電子証明書の番号と自己の公開鍵を指定して、いつでも(何回でも)、インターネットを通じて、電子認証登記所から電子証明書を取得(ダウンロード)することができます(注1)(注2)(注3)。取得(ダウンロード)の際は、公開鍵と秘密鍵の生成及び証明書発行申請ファイルの作成の際に使用した専用ソフトウェア(前記1の(注3)参照)が必要になります。
なお、一度取得した電子証明書は、何度でも使用することができます。 |
| |
|
| |
| (注1 |
) 電子証明書の取得は、その「証明期間」内であって、かつ、電子証明書に記録された事項(会社の商号、本店、代表者の資格・氏名等)に変更が生じるまで(変更の登記がなされるまで)に行う必要があります。電子証明書に記録された事項に変更が生じた場合には、電子証明書は「無効」として扱われ、それ以降、取得することができなくなります。 |
| |
|
| (注2 |
) 電子証明書の取得時には、電子証明書の発行申請の際に管轄登記所に提出した公開鍵(自己の公開鍵、前記3(2)参照)に対応する秘密鍵が必要となります(この秘密鍵を紛失されますと、電子証明書を取得することができなくなってしまいますので、データの削除等により秘密鍵を紛失することのないよう御注意ください。)。 |
| (注3 |
) 法人代表者の電子証明書が、本当に電子認証登記所の登記官によって発行されたものであるかどうかは、電子証明書に添付される登記官(発行者)の自己署名証明書のハッシュ値が告示されている電子認証登記所の登記官の電子証明書のハッシュ値と一致しているかどうかを調べることにより確認することができます(詳しくは、「電子認証登記所登記官の電子証明書について」のページを参照してください。)。 |
|