保護観察官区分
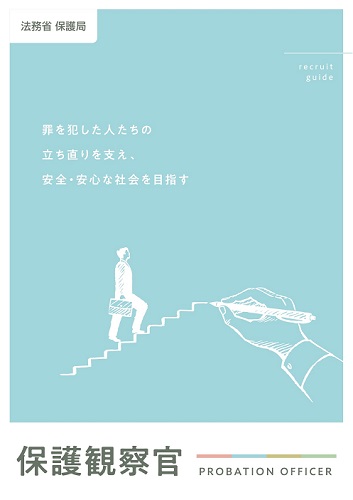
保護観察官パンフレット(表紙)
◇採用後の給与等について
・給与・諸手当
・勤務時間・休暇
・研修・昇進
・福利・厚生
◇採用に関するQ&A
◇1期生による業務紹介&メッセージ
保護観察官は、犯罪をした人や非行のある少年が社会の中で自立できるよう、彼らを取り巻く地域の力を活かしながら、その再犯・再非行の防止と社会復帰のための指導や援助を行う「社会内処遇」の専門家です。
保護観察官とは
地方更生保護委員会や保護観察所に勤務し、心理学、教育学、福祉及び社会学等の更生保護に関する専門的知識に基づき、社会の中において、犯罪をした人や非行のある少年の再犯・再非行を防ぎ改善更生を図るための業務に従事します。
1.地方更生保護委員会に勤務した場合
刑事施設からの仮釈放や少年院からの仮退院に関する審理のために必要な調査を行うほか、仮釈放の取消しや仮退院中の者の退院、保護観察付執行猶予者の保護観察の仮解除等に関する事務に従事します。
2.保護観察所に勤務した場合
家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年や仮釈放者等を対象とする保護観察を実施するほか、矯正施設被収容者の出所後の住居や就業先等の生活環境の調整、犯罪予防活動等の業務に従事します。
1.地方更生保護委員会に勤務した場合
刑事施設からの仮釈放や少年院からの仮退院に関する審理のために必要な調査を行うほか、仮釈放の取消しや仮退院中の者の退院、保護観察付執行猶予者の保護観察の仮解除等に関する事務に従事します。
2.保護観察所に勤務した場合
家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年や仮釈放者等を対象とする保護観察を実施するほか、矯正施設被収容者の出所後の住居や就業先等の生活環境の調整、犯罪予防活動等の業務に従事します。
- 保護観察官を目指す方へ

- 保護観察官パンフレット[PDF:10585KB]
採用後の給与等について
○給与・諸手当
保護観察官区分採用者は行政職俸給表(一)が適用されます。
2022年度現在、東京都特別区内に勤務する場合の初任給は222,240円です(地域手当を含む。)。なお、保護観察官に任命された場合は、俸給の調整額が加算されます。このほか、各種手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等)が支給されます。
○勤務時間・休暇
原則1日7時間45分の勤務(午前8時30分から午後5時15分まで)です(ただし、配属庁によっては宿直勤務があります。)。なお、大都市では時差通勤制度を採用しています。
○研修・昇進
採用後、保護観察所又は地方更生保護委員会に配属となり、一定期間一般的な事務に従事した後、保護観察官に任命されます。その後は、実務経験や勤務成績に応じ、統括保護観察官、保護観察所長などへと昇任します。
保護観察官に任命された直後の2年間は、保護観察官として必要な基礎的能力を身につけるための「実務訓練期間」と位置づけ、その期間中に、「保護観察官中等科研修」及び「保護観察官専修科研修」に参加するほか、所属庁において保護観察官としての業務に従事しながら、統括保護観察官等の指導官から実務指導を受けます。また、少年院、刑事施設、地方検察庁などへの短期派遣研修も実施しています。
○福利・厚生
国家公務員は、国家公務員等共済組合に加入することとなり、組合員として、病気、負傷、出産等に関連した各種の給付を受けることができます。また、退職、高度障害、死亡した場合には、共済組合制度の適用を受けることができます。
その他、疾病の予防と人間ドック受検、臨時の出費等による資金の貸付け、貯金及び保険事業など、組合員とその家族の方々が健康で明るい豊かな生活ができるよう、様々な制度・事業があります。
保護観察官区分採用者は行政職俸給表(一)が適用されます。
2022年度現在、東京都特別区内に勤務する場合の初任給は222,240円です(地域手当を含む。)。なお、保護観察官に任命された場合は、俸給の調整額が加算されます。このほか、各種手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等)が支給されます。
○勤務時間・休暇
原則1日7時間45分の勤務(午前8時30分から午後5時15分まで)です(ただし、配属庁によっては宿直勤務があります。)。なお、大都市では時差通勤制度を採用しています。
○研修・昇進
採用後、保護観察所又は地方更生保護委員会に配属となり、一定期間一般的な事務に従事した後、保護観察官に任命されます。その後は、実務経験や勤務成績に応じ、統括保護観察官、保護観察所長などへと昇任します。
保護観察官に任命された直後の2年間は、保護観察官として必要な基礎的能力を身につけるための「実務訓練期間」と位置づけ、その期間中に、「保護観察官中等科研修」及び「保護観察官専修科研修」に参加するほか、所属庁において保護観察官としての業務に従事しながら、統括保護観察官等の指導官から実務指導を受けます。また、少年院、刑事施設、地方検察庁などへの短期派遣研修も実施しています。
○福利・厚生
国家公務員は、国家公務員等共済組合に加入することとなり、組合員として、病気、負傷、出産等に関連した各種の給付を受けることができます。また、退職、高度障害、死亡した場合には、共済組合制度の適用を受けることができます。
その他、疾病の予防と人間ドック受検、臨時の出費等による資金の貸付け、貯金及び保険事業など、組合員とその家族の方々が健康で明るい豊かな生活ができるよう、様々な制度・事業があります。
採用に関するQ&A
Q1.採用にあたっては、どのような人材を求めているのですか。
社会内処遇の専門家である保護観察官の業務は、1対1の面接から関係諸機関との連携業務まで非常に幅広く、個々のケースについて、どういった形の処遇が必要かつ相当か、多角的に検討、実施する力が必要となります。そのためには、人間諸科学の知識や技能が不可欠ですが、そういった知識等は、採用後の研修や実務を通して身につけることができます。
重要なのは何よりも、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生や再犯の防止、安心・安全な地域社会の実現に向けた熱意と行動力だと考えています。
Q2.一般職試験に合格しても、保護観察所や地方更生保護委員会に採用されますか。
保護観察官は、国家公務員採用総合職試験や法務省専門職員(人間科学)採用試験保護観察官区分の合格者から主に採用していますが、一般職試験合格者からも採用しています。詳しくは、一般職試験のページ(https://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji05_00011.html)を参照して下さい。
Q3.採用にあたり、法律に関する専門的な知識は必要ですか。
保護観察官として勤務する中では、法律的な専門知識が必要となりますが、採用の時点で、そういった知識を求めているわけではありません。人間諸科学に関する知識や技能と同様に、採用後、様々な研修や実際の業務を通じて、身につけていくことになります。
Q4.どれくらいの頻度や範囲で異動がありますか。
おおむね2、3年ごとに、採用管内の地方更生保護委員会又はその管内の保護観察所を異動することになりますが、昇任に応じて異動の地域は広くなります。
Q5.女性にとって働きやすい職場でしょうか。
保護観察所や地方更生保護委員会に勤務する職員の約4割が女性で、管理職として活躍されている女性職員も多くいます。また、産前・産後休暇、育児休業等の制度があり、結婚・出産後も第一線で活躍することができます。
社会内処遇の専門家である保護観察官の業務は、1対1の面接から関係諸機関との連携業務まで非常に幅広く、個々のケースについて、どういった形の処遇が必要かつ相当か、多角的に検討、実施する力が必要となります。そのためには、人間諸科学の知識や技能が不可欠ですが、そういった知識等は、採用後の研修や実務を通して身につけることができます。
重要なのは何よりも、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生や再犯の防止、安心・安全な地域社会の実現に向けた熱意と行動力だと考えています。
Q2.一般職試験に合格しても、保護観察所や地方更生保護委員会に採用されますか。
保護観察官は、国家公務員採用総合職試験や法務省専門職員(人間科学)採用試験保護観察官区分の合格者から主に採用していますが、一般職試験合格者からも採用しています。詳しくは、一般職試験のページ(https://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji05_00011.html)を参照して下さい。
Q3.採用にあたり、法律に関する専門的な知識は必要ですか。
保護観察官として勤務する中では、法律的な専門知識が必要となりますが、採用の時点で、そういった知識を求めているわけではありません。人間諸科学に関する知識や技能と同様に、採用後、様々な研修や実際の業務を通じて、身につけていくことになります。
Q4.どれくらいの頻度や範囲で異動がありますか。
おおむね2、3年ごとに、採用管内の地方更生保護委員会又はその管内の保護観察所を異動することになりますが、昇任に応じて異動の地域は広くなります。
Q5.女性にとって働きやすい職場でしょうか。
保護観察所や地方更生保護委員会に勤務する職員の約4割が女性で、管理職として活躍されている女性職員も多くいます。また、産前・産後休暇、育児休業等の制度があり、結婚・出産後も第一線で活躍することができます。
1期生による業務紹介&メッセージ
法務省専門職員(人間科学)採用試験は、平成24年度から新たに始まった試験制度で、同試験に合格して採用された職員が全国で活躍しています。
ここでは、専門職試験1期生が現在担当している業務や、専門職試験の受験を考えている皆さんへのメッセージを紹介します。
ここでは、専門職試験1期生が現在担当している業務や、専門職試験の受験を考えている皆さんへのメッセージを紹介します。
- ★専門職試験採用職員からvol.1:「保護観察官の仕事について感じること」[PDF:248KB]
- ★専門職試験採用職員からvol.2:「新任の保護観察官として勤務して」[PDF:256KB]
- ★専門職試験採用職員からvol.3:「まずは『受け入れる』ことから」[PDF:207KB]
- ★専門職試験採用職員からvol.4:「地方更生保護委員会事務局保護観察官の一日」[PDF:197KB]
- ★専門職試験採用職員からvol.5:「立ち直りを支える保護観察官」[PDF:111KB]
- ★専門職試験採用職員からvol.6:「自立更生促進センターの1日」[PDF:148KB]
- ★専門職試験採用職員からvol.7:「様々な人とのかかわりを通して」[PDF:190KB]
- ★専門職試験採用職員からvol.8:「人がつなぐ更生保護」[PDF:270KB]
- ★専門職試験採用職員からvol.9:「地域の皆様の優しさに触れながら、地域の皆様と共に進めていく仕事」[PDF:160KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

