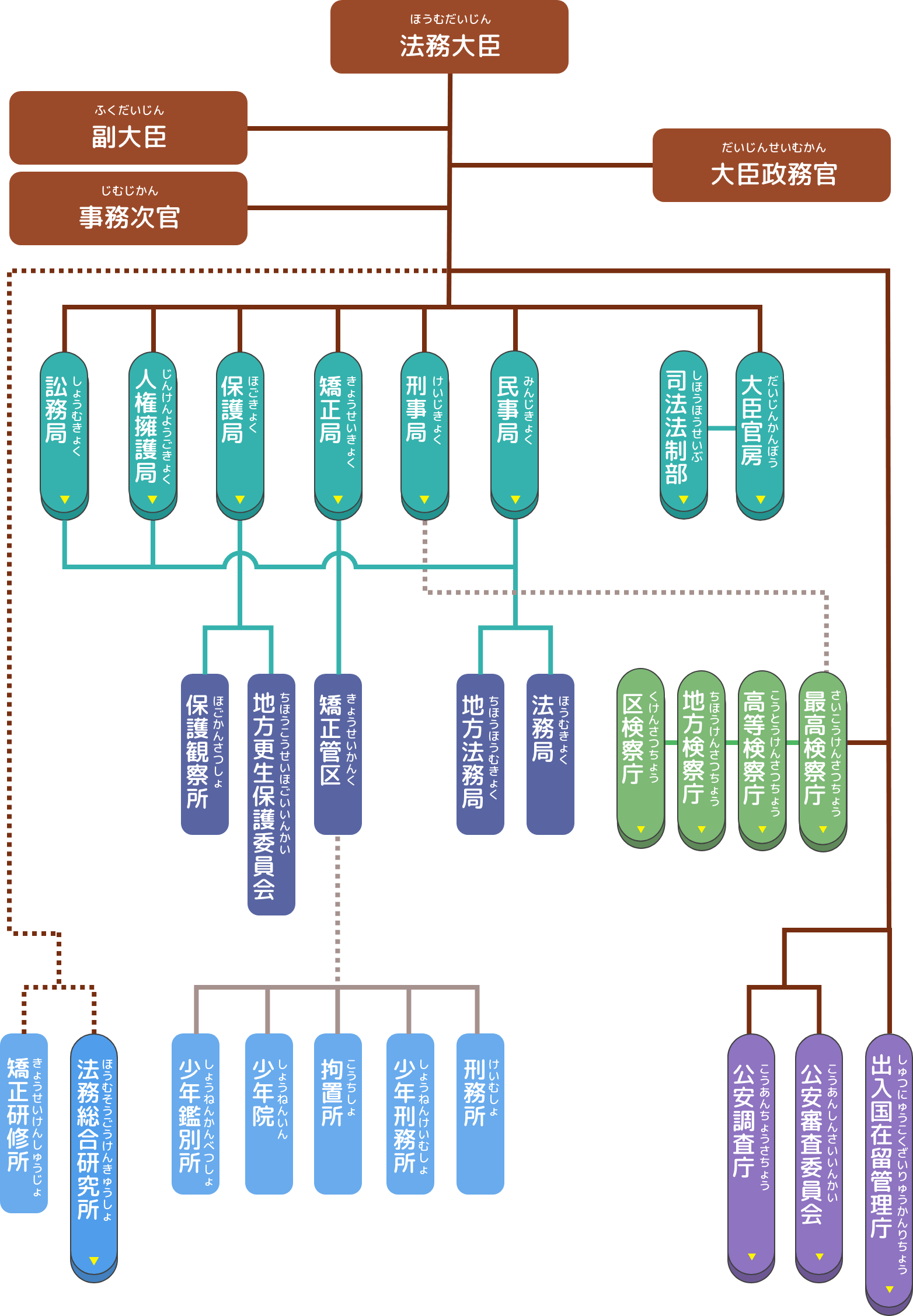保護局
「
また、
犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支える主なボランティア団体としては、更生保護女性会とBBS会があります。更生保護女性会は、犯罪予防活動を行うとともに、青少年の健全育成活動のほか、子育て支援活動、更生保護施設への支援など、幅広い活動を行うボランティア団体です。また、 BBS会は、非行など様々な問題を抱える少年たちと、「兄」や「姉」のような立場で接し、いっしょに悩み、いっしょに学び、いっしょに楽しむことを通して、少年の立ち直りや自立を支援する青年ボランティア団体です。
これらの団体は、保護司といっしょになって更生保護に関する活動に取り組んでいます。
このような
また、
また、
すべての
"
保護観察所では、地域の方からの犯罪や非行に関する相談を受け付ける
→くわしい情報はこちらから