8. 裁判後の段階での被害者支援
1 加害者の受刑中の刑務所における処遇状況や出所情報等の通知
加害者が刑務所に入った場合は、受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所から釈放される時期や釈放された年月日などについても知っておきたい方がいらっしゃると思います。そこで、加害者の受刑中の処遇状況、加害者が刑務所から釈放になる時期又は釈放になったことなどの通知を行う制度を設けています。
Q1 受刑中の処遇状況や出所情報などの通知制度はどのようなものですか。
A この制度には、2つの種類のものがあります。
第1は、被害者等通知制度に基づくものであり、被害者等であれば、特段の理由を必要とせず通知を受けられるものです。これにより通知を受けることができる情報は、満期出所の予定時期、受刑中の刑務所における処遇状況や、実際に釈放された後に釈放された年月日などです。
第2は、特に再被害防止のために必要がある場合に限って通知を受けられるものです。これにより通知を受けることができる情報は、加害者の釈放直前における釈放予定時期などです。
*少年審判後の通知についてはこちらをご覧ください。
Q2 第1の制度の通知内容はどのようなものですか。
A 第1の制度の通知内容は、以下のとおりです。
ア 収容されている刑務所の名称・所在地
イ 実刑判決が確定した後、刑務所から釈放される予定(満期出所予定時期)の年月
ウ 受刑中の刑務所における処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
エ 刑務所から釈放(満期釈放、仮釈放)された年月日
オ 執行猶予の言渡しが取り消された年月日
カ 仮釈放審理を開始した年月日
キ 仮釈放を許す旨の決定をした年月日
ク 保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定年月日
ケ 保護観察中の処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
コ 保護観察が終了した年月日
Q3 誰でも釈放に関する通知を受けられるのですか。
A 第1の制度により通知を受けることができるのは、
ア 被害者、その親族又は内縁関係にある方、婚約者など親族に準ずる方
イ 目撃者など参考人の方(Q2のイ、エに限ります。)
です。
Q4 第1の制度では、希望すれば、必ず釈放に関する通知を受けられますか。
A 事件の性質などから、加害者の更生を妨げるおそれがあるなど、通知することがふさわしくないと検察官が判断した場合には、通知希望があっても、通知をしない場合があります。
Q5 第1の制度により通知を受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
A 希望される方には希望する通知先、通知方法等を明らかにした書面を作成していただくことになります。申出は、加害者の刑事裁判が確定した後であればいつでもできますので、事件を取り扱った検察庁に書面を提出してください。なお、裁判確定の通知を希望された方には、裁判確定の通知を差し上げる際に申出の書面をお送りします。詳しくは、各検察庁の被害者支援員又は事務担当者にお尋ねください。
Q1 受刑中の処遇状況や出所情報などの通知制度はどのようなものですか。
A この制度には、2つの種類のものがあります。
第1は、被害者等通知制度に基づくものであり、被害者等であれば、特段の理由を必要とせず通知を受けられるものです。これにより通知を受けることができる情報は、満期出所の予定時期、受刑中の刑務所における処遇状況や、実際に釈放された後に釈放された年月日などです。
第2は、特に再被害防止のために必要がある場合に限って通知を受けられるものです。これにより通知を受けることができる情報は、加害者の釈放直前における釈放予定時期などです。
*少年審判後の通知についてはこちらをご覧ください。
Q2 第1の制度の通知内容はどのようなものですか。
A 第1の制度の通知内容は、以下のとおりです。
ア 収容されている刑務所の名称・所在地
イ 実刑判決が確定した後、刑務所から釈放される予定(満期出所予定時期)の年月
ウ 受刑中の刑務所における処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
エ 刑務所から釈放(満期釈放、仮釈放)された年月日
オ 執行猶予の言渡しが取り消された年月日
カ 仮釈放審理を開始した年月日
キ 仮釈放を許す旨の決定をした年月日
ク 保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定年月日
ケ 保護観察中の処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
コ 保護観察が終了した年月日
Q3 誰でも釈放に関する通知を受けられるのですか。
A 第1の制度により通知を受けることができるのは、
ア 被害者、その親族又は内縁関係にある方、婚約者など親族に準ずる方
イ 目撃者など参考人の方(Q2のイ、エに限ります。)
です。
Q4 第1の制度では、希望すれば、必ず釈放に関する通知を受けられますか。
A 事件の性質などから、加害者の更生を妨げるおそれがあるなど、通知することがふさわしくないと検察官が判断した場合には、通知希望があっても、通知をしない場合があります。
Q5 第1の制度により通知を受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
A 希望される方には希望する通知先、通知方法等を明らかにした書面を作成していただくことになります。申出は、加害者の刑事裁判が確定した後であればいつでもできますので、事件を取り扱った検察庁に書面を提出してください。なお、裁判確定の通知を希望された方には、裁判確定の通知を差し上げる際に申出の書面をお送りします。詳しくは、各検察庁の被害者支援員又は事務担当者にお尋ねください。
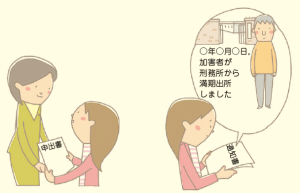
『加害者の受刑中の刑務所における処遇状況や出所情報等の通知』
A 通知を受けることができるのは、被害者の方が再び被害に遭わないように転居その他加害者との接触を避けるための措置をとる必要があるため、特に通知を希望する場合で、犯罪の動機及び組織的背景、加害者と被害者やその親族等の方々との関係、加害者の言動その他に照らし、検察官が通知を行ったほうがよいと認めたときです。

『再被害防止のための通知制度』
Q7 通知の内容はどのようなものですか。
A 受刑者の釈放直前における釈放予定(仮釈放の場合を含む。)の時期(通常は、月の上、中、下旬)を通知します。また、特に必要があるときは、釈放された後の住所地を通知することもあります。
Q8 通知を受けるにはどうしたらよいのですか。
A 通知を希望するときは、担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員にお申し出ください。
A 受刑者の釈放直前における釈放予定(仮釈放の場合を含む。)の時期(通常は、月の上、中、下旬)を通知します。また、特に必要があるときは、釈放された後の住所地を通知することもあります。
Q8 通知を受けるにはどうしたらよいのですか。
A 通知を希望するときは、担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員にお申し出ください。
2 証拠品の返還
検察庁では、被害者の方からお預かりした証拠品については、捜査・公判上の必要がなくなり次第、速やかに被害者の方にお返しすることとしています。
加害者から差し押さえられた窃盗事件や強盗事件の被害品についても、捜査・公判上の必要がなくなり次第、速やかに被害者の方にお返しします。
そのほか、被害者の方の所有物が証拠品となっていて、その返還を希望される場合は、担当の検察官・検察事務官又は被害者支援員にご相談ください。
加害者から差し押さえられた窃盗事件や強盗事件の被害品についても、捜査・公判上の必要がなくなり次第、速やかに被害者の方にお返しします。
そのほか、被害者の方の所有物が証拠品となっていて、その返還を希望される場合は、担当の検察官・検察事務官又は被害者支援員にご相談ください。

『証拠品の返還』
3 証拠品の廃棄処分への立会い

『証拠品の廃棄処分への立会い』
4 確定記録の閲覧
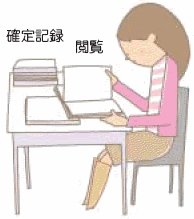
『確定記録の閲覧』
具体的な手続については、各検察庁の記録事務担当者又は被害者支援員にお尋ねください。
5 矯正施設における被害者等の心情等の聴取・伝達制度
被害者やご遺族の方々の被害に関する心情、被害を受けられた方の置かれている状況、受刑・在院中の加害者の生活や行動に関するご意見をおうかがいし、これを受刑生活中・在院生活中の加害者に伝える制度です。
刑事施設・少年院には、本制度の担当者を配置しており、おうかがいしたご意見等を踏まえ、加害者に被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるよう指導を行います。
制度の利用を希望される場合には、最寄りの矯正管区又は矯正施設(刑事施設・少年院・少年鑑別所)までお問い合わせください(参考 法務省ホームページ「刑の執行段階等における被害者等の心情等聴取・伝達制度」)
Q1 どのような人が制度を利用できるのですか。
A (1)加害者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪等により被害を受けた方、(2)被害を受けた方の法定代理人、(3)被害を受
けた方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障(病気やけがなど)がある場合におけるその配偶者、直系親族又は兄弟姉妹の方です。
Q2 加害者がどの施設にいるかわからなくても利用できるのですか。
A 加害者の収容施設がわからなくても、制度を利用することは可能です。最寄りの矯正管区・矯正施設にご相談ください。なお、加害者の収容施設や処遇状況等については、被害者等通知制度をご利用いただくことにより、知ることができます。
Q3 聴取の際は、矯正施設まで行かなくてはならないのですか。
A ご事情により、心情やご意見等を記載した書面の提出も可能ですが、お気持ちをより正確にうかがうためにも、矯正施設にお越しいただき、直接担当者にお話しされることをお勧めします。なお、矯正施設までお越しいただく場合は、所定の交通費をお支払いすることができます。
刑事施設・少年院には、本制度の担当者を配置しており、おうかがいしたご意見等を踏まえ、加害者に被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるよう指導を行います。
制度の利用を希望される場合には、最寄りの矯正管区又は矯正施設(刑事施設・少年院・少年鑑別所)までお問い合わせください(参考 法務省ホームページ「刑の執行段階等における被害者等の心情等聴取・伝達制度」)
Q1 どのような人が制度を利用できるのですか。
A (1)加害者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪等により被害を受けた方、(2)被害を受けた方の法定代理人、(3)被害を受
けた方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障(病気やけがなど)がある場合におけるその配偶者、直系親族又は兄弟姉妹の方です。
Q2 加害者がどの施設にいるかわからなくても利用できるのですか。
A 加害者の収容施設がわからなくても、制度を利用することは可能です。最寄りの矯正管区・矯正施設にご相談ください。なお、加害者の収容施設や処遇状況等については、被害者等通知制度をご利用いただくことにより、知ることができます。
Q3 聴取の際は、矯正施設まで行かなくてはならないのですか。
A ご事情により、心情やご意見等を記載した書面の提出も可能ですが、お気持ちをより正確にうかがうためにも、矯正施設にお越しいただき、直接担当者にお話しされることをお勧めします。なお、矯正施設までお越しいただく場合は、所定の交通費をお支払いすることができます。
6 仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度
被害者やご遺族等の方々が、加害者の仮釈放や少年院からの仮退院等を許すか否かの審理を行う地方更生保護委員会に対して、仮釈放等、生活環境の調整(※)、保護観察に関するご意見や被害に関する心情を伝えることができる制度です。
制度の利用を希望される場合には、地方更生保護委員会までお問い合わせください(参考 法務省ホームページ「地方更生保護委員会・保護観察所連絡先一覧(被害者専用番号)」)。
※ 生活環境の調整とは、収容されている加害者の社会復帰を図るため、釈放後の帰住環境を調査・調整するものです。
Q1 どのような人が制度を利用できるのですか。
A (1)被害者の方、(2)被害者の方の法定代理人、(3)被害者の方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障(病気やけがなど)がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の方です。
Q2 地方更生保護委員会に対して述べた意見などはどのように扱われるのですか。
A 仮釈放等を許すか否かの判断や生活環境の調整に当たり考慮されるほか、仮釈放等が許可されて保護観察となった場合は、保護観察を実施する上での指導などで考慮されます。
Q3 いつ制度を利用できるのですか。
A 制度を利用できる期間は、加害者の仮釈放等の審理が行われている間に限られます。なお、被害者やご遺族等の方々は、被害者等通知制度を利用することにより、審理の開始を知ることができます。
制度の利用を希望される場合には、地方更生保護委員会までお問い合わせください(参考 法務省ホームページ「地方更生保護委員会・保護観察所連絡先一覧(被害者専用番号)」)。
※ 生活環境の調整とは、収容されている加害者の社会復帰を図るため、釈放後の帰住環境を調査・調整するものです。
Q1 どのような人が制度を利用できるのですか。
A (1)被害者の方、(2)被害者の方の法定代理人、(3)被害者の方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障(病気やけがなど)がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の方です。
Q2 地方更生保護委員会に対して述べた意見などはどのように扱われるのですか。
A 仮釈放等を許すか否かの判断や生活環境の調整に当たり考慮されるほか、仮釈放等が許可されて保護観察となった場合は、保護観察を実施する上での指導などで考慮されます。
Q3 いつ制度を利用できるのですか。
A 制度を利用できる期間は、加害者の仮釈放等の審理が行われている間に限られます。なお、被害者やご遺族等の方々は、被害者等通知制度を利用することにより、審理の開始を知ることができます。
7 保護観察中における心情等聴取・伝達制度
被害者やご遺族等の方々の被害に関する心情、その置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関するご意見を保護観察所がお聴きし、ご希望がある場合には、これを保護観察中の加害者に伝える制度です。制度の利用を希望される場合には、加害者の保護観察を実施している保護観察所又はお住まいの地域にある保護観察所までお問い合わせください(参考 法務省ホームページ「地方更生保護委員会・保護観察所連絡先一覧(被害者専用番号)」)。
Q1 どのような人が制度を利用できるのですか。
A (1)被害者の方、(2)被害者の方の法定代理人、(3)被害者の方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障(病気やけがなど)がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の方です。
Q2 保護観察所に対して述べた心情などはどのように扱われるのですか。
A 加害者への伝達を希望する場合、保護観察所において、加害者が被害の実情などに向き合い、反省や償いの意識を深めるよう指導を行います。
加害者への伝達を希望しない場合、お聴きした心情などは、加害者の保護観察を実施する上での指導などで考慮されます。
Q3 いつ制度を利用できるのですか。
A 制度を利用できる期間は、加害者が保護観察を受けている間に限られます。なお、被害者やご遺族等の方々は、被害者等通知制度を利用することにより、保護観察の開始を知ることができます。
Q1 どのような人が制度を利用できるのですか。
A (1)被害者の方、(2)被害者の方の法定代理人、(3)被害者の方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障(病気やけがなど)がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の方です。
Q2 保護観察所に対して述べた心情などはどのように扱われるのですか。
A 加害者への伝達を希望する場合、保護観察所において、加害者が被害の実情などに向き合い、反省や償いの意識を深めるよう指導を行います。
加害者への伝達を希望しない場合、お聴きした心情などは、加害者の保護観察を実施する上での指導などで考慮されます。
Q3 いつ制度を利用できるのですか。
A 制度を利用できる期間は、加害者が保護観察を受けている間に限られます。なお、被害者やご遺族等の方々は、被害者等通知制度を利用することにより、保護観察の開始を知ることができます。

