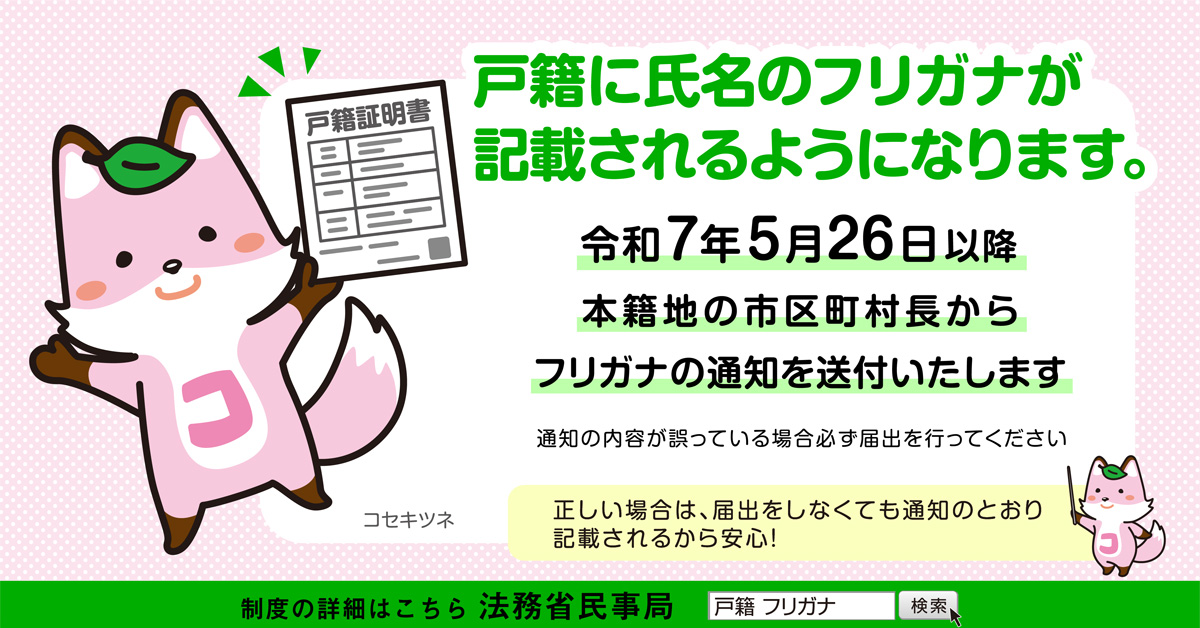CONTENTS
記者が行く!
~国際知財司法シンポジウムフォローアップセミナー~
皆さま、こんにちは!
今日は、2024年12月4・5日にジャカルタ(インドネシア)で行われた「国際知財シンポジウムフォローアップセミナー」について大臣官房国際課の担当者にお話を伺ってみたいと思います!
国際知財シンポジウムフォローアップセミナーとは、どのような会議ですか?
担当者「国際知財司法シンポジウム(Judicial Symposium on Intellectual Property:通称JSIP(ジェーシップ)」は、知的財産分野における日本で最大規模のシンポジウムです。法務省は、平成29年から、最高裁判所や特許庁などと共に開催しています。ビジネスのグローバル化が進んで、国境を越えた海賊版被害や模倣品販売が広がる中で、知的財産権の保護は各国共通の関心事となっています。日本は、ASEANを中心とするアジア地域の国々に法制度整備支援を行ってきましたが、知的財産に関する制度が不十分で専門家が不足している国も多いことから、近年、知的財産保護の分野での支援ニーズが高まっています。日本がこうした国々を支援することによって、知的財産権保護の法制度や運用が充実していけば、その地域で法の支配の定着が図られて、相手国の持続的成長につながりますし、日本企業によるASEAN地域への進出も後押しされます。そのため、法制度整備支援の一環として、法務省はこうした国々から法曹関係者や政府関係者をJSIPに招き、法務省プログラムとして、知的財産分野の重要なテーマを取りあげ、基調講演やパネルディスカッションを行ってきました。(過年度のJSIPについては、法務省HP「国際知財司法シンポジウム」を御覧ください。)
2023年のJSIPの法務省プログラムでは、アジア地域でも課題となっているEコマース上の模倣品対策などを討議しました。今回、そのフォローアップとして開催されたのが「国際知財シンポジウムフォローアップセミナー」なんです!
記 者今回のフォローアップセミナーは一昨年のJSIPとはどう違うのですか?
担当者JSIPのように日本開催としたのではなく、インドネシアのジャカルタで開催したことがまず大きな違いです。また、その開催場所がASEAN域内であることから、JSIPの法務省パートで呼べたよりも多くの国々、具体的には、ASEAN10か国全てと、東ティモール、日本から、知的財産権を専門とする裁判官・行政官・弁護士などの皆さんに参加いただくことができました。
さらに、会場となったインドネシアでは、JICAによる知的財産保護に関するプロジェクトも長く行われてきていましたので、このプロジェクトともコラボすることができ、インドネシア最高裁判所の裁判官を含め多くの裁判官が参加してくださり、とても活気ある会議となりました。
記 者JSIP以上に、ASEAN全体への支援という色合いがより強く感じられますね。
担当者そうなんです。日本とASEANは、一昨年友好協力関係50周年を迎えて、法務省も「日ASEAN特別法務大臣会合」という大臣級の会合を主催し、協力に向けた具体的なワークプランもできました。このように、今後さらに協力関係を強めていこうという機運が生まれていることが背景にあります。
ASEAN地域全体での知的財産の紛争処理能力の向上を図るためにも、ASEANを一体として支援する視点はとても重要だと思っています。そのためには、より幅広い国々から参加してもらい、実務家同士の知見の共有やネットワーク形成が一層図りやすい開催形態を模索してみることが大切だと考えて、フォローアップセミナーとしてはかなり力を入れて、今回のような開催形態をとりました。

開会式・集合写真
セミナーには、専門家の方々が集まったとの事ですが、どういった話題について議論がされたのでしょうか?
担当者Eコマース(ネット通販)上の模倣品対策について1日目は裁判官の参加者を中心として、「商標権侵害訴訟をめぐる課題」、2日目は行政官の参加者を中心として、「商標権のエンフォースメント」について各国法制度・実務の紹介や意見交換等が行われました。例えば、あるブランドの模倣品だとして訴えられたネット上の商品について、商標登録されたものと似たものだと言えるのかについて、各国裁判所がどのような基準で判断しているかですとか、模倣品がネット通販されていることで権利侵害を受けている会社が侵害者に関する情報の提供を求められる仕組みがあるか、販売者ではなくEコマースサイトの運営者の責任を問えるのか、など多様な論点について討議され、各国の法制度や実務に関する経験が共有されました。各国参加者による制度説明に対して、フロアからもたくさんの質問が寄せられるなど、模倣品対策への関心の高さがうかがえました。

セッション1日目

セッション2日目
知的財産に関する取組状況は国によって異なりますが、参加者の皆さんは他国の取組から学ぼうと、とても熱心に参加してくださいました。セミナー終了後「ASEAN地域の知的財産権に関する知識が増え、とても勉強になった」、「セミナーを通してネットワーク構築ができた」とのお言葉をいただき、満足いただけたようで私たちも嬉しく思っています。
こういった情報共有の場を提供することで、アジア地域全体の知的財産に関する法制度構築やそれを運用する方々の能力向上の一助になればと考えています。

閉会式後・集合写真
これだけの会議を開催するには、準備も大変だったのではないでしょうか。セミナーを終えてみての感想や、印象に残っていることはありますか。
担当者たしかに、初めての試みでしたので、準備には多くの苦労がありましたが、このように多くの国が参加して実りあるセミナーを開催することができたのは、各国からのセミナー参加者の貢献はもちろんのこと、共催・後援いただいた関係機関・団体の皆様の協力のおかげです。このように、様々な国・立場の参加者や関係機関と協力して、1つのイベントを作り上げるのは、国際関係業務のひとつの醍醐味です。
そして印象の残ったことは、「海外でセミナーを開催した」ことでしょうか。国際課では、年に何度も国際会議を開催、もしくは海外で開催される国際会議へ出席しています。しかし、セミナーを海外で開催する機会はめったになく、開催地が通常と異なるという意味では、今回のセミナーは大きな挑戦でした。私自身、準備を始めた頃は大きな不安を抱えていたのですが、セミナー参加者の皆さん・同じ国際課内の職員・現地の業者に協力してもらいながら、無事に終えることができました。セミナー参加者とのコミュニケーションや現地ならではの食事など楽しい思い出もたくさんできましたが、やはり、国際会議の運営に携わり無事に成功したことが、一番忘れられない経験です。
記 者本日は、ありがとうございました!