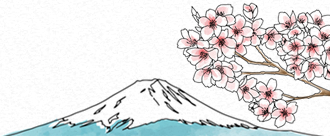| ○ |
総人口や生産年齢人口の減少下においても、女性、高齢者の労働力率の引き上げ、生産性の向上等により、経済的にはある程度国内で対処できることについては、一定のコンセンサスが得られているが、その経済的効果については必ずしも判然としない。 |
| ○ |
社会の多様性が進むことが社会の活力につながると考えられ、そのような多様化に資するような人材の受入れを進めていくべきであり、現在受け入れている高度人材の範囲については、実情に即して見直すべきである。 |
| ○ |
国内の失業問題との関係で受入れ反対論もあるが、ミスマッチによる失業が多い状況において、失業率が高いから受け入れないという問題ではないのではないか。雇用ニーズに合う外国人を受け入れれば、ミスマッチの解消にもつながるのではないか。 |
| ○ |
移民の受入れは、国内需要の増大によって雇用が創出されることから、失業の増大にはつながらない。経済的にはむしろプラスになる。 |
| ○ |
受入れに伴う社会的コストは、日本人にも同様にかかるものであり、社会的便益の方が大きい。 |
| ○ |
日本の雇用の7割は中小企業においてであり、産業構造の高度化が更に進展してもそのような現場は必要であり、外国人を受け入れないと立ちゆかなくなる。その場合、就労管理のシステム作りが重要となる。 |
| ○ |
外国人労働者の受入れを厳しく制限すれば、雇用ニーズのある現場において、不法就労者の雇用が増大するのではないか。 |
| ○ |
単に人材不足や人手が足りないという理由で外国人労働者の受入れを考えるのではなく、そのような職種に就こうとしない理由をまず考え、労働環境の改善等原因の除去に努めることが先決である。 |
| ○ |
受け入れた外国人労働者の適正な管理のためには、関係機関の緊密な連携が特に重要である。 |
| ○ |
外国人労働者の受入れに当たっては、受入れに伴うコストを雇用者側が負担するなど責任体制を確立させるとともに、雇用に係る法令の遵守を確実に担保できる公的チェック体制を強化することが必要である。 |
| ○ |
女性の労働力移動については、送出し国の貧困対策支援が必要であるとともに、その背景事情として、女性に対する暴力や不平等があること等を常に念頭に置いておくべきである。 |
| ○ |
社会の活性化を図る上で有用な人材は受け入れるべきであるが、その範囲を考える上で、ポイント制について検討することも有意義である。 |