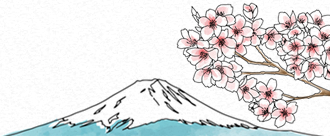| ○ |
看護師は不足しているが、資格があっても働いていない人が多くいる。これは、残業など就労環境が厳しく、働きたくても働けないのが実情ではないか。 |
| ○ |
看護師については、専門性を担保した上で徐々に受入れ範囲を広げていくのが現実的な政策であると思われる。 |
| ○ |
看護、介護分野等について、単に足りないから外国人労働者を受け入れるということではなく、レベルの高い人材を育成して、人的国際交流を進めるという観点が重要である。 |
| ○ |
欧米では現実に看護師が不足しており、このような国では外国人看護師の受入れを行っているが、受け入れ国、送出し国双方にとってプラスであるとの評価がなされている。 |
| ○ |
看護師資格の相互認証を行い、入国後はある程度簡単な業務からOJTを通じて能力を高めていくような受入れ方法が実効的ではないか。 |
| ○ |
留学生等として来日し、日本で看護分野の教育を受けた上で就労し、我が国で取得した資格を本国で活かすような枠組みが構築されれば、送出し国への貢献にもなる。 |
| ○ |
日本語のコミュニケーションは不可欠であり、日本語で日本の看護師資格を取得することは、入国を認める際の最低限の条件である。 |
| ○ |
英語圏の外国人患者のために、英語を解する看護師も必要であり、日本語の条件は柔軟に考えてもいいのではないか。専門分野の外国人労働者の受入れを積極的に推進する観点から、そのような看護師の受入れも必要ではないか。 |
| ○ |
看護師資格を有しているものの、育児、介護等を理由に就業できない人が多い状況の中で、受入れを進めるべきか疑問がある。 |
| ○ |
女性が主たる対象となる分野で労働者を受け入れる際には、人身取引等の問題が絡む可能性を常に念頭に置いておくべきである。 |
| ○ |
ホームヘルパーの1~3級の課程を修了した者は200万人以上おり、実際問題としてどのような場面で不足しているのかわからない。単に諸外国からの受入れ要望に応えればいいという問題ではない。 |
| ○ |
介護分野については、単純労働力の受入れにつながる可能性も否定できないので、慎重に検討すべきではないか。 |
| ○ |
介護分野については、専門性の高い人材を国内で養成中であり、外国人労働者の受入れによりレベルの低下を招くおそれがあるのではないか。 |
| ○ |
家事使用人の受入れについては、当該外国人の母国の言語、文化による養育が行われ、それが問題となっている例も諸外国にはある。 |
| ○ |
家事使用人の受入れについては、英語教育等の面でもメリットがあるのではないか。 |
| ○ |
受入れの議論をするに当たっては、どの分野を専門的、技術的と定義付けるか明確にする必要がある。 |