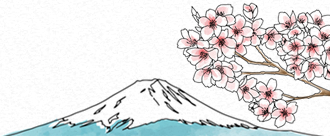- トップページ
- 政策情報(会議・統計等)
- 会議・委員会等
- 出入国在留管理政策懇談会
- 第4次出入国管理政策懇談会状況
- 第四次出入国管理政策懇談会第21回会合:議事概要
第四次出入国管理政策懇談会第21回会合:議事概要
| 1 日 時 | 平成16年9月27日(月)午後2時~午後4時 |
| 2 場 所 | 法曹会館・高砂の間 |
| 3 出席者 | (敬称略) |
| (1) | 第四次出入国管理政策懇談会 |
| 楠川絢一(座長)、紀陸 孝、グレゴリー・クラーク、高橋 進、多賀谷一照、中谷 巌、目黒依子、吉川精一 | |
| (2) | 法務省入国管理局 |
| 三浦入国管理局長、蒲原官房審議官、榊原総務課長、高宅入国在留課長、西尾警備課長、三好登録管理官、沖参事官、佐々木難民認定室長、石田出入国情報管理室長、上原入国管理企画官 |
| 4 | 会議経過 訪日観光客の拡大等、留学生等の受入れ問題、研修・技能実習制度の在り方について、それぞれ入国管理局から説明を行った後、意見交換が行われた。主な意見は以下のとおり。 |
| (1) | 訪日観光客の拡大等について |
| ○ | 上陸審査の際、再入国者以外の者等に絞った重点審査を行うことで、不法入国者等をいかに阻止するかということが重要である。 |
| ○ | 上陸の許否を決するに当たっては、判断の客観性をこれまで以上に担保することが重要である。 |
| ○ | 訪日観光客の拡大のためには、具体的な方策に基づくロードマップが必要である。 |
| (2) | 留学生等の受入れ問題について |
| ○ | 留学生が卒業後に就職活動を行うことができる「短期滞在」の在留資格を容認したことは評価に値するが、180日間では就職のための準備期間としては半端であり、1年程度の準備期間を設けてはどうか。また、インターンシップを活用するなどの措置も重要である。 |
| ○ | 日本における留学生のアルバイトが可能な時間の上限は、欧米諸国と比べて緩く設定されている。このことが、日本ではかなり長時間働くことができるというメッセージとなり、勉学以外の目的で来日する留学生を増やす要因になっているのではないか。 |
| ○ | 留学生の卒業後の滞在について、就職先の有無で画一的に判断するのではなく、留学生の学力レベルや資格、文系・理系の違い等も考慮に入れて判断するべきではないか。 |
| ○ | 留学生の就職という観点からすると、一大学にあまりに多数の留学生がいる場合は、就職支援を行う大学の留学生課の職員が限定されていることから、十分な支援ができないと思われる。 |
| ○ | 留学生の管理を大学側に求める取組みも重要である。 |
| (3) | 研修・技能実習制度の在り方について |
| ○ | 研修生、技能実習生が単純労働者として日本に定着しない仕組みが必要である。そのため、例えば、研修・技能実習期間を一定期間にして、延長を認めない代わりに何度も来日できるようにするなどの方策も考えられる。 |
| ○ | 研修・技能実習制度が効果的に運用されている事例もあるが、趣旨の徹底が図られていない面もあり、受入れ機関の責務の強化を含めた厳格な対応と、制度趣旨を踏まえた柔軟な対応のメリハリが重要である。 |
| ○ | 研修・技能実習制度には国際貢献という趣旨も含まれるが、実際は日本の必要性が中心となっている場合が多く、現地の開発計画等、送り出し国のニーズを把握することも必要ではないか。 |
| ○ | 技能実習移行対象職種には、ソフトウェア開発等が含まれておらず、現在の日本の産業構造を反映したものになっていない。 |
| (文責 法務省入国管理局) |