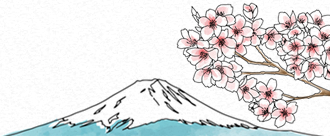| ○ |
不法残留者の中には、日本の経済社会へ貢献している者も多く、そのような者を退去強制することは日本にとっても好ましくないので、善良な外国人であればアムネスティ又は在留特別許可の基準の明確化を通じて正規化し、引き続き日本に滞在することができるようにするべきである。 |
| ○ |
かつてのバブル期にも不法滞在者は存在したが、彼らがそれほど犯罪を引き起こさなかった背景には、十分に職が確保され、それなりの賃金水準が維持されていたという事情がある。低賃金・劣悪条件の下での労働は、外国人を犯罪に駆り立てやすくするため、現行の入管行政を維持しつつ、いかに外国人が働きやすい環境を作っていくかということが今後の課題である。 |
| ○ |
米国ではアムネスティが実施されているが、むしろ不法滞在問題等が深刻化したとの話を聞いたことがある。 |
| ○ |
不法滞在者全てが危険な存在ということではないが、不法残留者による犯罪の発生率は日本人よりかなり高いのは間違いなく、現行の方針は維持すべきであるが、あわせてどういう外国人に来てもらうかを考えるべきである。 |
| ○ |
アムネスティによる正規化は問題を大きくするだけである。 |
| ○ |
アムネスティの要件の設定次第では、問題を重くしない形で、不法残留者ではあるが、退去強制することが人道的に好ましくない外国人や、日本に貢献し得る外国人を退去強制させずに対処することが可能となるであろう。 |
| ○ |
不法滞在者イコール犯罪者という見方は単純に過ぎるが、他方、外国人の単純労働の自由化は、外国人犯罪の増加につながるおそれがある。 |
| ○ |
米国でのアムネスティは、政策転換時、すなわち、新方針に基づく受入れ要件で見た場合に当該新要件に該当する不法滞在者を合法化する,または、以後の取締りを強化する際に実施されているようである。 |
| ○ |
在留特別許可の事例公表は、むしろ不法滞在の長期化につながり、子供の未就学や未就学児童の犯罪への関与といった問題が懸念される。 |
| ○ |
外国人を雇用する側の日本人にも責任があることを自覚させるために、不法就労助長罪を更に厳しくするべきである。 |
| ○ |
トラフィッキング対策については、入管局が使命感を持って積極的に取り組んでほしい。 |