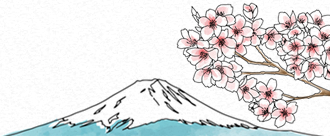- トップページ
- 政策情報(会議・統計等)
- 会議・委員会等
- 出入国在留管理政策懇談会
- 「人口減少時代における出入国管理行政の当面の課題~円滑化と厳格化の両立に向けて~」
- 「人口減少時代における出入国管理行政の当面の課題~円滑化と厳格化の両立に向けて~」
「人口減少時代における出入国管理行政の当面の課題~円滑化と厳格化の両立に向けて~」
| (1) | 専門的、技術的分野における受入れ全般についての基本的考え方と対応 今後とも我が国経済の持続的な発展を維持していくためには、生産性の向上に資する機器やビジネスモデルの構築を行う人材など、全要素生産性(※1)の向上に寄与するような専門的、技術的分野の人材への需要は一層高まっていくものと考えられる。また、国際的な分業や我が国の構造改革の進展に伴って、可能な限り高付加価値を生み出す分野の発展を図っていくことが重要であり、そのような分野での活躍が期待できる専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れは、今後の我が国経済社会の一層の発展に資するものであると考えられる。加えて、FTA(自由貿易協定)/EPA(経済連携協定)の進展等に見られるように、近隣諸国を中心とする諸外国との経済的な連携が深化することによって、円滑な経済活動の実際の担い手となるこれらの外国人労働者の受入れニーズは高まっていくと思われる(※2)。専門的、技術的分野の外国人労働者が様々な分野で日本人と協働することにより、多様な価値観や発想による我が国の経済社会の活性化も期待される。 また、企業の経済活動の変化に伴い、多様な経済活動に対応する新たな形態の専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れニーズが生じていくことも想定されるところ、このようなニーズに的確に対応し、外国人の円滑な受入れを実現することも出入国管理行政には求められている。 専門的、技術的分野の外国人労働者の積極的な受入れのため、入国管理局においては、これまでも日本のIT関連資格と相互認証された外国の試験等のうち、告示で定めたものに合格等した外国人については、学歴や実務経験にかかわらず入国することを認めることとし、順次その対象を拡大しているほか、構造改革特区における特例措置を講ずる等してきたところである(資料1)。在留資格「外交」、「公用」及び「興行」を除く就労を目的とする在留資格について見ると、新規入国者数は増減を繰り返しているものの(資料2)、在留者数自体はほぼ一貫して増加している(資料3)。今後とも、専門的、技術的分野の外国人労働者の積極的な受入れを図っていくためには、例えば以下のような措置について検討することが重要である。 |
| ※ | 1 成長会計の手法で経済成長率を要因分解すると、以下の3要因からなる。人口減少下においては、労働投入の減少が経済成長の押し下げ要因となるため、持続的な経済発展を維持していくためには、全要素生産性を向上させることの重要性が一層高まる。 |
| 経済成長率=労働の寄与(労働の伸び率×労働分配率)+資本の寄与(資本の伸び率×資本分配率)+全要素生産性の寄与 | |
| ※ | 2 平成15年の「貿易統計」(財務省作成。平成16年3月確定)によれば、ASEAN諸国、中国、台湾、香港及び韓国との貿易額の合計は、平成11年と比べて同15年には輸出で44.0%,輸入で42.4%それぞれ増加しているところ、これらの国・地域出身の「外交」、「公用」及び「興行」を除く就労を目的とする在留資格に係る外国人登録者数は、同期間に26.3%増加した。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| (2) | 特に高度な人材の受入れの促進 専門的、技術的分野の外国人労働者の中でも、特に高度な人材については、国際的な人材獲得競争が繰り広げられており、前記(1)で言及した受入れによる我が国への貢献は更に大きいものと思われる。こうした特に高度な人材については、現行制度においても受入れが可能であり、出入国管理制度上の障壁はほとんどないものと考えられるが、出入国管理行政としてもその受入れ促進のために一定のインセンティブを与えるための措置など最大限の方策を講じていくべきであると考えられる。そこで、例えば以下のような措置について検討することが重要である。 なお、民間企業における取組として、能力評価に基づく賃金制度の構築等高度な人材にとって魅力ある就労環境が提供される必要があるとの意見も出された。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| 3 | 人材育成を通じた国際関係の展開 |
| (1) | 研修・技能実習制度 研修・技能実習制度は、主として開発途上国の人材育成を支援する国際貢献のための制度である。在留資格「研修」の新規入国者数は年々増加しており、平成15年には初めて6万人を突破し(資料5)、技能実習への移行者数も同年に約2万800人に達する(資料6)など、アジア地域を中心としてこの制度の利用者は増加の一途を辿っている。今後とも、アジア地域全体の経済発展が見込まれる中で、研修生・技能実習生は増加していくことが見込まれ、我が国で修得した技術・技能を活かして出身国の経済発展に貢献することが期待されるほか、日本語や日本の文化に理解を深めた研修・技能実習経験者が増加することは、近隣諸国との経済的な結びつきが強まる中で、研修生等の受入れ企業等の国際的な発展にも資するものと考えられる。 他方、研修・技能実習制度をめぐる問題点も一部に顕在化している。例えば、地方入国管理局が行った実態調査の結果、平成15年の1年間に92の受入れ機関が不正行為認定されており(※1)、そのほとんどがいわゆる団体監理型の研修(※2)である。不正行為の主な態様は、中小企業団体等の第1次受入れ機関については、監査の虚偽報告及び集合研修の未実施等となっており、研修の実施主体である第2次受入れ機関については、研修生に対する所定時間外の活動の実施、日本語教育・安全教育等の非実務研修を実施しない等研修計画との齟齬、人手不足の他の機関で研修を実施させる等の名義貸し、虚偽文書の作成、不法就労者の雇用等となっている。これらの不正行為の態様から、受入れ企業の一部は、内外の企業との厳しい競争や労働力不足を背景として、研修・技能実習制度を低廉な労働力を確保するための手段であると認識していることが垣間見え、制度趣旨の徹底が図られていない面があることは否めない。他方、多数の研修生・技能実習生が失踪しているが、こうした失踪の背景には、研修生等自身も研修・技能実習制度を報酬を得て働くための手段であると認識しており、高い報酬を目指して失踪することがあると考えられる。また、高い報酬を得ることを目的としていれば、研修手当と技能実習生の賃金との格差に不満を持つケースも少なくないと思われ、特に研修生・技能実習生の受入れ機関は中小企業であることが多いことを考慮すると、研修生・技能実習生で異なる作業をしていたとしても、比較的狭い空間での一連の作業の中で技能実習生と異なる収入を得ることに研修生が不満を持つ傾向は一層高まるものと推測される。こうした問題の背景としては、研修生の選抜段階のほか、入国前や入国直後のオリエンテーションにおいて、研修・技能実習の制度趣旨を理解させる指導が徹底していないことも考えられる。 このように多様な側面で多くの効果を生んでいるものの、問題事例も発生している研修・技能実習制度については、これまでの実態調査の実施や、「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」の策定等を通じた適正化への取組を踏まえて、今後、実態調査の更なる強化や不正行為認定等を通じた厳格な対応により、まず一層の適正化を図るとともに、制度そのもののプラスの効果が一層発揮されるような取組が重要である。また、実務研修と技能実習という、活動形態が一見して同様であるにもかかわらず在留資格が異なることに起因する問題など、制度的な問題点を克服するための措置についても検討が必要であろう。そこで、例えば以下のような措置について検討することが重要である。 |
| ※ | 1 不正行為認定された機関は少なくとも現行の上陸許可基準では今後3年間にわたって研修生の受入れができないこととなる。 |
| ※ | 2 団体監理型の研修とは、中小企業団体や公益法人等を研修事業主体としてこれらの団体の監理の下で研修生を受け入れるもの。これに対し、企業単独型の研修は、海外の現地法人の社員等を受け入れるものである。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| (2) | 留学、就学 留学生、就学生の受入れについては、諸外国との相互理解、友好関係の促進に資するものであり、我が国と近隣諸国を中心とする諸外国との経済活動の緊密化が進む中にあって、勉学を終了した後に日本国内で就職し、出身国との経済活動の連携の面で活躍する者や、出身国に帰国後も我が国と様々な面で関係を保ちつつ、活躍する人材も増加している。また、我が国で学ぶ外国人学生の増加は、これらの学生との接点を持つ日本人学生等に対して異なる文化等を背景とした発想や知識等に触れる機会の増加を意味するものである。同じように、これらの外国人学生が我が国企業に就職した場合には、他の日本人従業員に同様の機会を提供するものであり、我が国の経済社会の活性化に資することとなる。このような観点から、入国管理局においては、「留学生・就学生の入国・在留審査の方針」を策定するなどし、問題のない事案については提出書類を大幅に簡素化するなどの措置を講じてその積極的な受入れに資する施策を講じてきたところであり、在留資格「留学」、「就学」での新規入国者数は、それぞれ一貫して増加しているほか(資料7)、これらの在留資格での平成15年末の外国人登録者数はそれぞれおよそ12万人、5万人を突破して過去最高を記録している(資料8)。この結果、各方面に留学生等の受入れのプラスの効果が波及してきているものと思われる。 しかしながら、近年、真の入国目的が不法就労である者が多く見られるほか、「留学」や「就学」の目的をもって来日しても、十分な資金を持たないために、生活費や学費を支払うことが困難となり、勉学の途中で退学したり、失踪する例、多額の借金をして来日した結果、許可された時間等の条件を逸脱してアルバイトに従事することとなってしまう例、生活に困難を来し、アルバイト先も見つからずに犯罪グループの一員となったり、自ら犯罪に走ることとなる例、更には偽造の卒業証明書、銀行預金残高証明書等を用いるものが多く見られるようになっている。 今後、アジア地域との経済連携の深化と、中国を始めとする近隣諸国の経済水準の向上に伴い真に勉学意欲を有する者の増加も予想されることから、留学生、就学生の適正な受入れのための措置を引き続き講じつつ、魅力ある留学、就学環境の構築のため、出入国管理行政としても貢献していくことが重要である。そこで、不法残留者が多数発生している国の出身者や不法残留者が発生している教育機関に入学する者に係る経費支弁能力等の審査を引き続き徹底するとともに、例えば以下のような措置について検討することが重要である。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| なお、大学における留学生の選抜方法の見直し等留学生の質の向上を図るための措置や、留学生政策全般に関することとして、文系・理系、学部・大学院といった違いに着目した施策を講ずるべきとの意見も出された。また、留学生の選抜に当たっては、日本留学試験の一層の活用が重要であり、同試験が実施される国の拡大の意義は大きい。日本に入国する留学生の中では中国出身者が最も多い状況にあるが、同国では日本留学試験が実施されていないことから、引き続き同国での実施に向けた努力がなされることが望ましい。 |
| 4 | 文化交流の拡大 |
| (1) | 訪日観光客の拡大 訪日観光客拡大のための取組は、その経済的な効果のみならず、我が国に対する理解、親近感の増進が地域や草の根レベルでも進むこととなり、諸外国との相互理解、友好関係の深化等に資するものである。また、地方空港への国際定期便の就航や国際チャーター便の増加に伴って、日本の各地を訪れる外国人が増加しており、地域経済の活性化にも大きな影響を与えるものとなっている。政府においては、平成15年7月に観光立国行動計画を取りまとめ、徐々に増加してきている我が国を訪れる外国人観光客を現在の約500万人から(資料9)、平成22年(2010年)までに1,000万人に倍増させる計画を進めており、外国人観光客の円滑な受入れの実現に向けて、出入国管理行政としても貢献していく必要がある。 他方、出入国管理行政の使命は、大多数の善良な外国人の円滑な受入れを図りつつ、テロリストや国際的な犯罪組織の構成員、不法就労を企図する者等の入国を水際において確実に阻止しなければならないという重大な責務も負っているところであり、前記行動計画の推進による入国者数の増加が予想される中で、一見相反する課題に対して的確に対応していく必要がある。 そこで、外国人観光客等の受入れの円滑化と審査の厳格化の両立のため、既に入国管理局において取り組むこととしている事項(資料10)の着実な推進及び必要な体制の確保や、不法滞在の発生状況等問題の分析を通じたメリハリのある審査の実施のほか、例えば以下のような措置について検討することが重要である。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| なお,訪日観光客の拡大のため、例えば日本の伝統芸能の鑑賞時における外国語による解説の実施、複数の外国語による案内表示の充実等が重要であるとの意見も出された。また、犯罪者等問題のある外国人の水際阻止に当たっては、日本国内の空・海港での阻止にとどまらず、そうした外国人を我が国に「来させない」ことが必要であり、そのためには、在外公館での厳格な査証発給審査が併せて重要である。 |
| (2) | その他の文化交流の拡大のための施策 ワーキングホリデー制度は、青少年交流の活発化、相互理解の促進に資するものである。また、我が国で開催される国際的な博覧会等の開催に際しての関係者や入場者の円滑な受入れを行うことも重要である。加えて、在留資格「文化活動」については、我が国特有の文化、技芸等について専門家の指導を受けて修得する場合に許可されるものであるが、我が国の伝統的な技芸等については国内にその継承者が不足しているのではないかとの指摘もある中で、こういった技芸等を修得しようとする外国人の円滑な受入れは重要である。そこで、例えば以下のような措置について検討することが重要である。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| 5 | 長期にわたり我が国に滞在する外国人への対応 |
| (1) | 永住許可の在り方 我が国社会の一員として我が国の経済社会の活性化や発展に貢献し、また、我が国社会において諸外国・地域との関係の円滑化等に資する外国人のうち、我が国に永住することを希望する外国人に対しては、速やかに安定した法的地位である在留資格「永住者」が与えられることが望ましい。また、そのような希望を有する外国人が、積極的に永住許可申請を行えるような環境の整備も望まれる。 ただし、永住を許可された外国人に対しては、在留期間更新時等の活動状況のチェックが行われなくなるほか、在留活動の制限もなくなることから、不正な手段を用いてその許可を求めるなどといった制度の濫用を企図する者を確実に排除することが重要である。そのためには、一般原則としては、永住許可申請時のみならず、その申請に至るまでの在留期間更新許可申請時等における在留活動の確認作業が必要であろう。 そこで、永住許可の弾力化・円滑化を図るため、例えば以下のような措置について検討することが重要である。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| 外国人が住みやすい環境作りのために必要な措置等 既に我が国には、人口の約1.5%に相当する約190万人の外国人が滞在しており(資料11)、その数は年々増加しているほか、今後更に専門性の高い外国人労働者の受入れを促進するとともに、我が国で知識、技術等を修得した留学生や研修生等が日本に対して引き続き関心を持ち、本国において日本の印象を伝えるなどする中で、我が国に在留する外国人にとって住みやすい環境を構築しておくことは非常に有益であることは言を俟たない。 また、我が国に多数在留している日系人については、職場や日常生活の様々な場面でその能力を発揮することが我が国社会の活性化にも資するほか、日本人との草の根レベルの交流が進み、文化や慣習等についての相互理解や日本社会の多様化にも資する。他方で、これらの外国人については、例えば請負や派遣の形態で就労していることが多いとの指摘があり、雇用の調整弁として不安定な就労環境にあることが多いとも言われているほか、社会保険への未加入、子弟の未就学といった問題も指摘されており、こうした問題への対応も急務となっている。 これらの外国人の在留に係る様々な環境整備の問題については、関係省庁、自治体、各企業、NGO等各種団体との連携を通じた対応が不可欠であり、出入国管理行政としても、可能な限りの貢献をしていくことが重要である。そこで、在留資格認定証明書交付申請時等における我が国での経費支弁能力に係る審査を引き続き徹底するほか、例えば以下のような措置について検討することが重要である。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| なお、外国人が住みやすい環境の整備のため、外国人に対する外国人(母国語)による医療の提供の推進や、社会保障協定による年金通算制度の構築の推進のほか、日系人等に対する就労支援、日本語修得機会の増加への取組、未就学児童への対応等も重要であるとの意見も出された。 ところで、日系三世等の外国人が該当する在留資格「定住者」については、これまでも我が国に在留する外国人の状況の変化に応じ、その範囲について見直しを行い、例えば日本人と離婚したものの日本人の実子を監護、養育しながら子供と共に日本に在留するケースについては、一定の要件の下で「定住者」の在留資格での在留を認めるなどの措置が執られている。今後とも、我が国に在留する外国人の状況の変化に応じた「定住者」の範囲の見直しを随時行っていくことが必要であろう。ただし、日系人の受入れについては、第三世代外国人、いわゆる日系三世等として本邦に在留している者の扶養を受ける未成年で未婚の実子の入国も認められているが、血統主義のみによる受入れは適当とは思われないという意見や、これらの者については前記のとおり子の教育、就労等に関する諸問題があり、まず国内の施策を整備し、受入れの環境を整えることが優先されるべきであるとの意見があった。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| 2 | 法違反者の状況に配慮した取扱い |
| (1) | 在留特別許可の在り方 強力かつ効果的な不法滞在者対策を推進する必要がある一方で、不法滞在者の中には不法滞在以外の罪を犯しておらず、既に日本人と結婚して子供もおり、地域社会で良識ある社会人として生活している者もいる。このような不法滞在者の状況を的確に把握し、人道上の配慮を欠くことなく、在留特別許可の許否を決定していくことも重要である。 在留特別許可の許否に当たっては、処分の性質上、その判断を行うに当たって法務大臣は広範な自由裁量を有するものとされ、あくまでも個別の事情を総合的に勘案してその許否が決定されているが、在留特別許可に係る予見可能性を高め、不法滞在者の出頭を促す観点からすれば、在留特別許可事例の公表は一応の目安を示すものとして一定の評価ができるものである。今後、その事例を充実させるとともに、更なる処分の透明性、公平性を図るための方策を検討していくことが重要である。ただし、このような事例の公表は、不法滞在の長期化や、それに伴う未就学児童の増加等につながるおそれもあることに配慮することも重要である。また、現行制度においては、在留特別許可を求める不法滞在者が、入管法違反事実を争わない場合であっても退去強制手続における全ての手続を経る必要があり、必ずしも効率的ではない。 そこで、例えば以下のような措置について検討することが重要である。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| なお、不法滞在者を一律に合法滞在化するアムネスティについては、不法に滞在して就労していること以外の罪を犯していないような者は、一面において地域経済へ貢献しているとも言えることから、一定限度で認めるべきとする意見があった一方、「一度限り」との条件で実施したとしても、次回を期待する不法滞在者の流入及び不法滞在の長期化を誘発し、かえって事態を悪化させる大きな危険があるため、実施すべきではないという意見や、現に諸外国で実施した場合でも以後の不法滞在の状況は悪化している等の意見が表明された。 |
| (2) | )人身取引の被害者に対する配慮等 人身取引は、他人を売春させて搾取することや強制的な労働をさせることなどを目的として暴力、脅迫、誘拐、詐欺、弱い立場の悪用などの手段を用いて人を採用、運搬、移送するなどの行為を指すが、このような人身取引は重大な人権侵害であり、決して許されるものではない、出入国管理行政としては、人身取引の水際防止のため、諸外国関係機関との情報交換を含めた連携強化や、被害者の状況に応じた在留特別許可等の弾力的な運用を含めた柔軟な対応など、被害者の保護のための方策(※)を講じていくことが必要である。また、これらの被害者の保護を一層充実し、確実なものとしていくため、法令改正を含め、必要な見直しを行っていくことが不可欠である。 そこで、出入国管理行政として、この問題に取り組んでいくに当たり、例えば以下のような措置について検討することが重要である。 |
| ※ | 被害者の保護の観点からは、被害者の帰国等については、本人の希望を最優先し、早期帰国を望んでいる者については、本国への送還が迅速に行われているが、我が国での在留を希望する者については、人身取引の被害者であることも在留特別許可に当たって考慮すべき事情の一つとされている。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
| なお、人身取引の被害者を保護するシェルターの充実や、人身取引のブローカーや雇用主などに対しては関係機関で連携した厳格な対応が必要であるとの意見も出された。 |
<検討すべき具体的な措置>
|
<検討すべき具体的な措置>
|
<検討すべき具体的な措置>
|