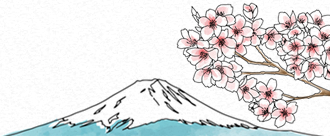- トップページ
- 政策情報(会議・統計等)
- 会議・委員会等
- 出入国在留管理政策懇談会
- 在留管理専門部会開催状況等
- 第11回 在留管理専門部会 議事概要
第11回 在留管理専門部会 議事概要
| 1 | 日 時 平成19年11月8日(木) 午後5時から午後6時30分まで |
| 2 | 場 所 法務省入国管理局10階会議室 |
| 3 | 出 席 者(敬称略) |
| (1) | 在留管理専門部会 多賀谷部会長、稲津委員、薄井委員、武井委員、西村委員、藤原委員、安冨委員、山脇委員 |
| (2) | 法務省 二階審議官、岩尾総務課長、田村入国在留課長、髙岡登録管理官、佐藤参事官、中川局付、佐々木出入国情報管理室長、坂本入国管理企画官、石岡審査指導官 |
| (3) | 関係省庁 警察庁、総務省、外務省、厚生労働省 |
| 4 | 議事概要 |
| 協議に先立ち、武井委員から、本日、同委員が会長をしている外国人登録事務協議会全国連合会から、法務大臣に対し、「適法な在留外国人の台帳制度の整備に関する要請書」を提出した旨の報告があり、続いて山脇委員から、11月28日に岐阜県美濃加茂市で開催される外国人集住都市会議「みのかも2007」の案内があった。その後、登録管理官から、9月14日に開催された外国人登録事務市区町村代表者会議の結果概要及び規制改革会議における最近の議論の状況について説明を行った。 |
| ◇ | 「新たな在留管理制度に関する検討結果(最終報告案・たたき台)」についての協議 |
| 最終報告案・たたき台の「在留カードの交付」及び「所属機関から法務大臣への情報提供」などについて協議を行った。委員からの主な指摘は以下のとおりであった。 | |
|
○ 外国人は、市区町村を経由して居住地の届出を行うことになるが、履行の担保としては、調査権や刑事罰、さらに入管行政上の厳格な対応などが考えられる。外国人登録法上、市区町村長の調査権があるが、これは任意調査である。一方、住民基本台帳法上の市区町村長の調査権には、罰則の担保もある。したがって、新たな制度においては、入管局や市区町村の調査権について、どこまで実効性のあるものにするか検討が必要である。
|
|
|
○ 上陸時に在留カードの交付を受けた外国人が、市区町村に居住地を届け出ることを確保するために、関係企業や学校に、在留カードには居住地が記載されていなければならないことを周知し、居住地記載のあるカードを持った人しか受け入れないようにすることを検討したらどうか。
|
|
|
○ 居住地の在留カードへの反映方法については、偽変造防止の観点も考慮し、ICチップの活用も検討すべきである。事後的には電子データとして保存して、疑わしいときにはチェックできるようなシステムにしておく必要もある。
|
|
|
○ ICチップ書込装置の管理も重要な問題である。
|
|
|
○ カード券面に居住地が反映されることで、様々な場面でカードの有用性が高まり、正確な届出のインセンティブにもつながり、そのカードの記載が正確であることを前提に、諸手続がカード1枚でできるということが合わさって実現されることが望ましい。
|
|
|
○ 改正雇用対策法においては、事業主が外国人雇用状況の届出を怠った場合等には罰則が科されることになっていたと思うが、教育機関等による法務大臣への情報提供について、いかなる形で義務づけるかを検討すべきである。
|
|
|
○ 現行でも、入管局へきちんと報告していない教育機関については、その機関を所属機関として入国を希望する外国人の審査を厳しくするなどの措置がとられている。罰則はなくても、実際の審査で影響があり、指導もしているので、報告をすることについて一定の担保があるという形にはなっている。
|
|
|
○ 大学から外国人の在籍事実についての情報提供を受ける必要があるとあるが、留学生の中には、学籍はあるが授業料を払わずにどこかへ行ってしまうような者もいる。どの程度の事実をもって「在籍」とするのか、検討課題である。
|
【以上】