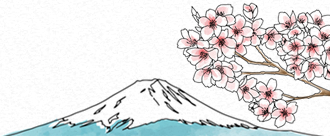- トップページ
- 政策情報(会議・統計等)
- 会議・委員会等
- 出入国在留管理政策懇談会
- 外国人受入れ制度検討分科会開催状況
- 第10回 外国人受入れ制度検討分科会 議事概要
第10回 外国人受入れ制度検討分科会 議事概要
1 日時
平成26年5月12日(月) 午後1時30分から午後2時40分まで
2 場所
三田共用会議所3階A・B会議室
3 出席者(敬称略)
(1)外国人受入れ制度検討分科会
多賀谷分科会長、青山委員、勝野委員、川口委員、新谷委員、高橋委員代理(岡田主席調査員)、吉川委員
(2)法務省
榊原入国管理局長、杵渕官房審議官、菊池総務課長、石岡入国在留課長、小新井参事官、福原企画室長、田口審査指導官
(3)オブザーバー
外務省、厚生労働省、経済産業省
多賀谷分科会長、青山委員、勝野委員、川口委員、新谷委員、高橋委員代理(岡田主席調査員)、吉川委員
(2)法務省
榊原入国管理局長、杵渕官房審議官、菊池総務課長、石岡入国在留課長、小新井参事官、福原企画室長、田口審査指導官
(3)オブザーバー
外務省、厚生労働省、経済産業省
4 議事概要
法務省からこれまでの議論を踏まえた「技能実習制度の見直しの方向性(素案)」について説明し、協議を行った。委員から出された主な意見は以下のとおりであった。
○ 現行制度上は、技能実習生が1つの実習機関に固定されているためになかなか不満があっても言えないということで人権侵害が助長されているのではないか。
○ 開発途上国に対して我が国で技術、技能を身につけて帰ってもらって母国の経済発展に資するということがこの制度の趣旨であるので、この趣旨を徹底し、安易な低賃金労働者の確保の手段にならないようにすべき。まず、今ある問題点を先に改善し、その後に制度の維持、拡充というところが議論されるべきである。
○ 実習実施機関に対して監督をする場合に、立入調査することができるような仕組みにすべきではないか。行政機関以外が立入調査を行うのは難しいところはあるが、何らかの形で実効的にするようにすべきではないか。
○ 法務省令で定める「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上」の要件を徹底するため、高度人材ポイント制のような、受入れにあたっての最低年収基準等を設けるべきではないか。
○ 日本人と同等報酬要件について、技能等の水準が日本人と全く同じようになってから引き続き最低賃金というのは問題であるが、まだ技能を修得している段階のもので当然最低賃金を払っているという部分もあるので、最低賃金だからといって直ちに低賃金労働だという判断はすべきではないのではないか。
○ 外部監査の義務化については、一斉に監理団体に適用するのか、組織形態に応じて方策を考えるのか、検討が必要ではないか。
○ 送出し機関について、国内がいくら適正化を図っても、送出し国に問題があるとなるとそちらまで踏み込めず、適正化できないことになるため、外国との交渉でしっかり担保することが必要ではないか。
○ 仮に実習期間の延長を検討する場合であっても、ただ3年から2年間延ばすだけではなく、延長の際とか、再技能実習の場合も同様であるが、一旦、必ず帰るという仕組みを取り込むべきではないか。また、ただ延ばすのではなく、技能検定など技能を評価する仕組みが組み込まれないといけないのではないか。
○ 技能実習生として単身で来て、母国に帰ってもらうという前提の制度であるため、3年で一度帰ってもらい、家族との時間を持ってもらうというのが本来制度のあるべき方向ではないか。
○ 仮に対象職種の拡大を検討する場合であっても、我が国の都合ではなく、送出し側の経済発展に対する人材ニーズを把握した上で検討する必要がある。
○ 職種の拡大に関して、海外展開の必要な人材という点では、店舗の管理、発注、従業員のシフトや売上等を管理する店長やそれに準じたような人たちを育てるために日本に来てもらって実地に技能を修得する、というニーズもある。
○ 職種の拡大の例について、店舗の店長候補というのであればまだ検討の余地はあるが、皿運びや片付けは評価すべき技能とは呼べず、受入れ職種とすることは認められない。
○ 職種の拡大について、全国津々浦々で必要とされている職種と、ある特定の地域で非常に進んでいる職種とがあるため、そのような扱いをどうするかというところも検討が必要ではないか。
○ 職種の拡大についても、制度所管省庁や業所管省庁等の関連行政機関が連携を密にしなければならないのではないか。
○ 現行制度上は、技能実習生が1つの実習機関に固定されているためになかなか不満があっても言えないということで人権侵害が助長されているのではないか。
○ 開発途上国に対して我が国で技術、技能を身につけて帰ってもらって母国の経済発展に資するということがこの制度の趣旨であるので、この趣旨を徹底し、安易な低賃金労働者の確保の手段にならないようにすべき。まず、今ある問題点を先に改善し、その後に制度の維持、拡充というところが議論されるべきである。
○ 実習実施機関に対して監督をする場合に、立入調査することができるような仕組みにすべきではないか。行政機関以外が立入調査を行うのは難しいところはあるが、何らかの形で実効的にするようにすべきではないか。
○ 法務省令で定める「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上」の要件を徹底するため、高度人材ポイント制のような、受入れにあたっての最低年収基準等を設けるべきではないか。
○ 日本人と同等報酬要件について、技能等の水準が日本人と全く同じようになってから引き続き最低賃金というのは問題であるが、まだ技能を修得している段階のもので当然最低賃金を払っているという部分もあるので、最低賃金だからといって直ちに低賃金労働だという判断はすべきではないのではないか。
○ 外部監査の義務化については、一斉に監理団体に適用するのか、組織形態に応じて方策を考えるのか、検討が必要ではないか。
○ 送出し機関について、国内がいくら適正化を図っても、送出し国に問題があるとなるとそちらまで踏み込めず、適正化できないことになるため、外国との交渉でしっかり担保することが必要ではないか。
○ 仮に実習期間の延長を検討する場合であっても、ただ3年から2年間延ばすだけではなく、延長の際とか、再技能実習の場合も同様であるが、一旦、必ず帰るという仕組みを取り込むべきではないか。また、ただ延ばすのではなく、技能検定など技能を評価する仕組みが組み込まれないといけないのではないか。
○ 技能実習生として単身で来て、母国に帰ってもらうという前提の制度であるため、3年で一度帰ってもらい、家族との時間を持ってもらうというのが本来制度のあるべき方向ではないか。
○ 仮に対象職種の拡大を検討する場合であっても、我が国の都合ではなく、送出し側の経済発展に対する人材ニーズを把握した上で検討する必要がある。
○ 職種の拡大に関して、海外展開の必要な人材という点では、店舗の管理、発注、従業員のシフトや売上等を管理する店長やそれに準じたような人たちを育てるために日本に来てもらって実地に技能を修得する、というニーズもある。
○ 職種の拡大の例について、店舗の店長候補というのであればまだ検討の余地はあるが、皿運びや片付けは評価すべき技能とは呼べず、受入れ職種とすることは認められない。
○ 職種の拡大について、全国津々浦々で必要とされている職種と、ある特定の地域で非常に進んでいる職種とがあるため、そのような扱いをどうするかというところも検討が必要ではないか。
○ 職種の拡大についても、制度所管省庁や業所管省庁等の関連行政機関が連携を密にしなければならないのではないか。