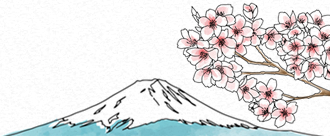- トップページ
- 政策情報(会議・統計等)
- 会議・委員会等
- 出入国在留管理政策懇談会
- 外国人受入れ制度検討分科会開催状況
- 第11回 外国人受入れ制度検討分科会 議事概要
第11回 外国人受入れ制度検討分科会 議事概要
1 日時
平成26年5月27日(火) 午後3時00分から午後3時30分まで
2 場所
法務省10階会議室
3 出席者(敬称略)
(1)外国人受入れ制度検討分科会
多賀谷分科会長、青山委員、川口委員、新谷委員、高橋委員代理(岡田主席調査員)
(2)法務省
榊原入国管理局長、杵渕官房審議官、菊池総務課長、石岡入国在留課長、福原企画室長、田口審査指導官
(3)オブザーバー
外務省、厚生労働省、経済産業省
多賀谷分科会長、青山委員、川口委員、新谷委員、高橋委員代理(岡田主席調査員)
(2)法務省
榊原入国管理局長、杵渕官房審議官、菊池総務課長、石岡入国在留課長、福原企画室長、田口審査指導官
(3)オブザーバー
外務省、厚生労働省、経済産業省
4 議事概要
法務省からこれまでの議論を踏まえた「技能実習制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」案について説明の上、協議を行い、分科会として報告書のとりまとめを行った。委員から出された主な意見は以下のとおりであった。
○ 仮に実習期間の延長や再技能実習の受入れ等の見直しを行った場合、技能レベルが上がっていって日本人と本当に同等のスキルを持った技能実習生も増えることが予測されるが、現状のように日本人の賃金の6割とか7割ほどしか払われていないという実態を放置していては、制度の逸脱した利用が拡大しかねない。その防止策として、分野ごとに技能実習生の報酬の具体的な指標を定めるなどして「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上」の要件の実効性を高める必要がある。
○ 再技能実習については今後の制度設計の中で議論されるであろうが、例えば日本企業が生産技術や製造技術を海外の生産拠点に移転する場合、日本で技能を修得した技能実習生が帰国してみると、やはりお国柄とか働き方とか、全世界統一的なやり方ではなじまず、効果的・効率的に技能移転が行われないこともあり得ることから、帰国した際に修得した技能の効果を測定した上で必要な再技能実習を行うこともあり得るという観点での議論も必要である。
○ 外国人の労働者問題を含めて外国人問題というのは、単に入管政策だけで決まるものではない。特に技能実習制度については、普段から監理団体、実習実施機関と送出し機関のレビューが必要不可欠であり、事が起こったときだけ議論するのではなく、関係省庁、関係機関で見直しを行う、不都合があれば改善する、もっと大きな課題があれば時間をかけて議論するという体制が必要ではないか。
○ 今回の見直しにより、技能実習制度が濫用的に使われているところを、より厳密な制度にするということになるが、それに対応できない分野が出てくると思われる。ただ、その対応できない部分は受入れをやめてしまうという議論にはならないであろうから、そのように技能実習制度では救えないような問題をどうするかについては出入国管理政策懇談会(親会議)で検討すべき。
○ 仮に実習期間の延長や再技能実習の受入れ等の見直しを行った場合、技能レベルが上がっていって日本人と本当に同等のスキルを持った技能実習生も増えることが予測されるが、現状のように日本人の賃金の6割とか7割ほどしか払われていないという実態を放置していては、制度の逸脱した利用が拡大しかねない。その防止策として、分野ごとに技能実習生の報酬の具体的な指標を定めるなどして「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上」の要件の実効性を高める必要がある。
○ 再技能実習については今後の制度設計の中で議論されるであろうが、例えば日本企業が生産技術や製造技術を海外の生産拠点に移転する場合、日本で技能を修得した技能実習生が帰国してみると、やはりお国柄とか働き方とか、全世界統一的なやり方ではなじまず、効果的・効率的に技能移転が行われないこともあり得ることから、帰国した際に修得した技能の効果を測定した上で必要な再技能実習を行うこともあり得るという観点での議論も必要である。
○ 外国人の労働者問題を含めて外国人問題というのは、単に入管政策だけで決まるものではない。特に技能実習制度については、普段から監理団体、実習実施機関と送出し機関のレビューが必要不可欠であり、事が起こったときだけ議論するのではなく、関係省庁、関係機関で見直しを行う、不都合があれば改善する、もっと大きな課題があれば時間をかけて議論するという体制が必要ではないか。
○ 今回の見直しにより、技能実習制度が濫用的に使われているところを、より厳密な制度にするということになるが、それに対応できない分野が出てくると思われる。ただ、その対応できない部分は受入れをやめてしまうという議論にはならないであろうから、そのように技能実習制度では救えないような問題をどうするかについては出入国管理政策懇談会(親会議)で検討すべき。