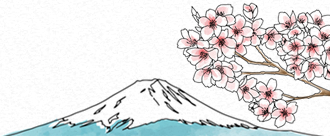漁業分野
2024年4月1日現在
漁業分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。
また、漁業分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
従事する業務
特定技能1号
- 漁業
漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等 - 養殖業
養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等
特定技能2号
- 漁業
漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 - 養殖業
養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
人材基準
特定技能1号
| 技能水準 | 「1号漁業技能測定試験」 ※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 |
|---|---|
| 日本語能力 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」 ※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。 |
特定技能2号
| 技能水準 | 「2号漁業技能測定試験」及び、「日本語能力試験(N3以上)」 |
|---|---|
| 実務経験 |
|
詳細情報
| 雇用形態 | 直接及び派遣 |
|---|---|
| 受入れ機関に対して特に課す条件 |
|
| 1号受入れ見込数(5年間の最大値) | 17,000人 |
| 担当省庁 | 農林水産省(水産庁)(農林水産省(水産庁)ウェブサイト内漁業分野情報ページにリンクします。) |