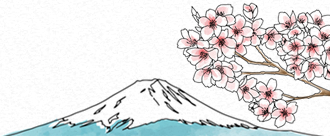- トップページ
- 政策情報(会議・統計等)
- 会議・委員会等
- 出入国在留管理政策懇談会
- 難民問題に関する専門部会
- 難民認定制度に関する検討結果(最終報告)
- 「難民認定制度に関する検討結果(最終報告)」
「難民認定制度に関する検討結果(最終報告)」
| 第1 | はじめに |
| 我が国において難民認定制度が発足した昭和57(1982)年以降の世界の動向を見ると、欧州地域においては東西冷戦の終結による難民(refugees)・避難民(displaced persons)の発生、旧ユーゴスラビアの解体に伴うバルカン半島からの大量の難民等の流出の動きがあり、また、アフリカにおいてもルワンダにおける200万人以上に上る難民の発生等、人道的見地から緊急の対応が必要とされる問題が相次いで発生しており、これらの問題は近年特に重要度を増している。 また、平成13(2001)年9月11日の米国における同時多発テロ事件を端緒として、アフガニスタンを実効的に支配していたタリバン政権が崩壊したことにより、それまで同政権の下で迫害を受け国外に逃れていた同国民の帰国が実現しつつある一方で、このテロ事件を教訓としてテロリストの排除が各国における重要な課題とされたこと(特に国連安全保障理事会決議1373号)に伴い、難民を偽装して入国を企てるテロリストないし犯罪者の入国防止が各国の入管当局に課せられた重要な責務とされるに至っている。 さらに、交通・通信手段の目覚ましい発達を受けて、国際交流の流れは、経済、文化など社会のあらゆる分野において、その速度、流量ともに飛躍的な増大を見せているが、経済活動のグローバル化に伴い、経済的により良い生活を求めて貧しい国から豊かな国へと国境を移動する人々(合法・非合法を問わず)の存在と、それらの人々が受入国の社会に与える様々な影響は、ここ数年、大きな社会問題として顕在化しつつある。 このような国際情勢の下にあって、我が国においても、難民認定申請件数の増加、申請者の出身国・地域の多様化、申請内容の複雑化が顕著となっており、これらの状況変化に適切に対応するための難民認定制度の見直しの必要性が認識されるようになった。 そのような状況を踏まえ、法務大臣が各方面の有識者から、難民認定制度の今後の在り方について意見を聴取し、今後の法務行政に活かすため、平成14年6月11日、法務大臣の私的懇談会「出入国管理政策懇談会」に対し、我が国の難民認定制度の中で議論の対象とされている事項のうち、アいわゆる「60日ルール」、イ難民認定申請中の者の法的地位、ウ不服申立ての仕組み、の3点について諮問し、それらの検討に当たるため、同懇談会の下に「難民問題に関する専門部会」(以下「専門部会」という。)が設けられた。 専門部会は、難民問題は我が国が真剣に取り組むべき重要課題であるとの認識の下に、真に難民である者を迅速かつ確実に難民として認定して保護するとともに、犯罪者等による制度の濫用を防止するという観点から、これらの諮問事項について検討を加え、議論を重ねた結果、以下のとおり意見を取りまとめ、提言するものである。 |
| 第2 | 難民認定制度の沿革、手続及び現状等の概要 |
| 1 | 難民認定制度の沿革 |
| 昭和25(1950)年12月14日の第5回国連総会で採択された決議に基づき、26か国の代表から成る全権会議がジュネーブで開催され、昭和26(1951)年7月28日、「難民の地位に関する条約」(以下「難民条約」という。)が採択された。難民条約は、難民問題に国際的に取り組むために、締約国に、難民を迫害が待つ所に追放又は送還しないこと及び自国に滞在する難民については積極的に諸種の権利を認めること等を義務付けた。 我が国は、難民の受入れを、国際社会において果たすべき重要な責務と認識し、昭和56(1981)年に難民条約に、次いで昭和57(1982)年には「難民の地位に関する議定書」(以下「議定書」という。)に順次加入したが、それらへの加入を控えた昭和56年3月13日の閣議において、難民認定事務の取扱いに関し、「条約及び議定書の実施に伴う難民の認定は、政府として統一的に行うこととし、法務大臣がこれを主管するものとする」ことが了解された。そして、この閣議了解を受けて、それまでの「出入国管理令」に現在の難民認定制度を盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という。)が定められ、難民条約及び議定書が効力を生じた昭和57年1月1日、これが施行されて、現在に至っているものである。 |
| 2 | 我が国の難民認定制度における「難民」の意味 |
| 入管法にいう「難民」とは、難民条約及び議定書が定める「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として本国(無国籍者にあっては常居所国)において迫害を受ける十分に根拠のあるおそれが存在し、そのために外国に逃れている者であって、そのようなおそれのために本国の保護を受けることができず又は受けることを望まないもの(無国籍者にあっては常居所国へ戻ることができず又は戻ることを望まないもの)」とされている。 したがって、我が国の難民認定制度においては、「迫害を受けるおそれがある」ことが極めて重要な要素となるが、その反面、保護を必要としている避難民であっても、その原因が、例えば、戦争、天災、貧困、飢饉等にあり、それらから逃れて来る人々については、難民条約又は議定書にいう難民に該当するとはいえず、「難民」の範疇には入らないこととなる。 |
| 3 | 難民認定手続等 |
| (1) | 申請期間 |
| 難民の認定を申請する者は、日本に上陸した日、あるいは我が国にいる間に難民となる事由が生じた場合はそのことを知った日から60日以内に申請を行うことが求められている。 これは、外国人が本国における迫害から逃れて我が国に庇護を求める場合、速やかにその旨を表明することが通常であることから、日本の地理的、社会的実情から見て、申請窓口である地方入国管理官署に行くために必要と考えられる期間として設定されたものと説明されている。ただし、事故・病気等のやむを得ない事情がある場合には、60日を経過した後であっても難民認定の申請をすることが可能とされている。 |
|
| (2) | 立証責任及び事実の調査 |
| 難民であることの立証責任は、申請者に課せられている。もっとも、難民認定の申請者は、一般に我が国においてその立証を行うことが困難な場合が少なくない。そこで、申請者の提出した資料のみで適正な認定ができないおそれがあるときは、難民調査官が事実の調査をすることとされており、難民調査官は、この調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができることとされている。公私の団体等に照会して必要な事項の報告を求めることも認められている。 難民認定の過程における事実調査は容易でなく、そのために処理が長期化する案件も少なくない。特に最近は、認定制度を濫用する者が各種証明書を偽造・行使する事案が増加しており、事実認定は一層困難かつ複雑となりつつある。 このため、法務省では、難民調査官の数を増やしたり、難民調査官に対する研修体制を充実するなどして、調査能力の向上に努めているが、今なお難民調査官の人員不足は否めない。 |
|
| (3) | 難民の認定・不認定の通知及び不認定に対する異議の申出 |
| 法務大臣が難民の認定をしたときは、申請者に対し難民認定証明書が交付され、認定をしないときは、申請者に対し理由を付して不認定である旨が通知される。 難民と認定されなかった者は、その処分に不服があるときは、通知を受けた日から7日以内に法務大臣に対して異議を申し出ることができる。 行政不服審査法においては、その第45条により、行政処分に不服のある者は60日以内に異議を申し立てることが求められているが、難民認定手続については同条の適用が除外されている。その理由については、難民の認定に関する処分の当否は早期に決着をつける必要があること、難民であるか否かは本人が最もよくこれを知り得る立場にあるから、不認定処分に不服があれば直ちに異議を申し出ることができることなどから、難民該当性を否定する処分に対する異議申出期間を7日以内に制限したと説かれている。 |
|
| (4) | 難民認定の効果 |
| 難民と認定された外国人については、その認定により自動的に我が国に在留することを認められるものではないが、難民と認定されたことにより、難民旅行証明書の交付を受けること、永住許可要件が一部緩和されること、退去強制事由に該当する場合でも法務大臣による在留特別許可を受けることが可能となることなどの効果がある。 また、社会保障の面から見ると、自国民あるいは一般外国人と同じ取扱いがなされるため、我が国において国民年金や児童扶養手当等の受給資格が得られることとされている。 |
| 4 | 我が国における難民認定状況の概要 |
| 難民認定制度が発足した昭和57年から平成14年までに難民として認定された者は合計305名であり、全体を通しての認定率は14パーセントとなっている。これを平成14年について見ると、難民認定申請を行った者は250名(前年比103名減)であり、同年内には14名が認定されている。各国の難民認定数や認定率は、その地理的・歴史的背景などから単純には比較できないが、平成13年において、イギリスの認定率は22パーセント(認定数2万4,265名、不認定数8万5,162名)、フランスは21パーセント(認定数9,703名、不認定数3万5,730名)、ドイツは7パーセント(認定数5,716名、不認定数7万5,788名)、オランダは3パーセント(認定数888名、不認定数2万4,504名)、スウェーデンは2パーセント(認定数307名、不認定数1万7,182名)である。 また、平成14年を例にとると、我が国においては、難民として認定されなかった者のうち人道的観点から特に在留を認められたものが40名いる。 なお、昭和50年代、インドシナ三国(ベトナム、ラオス、カンボジア)で相次いで政変が発生し、社会主義体制へと変革されたことに伴い、新しい体制の下での生活に不安を感じる人々や新体制になじめない人々が避難民となって周辺諸国へ流出を始めた。これらベトナム人、ラオス人及びカンボジア人はいわゆるインドシナ難民と呼ばれるが、昭和50年から平成14年までの間に、我が国に1万4,322名のインドシナ難民が入国し、そのうち1万941名が、難民認定手続とは別に、政府の受入れ方針に沿って我が国での定住を認められた。 |
| 第3 | 専門部会における調査・審議の概要と法務省の取組等 |
| 1 | 中間報告に至る経緯 |
| 専門部会においては、平成14年10月15日までの間、いわゆる「60日ルール」及び難民認定申請者の法的地位の2項目を中心として、合計7回、延べ約22時間にわたり、各委員が意見を交換したほか、東日本入国管理センター及び東京入国管理局を視察して難民認定を含む入管行政の実情を見聞し、さらに、複数の在京大使館の担当職員から各国における難民認定制度の仕組みと現状等について説明を受け、我が国で難民として認定され在留している者からその経験を聴取し、国際法学者から国際法の視点から見た難民問題について講演を受けるなどして、難民問題についての理解を深めることに努めた。 その結果、専門部会は、ひとまず平成14年11月時点での専門部会の検討結果を取りまとめ、早期に実現されることが望ましいと考えられるいくつかの事項を中間報告として出入国管理政策懇談会に報告した。 出入国管理政策懇談会は、これを了承し、若干の意見を付した上で、法務大臣に対して中間報告として提出した。 |
| 2 | 中間報告の概要 |
| 中間報告において示された基本的理念、盛り込まれた主な提言等は、以下のとおりであった。 |
| (1) | 難民問題に関する基本的理念と方向性 |
| 難民問題は我が国全体として真剣に取り組むべき課題であると考える。そして、今日の国民一般の人権や人道に対する意識の向上、自由民主主義国家として基本的人権の尊重と保護を掲げる我が国の国際的立場や責任等にかんがみると、社会の安定等慎重に考慮すべき問題はあるものの、基本的には、難民問題の解決に積極的に取り組む姿勢を示すことが期待されているものと思われる。すなわち、真実、政治的迫害等から逃れてきた難民として庇護を必要とする者を迅速かつ確実に難民として認定し保護することは極めて重要である。それと同時に、難民認定手続を他国への入国あるいは在留の手段として悪用する者、いわゆる偽装難民を的確かつ早期に我が国から排除するシステムの構築も併せて考慮される必要があると思われる。 | |
| (2) | いわゆる「60日ルール」について |
| いわゆる「60日ルール」、すなわち難民認定申請を60日以内に行うという期間制限が厳格に適用されれば、難民条約上の難民に該当する者であっても、60日以内という申請期間を経過したことを理由として難民認定を受けられないという不当な結果を招きかねない。そのため、「60日ルール」の厳格な適用は行わず、申請期間内に申請されたかどうかにとらわれず,難民であるかどうかの実体審査を重視すべきであるとの批判があり、これが難民不認定処分取消訴訟における主要な争点の一つになっていると指摘されている。 他方、60日を経過した後の申請であっても、申請が遅延したことに「やむを得ない事情」があるときは申請が許容される旨の規定があるが、「やむを得ない事情」をいたずらに拡大して運用するのではルールの形骸化を招き、申請期限を無意味なものとするおそれがある。 専門部会においては、これらの批判や問題点を視野に入れながら、申請期間を設けることの当否及びその期間の長短等について検討を加えたが、我が国に庇護を求める者は入国して間もない時期に申請を行うことが通常であると思われること、また、無期限に申請を認めると証拠の散逸等により適正な難民認定が妨げられるおそれがあるばかりか、濫用者を誘発するおそれもあること等から、申請期間を設けることには、現在でも合理的理由があると考える。そして、この申請期間の問題を、難民認定制度全体の中での公平性、透明性にかかわる問題と位置付け、我が国が、今後、積極的に難民を受け入れていく姿勢を国際社会に示すメッセージとして、申請期間を現在より延長し、これを6月ないし1年とする方向で法改正されることを提言した。 |
|
| (3) | 難民認定申請中の者の法的地位について |
| 現行法の下では、難民認定を申請した者が不法滞在者であれば、退去強制事由該当者として退去強制手続が進められることとなる。そのため、申請者が不法滞在者の場合、難民認定申請手続と退去強制手続が同時に進行することとなり、申請者が退去強制手続のため当局に収容されることについて人権上問題であるとの批判があることも事実である。 また、申請者が合法的に在留している場合の在留資格内訳を見ると、大多数が「短期滞在」で在留し、当面の生計を維持するために資格外活動の許可を受けた上で就労しているが、難民認定申請中であれば資格外活動許可を受けて就労できるとの情報が流布し、我が国での就労のために難民認定申請を行う者が跡を絶たないという実情にも目を向ける必要がある。 他方、難民認定申請中の者のうち衣食住に欠ける等生活に困窮する者に対しては、昭和57年7月の難民行政監察に基づき、外務省が予算措置を講じ、翌年から保護措置を実施し、平成7年以降は外務省が財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部に支援事業を委託して実施している。 このような実情を踏まえて専門部会において検討を重ねた結果、難民認定申請者については、安心して審査が受けられるよう、ア法務大臣による難民認定の許否の決定(異議申出を含む。)が下されるまでの間は、退去強制事由該当者であっても退去強制されないよう法的に保障すること、イ政府として衣食住の提供や保護施設の設置等必要な経済的・物質的保護措置の充実を図り(NGOとの効果的な連携も検討する。)、申請者が審査を受けることに専念できるような生活環境を確保することを提言した。ただし、経済的・物質的援助を目当てとする難民認定制度の濫用者を排除することに努力する必要がある。 |
|
| (4) | 関連する提言 |
| 難民認定申請に対する判断が遅延することは好ましくないので、真の難民を保護し、審査手続の合理化・迅速化を図り、審査が1年以内に終結することをめどとした難民調査官の大幅な増員、適正な人員配置、難民調査官の能力と専門性向上のための研修等の充実・強化、及び適切な通訳の確保に努められることを要望する。 さらに、難民認定制度濫用者を排除する基準ないし指針として、外国において既に難民不認定処分を受けた者、明らかに安全な第三国を経由して来た者、身分事項を偽り又は偽造証明書を提出するなど不正の手段を用いて庇護を受けようとする者等を排除している欧州諸国の対応が参考にされてよいであろう。 |
|
| (5) | 今後の課題 |
| 真に政治的迫害等から逃れて我が国に難民として庇護を求めて来た者については、迅速に庇護し、必要に応じた援助を行うことが望ましい。これを実現するため、関係省庁が真の難民の円滑な受入体制を整備するため相互に緊密な連携を保ちつつ積極的に取り組んでいくことを希望する。 また、新たに構築される難民認定制度は、全体として合理性と透明性の高められたものであることが要請されているのであって、例えば、不認定理由の具体的で明確な告知などについて改善が図られる必要がある。 |
|
| (6) | 出入国管理政策懇談会により追加された意見 |
| 出入国管理政策懇談会は、専門部会から報告を受けた中間報告を了承したが、その際、以下の補足意見を付して、法務大臣に中間報告として提出した。 |
| ア | 難民を保護するための制度が不法滞在者や不法就労者、さらには、テロリスト等不正な目的を有する者に悪用されることを防止することが必要であり、この点に十分留意した制度を構築すべきである。 |
| イ | 申請中の者について退去強制をしないことを法的に保障し、また、経済的援助等を行うことは、真に難民として保護を求める者に対してその目的の範囲内で行うべきであり、このような者の日本国内での就労は認めない等一定の条件の下に実施すべきである。 |
| 3 | 中間報告等を踏まえた法務省の取組 |
| (1) | 入管法の一部を改正する法律案の提出 |
| 平成15年3月4日、第156回通常国会に難民認定制度の見直しを含む入管法の一部を改正する法律案が提出された。 上記法律案は、難民として認定されるべき者等の法的地位の安定化を可能な限り迅速に図るため、難民認定制度に関して以下の改正を行うことなどを内容とするものである。 |
| ア | 仮滞在許可制度の創設等 |
| 不法滞在者である難民認定申請中の者の法的地位の安定化を図るため、仮滞在を許可する制度を創設することとし、仮滞在の許可を受けた者については、退去強制手続を停止し、難民認定手続を先行して行うこととし、仮滞在の許可を受けていない者についても、難民認定申請中の間は送還を行わないこととする。 | |
| イ | 難民として認定された者等の法的地位の安定化 |
| 難民として認定された者で、一定の要件を満たす場合には、一律に在留を認めることとし、その者の法的地位の早期安定化を図る。 なお、上記法律案は上記国会において継続審議とされたが、平成15年10月10日、衆議院解散に伴い、廃案となった。 専門部会としては、中間報告の内容が反映された上記法律案は難民認定制度を前進させる内容であると評価できるので、法案の再提出と成立により、新たな制度が早期に実現することを強く期待するものである。 |
| (2) | 難民調査官の増員等 |
| 平成15年度において、難民調査官として入国審査官6名が増員され、難民調査官は50名となった。また、平成15年度から東京入国管理局において、難民関係業務を専従して行う難民調査部門が新設された。 | |
| (3) | 難民調査官の研修等の充実・強化 |
| 平成15年度に実施した研修においては、従来より研修期間を伸長し、これまでの供述録取の手法、難民出身国情報、心的トラウマを受けた難民へのインタビュー法に加え、外国人の人権及びアジア諸国情勢等の科目を新たに追加し、実務研修時間を増やすなどして充実・強化された。 | |
| (4) | 不認定理由の具体的で明確な告知 |
| 平成15年1月から、難民不認定理由の付記に当たって、不認定判断の基礎となった理由を具体的に付記する運用に改められた。 | |
| (5) | 空港における案内窓口の設置 |
| 平成15年1月6日から成田空港に、同年4月14日から関西空港に、それぞれ「入国・難民申請手続総合案内所」が試行的に設置され、出入国手続及び難民認定手続に関する案内が実施されている。 |
| 4 | 不服申立制度に関する調査審議経過 |
| 専門部会においては、前記中間報告を提出した後も、平成15年11月21日までの間、不服申立制度を中心として、合計11回、延べ約21時間にわたり、各委員が意見を交換したほか、財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部「国際救援センター」及び東京入国管理局新庁舎の難民調査のためのインタビュールーム等の施設を視察した。また、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)職員からは難民をめぐる諸問題について、行政法の学者からは行政不服審査制度全般について、それぞれ説明を受けたほか、主要国における難民不服申立制度の仕組みと実情について把握すべく、イギリス、フランス、ドイツに派遣され調査に当たった専門の学者から、その調査結果について報告を受けるなどして、不服申立制度についての理解を深めることに努めた。 |
| 第4 | 不服申立制度の現状 |
| 1 | 我が国の不服申立制度 |
| (1) | 異議申出制度の概要 |
| 難民認定の申請をした者は、認定をしない処分及び難民の認定の取消処分について、法務大臣に対して異議を申し出ることができる(入管法第61条の2の4)。法務省においては、難民の認定に関する処分の事務は入国管理局総務課難民認定室が、異議申出手続の事務は同局審判課がそれぞれ所管している。地方入国管理局等においては、それぞれの案件の調査に当たる難民調査官について、難民の認定に関する処分に関与する者と異議申出手続に関与する者とが重複しない配慮が払われている。 異議の申出は、原則として、申出人の居住地を管轄する地方入国管理局、同支局又はそれらの出張所に、申出人が自ら出頭して行う。申出の期間は、難民の認定をしない旨の通知書又は難民認定取消通知書により通知を受けた日から7日以内とされている。 異議申出手続については、期間の定め(法第61条の2の4)に特則があるほかは行政不服審査法の規定が適用される。 異議の申出に理由があるときは、異議申出人に難民認定証明書を交付するが、理由がないときは、その旨の通知書を交付する。 異議の申出は代理人によってすることができ、代理人はインタビューに立ち会うことができる。 なお、異議の申出に理由がない旨の決定に不服のある者が難民不認定処分の取消しを求めて裁判所に提訴することについて,特段の制約はない。 |
|
| (2) | 異議申出状況 |
| 我が国の難民認定制度が発足した昭和57年以降平成14年末までの難民の認定をしない処分に対する異議申出件数は1,244件である。 不認定処分を受けた者で異議の申出を行った者の割合は、平成10年75.7パーセント、平成11年74.9パーセント、平成12年61.6パーセント、平成13年70.8パーセント、平成14年84.4パーセントであり、過去5年間の平均異議申出率は73.5パーセントとなっている。 異議の申出に対する「理由あり」の裁決は、平成7年1件、同10年1件、同11年3件、同13年2件の合計7件である。 |
| 2 | 主要国における不服申立制度 |
| イギリスにおける難民認定行政は、出入国管理行政の一環として行われており、不服申立てについても、他の出入国管理関係の行政処分に対する不服申立てと同様、入国管理不服審査機構による審査を受けることとなる。同機構は、審判官による審査と入国管理不服審判所による審査の二階層制が採用されている。これら不服申立制度は、司法機関の長たる大法官が審判官を任命するなど、今日では司法的性格が強化され、特別裁判所としての性格が強められている。 同機構の判断に不服がある者は、司法裁判所たる控訴院(後記高等法院の上級裁判所)等に上訴することができるが、この場合、審査の範囲は法律によって定められている範囲に限られ、上訴の対象は入国管理不服審判所の判断に重大な影響のある法律問題に限られるほか、上訴について同審判所又は控訴院等の許可が必要とされる。また、これとは別に、入国管理不服審査機構の判断に不服のある者は、重要事件について第一審管轄権を有する司法裁判所である高等法院に対し、司法審査を求めることができるが、この場合、イギリスの法体系自体の特色として、司法審査請求が認められるためには高等法院の許可が必要とされ、事実上重要事件に限って司法審査が認められるなど、司法審査の機会が制限されている。 フランスにおいては、難民認定に関する一次処分を行うOFPRA(フランス難民及び無国籍者保護局)の判断に対する行政上の不服申立手続は存在せず、同局の判断に不服のある者は、難民独自の特別な行政裁判所として位置付けられるCRR(難民不服申立委員会)に対して訴えを提起して審査を求めていくことになる。CRRの判決に不服のある者は、最高行政裁判所たるコンセイユ・デタに上訴することができるが、上訴が許されるのは法律問題を不服として争う場合に限定されている。司法裁判所による司法審査を受ける機会は与えられていない。 ドイツにおいても、難民認定に関する一次処分を行う連邦外国人難民認定庁の判断に対する行政上の不服申立手続は存在せず(庇護手続法第11条)、同庁の判断に不服のある者は、行政訴訟を取り扱う州の行政裁判所に対して訴えを提起して審査を求めていくことになる。行政裁判所の判決に不服のある者は、高等行政裁判所に対して控訴することができるが、控訴するには同裁判所の許可が必要である。 |
| 第5 | 不服申立制度に関する提言 |
| 1 | 第三者関与の妥当性と配慮すべき諸点 |
| 我が国の難民認定制度においては、難民の認定に関する処分の事務は法務省入国管理局総務課難民認定室が、不服申立手続の事務は同局審判課がそれぞれ担当しており、それぞれの案件の調査に当たる難民調査官についても、一次処分に関与する者と不服申立手続に関与する者とが重複しない配慮が払われているものの、いずれも法務省入国管理局職員のみによって手続が進められている点等において、公正性・中立性が必ずしも十分ではないとの指摘が従来からあった。 専門部会は、難民認定業務に対する信頼性を高めていくためにも、手続の公正性・中立性等に対する配慮が強く求められるとの観点から、複数かつ奇数から成る第三者(難民調査官等の法務省入国管理局職員ではない専門家)を不服申立ての審査手続に関与させることを提言する。そして、第三者の関与の在り方を検討するに当たっては、以下の点に十分な配慮が払われることを要望する。 |
| (1) | 公平性、客観性 |
| 難民認定行政に対する信頼を確保する見地から、難民認定に関する判断は公平で客観的なものでなければならない。 例えば、ある国から迫害を受けるおそれがあるとして同時に多数の者が我が国に来て難民認定の申請を一斉に行った場合、その迫害状況や出国経緯等がほぼ共通であれば、その難民該当性についての判断はおよそ統一されたものとなろう。 新たな不服申立手続を検討するに当たっては、難民該当性についての判断がこのように公平で客観的なものであって、統一性・整合性の取れた仕組みとなるよう配慮されなければならない。 |
|
| (2) | 専門性 |
| 法務省においても難民調査官の研修を繰り返し実施するなどしてその専門性を高めるべく努めているところではあるが、難民認定手続においては、証拠が海外にあって収集が困難であり、限られた証拠を的確に評価して適正な事実認定を実現していかなければならず、また、諸外国の政治情勢を正確に把握することが必要不可欠である。そのためには、各国の政治状況、地域紛争状況、民族問題、宗教問題等関係する様々な分野の専門家の知見を求める制度とすることが望まれるとともに、これら専門家の意見が特に不服申立手続において十分に斟酌されるような体制を構築していくことが必要である。 | |
| (3) | 迅速性 |
| 真に政治的迫害等から逃れてきた難民として保護を必要とする者は、迅速に難民として認定され保護される必要があるが、それとともに、我が国に滞在するための方便として難民認定制度を悪用しようとする不法就労者や犯罪者を排除するためにも、難民認定手続は全体として迅速に進められる必要がある。近年、欧州諸国において、難民に係る手続の迅速化が進められているのも、同様の配慮によるものと思われる。 特に我が国においては、欧州主要国とは異なり、行政の判断に不服のある者は何らの制約もなく裁判所の救済を求めることができる。平成11年、12年に裁判所に提訴された難民認定手続関係訴訟が現在も多数係属中であり、司法審査に長期間を要しているのが実情である。 このような現状に照らせば、迅速性の要請は一層高いものと考えられる。不服申立手続については、従来は手続に6か月以上の期間を要していたようであるが、原則として例えば申立て後3か月以内に結論を出すような体制ないし仕組みの構築が望ましい。 |
| (4) | 行政改革の趣旨 | |
| 国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画(中央省庁等改革の推進に関する方針)の趣旨に照らせば、新たに過大な組織を設置することには慎重な配慮が望まれる。 | ||
| なお、不服申立手続においても、真実難民である者について迅速かつ確実に保護することの重要性は言うまでもないが、いわゆる偽装難民を的確かつ早期に我が国から排除するシステムの構築も同様に重要である。来日外国人による犯罪の増加といった事態に適切に対処し、社会の安全に対する国民の信頼を回復するため、犯罪者等が偽装難民として流入してくる事態は未然に防止する必要がある。難民条約第1条F項の趣旨に照らしても、国家の安全及び公の秩序にとって危険となるような者が難民認定制度を悪用して我が国に入国・滞在しようとする試みは阻止されなければならない。 | ||
| 2 | 第三者関与の具体的な制度案 |
| (1) | 諮問機関としての位置付け |
| 専門部会においては、以上の諸点を踏まえ、第三者関与の望ましい在り方について検討を重ねた結果、独自の裁決・決定権を有する第三者機関の設置は必ずしも最善とはいえず、法務大臣に対する諮問機関として関与することが望ましいとの結論に至った。 すなわち、不服申立手続に関与する第三者に裁決・決定権を付与する仕組みを作るとすれば、難民認定に携わっていない第三者が一から当該案件の検討をしなければならず、最終判断に至る過程が長期化するおそれが大きい。また、特に複数の第三者が関与する場合、各自の判断が異なる可能性があるが、第三者に最終判断権を付与するとなれば、判断の統一性が損なわれる場合の生じることが心配される。さらに、新たに独立した機関を設けることについては、行政改革の趣旨からも制約が多い。したがって、現行制度のように法務大臣が統一的観点から最終的な判断を行うことが好ましいものと思われる。 諸外国においては、独立した行政裁判所ないし行政審判所が設置されている例が多いが、今回調査した結果からも明らかなように、不服申立手続を充実させている国ほど、司法審査の機会を制限し、全体としての救済手続における慎重な審査の要請と迅速性の要請の均衡を図ろうとしている。これに対し、我が国では、行政裁判所の設置には憲法上の制約がある上、難民認定及びその不服申立手続に対する司法審査が保障されている。我が国における司法審査に長期間を要しているという現状等に留意すれば、行政手続における不服申立段階では、公平性、迅速性といった諸要請に従い、最終決定権を有する第三者機関の新設は回避すべきと思われる。 以上からすれば、不服申立手続の公正性等を担保するために関与する第三者には、あくまで諮問機関としての役割が付与されることが望ましい。 |
|
| (2) | 専門委員制度の導入 |
| 諮問機関としての意思決定の在り方については、難民認定制度の特殊性に十分配慮されることが必要である。 すなわち、複数の分野から複数(具体的には一つの案件につき3名程度)の専門家を関与させるとした場合、専門家間で情報を共有するとともに意見交換を行う機会を有することが考慮されなければならない。 他方、常に合議体としての意思決定を求めるとなれば、その前提として、これら専門家が一つの結論に達するまで討議を行わなければならず、各専門家の分野が異なれば異なるほどその討議には時間を要することが予想され、迅速性の要請を十分に充たし得るか疑問がある。また、最終的に意見が一致しないことも当然あり得ようが、法務大臣が専門家の意見を聴く制度とする以上は、多数意見に重きを置きつつ少数意見も尊重して判断を下すことになるのであって、合議体として一つの結論に到達する必要は必ずしもない。さらに、合議制機関を新たに設置することについては、行政改革の趣旨からの制約があることも考慮すべきである。 以上の諸点から、専門部会は、複数の第三者が一つの結論に達することを義務付けず、協議の上共同で意見を答申することも、第三者が個別の意見を直接答申することも可能な制度として、いわゆる専門委員制度の導入を提言するものである。 この制度においては、各案件の審理の進め方や報告書の形式等に関しても、第三者である専門委員の判断に委ねてよいのではないかと考える。 |
|
| (3) | 専門委員の人選 |
| 以上のような専門委員制度が信頼に値する制度として機能する前提として、法務大臣が専門委員を選任するに当たっては、適切な人選に十分配慮する必要がある。 すなわち、専門委員は、学識及び経験が豊かで人格高潔な、社会的常識を持った人物が選任されるべきであるが、具体的には |
| ア | 難民認定手続においては、証拠が海外にあって収集が難しく、限られた証拠を的確に評価して適正な事実認定を実現しなければならないという要請があることから、事実認定を含む法律実務の経験豊富な法曹実務家 |
| イ | 海外情勢を審査・判断に正確に反映させるという観点から、地域情勢や国際問題に明るい元外交官・商社等海外勤務経験者・海外特派員経験者・国際政治学者・国連関係機関勤務経験者等 |
| ウ | 法律的知識・素養も求められることから、国際法・外国法・行政法等の分野の法律専門家等 の中から選任されることが望ましい。また、専門委員の人選に当たっては、男女共同参画基本計画の趣旨に沿って、女性委員の積極的な登用に努めることが必要である。 そして、このように各分野から広く専門的知見を求めるため、一つの案件に関与する専門委員は複数、おおむね3名程度であることが望ましい。もちろん、専門委員の総数としては、現行制度の下における不服申立(異議申出)件数が年間200件を超える実情にあることにかんがみると、少なくとも十数名程度の選任を必要とするであろう。 |
| (4) | 審査手続の改善 |
| 不服申立ての審査手続についても改善に努めるべきであり、専門委員制度を有効に機能させるためには、各専門委員が的確な判断を行うことができるよう、従来の難民調査官による事情聴取に代えて、自ら申出人から直接意見を聴取する手続を設けることが考えられる。その際、専門委員は、申出人に対して質問を行うことも認められるべきである。 他方、現在の不服申立手続の運用を見ると、不服申立手続においても新たな主張や証拠の提出には一切制約が設けられておらず、不服申立手続はいわゆる続審として機能しているが、再検討の要がある。我が国では司法審査における主張内容が不服申立手続におけるそれによって制限されることはなく、事実認定についても不服申立手続のそれに拘束されないなど、事後的に司法の場で十分な審査が行われるのであるから、不服申立手続を迅速に進めるためにも、不服申立手続はいわゆる事後審査審として位置付けることが考慮されてよいのであって、判断対象は一次処分の当否それ自体に限定されるのが好ましい。 その意味では、新たな不服申立手続において必ず口頭審理が行われるとする必要はなく、申出人に意見陳述の機会を与える一方で、申出人が希望しない場合や申出人から意見聴取をするまでもなく結論が明らかな場合等一定の場合には意見陳述を不要とし、書類審査による手続簡略化を認めることも考えられる。 また、現在の不服申立ての実態に照らせば、各地方入国管理局すべてに常時専門委員を設置することは組織として非効率であるから、専門委員を東京及び大阪の二局に集中させるなどして、組織としての合理化を図ることも考えられる。また、本制度の円滑な運営を期するためには、事務処理体制の充実についても配慮する必要がある。 さらに、不服申立手続の過程においても、手続の内容等について申出人に十分な説明を行い、手続の透明性を高めて、申出人がより納得しやすい環境作りに配慮するとともに、専門委員が申出人から意見聴取する際、申出人の代理人がこれに立ち会うことを認めるべきである。 |
| 3 | 不服申立期間 |
| 不服申立期間については、現行の7日間が不服を申し立てるまでの期間として特に短いとは思われないとの意見が多数を占めた。 |