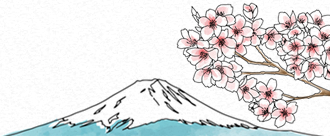| ○ |
在留資格「留学」の在留期間を4年に延長すると、不法就労などの不法滞在者が増加するのは明らかである。大学による留学生の在籍状況のチェックや在籍状況に関する情報を入国管理局にフィードバックするなど、留学生の在籍状況に関するチェック体制の強化が必要である。現在検討中の「新たな在留管理制度の見直し」に、留学生に対する在籍状況について大学によるチェックが働く仕組みを盛り込んではどうか。 |
| ○ |
大学評価の枠組みの中に、例えば留学生の在籍状況の管理状況の評価を盛り込むことができれば、在留資格「留学」の在留期間を「4年」に延長するなどしてもよいのではないか。 |
| ○ |
学生の勉学状況について、学問水準の質については大学が、在学の事実については入国管理局がそれぞれチェックを行うなど、大学と入国管理局との役割分担を明確化してはどうか。 |
| ○ |
入国管理局は、専攻科目と就職先で従事する業務内容との関連性について柔軟に判断しているというが、そういった取扱いが学生側に伝わっていないのではないか。 |
| ○ |
留学生・就学生の受入れの検討においては、都市部や地方など、地域ごとの受入れのキャパシティーをどう評価するか、という観点も必要である。 |
| ○ |
留学生の日本企業への就職状況を見ると、大企業よりも中小企業へ就職する留学生が多い。大企業に対し、留学生の雇用を図るための何らかのインセンティブを付与する必要があるのではないか。 |
| ○ |
日本企業への就職を希望する学生が、ビジネス上の知識や語学力などの点で、企業が求めるレベルに達していないケースが多い。日本企業への就職の拡大には、大学において、大企業でも通用する人材を育成することが重要である。 |
| ○ |
留学生にとって、日本企業への就職はキャリアアップの一つにすぎず、就職後、母国や第3国の企業に転職するケースが多い。留学生の雇用は企業によってリスクがある。 |
| ○ |
留学生の日本企業への就職の軌跡を調べる必要があるのではないか。 |
| ○ |
就学生の中には、留学を目的としない者もいるので、そうした一部の者のために「就学」を残す意味はあるかもしれない。 |