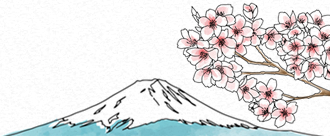- トップページ
- 政策情報(会議・統計等)
- 会議・委員会等
- 出入国在留管理政策懇談会
- 「新たな在留管理制度に関する提言」
- 「新たな在留管理制度に関する提言」
「新たな在留管理制度に関する提言」
| 第1 | はじめに |
| 1 | 在留管理専門部会設置の経緯 |
| 我が国に入国、在留する外国人の数は年々増加しており、平成18年における外国人入国者数は約811万人、平成18年末現在の外国人登録者数は約208万人と、いずれも過去最高を記録した。外国人が我が国に入国、在留する目的も、観光のほか、就労、留学、研修、永住など多様化しており、各種行政において外国人の入国、在留状況を正確に把握することの重要性が増している。 このような中、政府は、平成17年7月19日、犯罪対策閣僚会議の下に「外国人の在留管理に関するワーキングチーム」を設置し、同ワーキングチームにおいて、法務省を含む関係省庁が、外国人の在留情報の把握や在留管理の在り方につき検討を行ってきたほか、規制改革・民間開放推進会議(現在の規制改革会議の前身組織)においても、外国人の在留管理制度について議論され、平成18年12月25日、同会議の第3次答申において、在留外国人の入国後のチェック体制の強化等につき、遅くとも平成21年通常国会までに関係法案を提出することが求められた(注1)。 以上のような状況を踏まえ、法務大臣が各方面の有識者から、新たな在留管理制度の在り方について意見を聴取し、今後の法務行政に活かすため、平成19年2月1日、法務大臣の私的懇談会である「出入国管理政策懇談会」(以下「政策懇談会」という。)の下に「在留管理専門部会」(以下「専門部会」という。)が設置された。 (注1)第3次答申を踏まえ、平成19年6月22日、「規制改革推進のための3か年計画」が閣議決定され、在留外国人の入国後のチェック体制の強化として、外国人に係る情報の相互照会・提供、外国人登録制度の見直し、使用者等受入れ機関等に対する責任の明確化等が盛り込まれた。また、同年7月3日、犯罪対策閣僚会議に「外国人の在留管理に関するワーキングチームの検討結果」が報告され、外国人の在留管理の在り方につき、法務大臣による在留情報の一元的把握、所属機関の協力、行政機関の情報の相互照会・提供、正確な在留情報に基づく的確な在留管理といった方向性が示された。
|
| 2 専門部会による中間報告書作成の経緯等 | |
| (1) | 専門部会による中間報告書の作成 |
| 専門部会は、設置後、平成19年7月12日開催の第9回会合まで、月に1、2回の頻度で会合を開き、各メンバーが意見を交換し、議論を行ったほか、東京入国管理局の在留審査部署及び外国人登録証明書調製部署等並びに東京都港区役所の外国人登録担当窓口を視察して、入国管理行政及び外国人登録事務の実情を調査し、また、外国人の在留管理の検討に当たって関係のある団体や関係者から広く意見聴取を行った。 その結果、現行の在留管理制度の問題点や今後検討すべき課題等が明らかになってきたため、これらを取りまとめて中間報告書を作成し、同年8月1日に開催された政策懇談会との合同会合において報告を行った。 |
|
| (2) | 政策懇談会における中間報告書に対する指摘 |
| 専門部会が作成した中間報告書に対する政策懇談会メンバーからの主な指摘は、以下のとおりであった。
(1) 制度改正の目的について、不法滞在、不法就労、外国人犯罪の抑止等治安対策が目的であるとのスタンスを明確にしたほうが良い。
(2) 制度改正の目的には、外国人の生活の利便向上等の目的も加えるべきである。不法滞在者等の取締りも重要であるが、法律を守って健全に暮らしている外国人の生活をいかに良くするかという視点も持って検討してほしい。
(3) 外国人の人権保障、個人情報の保護の観点から、法務大臣が収集する情報は、在留管理上必要最小限にするとともに適正な情報管理を行うべきである。
(4) 国が外国人の情報を正確に把握する仕組みを構築することがサービス行政を含めあらゆる行政の大前提であり、そのためには情報把握の一元化や関係機関相互の情報の共有が必要である。
|
|
| 3 政策懇談会による報告書「新たな在留管理制度に関する提言」の作成 | |
| (1) | 専門部会による最終報告書の作成 |
| 専門部会は、平成19年8月1日開催の政策懇談会との合同会合後、同年12月26日まで、計4回会合を開き、中間報告書に対する政策懇談会メンバーからの指摘を踏まえて議論を行い、専門部会による最終報告書として、「新たな在留管理制度に関する提言(案)」を取りまとめ、平成20年1月31日に開催された政策懇談会との合同会合において報告を行った。 | |
| (2) | 政策懇談会による報告書「新たな在留管理制度に関する提言」の作成 |
| 政策懇談会は、平成20年1月31日開催の専門部会との合同会合を踏まえ、専門部会が作成した最終報告書に必要な修正を施した上で了承し、政策懇談会による報告書「新たな在留管理制度に関する提言」を取りまとめた。 | |
| (3) | 政策懇談会メンバーからの意見 |
| なお、専門部会が作成した最終報告書に対して、政策懇談会メンバーから、個別の意見として以下の意見が述べられた。
(1) 最終報告書は、外国人の在留管理の必要性と利便性の向上の重要性とのバランスが取れている内容であるので、今後は、適法に在留している外国人の立場に立って、利便性について詳細を検討していって欲しい。
(2) 外国人の在留情報を一元的に把握、管理するだけでなく、国の側から、外国人に対して、日本で生活していく上で必要な情報を提供することも必要である。
(3) 法務大臣が在留外国人の正確な情報を把握するため、外国人の所属機関からの情報提供は重要で、情報提供の義務があることを明確にすべきである。
(4) 在留管理の目的で収集された情報が、無制限に他の目的に利用されることがないよう慎重な配慮が必要であり、個人情報保護の観点から厳格な管理運営を行っていくべきである。
|
|
| 第2 | 現行の在留管理制度の概要及び問題点 |
| 1 | 現行の在留管理制度の概要 |
| 我が国に在留する外国人の在留管理は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づく入国・在留関係の許可の手続と外国人登録法(以下「外登法」という。)に基づく外国人登録制度によって担われている。 入管法は、外国人が我が国に上陸し在留するためには、原則として、在留資格を有しなければならないとし、27種類の在留資格を定めている。我が国に入国、在留することを許可された外国人は、入管法の定める在留資格のいずれか1つを付与され、定められた在留期間、付与された在留資格が予定する活動を行い、以後、在留期間の更新の許可、在留資格の変更の許可、資格外活動の許可等、様々な在留上の許可の手続を経て在留を継続することになる。これら在留上の許可の申請は、原則として、外国人本人が地方入国管理局に赴いて行い、その際、地方入国管理局は、当該外国人の氏名、国籍等の身分事項、居住地、所属先などの情報を入手する。 一方、外登法は、第1条において、「この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによって外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もって在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。」と規定しており、我が国に在留する外国人は、入国後90日以内に、居住地の市区町村の長に対し、氏名や国籍といった身分事項、居住地、勤務先等の登録を申請しなければならない(新規登録)。市区町村の長は、これら登録事項を記載した外国人登録原票(以下「登録原票」という。)を作成し、市区町村の事務所に備えるほか、外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を作成し、登録申請をした外国人に交付する。16歳以上の外国人は、登録証明書を常に携帯していなければならない。外国人は、登録事項に変更があった場合には変更登録を申請しなければならず、市区町村の長は、当該外国人の登録原票に変更の登録をするとともに、登録証明書に変更に係る記載を行う。なお、外国人が、別の市区町村へ転居し、新居住地の市区町村において居住地の変更登録を申請した場合には、旧居住地の市区町村の長から新居住地の市区町村の長へ当該外国人の登録原票が送付される。また、外国人は、原則として、新規登録を受けた日等の後の5回目(永住者及び特別永住者は7回目)の誕生日から30日以内に、居住地の市区町村の長に対し、登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認を申請しなければならず、市区町村の長は新たに登録証明書を外国人に交付する。 以上のような各種登録によって市区町村の長が取得した情報については、登録証明書の作成や変更登録の報告等の手続により、法務大臣に伝えられる。 外国人は、出国する場合(再入国許可を受けて出国する場合を除く。)、外国人でなくなった場合及び死亡した場合には、登録証明書を市区町村の長等に返納しなければならず、登録原票は閉鎖される。外国人が再入国許可を受けることなく出国した場合及び再入国許可を受けて出国しながら、同許可の有効期間内に再入国しなかった場合には、当該事実が法務大臣から市区町村の長に通知され、この通知に基づき、市区町村の長は登録原票を閉鎖する。一方、市区町村の長が、外国人の死亡等により登録証明書の返納を受けて登録原票を閉鎖した場合には、市区町村の長から法務大臣にその旨報告される。 |
| 2 現行の在留管理制度の問題点 | |
| (1) | 法務大臣による在留情報の随時把握が不十分 |
| (1) | いわゆる「点」の管理の問題 |
| 入管法上、外国人の在留管理は入国時や在留期間の更新時に審査を行ういわゆる「点」の管理となっており、その間は在留資格の取消事由や退去強制事由に該当すれば、これらの処分が行われる。一方で、外国人は、転職(退職)や転校(退学)等在留期間の途中における事情の変更について法務大臣に報告する義務はなく、外登法上も、留・就学生の通学先は登録事項となっていない。また、法務大臣には、市区町村の長から受ける外国人登録の報告に関して調査を行う権限がない。このため、法務大臣は、外国人の在留期間の途中における事情の変更を十分に把握できておらず、事情の変更が在留資格の取消事由等に該当する場合の対応が必ずしも十分に行えていない。 | |
| (2) | 外国人の申請のみに基づく外国人登録制度の問題 |
| 外登法上、居住地や勤務先の名称・所在地は登録事項になっており(ただし、永住者は、勤務先の名称・所在地が登録事項となっていない。)、これらの事項に変更があれば外国人が変更登録の申請をする義務が定められている。しかし、
ア 虚偽申請や申請義務違反に対しては、罰則が定められているものの、在留資格の取消しや退去強制等の入管法上の処分と直接関連していないこと
イ 市区町村の長による事実の調査は、登録の申請があった場合にのみ可能で、登録後に調査を行うことは定められていないこと
ウ 仮に市区町村の長が登録事項が事実と異なることを知っても、職権で変更登録することができないこと
から、正確な登録が行われるためには、外国人による適切な申請を待つほかない。 |
|
| (2) | 入管法と外登法の二元的な情報把握の制度の問題 |
| (1) | 法務大臣(入管法)と市区町村の長(外登法)の二重の情報把握・管理による問題 |
| 外国人の在留情報は、入管法に基づく入国・在留関係の許可手続時と外登法に基づく外国人登録時に把握しているため、法務大臣と市区町村の長とで二重に情報が把握、管理されている。また、外登法の対象が短期滞在者から特別永住者さらには不法滞在者まで幅広いにもかかわらず、登録事項がほぼ一律に近くなっている。そのため、法務大臣が、在留資格に応じて的確に在留情報を把握し、適正な在留管理を行うことが必ずしも十分ではないのみならず、行政の非効率や外国人の負担も生じている。 | |
| (2) | 不法滞在者への外国人登録証明書交付の問題 |
| 本来在留が認められない不法滞在者が外国人登録の対象となり、登録を行えば登録証明書が交付され、登録原票記載事項証明書の交付も受けられる。そのため、一般の人々がこれら証明書を見て正規滞在者と誤解したり、これら証明書が預貯金口座の開設や携帯電話の契約等における本人確認書類として使われるなどして、不法滞在者の在留継続を結果として容易にしている。 | |
| 3 その他の問題点 | |
| (1) | 外国人登録制度の目的と実際の運用との齟齬による限界 |
| 外国人登録制度は、「外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もって在留外国人の公正な管理に資すること」(外登法第1条)を目的としている。ところが、外国人については、住民たる地位に関する記録であり住民に関する事務処理の基礎となる住民基本台帳の制度の適用がないことから、市区町村は、事実上、外国人登録を行った外国人を住民として把握し、外国人登録の情報を各種行政サービス提供の基礎としている。 しかし、日本に在留する外国人を対象とした外国人登録制度と市区町村の住民を把握するための住民基本台帳制度はその趣旨及び目的が異なるため、市区町村が、外国人登録の情報に基づき外国人に行政サービスを提供するに当たり支障が生じている。例えば、再入国許可により長期出国中の者や出国はしていないが所在不明の者については、市区町村の区域内に居住していないことのみを理由に登録原票を閉鎖することはできず、外国人登録上居住している旨の記録が残るため、市区町村において、その者についての課税、国民健康保険、就学等の事務が発生し、負担になっているとの指摘がある。 |
|
| (2) | 混合世帯の問題 |
| 日本人の国際結婚件数は毎年増加を続け、今日では17組に1組に及ぶが、市区町村において、日本人は住民基本台帳制度、外国人は外国人登録制度と、それぞれ異なる制度の対象となるため、日本人と外国人が結婚した世帯等1つの世帯に外国人と日本人が含まれる世帯(以下「混合世帯」という。)については、いずれの制度においても1つの世帯として把握することが困難となっている。そのため、実態としては1つの世帯であるにもかかわらず、外国人登録上の世帯主と住民基本台帳上の世帯主が異なり、その結果、児童手当の支給等円滑な行政サービスの提供を行う障害となっているほか、混合世帯の構成員が、同居の家族・親族を対外的に証明する場合にも支障が生じているとの指摘がある。 | |
| 第3 | 新たな在留管理制度に関する提言 |
| 1 | 在留管理制度見直しのねらい |
| 外国人登録制度が発足した終戦直後は、我が国に在留していた外国人のほとんどが戦前から引き続き我が国に在留していた朝鮮半島等出身者であった。その後、我が国の国際化が進み、様々な目的を持って新たに来日した外国人いわゆるニューカマーが増加した結果、我が国に在留する外国人の構成が制度発足当時とは大きく変化した上、ニューカマーの中には、国内に安定した生活基盤がないため、外国人登録に際して正確な申請を行わなかったり、頻繁に転居したり、あるいは、再入国許可を受けて本国に帰国したままで再入国するか否かが不明な者も現れ、法務大臣や市区町村の長による在留外国人の情報の把握が困難になってきている。こうした外国人の構成の変化及びそれに伴う外国人の行動様式の変化が、先に述べた「現行の在留管理制度の問題点」や「その他の問題点」の原因となっている。よって、このような現状を改め、法務大臣が外国人の在留状況を十分に把握するためには、外国人の在留に関する情報体制の再構築が必要である。 そこで、新たな在留管理制度においては、外国人登録制度を抜本的に見直し、法務大臣が、我が国に在留する外国人の在留管理に必要な情報を一元的、正確かつ継続的に把握する制度を構築する。これにより、法務大臣は、把握した正確な情報を不法滞在者、不法就労者対策を含め出入国管理行政に有効に活用して国民の信頼を高め、同時に、適法に在留する外国人が、より安定的に我が国で活動しやすくするための諸方策を講じていくこととする。 一方、現在外国人登録事務を処理している市区町村にとって、外国人住民に関する正確な記録を常に整備しておくことは、行政サービスの提供を通じて外国人住民の利便の増進を図る上で欠かせない。「規制改革推進のための3か年計画」(平成19年6月22日閣議決定)においても、市区町村が外国人について住民として正確な情報を保有して、その居住関係を把握する法的根拠を整備する観点から、住民基本台帳制度を参考とした適法な在留外国人の台帳制度の必要性が指摘されている。法務大臣は、同制度の重要性にかんがみ、市区町村に対して必要な情報を提供することにより、正確な情報を基盤とする台帳制度の整備・運用に協力し、もって地域における外国人住民に対する各種行政サービスの向上に積極的に貢献する。 そして、このような法務大臣による情報把握制度の構築や外国人の台帳制度の整備を通じて、労働、教育、福祉等様々な分野で、我が国で暮らす外国人を支援する施策が講じられ、外国人が生活しやすい温かい環境が醸成されていくことにより、日本人と外国人がお互いを尊重し合い、支え、助け合いながら共に生きていく、共生社会の実現を目指すべきである。 |
| 2 | 新たな在留管理制度の概要 |
| 現在、外国人の在留情報について、入管法に基づく入国・在留関係の許可手続時と外登法に基づく外国人登録時に、各々法務大臣と市区町村の長とで二重に情報が把握、管理されている制度を入管法に集約・一元化した新たな制度として再構築する。 すなわち、我が国に在留する外国人は (1) 上陸許可、在留期間の更新、在留資格の変更等の許可の申請時に在留管理に必要な事項の記録を受けた上、当該許可に伴い、在留カード(仮称)(以下「在留カード」という。)の交付を受け
(2) 在留期間の途中で上陸許可等許可の申請時から変更された事項(詳細は4(2)「届出事項」参照)があれば、当該変更を法務大臣に届け出る(ただし、居住地については、市区町村の長を経由して法務大臣に届け出る)
こととする。さらに
(3) 法務大臣が、外国人の留・就学先、研修先等の所属機関から、所属する外国人に関する情報の提供を受ける制度を創設するとともに
(4) 関係行政機関において、それぞれの事務又は業務の遂行に必要な限度で、外国人に関する情報を相互に照会、提供できる仕組みを整備する。
これにより、法務大臣は、外国人が届け出た情報と所属機関等から提供された情報とを照合するなどして、当該外国人の在留状況をより正確に把握する。 |
| 3 | 新たな在留管理制度の対象となる外国人 |
| 基本的に、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象とする。 短期間で我が国から出国することが予定されている「短期滞在」者及びその有する歴史的経緯により、入管法上の在留資格を有しないで在留する「特別永住者(注2)」は対象外とする。また、入管法上の在留資格を受けておらず、短期間の滞在が予定されている特例上陸許可者及び仮滞在許可者についても対象外とする(注3)。 入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人であっても、現在も外国人登録の対象外となっている「外交」及び「公用」の在留資格で在留する者は、新制度の対象外とする(注4)。 (注2)日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者で終戦前から引き続き日本に在留しているもの及びその子孫が、日本に永住できる法的な地位をいう。
(注3)現在、外国人登録の対象となっている「短期滞在」者、一時庇護上陸許可者及び仮滞在許可者については、適正な在留管理の観点から、登録証明書を交付しないこととする。
(注4)「外交」及び「公用」の在留資格で在留する者は、国際儀礼上、配慮の必要性が高いので、対象から除く。
|
| 4 外国人からの在留状況の届出 | |||||
| (1) | 概要 | ||||
| 外国人(以下、特段の断わりのない限り、3で述べた新たな在留管理制度の対象となる外国人を指す。)は、上陸許可等許可の申請時に在留管理に必要な事項として記録された事項について、在留期間の途中で変更が生じた場合、変更の事由が生じた日から一定期間内に、当該変更のあった旨を法務大臣に届け出なければならない。 | |||||
| (2) | 届出事項 | ||||
| 届け出る事項については、在留資格によって在留管理上の必要性も異なることから、各在留資格ごとに、個人情報保護の要請を踏まえて、検討する必要がある。主な事項は以下のとおりである。 | |||||
| (1) | 身分事項 | ||||
| 基本的な身分事項である氏名、生年月日、性別、国籍については、各種許可の申請時から変更が生じた場合には法務大臣へその旨を届け出ることとする。 その他、配偶者等の在日親族の氏名等については、個人情報保護の要請を踏まえて、在留管理上当該外国人の身分関係を把握する必要性を検討した上で、例えば、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び「家族滞在」といった身分に基づいて在留資格が定まった者につき、その基礎となる身分関係を届出事項とする(注5)。 (注5)在日親族及び同居者の氏名等については、現在、在留期間の更新等の審査時に把握している。また、外国人登録制度において、同一人性確認のため、在日父母及び配偶者の氏名等が登録事項となっている。
|
|||||
| (2) | 居住地 | ||||
| 居住地は、在留管理上、随時的確に把握しておくべき情報であり、外国人が我が国に入国後、新たに居住地を定めた場合及び居住地を変更した場合には、法務大臣へその旨を届け出ることとする。 | |||||
| (3) | 所属機関等の名称及び所在地,所属機関等における労働条件等 | ||||
| 所属機関及び活動先の名称及び所在地は、在留管理上、随時的確に把握しておくべき情報であり、外国人が所属している機関(外国人が契約等で所属している場合におけるその所属機関。例えば、就労先や留・就学生の通学先。)の名称及び所在地のほかに、実際の活動先の名称及び所在地を届け出ることとする。 その他の情報については、個人情報保護の要請を踏まえて、在留管理上の必要性を検討した上で、いかなる情報を届出事項とするか検討する必要がある。例えば、「職業」及び「報酬」を届出事項とすることが考えられるが、個人情報保護の要請や外国人の届出に係る負担等を考慮すると、一定の在留資格の者に限って届出事項とすることや所属機関又は活動先の変更の届出に伴い、併せて届け出ることが適当である(注6)。 (注6)現行外国人登録法上、永住者については、職業、勤務先は登録事項となっていないが、不法滞在者等が永住者を偽装し不法就労に従事することを防止する等適切に在留管理を行う観点から、永住者であっても、勤務先等について把握する必要があると思われる。
なお、平成19年10月から施行されている改正雇用対策法の外国人雇用状況の届出においては、事業主が新たに外国人(永住者を含む。)を雇用したときに厚生労働大臣に届け出る事項として、「勤務先」、「賃金」が含まれている。 |
|||||
| (3) | 届出方法 | ||||
| (1) | 居住地以外の届出事項 | ||||
| 外国人は、居住地以外の届出事項に変更が生じた場合には、原則として、地方入国管理局に赴き、当該変更を届け出ることとする。 ただし、外国人の負担を考慮し、在留申請手続の電子化が図られ、インターネットを利用した申請手続等が整備されること(注7)を前提に、インターネットを利用した届出を可能とする。 (注7)出入国管理業務の業務・システムの最適化計画(改定)
在留申請手続の電子化 インターネットを利用した申請手続【平成21年度までに実施】 外国人登録証明書を持つ外国人及び事前登録済みの申請者(申請取次者や受入機関等の頻繁に申請する利用者)に対して、インターネットを利用した申請書作成及び郵送による申請を可能とし、申請者の窓口出頭の手間を省くとともに、申請受理に係る業務の合理化を図る。 |
|||||
| (2) | 居住地
|
||||
| (4) | 届出情報の正確性・届出の実効性担保の在り方 | ||||
| (1) | 法務大臣は、外国人が届け出た情報と外国人の所属機関又は関係行政機関から提供を受けた情報を照合することによって、外国人の在留情報の正確性を向上させる。 | ||||
| (2) | 法務大臣は、外国人が届け出た情報及び外国人の所属機関等から提供を受けた情報につき、調査の必要があると認めるときは、職員に事実の調査をさせることができることとする。調査の方法としては、例えば、届出を行った外国人その他の関係人に対して出頭を求め、質問をし又は文書の提出を求めること、公務所又は公私の団体に照会することとする(注10)。
(注10)居住地情報に関しては、市区町村の長の調査権限を設けるべきかどうかの論点がある。この点に関しては、「適法な在留外国人の台帳制度」(下記5(2)参照)において、住民基本台帳制度を参考に、市区町村の長の調査権限が適切に整備されることとなれば、当該制度との連携をも視野に入れつつ検討を進めていくのが望ましい。
|
||||
| (3) | 届出義務を履行しない者及び虚偽届出を行った者に対しては、刑事罰を科すほか、後述のとおり、在留期間の更新等の在留審査において考慮するなど入管行政上厳格な対応をすることとする。 | ||||
| 5 市区町村との関係 | |
| (1) | 新たな在留管理制度における市区町村の役割 |
| 新たな在留管理制度において、外国人は、居住地を、当該居住地の市区町村の長を経由して、法務大臣に届け出ることになる。この場合、市区町村の長が居住地の届出を受ける事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する法定受託事務となるところ、当該法定受託事務は、「国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」であって、地方分権を推進する観点から、できるだけ抑制されるべきである。 そこで、新たな在留管理制度における市区町村の役割(法定受託事務の範囲)は (1) 外国人が法務大臣に居住地を届け出る際の窓口となること(経由事務)
(2) 当該届出に伴い、届出に係る居住地情報の在留カードへの反映に関与すること
とすることが適当である。 |
|
| (2) | 市区町村による情報の取得、保有及び利用(適法な在留外国人の台帳制度) |
| 「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」(地方自治法第1条の2)とされている市区町村にとって、住民に関する正確な記録を常に整備することは住民行政の基礎であり、行政サービスの提供を通じて住民の利便の増進を図る上で欠かせないものである。これらのことは外国人住民についてもいささかも変わるところがない。この点、地方自治法第13条の2は、「市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。」と規定し、別に定める「法律」として、住民基本台帳法が制定されている。しかし、住民基本台帳法は外国人には適用されない。 そこで、現在、市区町村は、事実上、外国人登録を行った外国人を住民として把握し、外国人登録の情報を各種行政サービス提供の基礎として利用しているが、外国人登録制度と住民基本台帳制度はその趣旨及び目的が異なるため、市区町村が外国人住民に行政サービスを提供するに当たり支障が生じている。 この問題を解決するためには、市区町村において外国人住民に関する正確な記録が作成されるよう、「規制改革推進のための3か年計画」(平成19年6月22日閣議決定)が指摘する、住民基本台帳制度を参考とした「適法な在留外国人の台帳制度」を整備することが必要である(注11)。 上記台帳制度の整備に当たっては、以下で述べるように法務大臣から外国人の在留情報の提供を受けるほかに、戸籍に関する届出(例えば,死亡届)と連携を行い、正確な台帳が作成されるようにすべきである。 また、混合世帯の正確な把握のために、住民基本台帳制度と連携を行い、行政サービスの提供に支障が生じないようにすべきである。 (注11)「規制改革推進のための第2次答申」(平成19年12月25日規制改革会議決定)において、「「遅くとも平成21年通常国会までに関係法案提出」とされた措置に向け、内閣官房の調整の下、総務省及び法務省が当該台帳制度の基本構想を作成し、公表すべきである。【平成19年度措置】その上で、両省は、地方公共団体の意見を十分に考慮しつつ、適切かつ着実に当該台帳制度を整備すべきである。【遅くとも平成21年通常国会までに関係法案提出】」とされた。
|
|
| (3) | 適法な在留外国人の台帳制度との連携の必要性 |
| 法務大臣は、「適法な在留外国人の台帳制度」の重要性にかんがみ、新たな在留管理制度下で自らが保有する情報のうち、上記台帳に必要な情報(例えば、外国人の身分事項に関する情報、在留期間の更新等の許可の情報、出国の情報など)を市区町村に円滑に提供し、市区町村において正確な台帳が作成されるよう協力する。さらに、上記台帳制度と法務大臣との連携が図られれば、法務大臣が外国人の在留情報をより正確に把握することも可能となる。例えば、法務大臣は、後述する在留カードの返納によって、独自に外国人の死亡事実を把握することが可能であるが、返納すべき在留カードが失われた場合などには、死亡事実を把握できないことが想定される。そこで、上記台帳制度において、外国人の死亡事実が台帳に反映された場合に、当該台帳を保有する市区町村の長と法務大臣との連携を図ることで、法務大臣がより的確に外国人の死亡事実を把握することができる。 なお、在留管理上把握する必要性がないことから法務大臣に届け出られない情報で、市区町村にとっては住民行政の基礎とするために必要な情報(例えば、世帯情報)については、台帳制度において、市区町村が外国人本人から取得することが合理的である。 |
|
| 6 在留カードの交付 | |
| (1) | 概要 |
| 法務大臣は、上陸、在留期間の更新及び在留資格の変更等の許可に伴い、当該許可を受けた外国人に対し、在留カードを交付する。在留カードの有効期限は、原則として在留期限と一致する。 外国人は、在留カードを常に携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官等の求めに応じて提示しなければならない。不法滞在者は、在留カードを持ち得ず、あるいは、有効期限の経過した無効な在留カードしか持っていないので、正規滞在者との違いが明らかになる。 |
|
| (2) | 交付方法 |
| 以下の場面において交付することが想定される。なお、各交付の性格や諸外国の実情を踏まえ、外国人から手数料を徴収する可能性も検討すべきである。 | |
| (1) | 上陸した海空港において、上陸許可に伴い、在留カードを交付する。 |
| (2) | 地方入国管理局において、在留期間の更新、在留資格の変更、在留資格の取得、永住許可、在留特別許可に伴い、在留カードを交付する。 |
| (3) | 外国人は、紛失、盗難、滅失等により在留カードを失った場合には、その事実を知った日から一定期間内に、地方入国管理局に赴き、在留カードの再交付を申請しなければならない。 |
| (3) | 機能・体裁 |
| (1) | 在留カードは、外国人にとって、身分事項及び在留資格等を証明する重要な身分証明書となることから、その信用性を保護するため、最新の技術動向などを踏まえて、偽変造対策を十分講じることが必要である。例えば、旅券及び運転免許証と同様にICチップを登載することとする。 |
| (2) | 在留資格の類型ごとに在留カードの色を変えるなどして、事業主が、外国人を雇用するに際し、当該外国人が所持する在留カードを見れば、就労可能な外国人かどうか判断できるようにして、不法就労の防止を図ることを検討すべきである。 |
| (4) | 記載事項 |
| 券面記載事項については、個人情報保護の要請、カード記載情報の正確性を維持する必要性、記載情報の変更によりカードの書き換えをしなければならない外国人の負担などにかんがみると、必要最小限にとどめることが望ましい。そこで、券面記載事項は、カード番号、氏名、生年月日、性別、国籍、許可の年月日(カードの交付年月日)、在留資格、在留期限(カードの有効期限)、居住地、顔写真とする。 なお、仮にICチップを登載することとした場合には、ICチップ登載情報については、券面記載事項と概ね同様とする。 |
|
| (5) | 記載事項の変更 |
| (1) | 居住地以外の記載事項 |
| 外国人は、居住地以外の記載事項に変更が生じた場合、地方入国管理局に赴き、当該事項の変更の届出を行い、変更を反映した新たな在留カードの交付を受けることとする。 | |
| (2) | 居住地 |
| 外国人は、市区町村に居住地を届け出ることになるので、これに伴い、速やかに在留カードに居住地情報を反映させることが適当である。反映の方法については、偽変造防止の観点からも検討する必要がある。 | |
| (6) | 永住者の在留カード |
| 永住者の在留期間は無期限であるため、原則に従えば、在留カードの有効期限も無期限となるが、それでは、在留カードによる同一人性確認効果を維持できなくなる。そこで、永住者については、現行の外国人登録証明書の切替制度を参考にして、在留カードの有効期限が在留期限と一致する例外として、在留カードの有効期限を別に設定し、当該有効期限が経過するまでに、顔写真等を提出して在留カードを切り替える制度を設けることを検討すべきである。 | |
| (7) | 携帯義務等 |
| (1) | 携帯・提示義務 |
| 一定年齢(例えば、16歳)以上の者に在留カードの常時携帯義務及び提示義務を課す。在留カードを携帯すれば、旅券等の携帯義務(入管法第23条)を免除する。 | |
| (2) | 返納及び失効 |
|
ア 在留カードの有効期限が経過したとき、在留資格の取消し又は退去強制令書の発付によって在留資格を失ったとき、外国人でなくなったとき、死亡したとき、新たな在留カードの交付を受けたときなどには、在留カードは失効する。
イ 在留カードが失効した場合、外国人又はその代理人は、当該カードを法務大臣に返納しなければならない。
ウ 在留カードの失効事実は関係機関に通知することとする。通知方法については、必要とする機関の範囲や個人情報保護の要請を考慮し、検討する必要がある。
|
|
| (8) | 罰則等 |
| (1) | 罰則 |
| 在留カード制度の実効性を担保するため、常時携帯・提示義務違反、再交付申請義務違反、返納義務違反、切替義務違反のほか、在留カードの譲渡や貸与等不正利用行為に対する罰則を整備する。 | |
| (2) | 上記違反行為については、在留期間の更新等の在留審査において考慮するなど入管行政上厳格な対応をすることとする。 |
| 7 所属機関から法務大臣への情報提供 | |||||||||
| (1) | 概要 | ||||||||
| 法務大臣は、外国人の所属機関から当該外国人に関する情報の提供を受け、外国人が法務大臣に届け出た情報と照合するなどして、外国人の在留情報を正確に把握できるようにする。 | |||||||||
| (2) | 各論 | ||||||||
| (1) | 外国人を雇用している機関 | ||||||||
| 平成19年10月から施行されている改正雇用対策法により、外国人を雇用する事業主は、厚生労働大臣に外国人労働者の雇用状況に係る情報を届け出なければならず、厚生労働大臣は、法務大臣から、入管法又は外登法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあったときは、当該情報を提供するという枠組みができている。 | |||||||||
| (2) | 留学生及び就学生が学ぶ教育機関 | ||||||||
世界中で留学生の獲得競争が進む中、優秀な留学生を積極的に受け入れるためには、留学生及び就学生が教育を受けようとする教育機関において適切な在籍管理が行われることが必要である。当該教育機関は、法務大臣に対し、受け入れた留・就学生の在籍状況について情報を提供することとし、適切な在籍管理を行うことができない教育機関については、外国人の受入れを認めないなどの厳格な措置が必要である。
|
|||||||||
| (3) | 研修生が所属する機関 | ||||||||
| 研修制度においては、研修生が労働者として扱われることなく適正に研修が実施されることが重要である。そのためには、受入れ体制の整備、研修内容の確保等の研修実施体制が備わっていることが必要である。 研修実施機関についても教育機関と同様、法務大臣に対し、研修生受入れ先の変更、研修生の失踪その他の研修の実施状況に係る問題が発生したことについての情報を提供することとし、適切に研修を行うことができない研修実施機関については、外国人の受入れを認めないなどの厳格な措置が必要である(注13)。情報提供の方法については、教育機関同様、インターネット等を利用した方法を可能とすることを検討すべきである。 なお、研修・技能実習制度については、現在、政府において見直しを検討中であり、同見直しを注視することとしたい。 (注13)「規制改革推進のための3か年計画」(平成19年6月22日閣議決定)において、「使用者以外の受入れ機関等に対する責任の明確化」として「(出入国管理及び難民認定法の関連法令への)格上げに当たっては、先述(1)(3)イの外国人雇用状況報告の対象とならない雇用関係のない者(研修生等)も含むべきであり、不適正な事案が判明した場合の対処、資格ごとに異なると考えられる徴求事項への対応を可能とする随時照会・回答といった手法についても規定すべきである。」とある。
|
|||||||||
| (4) | その他の所属機関(外国人が経営する一人会社も含む。) | ||||||||
| これらの所属機関については、法務大臣が、必要に応じて所属する外国人に関して照会を行うことができる(所属機関は回答義務を負う)ようにする。 | |||||||||
| (5) | 履行担保の方法 | ||||||||
|
ア 法務大臣は、所属機関における在籍、研修実施状況等につき、調査の必要があると認めるときは、職員に事実の調査をさせることができることとする。調査の方法としては、例えば、所属機関その他の関係人に対して出頭を求め、質問をし又は文書の提出を求めること、公務所又は公私の団体に照会することとする。
イ 情報提供をしなかった機関又は虚偽の情報提供をした機関は、外国人の受入れ機関としての適格性に欠けることから、新たに外国人が当該機関を所属機関として申請してきた際に、当該外国人の受入れを認めないといった入管行政上の対応をすることが考えられる。
|
|||||||||
| 8 | 行政機関による情報の相互照会・提供 |
| 既に述べたとおり、改正雇用対策法により、厚生労働大臣は、法務大臣から、入管法又は外登法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあったときは、外国人労働者の雇用状況に係る情報を提供するという枠組みができ、同法に従って適正な運用がなされることが望まれる。 その他に、いかなる行政機関が、他のいかなる行政機関が保有する、いかなる範囲の外国人に関する情報を必要とし、いかなる方法で情報提供を行うかについては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)に則って関係行政機関により検討が進められることが望まれる。 |
| 9 | 法務大臣による情報の保有及び利用の在り方 |
| 法務大臣による情報の保有及び利用は、行政機関個人情報保護法に従って、適切に行われなければならない。 |
| (1) | 法務大臣による情報の保有の在り方 | ||||||||||||
| (1) | 在留情報の正確性の確保 | ||||||||||||
| 法務大臣は、行政機関個人情報保護法に基づき、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報の正確性を確保する措置を講ずるよう努めなければならない。 | |||||||||||||
| (2) | 在留情報の開示請求等 | ||||||||||||
| 法務大臣は、外国人から自己を本人とする在留情報に関する開示、訂正及び利用停止の請求があった場合には、行政機関個人情報保護法に基 づいて対応する(注14)。
(注14)基本的身分事項、在留資格、在留期間、居住地については、在留カードにより証明することが可能である。一方、世帯単位で居住関係を明らかにしたい場合は、「適法な在留外国人の台帳制度」において証明書交付の規定が整備されれば、市区町村の長に対し、当該証明書の交付を請求することになろう。
|
|||||||||||||
| (3) | 情報セキュリティ対策 | ||||||||||||
| 法務大臣は、行政機関個人情報保護法に基づき、外国人からの届出や所属機関・行政機関からの情報提供により取得した情報を保有するに当たり、漏えいや改ざん等を防止するために必要な措置を講じなければならない。 | |||||||||||||
| (2) | 法務大臣による情報の利用の在り方 | ||||||||||||
| (1) | 概要 | ||||||||||||
| 新たな在留管理制度において法務大臣が取得する情報は、まず第一に、退去強制手続、在留資格の取消手続及び在留期間の更新等の在留審査において、十分に活用されるべきである。すなわち、在留期間の途中で判明した事情に基づき又はそれを端緒として、退去強制手続若しくは在留資格の取消手続を行い、又は、在留期間の更新等の在留審査において考慮することとする。 他方、在留期間の途中において、退去強制事由や在留資格の取消事由には該当しないものの、在留管理上適切と言えない活動状況が判明した場合には、的確な在留管理を行う必要から、これに対処する新たな制度を設けることを検討すべきである。 |
|||||||||||||
| (2) | 各論 | ||||||||||||
|
| 10 適法に在留する外国人の利便性の向上 | |
| (1) | 出入国管理行政における利便性の向上 |
| 法務大臣が外国人の在留状況を正確に把握する新たな在留管理体制が構築されることにより又はこれを前提にして、出入国管理行政において、適法に在留する外国人の利便性の向上を図る以下のような施策を検討すべきである。 | |
| (1) | 在留期間の上限の伸長 |
| 現在、我が国における外国人の在留期間は概ね3年となっているところ、その在留状況が正確に把握でき、的確な在留管理を行うことが可能となること等から、一定の在留資格については、在留期間の上限を5年程度に引き上げることとする(注15)。
(注15)「規制改革推進のための3か年計画」(平成19年6月22日閣議決定)において、「不法残留者等の不法滞在者のみならず、正規の在留資格を有しながら本来の目的と異なる活動を行う偽装滞在者が社会問題化し、厳格な対応が求められている点について、在留資格取消し制度の運用状況が安定し、実態調査体制の整備状況も目途が立ちつつあることを勘案し、専門的・技術的分野の外国人労働者については、外国人の勤務先に一定の要件を設けるなどの措置も講じた上で、在留期間の上限を5年程度に引き上げるべきである。」とある。
|
|
| (2) | 再入国許可制度の見直し |
| 上陸許可や在留期間の更新等の許可に伴い、在留カードの交付を受けた者については、現在以上に在留状況の正確な把握が可能となることから、原則として、これら許可とは別に許可を受けることなく一定期間内の再入国を可能とする。 | |
| (3) | 外国人の在籍する受入れ機関からの在留期間更新等の取次申請に対する手続の簡素化 |
| 法務大臣に対して、定期又は随時の情報提供を適切に行っている受入れ機関が取り次ぐ所属外国人に関する在留期間の更新等の申請については、提出書類の省略等手続の簡素化を行う。 | |
| (2) | その他の利便性の向上 |
| 出入国管理行政以外で、例えば以下のような利便性の向上が期待される。 | |
| (1) | 適法に在留する外国人の台帳制度の整備による行政サービスの向上 |
| 市区町村において、適法に在留する外国人の台帳制度が整備されれば、外国人住民に対して教育、医療、福祉等各種行政サービスが円滑に提供されることが期待される。また、同制度と住民基本台帳制度の連携により、混合世帯が実態に沿った形で正確に把握できるようになれば、混合世帯に対する児童手当の支給等各種行政サービスの提供が円滑に行われるようになることも期待される。 | |
| (2) | 各種分野における新たな外国人支援施策の促進 |
| 法務大臣が正確に把握する情報や市区町村の長が上記台帳制度により把握する情報を活用することにより、現在、政府全体で進めている、日本語教育の充実、外国語による情報・サービスの提供等の外国人が暮らしやすい地域社会づくり、就学促進等の外国人の子供の教育の充実、外国人の労働環境の改善、社会保険の加入促進といった生活者としての外国人を支援する各種施策が推進されることが期待される(注16)。とりわけ、外国人の子供の就学促進は、外国人が将来に向かって我が国で安定的に生活していく上で非常に重要であることから、法務大臣も、在留期間の更新等において義務教育の年齢にある外国人の子供の不就学を知った場合には、市区町村と連携して不就学の解消に向けた対応を行うなど、外国人が生活しやすい環境の醸成に貢献することが望まれる。
(注16)「生活者としての外国人」に関する総合的対応策(平成18年12月25日、外国人労働者問題関係省庁連絡会議決定)
|
|
| (3) | 在留カードの身分証明書としての機能充実 |
| 在留カードは、国が適法に在留する外国人に対してのみ発行するものであり、外国人の身分・居住関係や在留の適法性を証明するものとして高い信用性を有することになる。そのため、金融機関における口座開設、店舗や住居の賃貸借契約その他生活の様々な場面で、身分証明書として在留カードの提示が求められることが予想され、そうなれば、外国人としては在留カードさえ持っていれば、身分証明が可能となり、我が国で生活していく上での利便性が向上すると思われる。 | |
| 11 | 特別永住者について |
| 特別永住者は、終戦前から我が国に引き続き居住し、我が国における定住性が高く、市区町村に住所を有する住民であることから、新たに、住民行政の基礎として、外国人住民の利便の増進を図る目的で整備される「適法な在留外国人の台帳制度」においては、その対象とされるべきである。 |
| 各種団体・関係者からの意見聴取結果(概要) |
|---|
| 専門部会においては、新たな在留管理制度の在り方について検討するに当たり、在留外国人と関係がある各種団体・個人から幅広く意見を聴取し、各界の実情を把握する必要があるとの認識で一致した。そこで、(1)市区町村のうち、特に外国人が多く居住し、様々な問題に直面している外国人集住都市から、静岡県浜松市、岐阜県美濃加茂市及び群馬県大泉町の外国人学校、(2)外国人留学生の支援や教育に関わる団体として、日本学生支援機構、全国専修学校各種学校総連合会及び日本語教育振興協会、(3)外国人を雇用する企業の立場から、日本経済団体連合会、日本自動車部品工業会及び全国中小企業団体中央会、(4)労働者の立場から、日本労働組合総連合会及び全日本金属産業労働組合協議会、(5)法曹の立場から、日本弁護士連合会、(6)日本に在留している外国人の立場から、タイ人ボランティアグループ及び全日本中国留学生学友会、また、外国企業の立場から、在日米国商工会議所の合計15団体・関係者から意見を聴取した。以下、その概要を紹介する。 |
| 1 外国人集住都市 | |
| (1) | 静岡県浜松市 |
| (1) | 外国人労働者は高度人材に限定しているという建前と、国内での活動に制限のない「定住者」、「日本人の配偶者等」という在留資格により日系人の単純労働者を受け入れているという実態との矛盾がある。 |
| (2) | 在留資格の内容に変更(離婚により日本人又は日系人の配偶者でなくなった場合)があっても、付与された在留期限までは滞在できるのは問題である。 |
| (3) | 定住(長期滞在)の実態が外国人登録に反映されていない。 外国人の子供のうち、約2割が不就学と推定されていたことから、2004年7月から9月にかけて、浜松市に外国人登録をしている義務教育相当年齢にあたる外国人の子供1,899人について戸別訪問調査を実施したところ、そのうちの約2割にあたる368人が登録居住地から転出していた、登録居住地に居住を確認できない、あるいは出国していたことが判明した。 |
| (4) | 在留資格が「短期滞在」や「なし」であっても外国人登録をすることができる(登録証明書が発行される)ことは問題である。一般的には、登録証明書はイコール合法的滞在と解釈されているため、登録証明書を保持していることで雇用したり、民間住宅入居等の各サービスを享受することができ、結果的に不法就労、不法滞在を増加させている。 |
| (5) | 外国人登録制度には転出届がないため、国民健康保険証の回収ができず、医療機関から(転出前の市区町村へ)過誤請求が行なわれ、その結果、医療費の未集金が発生する。 転入先では国民健康保険や児童手当の手続が円滑にできない(児童手当の過払い)。市民税の未収が発生している。 |
| (6) | 再入国許可を受けて出国している間は外国人登録の住所の変更を行う必要はなく、入国管理局から市区町村に一時出国の情報は提供されない。これらの者は、居住実態のない外国人登録になっている。再度、日本に来ても、従前の住所地に戻らないことも多い。 |
| (7) | 外国人の氏名についてはパスポートと登録証明書では、順序が違うため、同一人と解釈されない等の誤解が生じやすい。 |
| (8) | 新たな在留管理制度としては、国籍、氏名、在留資格等の正確な身分記録は、国(入国管理局)が責任をもって管理し、住所移動・世帯移動等を把握する住民としての正確な記録は、市区町村が管理し、適正な行政サービスの提供等に役立てることが望ましい。 |
| (9) | 住民を把握する制度が、住民基本台帳と外国人登録の二つの制度に分かれているために、世帯等の把握に支障が生じている。特に日本人と外国人のいわゆる混合世帯においては、実際には、外国人が世帯主にも関わらず、住民基本台帳上は、日本人の配偶者又は子供が世帯主となっているので、国民健康保険、児童手当、就学等の個別事務において支障を来たしている。 |
| (2) | 岐阜県美濃加茂市(平成19年度外国人集住都市会議座長都市) |
| (1) | 外国人登録には転出届がなく、転出事実を即時に把握できないので、国民健康保険や児童手当等をただちに停止することができない。ただし、転出届を制度化しても、単身者については、国民健康保険や子どもの児童手当、就学等のサービスを受ける必要性が少ないことから、日本人でも学生が住所の変更を行わないのと同様に、転出届は出さないと思われる。解決策としては、例えば、雇用主等が責任をもって手続を行わせるようにする方法もあるのではないか。 |
| (2) | 外国人登録には、既婚・未婚の区別がなく、また、日本における婚姻の事実が本国に通知されることもないため、外国人同士の日本国内での婚姻は,何回でも繰り返すことが可能になっている。 |
| (3) | 外国人学校(日伯学園、群馬県大泉町職員の報告) |
| (1) | 町と外国人学校は極力連携をとる努力をしているが、制度上、教育委員会(町)とは一切関係がない。したがって、町として外国人学校に通う子供やその家族の情報について常時把握できるわけではない。 |
| (2) | 登録上の居住地と実態の乖離はあると思うが、詳細は分からない。外国人は、国民健康保険を使いたいとか運転免許を取得したいといった必要性がないと居住地の変更登録をしないという事情もあると思われる。 |
| (3) | 外国人の子供は、小学校までは何とかついていけるが、中学校にいくと、急に学習が難しくなりついていけなくなる子が多い様である。外国人学校に行った方がいい場合もある。高校まで進学するためには、本人や家族の意識と努力が必要である。教育内容に興味の無い親も多く、学校任せにしている。託児所が特に問題で、長時間預けることが大きな目的である親は、子供のしつけや生活指導をほとんどしていないので、マナーや基本的な生活習慣が確立されていない様である。 |
| 2 教育関係団体 | |
| (1) | 日本学生支援機構 |
| (1) | 在留管理制度の見直しは、在留外国人への行政サービスの向上、負担の軽減という観点から行うべきである。 |
| (2) | 現行行われている外国人学生の在籍状況等の入国管理局への報告を、関係法令へ格上げすることについては、異存はない。 |
| (3) | 在留情報把握の制度の一元化や在留カード(仮称)の発行に異存はないが、窓口が入国管理局になることで、申請者等の利便性が低下するのでは困る。 |
| (2) | 全国専修学校各種学校総連合会 |
| 在留情報把握の制度の一元化には反対ではないが、制度を変えるのであれば、留学生を受け入れる教育機関としても、留学生としても、公正で平等な制度にする必要がある。具体的には、 | |
| (1) | 入国管理局の窓口はいつも混雑していて、審査に時間がかかるので、学校単位で 一括して代理で届け出るような仕組みを作ってほしい |
| (2) | 専門学校卒業生の就職の門戸をもっと拡げてほしい |
| といった要望がある。 | |
| (3) | 日本語教育振興協会 |
| (1) | 不法残留者を雇用することのないよう、雇用主に対し、外国人を雇用する際に在留資格を確認することを徹底させるための措置をお願いしたい。 |
| (2) | 日本語教育機関から、毎月、犯罪や所在不明等の発生状況の報告を求め、必要があれば指導するなどして、学生の管理を徹底させているが、入国管理局からの情報も必要であり、今後は、情報提供をお願いしたい。 |
| (3) | 就学生等が退学した場合、直ちに帰国させることができるような措置をとってほしい。 |
| (4) | 学生の在留資格は、「就学」と「留学」の2つに分かれているが、「就学」を「留学」に一本化してほしい。 |
| (5) | アルバイトの資格外活動許可について、留学生は1週間28時間以内、就学生は1日4時間以内となっているほか、夏休み中の取扱いについても差異がある。就学生についても、留学生と同じ扱いとしてほしい。 |
| (6) | 各国と競って優秀な学生を確保するために、在留資格認定証明書の交付申請等の審査期間を短縮してほしい。特に、不法残留の問題の少ない国等については、早急にお願いしたい。 |
| 3 経済・産業団体 | |
| (1) | 日本経済団体連合会 |
| 経団連の「外国人材受入問題に関する提言」(平成17年4月)及び「外国人材受入問題に関する第2次提言」(平成19年3月)において、在留管理・就労管理は重要課題のひとつと位置づけられている。 | |
| (1) | 外国人材を積極的に受入れていくためには、外国人が満足して働き、快適に生活できるようにすべきであり、その前提として、外国人が義務を履行、権利を享受し、適切かつ合法的に働くことのできる環境を整備する必要がある。 治安の悪化や地域社会でのトラブル増加といった懸念から外国人の受入れに不安があるため、これを払拭するために、外国人の在留・就労管理について法的・制度的な基盤整備を早急に進めることが重要課題の一つと考えている。 その際、制度の安定性や実効性を確保するために、外国人本人にとっても、外国人を雇用する事業者にとっても、各種登録・届出等の手続が過度な負担となることのないよう、簡素で効率的なものとするとともに、制度間の連携を図ってもらいたい。 |
| (2) | 改正雇用対策法の外国人雇用状況届出を出入国管理行政や、各地域での就労場所の把握、社会保険の加入徹底等に活用すべきである。同改正法施行に際しては、経団連として、会員企業に周知徹底を図っていくとともに、請負・派遣業者に働きかけを行っていきたい。 |
| (3) | 外国人登録制度を見直し、住民基本台帳制度(ネットワーク)との融合を図り、世帯単位での管理をすべきである。 |
| (4) | 外国人雇用状況届出や外国人登録、出入国管理の情報を相互に照会可能となるようにすべきである。これにより、外国人の居住状況をより的確に把握し、外国人に対する行政サービスの充実につながることが期待される。 改正雇用対策法にあるように、雇用状況届出と在留管理との連携は必要であると考える。必要に応じ、同様の規定を他法令にも拡充し、関係省庁間の情報共有と連携を図るべきである。 |
| (5) | また、転出届を義務付けるとともに、その実効性を確保するために、これらの遵守状況を在留期間更新等の審査等とリンクさせるという手法も有効ではないか。同時にこうした在留資格手続の審査基準のガイドライン化、許可・不許可事例の公表等を進め、手続の透明性の向上を図るべきである。 |
| (6) | 外国人が我が国で快適に働き、生活し、年限がきたら本国に戻るというローテーション型の外国人材受入れを進めていくべきである。その前提として、在留管理、企業の就労管理はきっちりと行い、外国人に対し、日本では不法就労はできないということを明らかにする社会基盤を作っていく必要がある。 |
| (2) | 日本自動車部品工業会(アイシン精機株式会社) |
| (1) | 現在、登録証明書は、携帯電話やアパートの契約、銀行口座の開設時に住民票の代わりとして使用され必要不可欠なものである。また、児童手当受給や公共施設利用時などにおいても身分証明書の代わりとして使われている。新たな在留管理制度において、在留カードを発行するようだが、これと従来の登録証明書との関係はどのようなものになるのか。 |
| (2) | 従来の登録証明書が持っていたメリットについては、在留カードに引き継がれるよう、手続きに関しては、従来よりも煩雑にならないよう配慮してもらいたい。また、申請者の利便性の向上についても検討してほしい。 |
| (3) | 全国中小企業団体中央会 |
| (1) | 入国管理局というと「取締り」のイメージが強く、市区町村は行政サービスの提供主体という色彩が強いという印象を持っている。今回の新たな在留管理制度では、入管に情報等を一元化し、取締りの強化ばかりが強調されている点が気がかりである。中小企業は地域社会に密着しており、在留情報について、外国人に対する市区町村の適切な行政サービスの充実につなげていくことが重要である。 |
| (2) | 住所情報について、どのようにしてその正確性を担保し、各自治体における行政サービスに活かしていくのかが一つの課題ではないか。行政サービスという点を考えるとき、まずは、各自治体が外国人の正確な住所を把握することが重要であり、仮に企業の側にそれを求めるのであれば、それは負担が大きく困難である。 |
| (3) | 研修・技能実習制度については、廃止するのでなく運用の適正化で対応し、制度を充実させていくべきである。悪質なブローカー等の制度悪用については、きちんと対処していくべき。団体監理型の廃止意見があるが、中小企業はこの仕組みがないとなかなか対応できない。 |
| 4 労働組合 | |
| (1) | 日本労働組合総連合会 |
| (1) | 外国人雇用状況届出制度により集めた情報を、法務省に提供することに懸念はあるが、人権・プライバシーに配慮した上で、在留管理に利用することまでは否定しない。事業主がいかに外国人であることを認識し、届出するのかは今後の課題としてとらえている。 |
| (2) | 改正雇用対策法による外国人雇用状況届出制度でも漏れてしまう人達がいる。日系人の多くが請負や派遣として働いているが、法律の施行により、届出義務から漏れる「一人親方」として働く日系人が増加することを懸念している。一人親方の扱いをどうするか、法務省のこの部会で検討する必要がある。 |
| (3) | 就労資格が無くても労働諸法は適用されており、雇用保険や労災保険の未加入、未払賃金等の請求については、円滑に行えるよう議論してほしい。 |
| (4) | 外国人登録を在留カードとすることは、組織として議論していないが問題ないと考える。ただし、発行に当たっては偽造防止対策を徹底する必要がある。 |
| (5) | 在留資格の取消しについては、例えば解雇の妥当性等で争いがある場合等について、一定の配慮をする必要がある。 |
| (6) | 居住地や勤務先の変更の届出をきちんとさせるためには、その届出をすることにより何らかのメリットがあるような仕組みとすべきである。 |
| (7) | 新たな台帳制度では、転居や出入国を何度も繰り返す人達も的確に把握できるようにすべきである。 |
| (8) | 特別永住者については、住民基本台帳を準用してもいいのではないか。 |
| (2) | 全日本金属産業労働組合協議会 |
| 金属労協は、日本の金属産業の大産業別労働組合組織であり、「電機連合」、「自動車総連」、「JAM」、「基幹労連」、「全電線」で構成されている。外国人を含めた非正規社員の組織化を積極的に進めようとしている。ただし、金属産業は製造現場であり、パートやアルバイトのような直接雇用の非正規社員より、派遣や請負といった間接雇用が多いので、他の産業に比べ組織化が難しいのが組織の現状である。その中で現場から以下のとおり聴取した。 | |
| (1) | 外国人労働者に頼った生産体制となっているために、技術や技能が日本人に継承されていない。日本のものづくりの強みは「現場」にあるので、現場の声を大事にして、長期安定雇用に支えられた技術・技能を大事にしていくべきである。 |
| (2) | 事業主は、日系人を中長期的戦力と考えておらず、将来的な生活設計に不安がある。就労制限がないので、定着を想定した受入れ体制を構築すべきである。一方、日系人労働者(定住者)について、犯罪履歴のある者に対する入管法上の取扱いを厳格にし、一定の日本語能力を入国の際の要件とするほか、就労の安定性や子弟教育、社会保険加入等を在留期間の更新の要件とすべきである。 |
| (3) | ベトナム等の送出し国の労働組合では、日本で働く自国労働者の状況を懸念している。 |
| (4) | 短期外国人就労制度案については、日本人と外国人の二分化、劣悪・低賃金の放置、産業高度化の阻害、国際競争力低下等につながるおそれがあり、導入すべきではない。また、帰国後の就職について配慮がなく反対である。 |
| (5) | 外国人研修・技能実習制度については、技術・技能を発展途上国に移転し、人づくりに寄与するという制度本来の趣旨が機能するよう、制度整備、運用改善を行うべきである。具体的には、次の事項を要望する。
・団体監理型にも「5%ルール」を適用させる。
・技能実習に移行できない職種・作業は、団体監理型での研修を認めない。
・団体監理型の研修生・技能実習生が、自らの意思で受入れ先を変更できるシステムを構築する。
・JITCOの地方駐在事務所を拡充し、チェック体制を強化する。
・企業単独型,団体監理型を問わず、生活指導員・研修指導員を専任にする。
・研修生も労働者として位置づけ、労働法,社会保障制度の対象とする。
・不正行為を行った受入れ企業・団体の新規受入れ禁止期間を5年間とする。
・再入国・再実習は企業単独型のみに認める。
・技能実習の対象職種拡大は慎重に。
|
| 5 日本弁護士連合会 | |
| (1) | 新たな在留管理制度における外国人の情報の取得、保有、利用については、プライバシー権、自己情報コントロール権の観点から、規制目的との関連性があるかどうか、対象事項、人的範囲、保有期間等が必要最小限のものであるか、取得目的と異なる利用を予定していないかなどの点に留意すべきである。また、外国人に対する差別的取扱いの禁止の視点、多文化共生社会の視点を持つべきである。 |
| (2) | 入国管理制度との関係で、入国時に採取した指紋等の個人識別情報を在留管理制度の中でどう活用するのか(また、しないのか)、本来テロリストの入国防止が目的のこれらの情報を在留管理全般に活用するという問題があり、入国時のチェックを終えて入国した全ての外国人の指紋が犯罪捜査にも利用されるのではないかなどの問題点について、きちんと議論すべきである。 |
| (3) | 改正雇用対策法では、厚生労働省が事業主から取得した情報を法務省に提供することになっており、また、これとは別に、教育機関からは法務省に情報提供することが検討されているが、これらの情報は、本来、外国人雇用の安定や教育目的で取得した情報であり、それを在留管理に転用するということは、法制度の目的の変容を意味するものであり、自己情報コントロール権の観点から問題があると考える。 |
| (4) | 行政機関相互の情報共有や、在留カードをICカードとして発行することは、行政が多くの個人情報を集積し、個人ごとに名寄せすることによって個々の生活状況を監視することが可能となり、また、情報の漏洩の危険性という観点から、問題視している。 |
| (5) | 新たな在留管理制度では、特別永住者は対象外であるのに対し、特に永住者は対象となるとのことであるが、永住者は不法滞在や資格外就労の問題は基本的に生じないのであり、就労状況や就学状況まで届出することを義務づけて日本人と異なる扱いをする必要はないのではないか。多文化共生の観点からも、きちんと検討すべきである。 |
| 6 在日外国人関係者 | |
| (1) | 日本在住タイ人ボランティアグループ(タワン) |
| (1) | 多くのタイ人女性たちが、日本人夫からのDVで苦しんでいる。身体的、精神的、経済的暴力をはじめ、ビザを更新させない、外国人登録証やパスポートを隠して逃げられないようにする、日本語を習得させないで助けを求められないようにするなどの行為が多く見られる。ICカードを導入するのであれば、彼女たちのような外国籍のDV被害者の実情を理解し、不利益が生じないよう配慮してほしい。例えば、「日本語習得が十分でなかったり、法律違反をした外国人のビザ更新をしない」方針について、このような状況にあるDV被害者に対してはどのような配慮または支援がなされるのか。また、様々な理由により、ひとり親家庭となった場合、仕事をしながら日本語学習をする機会はどの程度準備されるのか。 |
| (2) | 今後、ICカード導入となり、様々な機関が、外国人の細かな個人情報を閲覧できるようになるのであれば、外国人は種々の不利益な取扱いを受けるのではないか。さらに、雇用先や教育機関等の変更届が義務化されるならば、どこからか不用意に情報が漏れ、例えば、DV被害者の外国人の所在が夫に見つかってしまうというような事態が生じることを危惧している。 |
| (3) | 外国人との共生を考えるならば、外国人の管理だけでなく、弱い立場にいる外国人を保護、支援するという視点も持ってほしい。役所などの公的な相談窓口を外国人が相談しやすい開かれた場所にしてほしい。 |
| (2) | 全日本中国留学生学友会(中国人留学生団体) |
| (1) | 在留情報把握の制度の一元化や在留カード(仮称)の発行に異存はないが、窓口が入国管理局になることで、申請者等の利便性が低下するのでは困る。 |
| (2) | 一元化に当たっては、入国管理局の窓口の増設、又は、可能であれば、外国人登録と同様、市区町村の窓口で各種手続ができること、必要以上のプライバシー情報を求めないこと、情報管理の徹底を望む。 |
| (3) | 教育機関からの在籍状況等の報告の実効性を高めることについては、単に管理のためでなく、手続期間の短縮、提出書類の簡素化等、外国人のメリットになるように活用してほしい。 |
| (4) | 部屋探しの際の保証人問題、日本語教育、医療援助など、政府として生活面での支援をもっと充実してほしい。 |
| (3) | 在日米国商工会議所 |
| 現在の外国人登録制度についてのコメントは控えるが、現在の入国管理制度に対しては以下の3項目について要望したい。 | |
| (1) | 家事や子供の保育の仕事をする外国人の査証の取得や在留資格について、もう少し柔軟な対応をすべきである。また、ある企業で働く外国人が、これらの外国人を雇用する際には、組織上の地位だけではなくその企業の規模・ニーズを考慮して、在留資格を判断していただきたい。 |
| (2) | 再入国許可手続については平成11年に簡素化されたが、申請者にはあまり周知されていない。また、入国管理局職員もこの点を熟知していないのではと思うことがある。新しい手続きについて、職員にも研修を行い、外国人にも周知できるような体制とすべきである。 |
| (3) | 「家族滞在(扶養家族)」について、外国人従業員と扶養家族とで在留期限が異なるケースがよくある。家族間で期限が異なると、その都度更新手続を行う必要があり、負担が大きい。このような者については、在留期限について調整が取れるようなオプションを付与したらどうか。必要があれば、在留期限を合わせるために、残りの在留期間を放棄することも考えてもよい。これによって、外国人従業員等の負担が軽減するのみならず、入国管理局の事務作業も簡素化するのではないか。 |