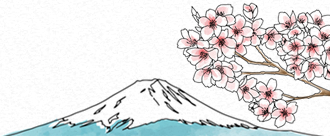外国人を受け入れて、一緒に生活するためにすること(2025年度に少し変えました)
大事な考え
日本政府は日本人と外国人がお互いを大切に思い、一緒に、安全で安心して生活できる社会を目指します。外国人が日本で働いて活躍できるようにすることで、日本が魅力のある国として外国人に選ばれるようにします。
そのためには、外国人も、日本で一緒に生きていくために、日本の文化や日本語がわかるようになることが大切です。また、外国人が日本のきまりやしくみをよく知って、自分の行動に責任をもつことも大切です。
おもにやること
1 外国人がもっと社会に参加できるように、日本語などを勉強できる機会をつくること
外国人が生活のために必要な日本語などを勉強できる機会をつくる。
- 都道府県などが行っている日本語教育をさらに広げるための取組を進める。市区町村が都道府県などと力を合わせて行っている日本語教育をサポートする。「日本語教育の参照枠」を使って、地域の日本語教育のレベルを上げる。《1》
- 「日本語教育の参照枠」に書いてある教育内容などに対応するため、いろいろな教育モデルをつくって、広める。《3》
- 日本語教室がない地域をなくすために、日本語教室を作り、続けていけるようにサポートする。普段の生活で使う日本語を学ぶことができるICT教材をつくって配る。《4》
- 日本語の勉強や、日本の社会に早くなれるために、生活のきまりやマナーを伝える動画を、もっと使ってもらえるようにする。《7》
日本語教育の内容をよくする。
- 日本語の学校として認めるしくみをつくる。日本語教師として認める制度を使って日本語教育を進める。《5》
- 会社などがお金を出して、日本語を教える学校が、学ぶ人の必要に合った、レベルの高い日本語の勉強ができるようにするモデルをつくる。《18》
育成就労外国人<=日本で働きながら技能や知識を学び、働く人として活躍する外国人>の日本語のレベルを上げる。
- 育成就労計画に、日本語能力をどこまで上げるかの目標を入れるように考える。《131》
※赤い文字で書かれたものは、新しくやることです。青い文字で書かれたものは、内容を変えたものです。数字は、やることの番号です。
2 今よりも外国人へもっと情報を伝えたり、外国人がいろいろなことを相談できるようにしたりすること
外国人にわかりやすい情報をもっと伝える。
- 「関係者ヒアリング」や「御意見箱」などを使って、外国人と日本人が一緒に生活する社会に役に立つ意見を聞く。《21》
- 「生活・就労ガイドブック」<=日本で生活する外国人が、安心して生活したり働いたりするために知っておいてほしいことを集めたガイドブック>と「外国人生活支援ポータルサイト」<=日本で安心して生活するために必要なことや大事なことを、お知らせするウェブサイト>に何を書くかを考える。《24》
- 防災<=災害を防ぐこと>や天気の情報をいろいろな言葉で伝えるようにする。《33》
外国人が困っていることを相談できるしくみをもっとつくる。
- 外国人受入環境整備交付金<=外国人が相談しやすくなるために、外国人がひとつの場所でいろいろな悩みを相談できるところをつくったり、運営したりするために必要なお金を、国から都道府県・市区町村へあげる制度>の見直しなどをする。そして、都道府県・市区町村がひとつの場所で悩みを相談できるところを増やすように考える。育成就労外国人を助けるための外国人育成就労機構のしくみをつくる。《36》
- FRESC/フレスク<=外国人在留支援センター>で外国人の受け入れについて助ける。外国人を助ける仕事をしている人たちが、近くの場所で集まって、外国人が困っていることを聞く会を開く。《37》
- 日本語を外国語に、外国語を日本語に変える技術を高める。誰でも使える同時通訳の技術を実現させる。対応する外国語を21に増やす。《38》
- 生活のことで困っている外国人を専門的にサポートする人を育てる。《6》
外国人に情報を伝えたり外国人が相談するときにやさしい日本語をもっと使うようにする。
- やさしい日本語を広めるための勉強会を行う。《49》
3 それぞれの人の生活に合わせて助けること
「乳幼児期<=0歳から5歳>」、「学齢期<=6歳から15歳>」の外国人に対するサポートなど。
- 地域に子育てをサポートする場所をつくって、子育てをしている親とその子どもに来てもらい話をしてもらうことや、子育ての悩みを話すことができるようにする。《53》
- 外国人の子どもが勉強するのに魅力のある教育モデルを作り、その方法を都道府県、市区町村、学校へ広める。《59》
「青壮年期<=16歳から64歳>」の初期の外国人に対するサポートなど。
- 日本語を教える方法の一つ、「特別の教育課程<=クラス以外の教室で勉強する>」の例をまとめて広める。《62》
「青壮年期<=16歳から64歳>」の外国人に対するサポートなど。
(1)留学生が仕事を始めることを助ける。
- 高度な知識や技術をもっている外国人が活躍できるように、関係のある地域の団体や人が協力して、外国人留学生を日本の会社で働けるようにする。《89》
(2)外国人が働いている場所でのサポート。
- 日本人の社員と外国人の社員が職場でお互いに学べるような動画や案内をつくって広める。《90》
- ハローワークの外国人雇用サービスコーナーに相談する人や通訳がいて、外国人が仕事をさがしたり、その人に合った仕事を紹介できるようにする。《92》
- 日本に住んでいる外国人に、日本語の能力に合った職業訓練を行う。《95》
(3)働きやすい環境などをつくる。
- 外国人が働く会社の雇用労務責任者に対して勉強会を行う。《98》
- 妊娠や出産をした技能実習生が使える制度を知らせて広める。《108》
「高齢期<=65歳以上>」の外国人に対するサポートなど。
- 年金の制度について外国人にもっと知ってもらうようにする。《109》
人生のどの時期にも共通する取組。
- 「在留外国人に対する基礎調査<=日本にいる外国人についての調査>」を行って、外国人が困っていることを知る。《22》
- 外国人が犯罪の被害者になることや外国人コミュニティに犯罪グループが入ってこないようにする。《116》
- 外国人が口座を開きやすいようにするなど、銀行などのサービスを使いやすくする。《119》
4 外国人が日本で安心して働けるようサポートするしくみをつくること
特定技能外国人<=決まった分野の仕事をする外国人>が仕事を見つけやすくするために助ける。
- 分野別協議会<=それぞれの分野の人が集まる会>で情報を伝え、外国人が働きやすいようにする。《127》
育成就労制度<=外国人が日本で働きながら技能や知識を学び、働く人として活躍する制度>と特定技能制度<=技能や知識のある外国人が決まった分野の仕事をして活躍する制度>を問題がなく使えるようにする。
- 日本語の能力を高くするしくみをつくって、育成就労制度で来た外国人が、働きやすいようにする。《131》
- 受け入れる会社や、特定技能外国人にとってもっと便利になるように、しくみの変更についてわかりやすく伝える。《138》
- ODA<=政府開発援助>を使って、日本と、日本に人を送り出す海外の国が一緒に考え、協力するネットワークをつくり動かす。《140》
悪い仲介事業者<=間に入る会社や人>を使わない。
- ODAを使って、途上国の関係する人たちと協力して外国人で働く人をサポートする。《152》
海外の日本語教育の基盤をつくる。
- 国際交流基金を通して日本語教育の基盤を強くし、日本の文化や社会のよいところを知ってもらうようにする。《13》
- JICA<=国際協力機構>が講師を外国に行かせることをサポートして、「日系四世受入れ制度」をすすめる。《153》
5 すべての人が生活しやすい制度をつくること
外国人と一緒に生活するために大切なことをみんなで考える。
- 「外国人と一緒に生活するために大切なことを考える月」を広める。みんなで考えるイベントを行う。《154》
- 外国人が少ない地域の子どもたちの様子がわかるようにネットワークをつくるための調査をする。《57》
日本に住んでいる外国人の生活を知るためにデータをとる。
- 日本に住んでいる外国人のデータを使って、外国人の暮らしの状況を知るための新しい資料をつくり、みんなに知らせる。《160》
- 「働いている外国人の働く条件など、どう外国人に働いてもらうか」「働いている外国人がどのように働く場所を変えるか」について知るために調べる。《161》
外国人と一緒に生活する社会をつくるための情報をもっと集める。外国人を助ける仕事をしている人たちがさらに協力する。
- 外国人を受け入れるために高い知識を持った担当の人を育てて、外国人を助けたり受け入れる環境をよくしていく。《163》
- 民間支援団体<=役所の人ではないが、外国人を助ける仕事をしている人たちのこと>が、困っている外国人に情報をもっと届けられるようにする。《164》
- 外国人が相談できる窓口で、関係のある人たちがつながり協力する。外国人在留総合インフォメーションセンターでもっと相談できるようにする。《165》
- 在留資格の手続きを便利にして、正しい情報で審査し、管理できるように、関係する人が協力できるようにする。《166》
- オンラインでの在留資格の手続きを便利にして使う人がふえるようにするため、システムをよくする。《167》
- マイナンバーカードをとりやすいようにする。マイナンバーカードと在留カードをひとつにして便利にする。《168》
- 外国人と一緒に生活する社会をつくるために役立つ情報などを伝える。《169》
- 病院のお金をはらわなかった外国人について入国するときなどにきびしく審査する。《43》
- 外国人が社会保険料をきちんとはらっているかを確認し、その結果を在留資格を審査するときに正しく使えるようにするしくみを考える。《125》
- 国民健康保険を使うことができない在留資格の外国人について、正しい資格を管理する。《174》
- 受け入れる会社や特定技能外国人が税金をちゃんとはらっているかをしっかりとたしかめる。ほかの在留資格の外国人についても、きびしく審査する。《175》
- 出入国に関係するところで働いている人が勉強する機会をつくる。出入国管理システムを使いやすくする。在留資格の審査のときにかかるお金について見なおすことなど、必要な人や物を整える。出入国の仕事をデジタルで便利にする取組の一つとして、電子渡航認証制度(JESTA)を早く取り入れることができるように考えるなどする。《180》
- 査証<=ビザ>にかかるお金を見なおし、デジタルの技術も使いながら、査証の仕事をいちばんよい方法で行う。また、組織を強くする。《181》
外国人と日本人が一緒に生きていく社会を外国人も支えていくことができるようにする。
- よいお手本になっている都道府県・市区町村の取組に対して、地方経済・生活環境創生交付金<=地域をよくする活動を国が応援するためのお金>を使って、サポートする。《184》
- 日系四世の受入れ制度を見なおす。《185》
- 都道府県や市区町村と協力して、外国人が地域に住み続けられるように地域おこし協力隊員<=都会から人の少ないところに引っ越して、その地域に協力して働く人>などが活躍できるようにする。《188》
外国人と日本人が一緒に安心して生活できるように、外国人が日本に住む状況がわかるしくみをつくる。
(1)外国人が日本に住んでいる状況をもっとわかるようにする。
- 永住者の在留資格の独立生計要件<=自分で生活できるお金や技能があり安定した生活ができる>などをはっきりと示す。永住者の在留資格の取消しについてのガイドラインをつくる。《189》
- 難民などを早く、確実に保護し助ける。《191》
- 外国人にマイナンバーカードをもっと使ってもらうために、マイナンバーカードの申込みを手伝う。《192》
- 仕事ができる在留資格をもらって日本に来るときの決まりや審査する方法を見なおす。外国人が日本に住んでいる状況をもっと正しくわかるようにする。《196》
- 在留資格でしてはいけない仕事をしたときにきちんと対応し、外国人が日本に住んでいる状況が正しくわかるようにする。《197》
(2)留学生が学校にいるかしっかりと確認する。
- 日本語教育機関を調べる。いろいろな基準に合っているかを確認する。《199》
(3)技能実習制度<=外国人を日本で決まった期間受け入れ、仕事しながら技術を学ぶ制度>を正しく使えるようにする。
- 技能実習制度について、相談と指導を一緒にできるようにする。申込みなどの手続きをオンラインでできるように考える。《100》
- しかたがない理由で会社をかえることについて、しっかりと知らせたり説明したりして、いなくなる技能実習生をへらすための取組を進める。《207》
(4)不法滞在者等<=法律を守らずに日本にいる外国人>に対してすること。
- 関係する機関が協力して、情報を集めて調べることで、デジタル社会に合ったとりしまりや、きまりに反することをふせぐ取組を進める。《211》
- 外国人が日本に住んでいる状況が正しくわかるようにするために、にせものの在留カードをつくらせないようにする。《212》
- 帰国の命令が出た外国人のそれぞれの理由に合わせた帰国のやり方をいろいろ準備する。自分から帰国するための工夫を強化する。《215》