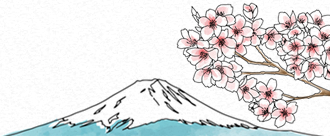引渡し(入管法第44条)
入国警備官は、監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、違反調査により容疑者を収容したときは、身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、その容疑者を入国審査官に引き渡さなければならないとされています。これを「引渡し(ひきわたし)」と呼んでいます。この引渡しを受けた入国審査官は、入国警備官の行った違反調査に誤りがなかったかどうかなどについて審査します。
また、監理措置に付する旨の決定がされた場合は、入国警備官は調書及び証拠物とともに、その容疑者に係る違反事件を引き継がなければならないとされており、これを「引継ぎ(ひきつぎ)」と呼んでいます。この引継ぎを受けた入国審査官は、入国警備官の行った違反調査に誤りがなかったかどうかなどについて審査します。
なお、入管法第63条には、容疑者が刑事処分等により身柄を拘束されているとき(未決勾留、服役中など)には、収容令書により身柄を拘束しないときでも退去強制手続を行うことができる旨の規定があり、容疑者を収容しないまま、違反調査を行い、入国警備官から入国審査官に事件を引き継ぐことがあります。
違反審査(入管法第45条から第47条)
入国警備官から容疑者の引渡し又は違反事件の引継ぎを受けた入国審査官は、容疑者が退去強制対象者(退去強制事由のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいいます。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならないとされています。
入国審査官が、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定し、容疑者がそれを認めて帰国を希望するときは、退去強制令書が主任審査官によって発付され、その外国人は退去強制されることになります。
一方、容疑者がその認定が誤っていると主張したときは、第2段階の審査に当たる口頭審理を請求することができます。
また、認定は誤ってはいないものの、日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、在留特別許可の申請をすることができます。
なお、違反審査の結果、その容疑者が退去強制事由のいずれにも該当しないことが分かり入国審査官がそのことを認定した場合や入国審査官がその容疑者が出国命令対象者に該当すると認定し、主任審査官から出国命令を受けたときは、入国審査官は直ちにその者を放免しなければならないとされています。
口頭審理(入管法第48条)
入国審査官が退去強制対象者に該当すると認定した場合で、容疑者がその認定が誤っていると主張したときは、認定の通知を受けた日から3日以内に口頭をもって特別審理官に対し、口頭審理を請求し、これに基づき、審問が行われることとなっています。これが特別審理官による口頭審理です。特別審理官は、出入国在留管理庁長官が指定する上級の入国審査官です。
特別審理官は、入国審査官の行った認定に誤りがあるかどうかを判定します。特別審理官が入国審査官の認定に誤りがないと判定し、容疑者がそれを認めて帰国を希望するときは、退去強制令書が主任審査官によって発付され、我が国から退去強制されることになります。
一方、容疑者がその判定が誤っていると主張したときは、第3段階の審査に当たる法務大臣への異議の申出を行うことができます。
また、判定は誤ってはいないものの、日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、在留特別許可の申請をすることができます。
口頭審理の結果、特別審理官が退去強制事由のいずれにも該当しないと判定をした場合や特別審理官がその容疑者が出国命令対象者に該当すると判定し、主任審査官から出国命令を受けたときは、特別審理官は直ちにその者を放免しなければならないとされています。
なお、口頭審理において、容疑者又はその代理人は、証拠を提出し、証人を尋問し、また、容疑者は特別審理官の許可を受けて親族又は知人の1人を立ち会わせることができます。他方、特別審理官は、証人の出頭を命じ、宣誓をさせ、証言を求めることができることとなっています。
異議の申出(入管法第49条)
入国審査官の認定、そして特別審理官の判定を経て、容疑者が、その判定が誤っていると主張したときは、その判定の通知を受けた日から3日以内に不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、最終的な判断を法務大臣に求めることができます。これが異議の申出です。
また、判定は誤ってはいないものの、日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、在留特別許可の申請をすることができます。
異議の申出は、特別審理官のさらに上級の入国審査官である主任審査官が法務大臣に書類を送付して行います。主任審査官とは、最も上級の入国審査官の一つであり、出入国在留管理庁長官が指定します。
法務大臣の裁決(入管法第49条)
異議の申出を受理した法務大臣は、直接容疑者を取り調べることはしませんが、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、そして特別審理官の口頭審理という一連の手続で作成された証拠(事件記録)を調べて裁決することになります。
そして、法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した場合は、主任審査官にその旨を通知することによって、主任審査官が退去強制令書を発付することになります。
一方、主任審査官は、法務大臣から容疑者が退去強制事由のいずれにも該当しないとして異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときや容疑者が出国命令対象者に該当するとして異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けて出国命令をしたときは、直ちにその者を放免しなければならないと規定されています。
在留特別許可(入管法50条)
法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であっても、次のいずれかに該当するときは、外国人からの申請又は職権により、在留を特別に許可できるとされています。
ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者又は法第24条第3号の2、第3号の3若しくは第4号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限られます。
・永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)
・かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項第2号)
・人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき(同項第3号)
・難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき(同項第4号)
・その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項第5号)
在留特別許可は、本来、我が国から退去される外国人に対して、法務大臣が例外的・恩恵的に在留を許可する措置です。
在留特別許可をするかどうかについては、個々の事案ごとに諸般の事情を総合的に考慮した上で判断されます。
退去強制令書の発付(入管法第51条ほか)
入国審査官の認定又は特別審理官の判定に服したことの知らせを受け、かつ、在留特別許可の申請をしないか、あるいは法務大臣への異議の申出に対して理由がない旨の裁決の通知を受け、かつ、在留特別許可の申請をしないときは、退去強制令書が発付されます。
また、在留特別許可の申請をした結果、在留特別許可が認められなかった場合も退去強制令書が発付されます。
一連の退去強制手続で「容疑者」と呼ばれた外国人は、この退去強制令書が発付されたときから我が国から退去させられることが確定した人となり、容疑者ではなく被退去強制者と呼ばれます。