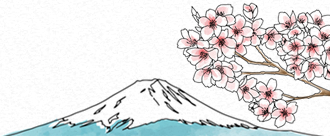- トップページ
- 在留手続
- J-Skip/J-Find
- 特別高度人材制度(J-Skip)
特別高度人材制度(J-Skip)
制度の概要
2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
・特別高度人材制度(J-Skip)概要資料
・Outline J-Skip (English)
・特別高度人材制度(J-Skip)概要資料
・Outline J-Skip (English)
要件
- 在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が我が国で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(2)「高度専門・技術活動」(高度専門職1号ロ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例:企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)「高度経営・管理活動」(高度専門職1号ハ):本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例:グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
- 「特別高度人材」の要件は、上記の(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
【(3)の活動類型の方】
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
出入国在留管理上の優遇措置の内容
「特別高度人材」の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
※ 「特別高度人材」として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
※ 「特別高度人材」として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
- 在留資格「高度専門職1号」の場合
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の雇用
- 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
- 入国・在留手続の優先処理
- 在留資格「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
- 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 在留期間が無期限となる
- 上記3から8までの優遇措置が受けられる
申請手続の流れ
| 新たに「高度専門職1号(特別高度人材)」として入国を希望する場合 |
|
|---|---|
| 「高度専門職1号」以外の在留資格で在留している方が「高度専門職1号(特別高度人材)」への在留資格変更を希望する場合 | 「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格変更許可申請を行ってください。 申請に必要な書類等については、本ページの「申請書類等について」を御確認ください。 |
| 高度人材ポイント制によって「高度専門職1号」の在留資格で在留している方が、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合 |
申請書類等について
〇 「特別高度人材の就労する配偶者」等に係る各種申請書類等は以下を御覧ください。
【高度専門職1号(特別高度人材)】※在留資格認定証明書交付申請
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
| 提出書類 | ※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
|
|---|
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
【高度専門職1号(特別高度人材)】※在留資格変更許可申請
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
(注)「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が、活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む。)についても、在留資格変更許可申請が必要です。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
(注)「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が、活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む。)についても、在留資格変更許可申請が必要です。
| 提出書類 | ※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
|
|---|
【高度専門職1号(特別高度人材)】※在留期間更新許可申請
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
なお、「高度専門職1号」の在留資格をもって在留している間は常に特別高度人材の基準への該当を維持することまでは要しません。したがって、例えば入国後に年収が入国の時点から減少した等の理由により、特別高度人材の基準を満たなくなった時点で、直ちに「高度専門職1号」の在留資格をもって在留することができなくなるわけではありません。ただし、在留期間更新許可申請の際に特別高度人材の基準を満たしていない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
なお、「高度専門職1号」の在留資格をもって在留している間は常に特別高度人材の基準への該当を維持することまでは要しません。したがって、例えば入国後に年収が入国の時点から減少した等の理由により、特別高度人材の基準を満たなくなった時点で、直ちに「高度専門職1号」の在留資格をもって在留することができなくなるわけではありません。ただし、在留期間更新許可申請の際に特別高度人材の基準を満たしていない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。
| 提出書類 | ※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
|
|---|
【高度専門職2号(特別高度人材)】
「高度専門職2号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
| 要件 (次のいずれにも該当することが必要です。) |
※ 申請人とは、日本で在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出書類 | ※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
|
申請に当っての留意事項
- 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112) - 特別高度人材(J-Skip)においては、ポイント計算は不要となりますが、同制度に係るオンライン申請においては、在留申請オンラインシステム上の「高度専門職ポイント計算表」画面で入力を求められる項目があります。
令和8年1月に実施した在留申請オンラインシステムの更改で、特別高度人材制度(J-Skip)を利用したオンライン申請に対応しています。つきましては、これまでとは入力方法が異なるため、「特別高度人材制度を利用した在留資格「高度専門職」に係るオンライン申請の在留申請オンラインシステムへの入力方法について(PDF)」のとおり入力していただきますようよろしくお願いいたします。 - また、特別高度人材(J-Skip)の家事使用人(告示2号の4)に係るオンライン申請においては、令和8年1月に実施した在留申請オンラインシステムの更改で、「特定活動(家事使用人(特別高度人材型))」のオンライン申請に対応しています。つきましては、これまでとは入力方法が異なるため、「特別高度人材・未来創造人材制度を利用した在留資格「特定活動」に係るオンライン申請の在留申請オンラインシステムへの入力項目について(PDF)」のとおり入力していただきますようよろしくお願いいたします。
- なお、利用者区分「外国人本人」の方が申請をする場合は、システムの入力項目に、紙申請書(所属機関等作成用)にある項目がなく、システム入力のみでは申請項目が不足しているため、上記の紙申請書(所属機関等作成用のみ)を添付してください。
※在留申請オンライン手続についてはこちらを御覧ください。