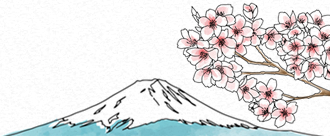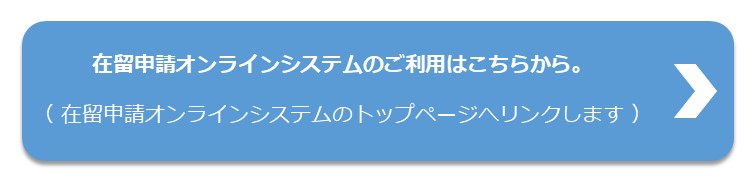- トップページ
- 在留手続
- オンライン手続
- 在留申請のオンライン手続
- 所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方
所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方
対象
■ オンライン申請を利用できる方
1.所属機関の職員の方- 所属機関とは、外国人の方を受け入れている(受け入れようとする)本邦の公私の機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)をいいます。
- 申請等取次者としての承認を受けている又は申請等取次者としての承認要件を満たしている必要があります。
なお、「申請等取次者としての承認要件を満たしている」ことについては、出入国在留管理庁ホームページに掲載されているに「申請等取次者としての承認手続」に記載された「承認を受けようとする方の条件」をご確認ください。
- 地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されている必要があります。
- 申請人の所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けている必要があります。
- 地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されている必要があります。
- 申請人の所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けている必要があります。
- 入管法第2条の5第5項の契約により特定技能所属機関から適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託されているものに限ります。
(注)弁護士及び行政書士以外の方が、業として、申請人又はその法定代理人などから手数料を得るなどして自ら在留申請オンラインシステムに申請情報を入力した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがありますのでご留意願います。弁護士及び行政書士以外の利用者が、在留申請オンラインシステムを利用する場合は、申請人や所属機関の職員と一緒に申請内容を入力するなど法違反とならないよう十分ご留意願います。(注意喚起のPDFはこちら。)
■ 利用可能な申請種別・在留資格
〇 利用可能な申請種別は、「利用者ごとの申請可能な手続(PDF)」をご参照ください。
〇 オンライン申請が可能な在留資格については、「オンラインで申請可能な申請種別・在留資格(対象範囲)(PDF)」をご確認ください。
■ 利用可能な期間
〇 在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
管轄内の地方出入国在留管理官署において申請してください。申請をする前に🔰
〇 「オンラインによる在留手続スタートアップガイド~所属機関等の職員」をご覧ください。
〇 事前にご準備いただくものは、下記「在留申請オンラインシステムの個人利用に必要な事前準備について」をご確認ください。
〇 詳しい操作方法は、下記「出入国在留管理庁在留申請オンラインシステム操作マニュアル(所属機関等の職員)」をご確認ください。
〇 所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方が、「在留申請オンラインシステム」を利用するためには、事前に利用申出を行っていただき、利用の承認を受ける必要があります。
申請の流れ
STEP1 利用者登録
〇 在留申請オンラインシステムにログインするためには、利用者登録をして「利用者ID」を取得する必要があります。
〇 メールアドレスを登録すると[利用者登録]画面に進むためのURLが送付されます。
〇 利用者登録をする際、利用者区分は「所属機関等の職員」を選択してください。
〇 完了すると登録したメールアドレスに「利用者ID」が記載されたメールが送付されます。
(注)利用者の方のメール設定において受信拒否設定がなされている場合がありますので、「@rasens-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いいたします。
(注)[利用者登録]画面に進めるのはメールが送付されてから 24 時間以内です。24 時間を過ぎた場合はメールアドレスの入力からやり直します。
STEP2 利用申出
〇 利用申出の承認後に、在留申請オンラインシステムを利用して申請を行うことが可能となります。
〇 利用申出は、オンラインや所属機関・公益法人又は登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署へ郵送又は窓口への持参により手続きが可能です。
(注)公益法人又は登録支援機関の職員の方は、所属機関(法人単位)からオンラインでの代行に係る依頼を受けている必要があります。そのため、誓約書については、複数の所属機関(法人単位)から依頼を受けている場合は所属機関(法人単位)ごとに提出する必要があります。(外国人を受け入れる機関の名簿(別記第2号様式の(2))を別紙として添付し、複数の所属機関をまとめて提出する形としても差し支えありません。)
なお、既に依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとに利用申出を行い、利用者IDを取得している場合、引き続き、当該利用者IDを使用して当該依頼を受けた所属機関に係るオンライン申請を行うことも可能です(ただし、依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとの複数の利用者IDを1つにまとめることはできません。公益法人又は登録支援機関の職員の方の固有の利用者IDを取得したい場合は、新たに利用申出を行っていただく必要があります。)。
〇 所属機関、公益法人又は登録支援機関(法人の場合は法人単位)として最初に在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けようとする方は、「新規利用申出」を行ってください。
〇 新規利用申出に必要な書類は以下のとおりです。
(1) 必要書類チェックシート(新規利用申出)
(2) 在留申請オンラインシステム利用申出書 [記載例]
→オンラインによる利用申出の場合は提出不要です。
(3) 本人確認資料の写し
(4) (所属機関の職員の方)申請等取次者証明書の写し又は研修会の修了証書等の写し
(公益法人の職員の方又は登録支援機関の職員の方)申請等取次者証明書の写し
(5) 在職証明書 [記載例]
(6) 誓約書 [記載例]
→複数の所属機関から依頼を受けている場合、外国人を受け入れる機関の名簿 [記載例]を別紙として添付し、まとめて提出することも可能です。
※カテゴリー審査を受ける在留資格に係る申請を行う機関の職員の方は、上記(1)~(6)に加えて、カテゴリー立証資料等を提出する必要があります。
必要書類チェックシート(新規利用申出)及び「在留資格から探す」 をご確認の上、該当するカテゴリーに応じた必要資料をご提出ください。
〇 同一の所属機関、公益法人又は登録支援機関(法人の場合は法人単位)で既に在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けている方がおり、更に別の方が承認を受けようとするときは、追加利用申出を行ってください。
〇 追加利用申出に必要な書類は以下のとおりです。
(1) 必要書類チェックシート(追加利用申出)
(2) 在留申請オンラインシステム利用申出書 [記載例]
→オンラインによる利用申出の場合は提出不要です。
(3) 本人確認資料の写し
(4) (所属機関の職員の方)申請等取次者証明書の写し又は研修会の修了証書等の写し
(公益法人の職員の方又は登録支援機関の職員の方)申請等取次者証明書の写し
(5) 在職証明書 [記載例]
(6) 誓約書 [記載例]
→複数の所属機関から依頼を受けている場合、外国人を受け入れる機関の名簿 [記載例]を別紙として添付し、まとめて提出することも可能です。
(注)オンラインで利用申出をした方で、申込後に入力した内容を修正する場合、追加資料がない場合であっても資料添付が必須となっています。追加資料の提出が必要ない方は、すでに提出済みの資料を添付することなく、「追加資料提出不要者用データ(PDF)」を添付してください。
利用申出の承認要件
1 |
利用申出人が申請等取次者証明書を有していること又は申請等取次者の承認要件を満たしていること |
2 |
所属機関が、申請等取次者の承認要件を満たしていること(申請等取次者の承認要件はこちらをご確認ください。) |
3 |
所属機関が、外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。外国人雇用状況届出を行わなければならない事業主においては、同届出を行っていること(公益法人又は登録支援機関を除く)
|
4 |
誓約書の提出があること |
5 |
カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する所属機関においては、経営状況、財務状況等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されていることが認められること(公益法人又は登録支援機関を除く) |
〇 申請等取次者に関連する情報は下記ページをご確認ください。
STEP3 在留申請
〇 在留申請オンラインシステムの使用に当たっては事前に留意事項をご確認ください。
(注)在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
管轄内の地方出入国在留管理官署において申請してください。
添付資料について
■ 顔写真
資料の添付が必須となっています。顔写真の提出が不要な申請の場合(注)は、「顔写真不要者用データ(JPEG)」を添付してください。
(注)16歳未満の場合、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合のことです。
■ 日本での活動内容(在留資格)に応じた資料
詳しくは「在留資格から探す」(クリックするとページが移ります。)からご確認ください。
日本での活動内容(在留資格)に応じた資料の内容については、窓口申請と同様ですので、最寄りの地方出入国在留管理官署(申請する在留資格の審査担当部門)又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
添付資料がアップロードできない場合
<添付資料が上限を超える場合の対応>
(1) 資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分(25MB)だけ資料を添付した上、「確認へ進む」ボタンを押し、「申込む」ボタンを押して在留申請を完了してください。(資料添付に係る申告書には「添付資料のデータの容量が上限を超えるため、在留申請オンラインシステム に資料を追加で添付します。」をチェックしてください。)
(2) 後日、申請を受け付けた地方出入国在留官署から追完依頼のメールが届きます。
(3) 在留申請オンラインシステムのトップページにある[申請状況の確認](又は[申請状況確認])を押すと[申込一覧]画面が表示されます。該当する申請の[詳細]ボタンを押して、再度、資料添付に係る申告書(参考様式9)の添付とともに、添付可能な分(25MB)だけ資料を添付してください。(注)(資料添付に係る申告書には「申請した地方出入国在留管理官署からの追加資料の提出依頼があったので、在留申請オンラインシステムに資料を追加で添付します。」をチェックします。)
(注)上記(3)においても、添付資料が25MBを超える場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。
なお、添付資料が膨大のため添付できない等理由により、窓口持参・郵送を希望する場合は、事前に管轄内の地方出入国在留管理官署にご相談ください。
(上記(1)の在留申請を完了する前にご相談ください。)
定期報告
〇 新規利用申出が承認され、有効期限後も継続してシステムの利用を希望する場合は、定期報告が必要です。
〇 定期報告に必要な書類や承認要件については、下記「定期報告」のページをご確認ください。
利用者の離職
〇 利用者が離職した場合は、速やかに、管轄内の地方出入国在留管理官署に郵送又は窓口への持参により「離職報告書」(別記第11号様式)を提出してください。
〇 郵送の場合には、封筒の表面に「オンライン関係提出資料」と記載してください。
〇 手続が完了した場合には、所属機関宛てに通知書を送付するとともに、利用者の方に利用者IDの抹消が完了したことをお知らせするメールを送信します。
よくある質問
Q1 新規利用申出の必要書類チェックシートについて、所属機関の場合、「カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関」と「カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望しない機関」との間で選択可能な記載となっていますが、どのような違いがあるのでしょうか。
A1 以前は、カテゴリー3の機関について、所属機関(法人単位)ごとに、利用申出や定期報告の際にカテゴリーを立証する資料等を求めていました。
令和6年3月19日以降、カテゴリー3の機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関の場合にのみ、カテゴリー3に該当することを立証する資料の提出を求めるよう見直しました。
したがって、カテゴリー3の所属機関である場合、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望される場合は、カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出してください。
Q2 提出書類を添付する際、何か条件はありますか。
A2 一度に添付できるのは、20ファイルまでとなります。
また、条件は以下のとおりです。
・PDFファイル(拡張子が「.pdf」)であること。
・ファイルサイズが合計25MB以下であること。
※ 一括入力用のテンプレートファイルを利用した場合であっても、個別の申請ごとに合計25MBとなります。
※ 利用申出・定期報告については合計20MBまでとなります。
・画像が鮮明で目視により内容の確認ができること(解像度が200dpi相当以上であることを推奨しています。)
(注)添付するファイルについて、次の場合エラーファイルとして処理されるため、当庁において資料を確認することができず、改めて郵送又は窓口への持参により「日本での活動内容に応じた資料」を提出いただくことになりますので、ご留意ください。
なお、エラーファイルとして処理される場合でも、エラーメッセージ等は表示されませんので、ご留意ください。
○ ファイルにセキュリティ上の設定等がされている場合
例:パスワードが設定されている
印刷禁止の設定がされている
コピー・ペースト禁止が設定されている
参照時にネットワーク認証が必要な場合
○「ISO 32000-1(PDFの規格)」に準拠しない形式の場合
Q3 申請後に受領方法を変更できますか。
A3 在留資格認定証明書の受領方法は変更できません。
在留カード及び就労資格証明書については、地方出入国在留管理局での審査が終わるまでは受領方法の変更が可能です。審査が終わっていて、受領方法を変更できなかった場合は、変更できないことが記載されたメールが送付されます。
Q4 利用申出の承認要件に記載されている「申請等取次者の承認手続を満たしていること」について教えてください。
A4 出入国在留管理庁ホームページに掲載されている「申請等取次者としての承認手続」に掲載された「承認を受けようとする方の条件」をご確認ください。
Q5 公益法人又は登録支援機関の職員が、新規利用申出が承認されて定期報告の確認を行うまでの間に、新たな所属機関からオンラインの代行に係る依頼を受けた場合、どうしたらよいですか。
A5 公益法人又は登録支援機関の職員の方が、新規利用申出の承認後、新たな所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けた場合、誓約書(別記第2号様式)、依頼を受けた機関の誓約書に係る送付書(参考様式11)及び利用者ごとの誓約機関一覧表(別記第2号様式の(3))を管轄内の地方局等又は地方局等の出張所宛てに簡易書留による郵送又は窓口に持参の上、提出してください。
このほかの質問は「オンラインによる申請手続に関するQ&A」(クリックするとページが移ります。)をご覧ください。
利用者情報の修正・変更等
〇 「利用者情報の修正・変更等」 (クリックするとページが移ります。)からご確認ください。
お問い合わせ
在留申請オンラインシステムヘルプデスクに電話かメールでお問い合わせください。
◆在留申請オンラインシステムヘルプデスク
TEL:050ー3786ー3053
Mail:mjf.support.cw@hitachi-systems.com
電話受付:月曜日から金曜日の9時00分から17時00分まで
(休日、12月29日から翌年1月3日までの日を除く)
メール受付:24時間365日受付